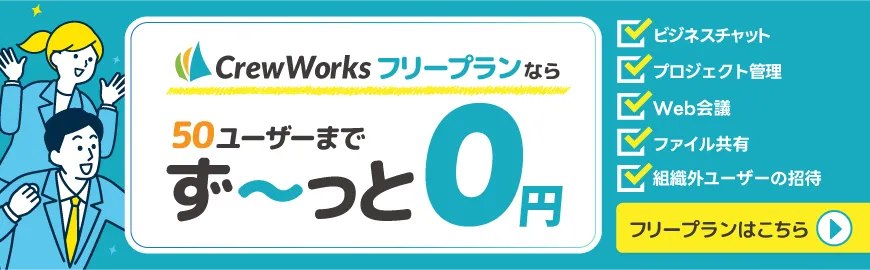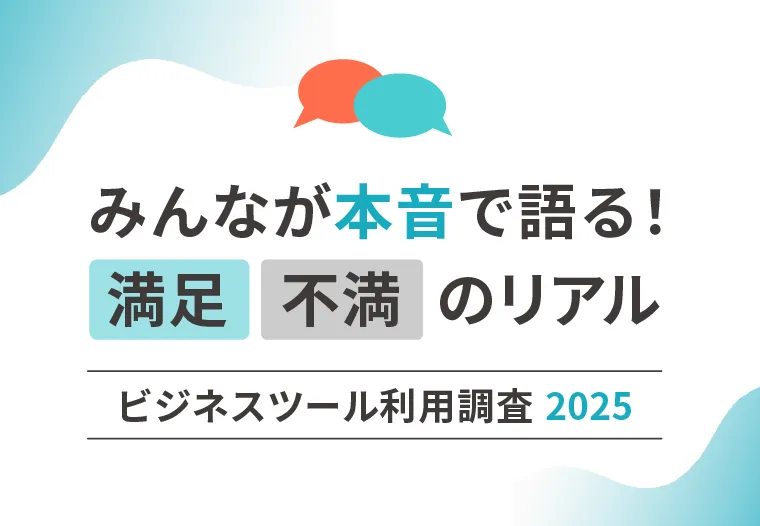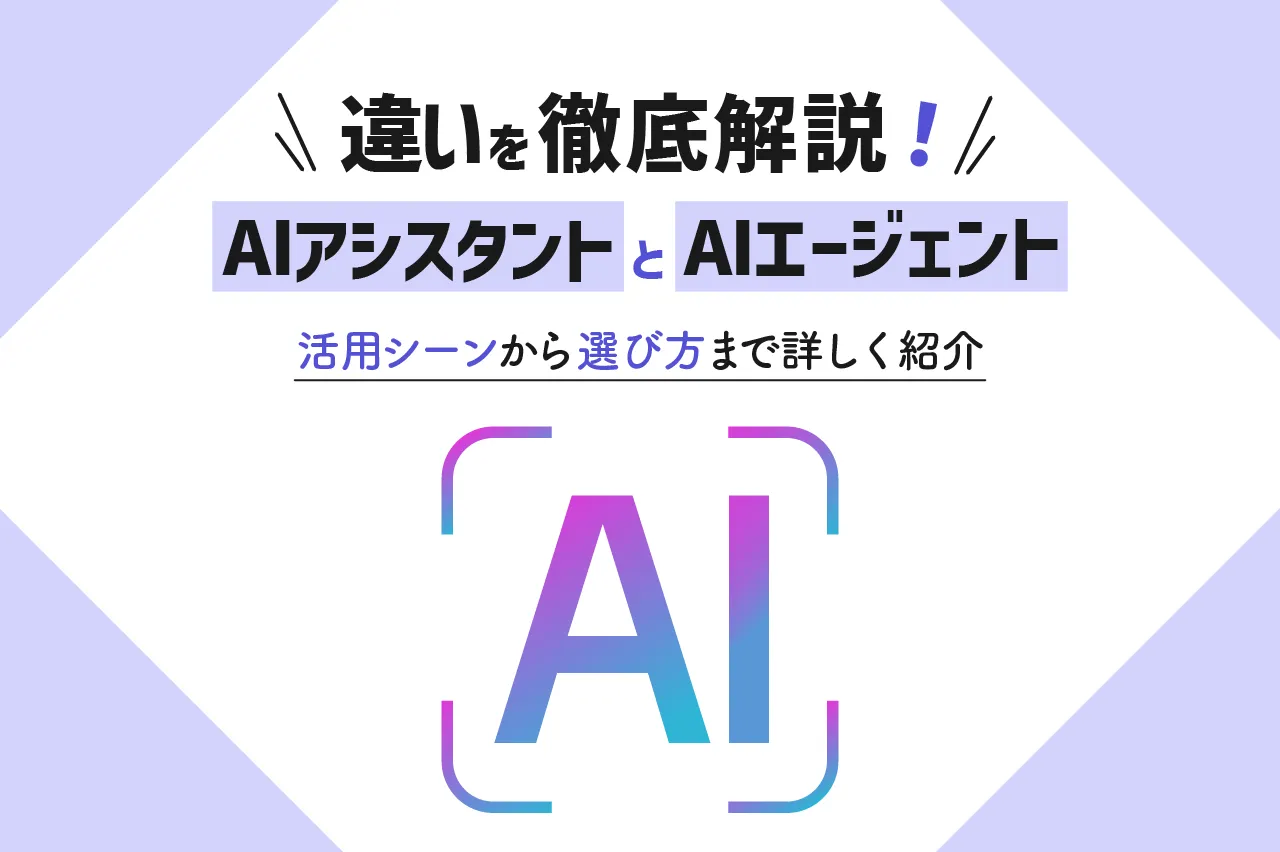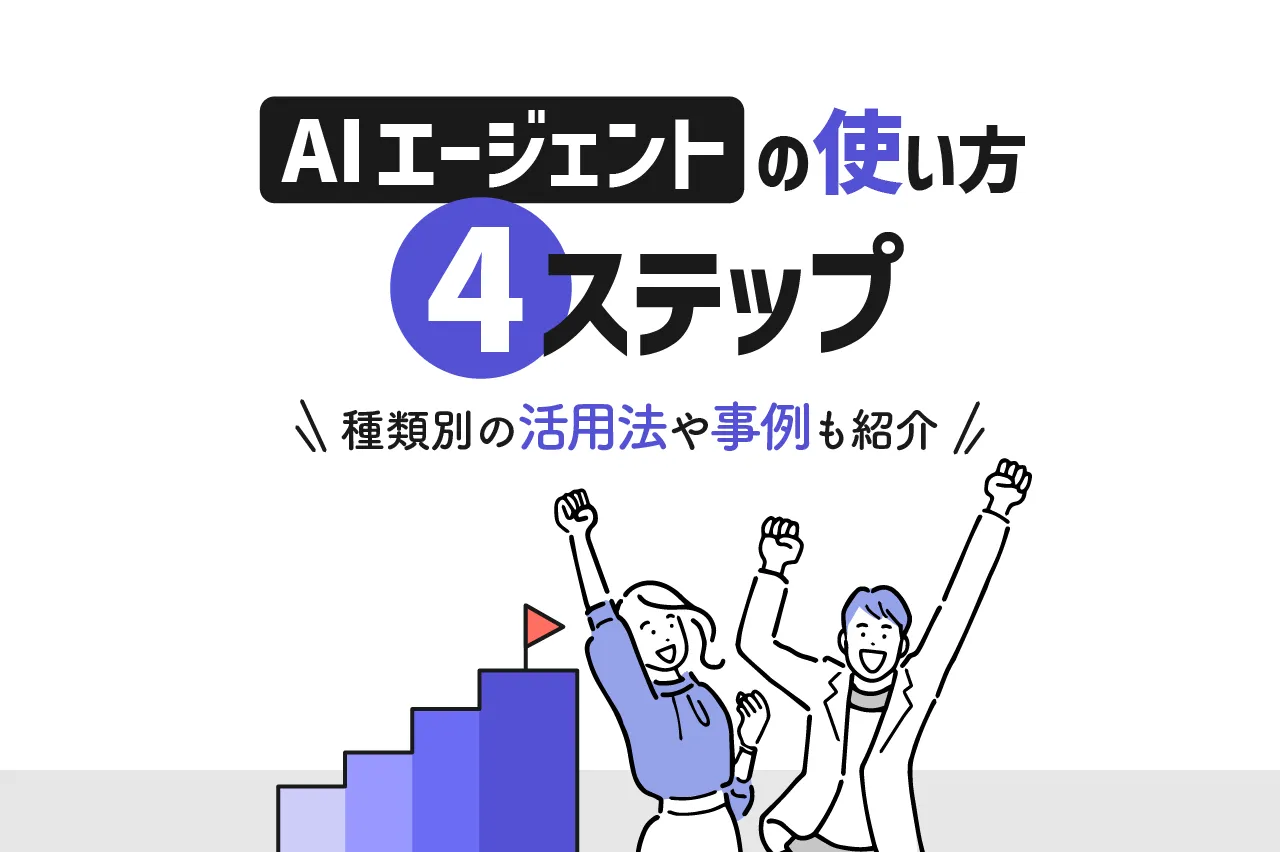生成AIビジネス利用のコツ!メリット・リスク・成功ポイントも詳しく紹介

しかし、「具体的にどのようにビジネスで活用すればよいのか」「導入によるリスクはないのか」といった不安から、実際に生成AIを業務に活かしている企業はまだ限られているでしょう。
本記事では、生成AIのビジネス利用シーン・メリット・リスク・成功ポイントを解説します。
生成AIを適切に活用することで、業務の効率化や新たな価値創出も可能ですので、生成AIをビジネス成長につなげたいとお考えの方はぜひご覧ください。
【目次】
■合わせて読まれている資料
利用者アンケートでビジネスツールの活用実態と課題を徹底調査しました!
利用者のリアルな声からツール選定や活用のヒントが見つかる資料です。
⇒「ビジネスツール利用調査2025」を無料ダウンロード
CrewWorks(クルーワークス)は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などの
仕事に使う機能が1つに統合されたビジネスコミュニケーションツールです。
AI議事録やAIアシスタントなど、生成AIを活用して業務効率化を促進するツールです。
https://crewworks.net/
生成AIのビジネス利用シーン

ここでは、生成AIのビジネス利用シーンについて、以下の7点を解説します。
- コンテンツ生成
- 情報収集・要約
- デザイン生成
- アイデア創出
- アプリ開発
- 顧客対応
- 社内QA
1つずつ見ていきましょう。
コンテンツ生成
生成AIのビジネス利用シーンの1つ目は、コンテンツ生成です。
生成AIは、記事や顧客向けの資料や企業SNSの投稿など、多様なコンテンツを短時間で自動生成できる革新的なサービスです。
例えば、企業コラム記事の下書きを作成し、企業の専門知識を活かした資料を迅速にまとめることもできます。SNSではターゲットに最適な投稿を量産できるなど、マーケティング効果を高めることも可能です。
生成AIは短時間で質の高いコンテンツを作成できる点が大きなメリットで、業務の効率化や情報発信の強化が期待できます。
ただし、生成AIが生成した内容は正確とは限らないので、人の目で最終チェックすることが不可欠です。
関連記事:生成AIの活用事例を徹底解説!ビジネスや自治体・学校教育への応用
情報収集・要約
生成AIのビジネス利用シーンの2つ目は、情報収集・要約です。
ビジネスの意思決定には、膨大な情報を素早く整理し、重要なポイントを抽出する力が求められます。
生成AIを活用すれば、ニュース記事、業界レポート、顧客レビューなど多様な情報源から必要なデータを自動収集し、短時間で要点をまとめることが可能です。
例えば、市場動向の調査や競合分析では、生成AIが複数の資料を横断的に解析し、キーワードやトレンドを抽出して簡潔に要約できます。
これにより、リサーチ時間を大幅に短縮し、効率的な意思決定を支援できるでしょう。ただし、生成AIが収集した情報が正確とは限らないため、人の目によるチェックが欠かせません。
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
デザイン生成
生成AIのビジネス利用シーンの3つ目は、デザイン生成です。
生成AIは、広告やプレゼン資料などのデザインを自動生成するなど、クリエイティブな業務を効率化できます。 例えば、SNS広告のバナーやプレゼン資料のスライドデザインを短時間で作成できます。
専門的なデザインスキルがなくても、視覚的に魅力的なコンテンツを簡単に作り出すことが可能です。企業カラーやフォントを指定すれば、統一感のあるデザインにできるでしょう。
生成AIがレイアウトを自動調整するため、視認性の高い資料の作成が可能で、提案資料やマーケティング施策の質を向上させます。
ただし、完全に生成AI任せにするのではなく、ブランドの意図に合ったデザインかを確認・調整することが重要です。
アイデア創出
生成AIのビジネス利用シーンの4つ目は、アイデア創出です。
新規事業の企画やマーケティング戦略の立案をするための「斬新なアイデアが欲しい」と思ったときに、生成AIはブレインストーミングのサポート役として、新しい発想や解決策を提示してくれます。
例えば、新商品のコンセプト作りでは、ターゲットに合わせたネーミングやキャッチコピーの提案が可能です。
さらに、マーケティング施策でも、過去のデータやトレンドを分析し、有効なプロモーション案を生成できます。
生成AIは人の思考を補完し、視点を広げることで、より創造的で実現可能なアイデアを生み出せるのが強みです。ただし、最終判断は人が行い、現実的な施策を立案しましょう。
関連記事:生成AIで壁打ちが劇的進化!おすすめツールとメリット・例・成功のコツまで解説
アプリ開発
生成AIのビジネス利用シーンの5つ目は、アプリ開発です。
生成AIを活用すれば、コードの自動生成や修正を行い、開発スピードを飛躍的に向上させることが可能です。
例えば、新機能の実装時、生成AIにプログラムのひな型作成を依頼すれば、エンジニアは修正やプログラム最適化に集中できます。
また、エラー修正やコードの最適化を生成AIで自動で行うことで、バグの発生を抑え、品質の高いアプリ開発を実現可能です。
繰り返しの多い作業や単純なコード記述を生成AIに任せれば、アプリ開発者はクリエイティブな業務に専念できます。
顧客対応
生成AIのビジネス利用シーンの6つ目は、顧客対応です。
顧客対応の迅速化と負担軽減を実現するため、今や多くの企業が生成AIを活用しています。特に、チャットボットやメール対応の自動化は、カスタマーサポートの効率を大幅に向上しています。
例えば、FAQに基づいた即時応答を行う生成AIチャットボットを導入すれば、顧客の問い合わせに24時間対応可能です。
また、メール対応では、適切な返信文を自動生成することで、迅速かつ一貫性のあるコミュニケーションを実現できます。
生成AIを利用すれば、対応時間の短縮や人的コストの削減が可能になり、オペレーターは高度な対応が求められるケースに集中できます。ただし、顧客からの複雑な問い合わせには人によるサポートが不可欠です。
関連記事:生成AIでナレッジマネジメントが劇的進化!活用メリットと注意点も解説
社内QA
生成AIのビジネス利用シーンの7つ目は、社内QAです。
社内問い合わせ窓口には従業員からの業務フローや手続きに関する質問が頻繁に発生するため、生成AIを活用した社内QAシステムを導入すれば、問い合わせ対応の効率が大幅に向上するでしょう。
例えば、「経費精算の手順は?」「社内システムのログイン方法は?」といったよくある質問に、AIが即時回答することで、従業員は業務をスムーズに進められます。
また、過去の問い合わせ履歴を学習させることで、より精度の高い回答を提供することも可能です。
これにより、総務・人事・IT部門の負担を軽減し、業務効率を向上できます。ただし、重要な手続きや例外対応には人による判断が必要です。
関連記事:社内ナレッジに生成AIを導入するときのポイントと注意点
生成AIをビジネスで利用するメリット

ここでは、生成AIをビジネスで利用するメリットについて、以下の4点を解説します。
- 業務効率化
- 人材不足解消
- 人的ミスの削減
- コスト削減
1つずつ見ていきましょう。
業務効率化
生成AIをビジネスで利用するメリットの1つ目は、業務効率化です。
生成AIを活用すれば、定型業務を自動化し、従業員がより価値の高い業務に集中できる環境を整えて業務効率化を実現することが可能です。
例えば、日報の作成やメール返信の自動化により、社員の手間を削減できます。また、データ分析では、AIが大量の情報を瞬時に整理し、必要なインサイトを抽出することで、意思決定のスピードを向上できるでしょう。
生成AIを活用することで、従業員は戦略立案やクリエイティブな業務に専念でき、企業全体の業務効率化につながります。
関連記事:業務効率化ツールとは?おすすめツール7選・種類・選び方を解説
人材不足解消
生成AIをビジネスで利用するメリットの2つ目は、人材不足解消です。
多くの企業が人材不足に悩んでいます。業務量が増加する中で十分な人手を確保できない場合、生成AIが従業員の補助的な役割を担うことで、限られた人材で業務をカバーすることが可能です。
例えば、顧客サポートではAIチャットボットが基本的な問い合わせに対応し、オペレーターの負担を軽減できます。
また、文書作成やデータ分析を自動化すれば、担当者の業務効率を向上させ、人材を有効活用できます。
生成AIを利用することで、少ないリソースでも業務の質を落とさず、生産性を維持・向上させることが可能です。
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
人的ミスの削減
生成AIをビジネスで利用するメリットの3つ目は、人的ミスの削減です。
生成AIを活用すれば、手作業によるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させることが可能です。
例えば、データ入力や数値計算をAIが自動処理すれば、人による転記ミスや計算間違いもなくなります。
また、AIが文章をチェックし、誤字脱字や表記の統一をサポートすることで、品質の高いドキュメントを作成できるでしょう。 生成AIを利用することで、従来の修正作業の手間が減ります。
コスト削減
生成AIをビジネスで利用するメリットの4つ目は、コスト削減です。
生成AIを活用すれば、業務の効率化や自動化を推進し、人件費や運用コストを抑えることも可能です。
例えば、定型業務を生成AIで自動化すれば、従来従業員が費やしていた単純作業の時間を削減できます。
これにより、従業員はより戦略的な業務に集中できるでしょう。また、カスタマーサポートにAIチャットボットを導入すれば、オペレーターの対応コストを削減しながら24時間稼働が可能となります。
さらに、データ分析やマーケティング施策を自動化することで、外部委託費や広告運用コストの削減も可能です。 生成AIを適切に活用することで、コストを最適化しながら、企業は競争力を向上できるでしょう。
関連記事:生成AIを仕事で活用!おすすめの使い方10選を事例とともに解説
CrewWorks(クルーワークス)は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などの
仕事に使う機能が1つに統合されたビジネスコミュニケーションツールです。
AI議事録やAIアシスタントなど、生成AIを活用して業務効率化を促進するツールです。
https://crewworks.net/
生成AIのビジネス利用時のリスク

ここでは、生成AIのビジネス利用時のリスクについて、以下の4点を解説します。
- 著作権問題
- 情報漏洩
- プライバシー侵害
- フェイクニュース生成
1つずつ見ていきましょう。
著作権問題
生成AIのビジネス利用時のリスクの1つ目は、著作権問題です。
生成AIは学習したデータに基づいてコンテンツを生成するため、既存の著作物に似た表現が生じる可能性があります。 例えば、生成した記事やデザインが他者の著作物と酷似していた場合、著作権侵害とみなされる恐れがあります。
特に、商用利用時には法的な問題に発展するリスクがあるため、慎重な対応が求められます。 このリスクを回避するためには、生成されたコンテンツを人の目でチェックすることを徹底し、オリジナリティを確保することが重要です。
また、生成AIの利用ポリシーを理解し、適切に運用することも、安全なビジネス活用につながります。
情報漏洩
生成AIのビジネス利用時のリスクの2つ目は、情報漏洩です。
生成AIに業務データを学習させると業務効率は向上しますが、利用サービスによっては入力した情報が外部に漏れるリスクがあるため、慎重な運用が求められます。
例えば、クラウドサービスとして公開されている生成AIに社内機密や顧客情報を入力すると、外部システムにデータが保存され、第三者にアクセスされる可能性があります。
適切なセキュリティ対策がなされていないインターネット上の生成AIでは、情報流出のリスクが高まるため注意が必要です。
このリスクを回避するためには、機密情報の取り扱いルールを明確化し、社内環境に適した生成AIを利用することが重要です。
さらに、セキュリティ対策が施された信頼性の高い生成AIを選定することで、安全な運用を実現できます。
プライバシー侵害
生成AIのビジネス利用時のリスクの3つ目は、プライバシー侵害です。
例えば、生成AIが顧客対応やデータ分析を行う際、誤って個人の名前や住所、取引履歴などを含む情報を生成し、公開してしまう可能性があります。
また、外部データを学習した生成AIが、過去の個人情報をもとに新たなデータを推測し、不適切に使用してしまうケースも考えられます。
このリスクを防ぐには、生成AIが取り扱うデータの管理を徹底し、機密情報を含むデータを安易に入力しないルールを設定することが重要です。
フェイクニュース生成
生成AIのビジネス利用時のリスクの4つ目は、フェイクニュース生成です。
生成AIは虚偽の情報を生成するリスクがある点に注意が必要です。学習データを基に文章を作成するため、事実と異なる情報や誤解を招く内容を生成し、それをそのまま利用してしまうと、企業の信頼を損なう可能性があります。
例えば、ニュース記事やレポートを生成する際、根拠のないデータや誤った情報が含まれることがあり、拡散されるとフェイクニュースの原因になりかねません。
また、誤った商品説明や市場動向のレポートが公表されると、企業の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、生成AIが生成した情報は必ず人が確認すること、信頼できる情報源と照合するプロセスを導入することが重要です。正しい情報の発信を徹底することで、企業の信頼性を維持しましょう。
関連記事:生成AIの活用で直面する7つの課題!解決のための施策も解説
生成AIのビジネス利用成功のポイント

ここでは、生成AIのビジネス利用成功のポイントについて、以下の3点を解説します。
- 目的に沿ったツール選定
- データ学習
- 従業員教育
1つずつ見ていきましょう。
目的に沿ったツール選定
生成AIのビジネス利用成功のポイントの1つ目は、目的に沿ったツール選定です。
適切な生成AIを選ぶことで、自社の目的に向かって効果的かつ効率的に活用でき、業務の最適化につながります。
例えば、コンテンツ作成を強化したい場合は文章生成AI、カスタマーサポートを自動化したい場合はチャットボットAIを活用すると、目的に沿った成果を得やすいでしょう。
また、プログラミングの効率化を求めるときはコード生成AI、データ分析を重視するときはAI解析ツールが適しています。
業務の課題を明確にし、それを解決できるツールを選定することが重要です。適切な選択をすることで、生成AIの導入効果を最大限に引き出せます。
データ学習
生成AIのビジネス利用成功のポイントの2つ目は、データ学習です。
生成AIを効果的に活用するためには、事前に適切なデータ学習を行うことが重要です。
特に、企業の業務に特化した情報を活用する場合、社内データを安全な環境で学習させることで、より実用的なAI運用が可能になります。
例えば、カスタマーサポートにAIを導入する場合、過去の問い合わせ履歴やFAQを学習させることで、より適切な回答ができるでしょう。
また、社内向けのAI活用では、業務マニュアルや社内ルールを学習させることで、従業員の業務サポートを強化できます。
関連記事:生成AIの社内データ活用術!学習法・メリット・デメリットも紹介
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
従業員教育
生成AIのビジネス利用成功のポイントの3つ目は、従業員教育です。
生成AIをビジネスに導入する際、従業員が適切に活用できるよう事前にトレーニングを行いましょう。
ツールの使い方や利用時の注意点をしっかりと教育することで、スムーズに導入でき、トラブルを最小限に抑えられます。
例えば、生成AIの基本操作や業務での具体的な活用方法をレクチャーすることで、従業員全員が効率的に生成AIを活用できるようになるでしょう。
また、生成AIが誤った情報を出力するリスクや、機密情報の取り扱いに関するガイドラインを明確にして提示することも大切です。
従業員教育では、定期的な研修やフィードバックを通じて、従業員が最新のAI活用スキルを身につけられるようにしましょう。
適切に教育を実施することで、生成AIを最大限に活用し、業務効率の向上やビジネスの成長につなげられます。
まとめ

今回は、生成AIをビジネス利用するシーン、メリット・リスク・成功ポイントを紹介しました。
生成AIをビジネスに利用すれば、業務効率化やコスト削減、人材不足の解消など、多くのメリットをもたらします。
一方で、著作権問題や情報漏洩、フェイクニュースの生成といったリスクもあるため、適切な管理と適したツール選択が不可欠です。
生成AIを導入するときは、目的に合ったツールを選び、信頼性のあるデータを学習させ、定期的に従業員教育を行いましょう。
生成AIは、使い方次第でビジネスの成長を加速させられる強力なサービスです。 本記事で紹介したメリット・リスク・成功ポイントを参考に、自社に合った導入・運用を進め、最大限の効果を引き出しましょう。
CrewWorks(クルーワークス)のAIアシスタント機能は、プロジェクトに蓄積されたチャット・Web会議・タスク・ファイルなどのコミュニケーション記録を参照し、的確な回答を提供します。
これにより、情報検索にかかる時間と手間を大幅に削減できます。 さらに、情報の要約機能により、検索結果を一つずつ確認する手間を省き、知りたい情報を瞬時に把握可能です。
また、プロジェクトの内容を元に新たなアイデアの壁打ちもでき、創造的な業務をサポートします。
CrewWorksに情報を集約することで、データの蓄積だけでなく、ナレッジとして効率的に活用でき、プロジェクトの成功を加速させます。
|
ビジネスツール利用調査2025
ビジネスコミュニケーションツールの活用実態と課題を徹底調査しました。
|