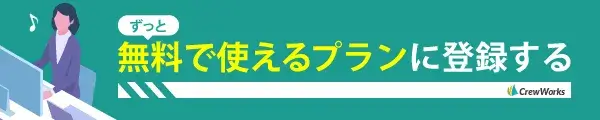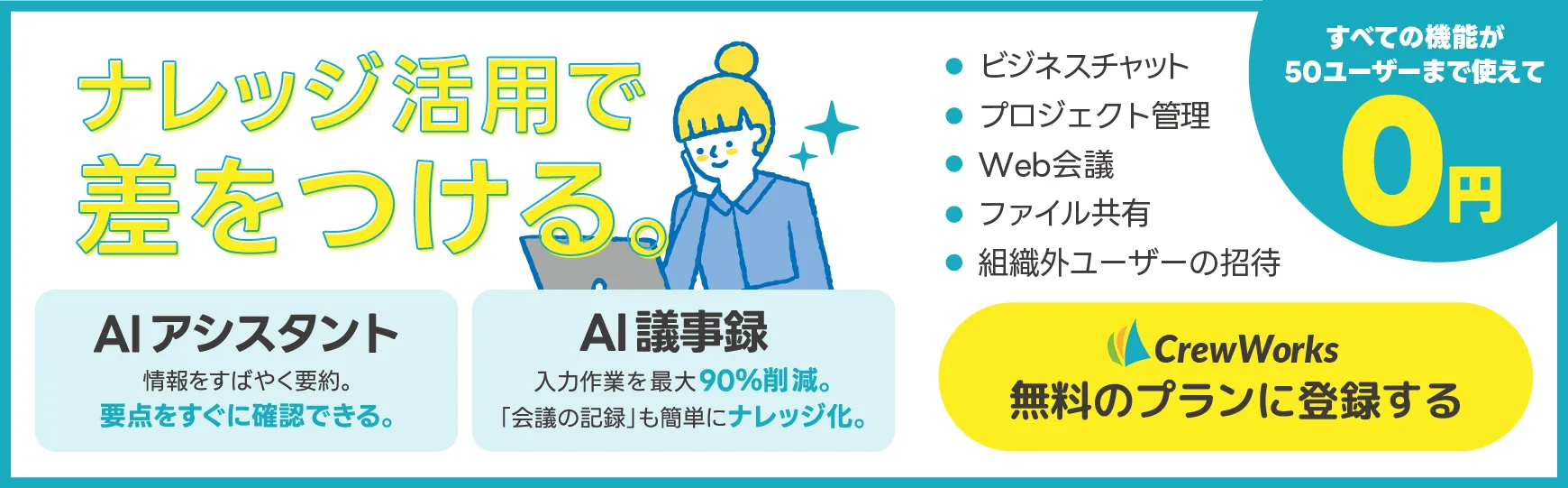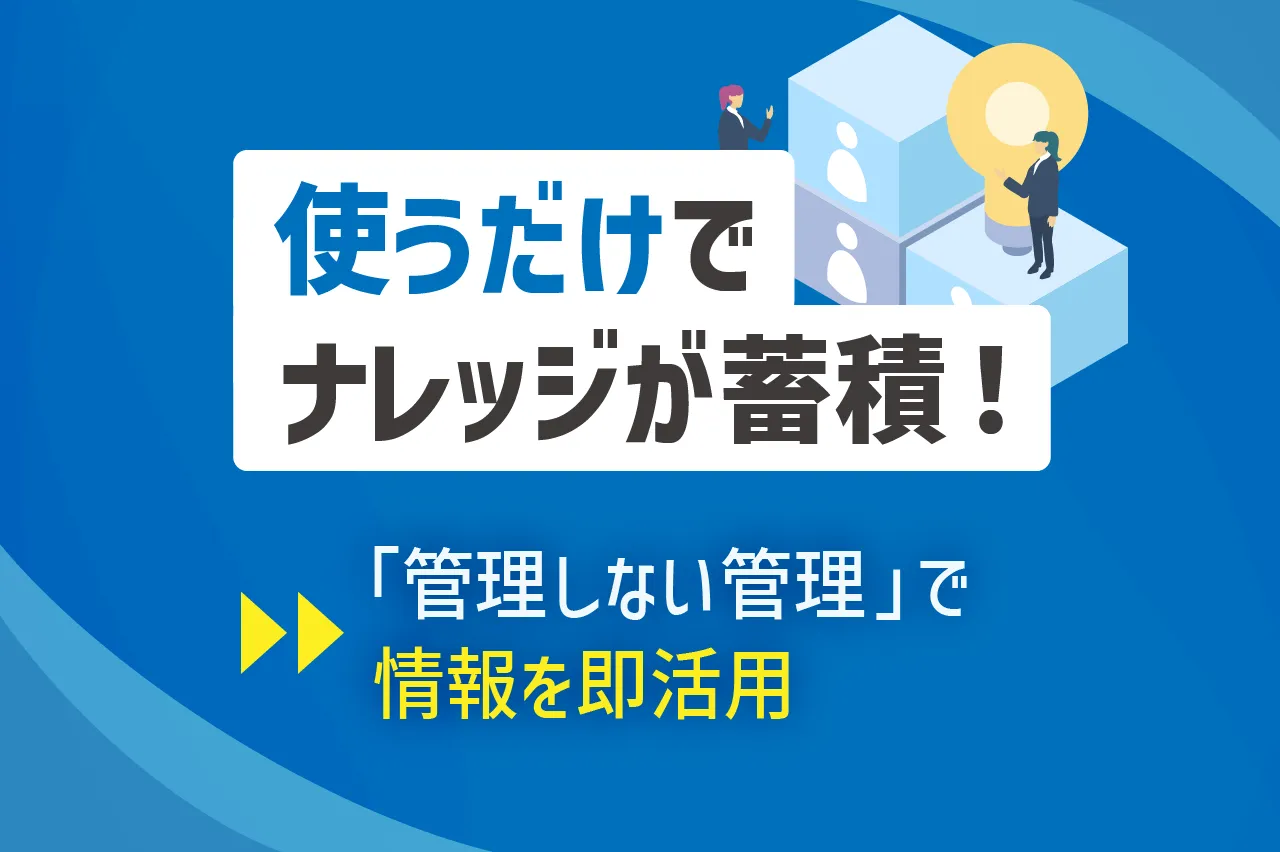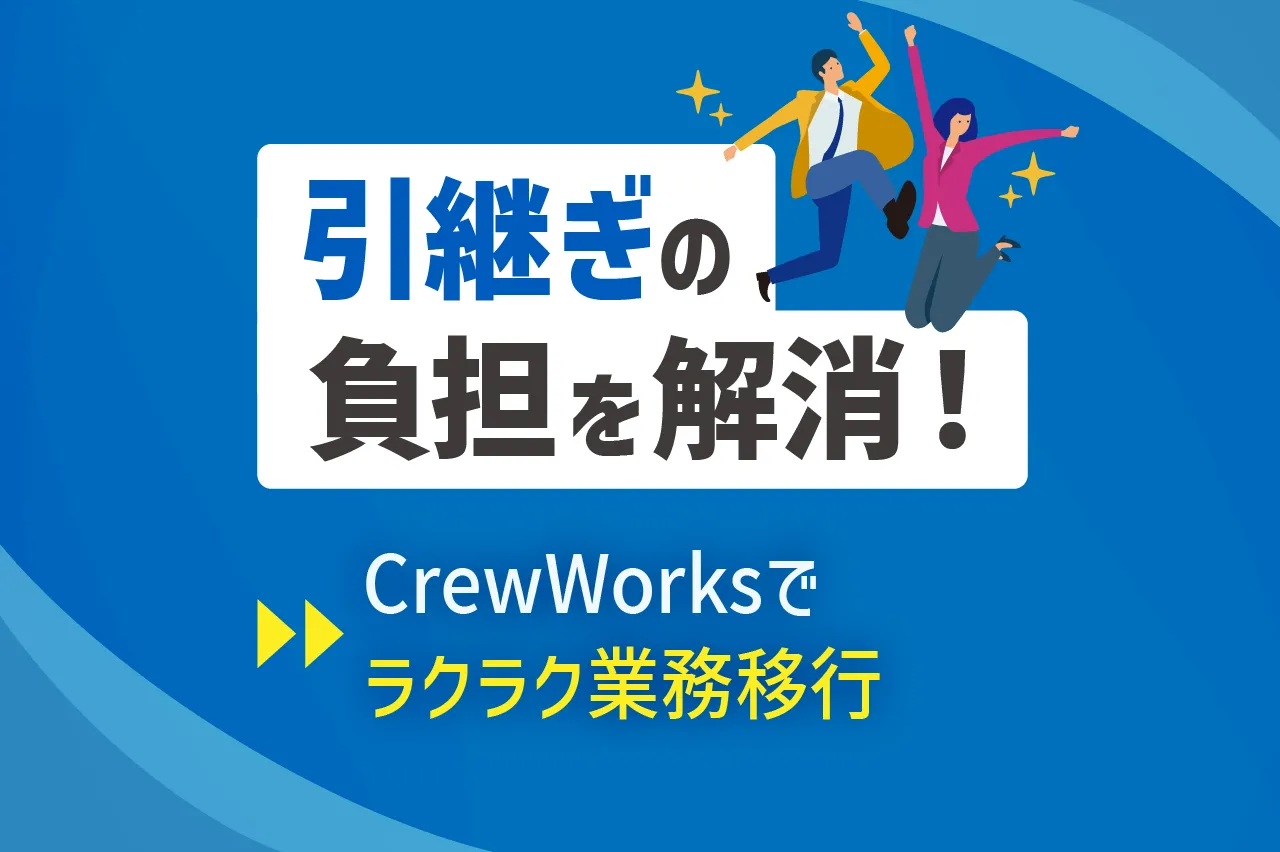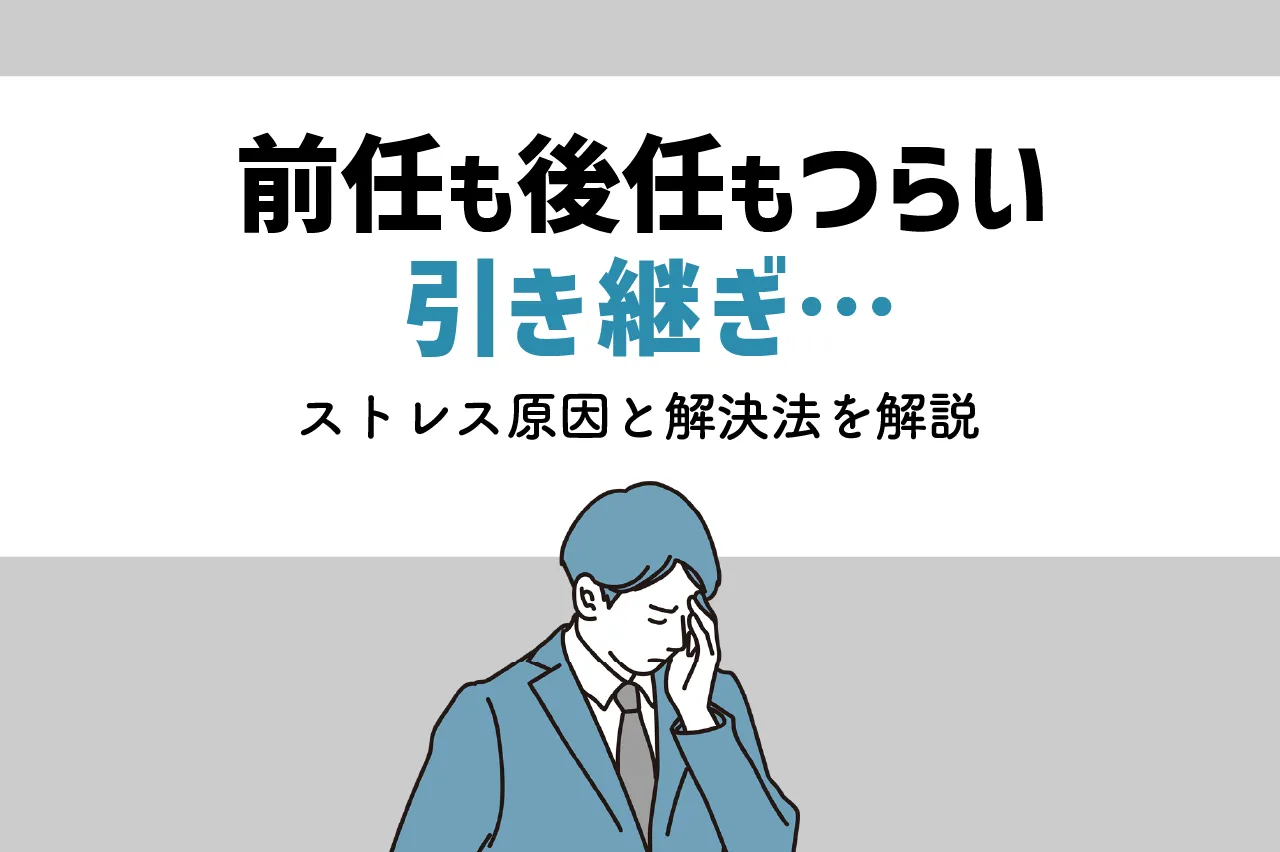社内ナレッジに生成AIを導入するときのポイントと注意点
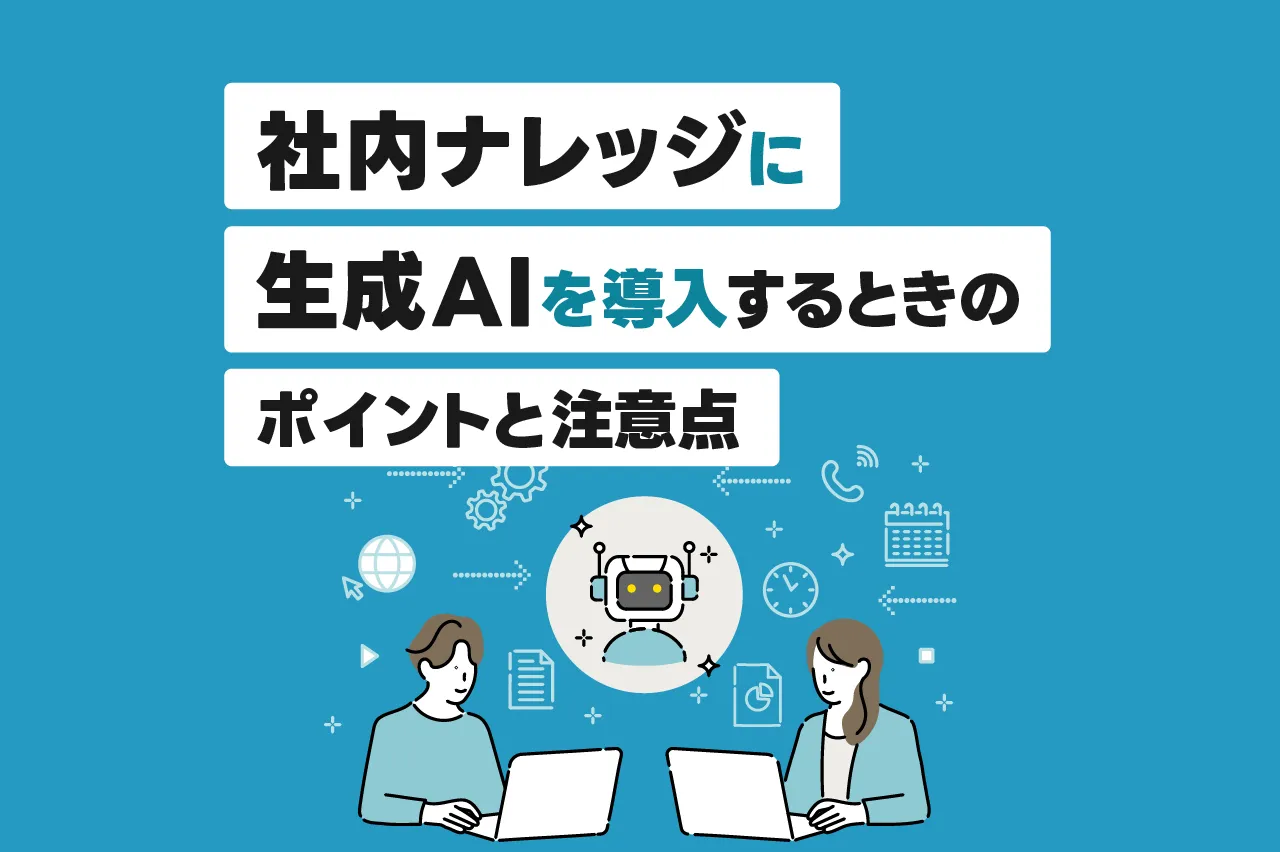
しかし実際には「ナレッジが社内にあるはずなのに、なぜすぐに見つからないのか?」「退職者の頭の中にあったノウハウは、どうすれば引き継げるのか?」といった課題に直面している企業も少なくありません。
このような課題を解決する手段として、近年注目されているのが、生成AIの活用です。
そこで今回は、社内ナレッジ管理における生成AIの活用方法やメリット、注意点、活用時のポイントについて詳しく解説します。
【目次】
■生成AIを利用して社内ナレッジを活用できるツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的なナレッジ活用ができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
社内ナレッジに生成AIを活用する方法

ここでは、社内ナレッジに生成AIを活用する方法について、以下の5点を解説します。
- 議事録の作成
- 議事録からのタスク抽出
- 業務の引き継ぎや情報共有
- アイデア出し
- ナレッジを元にしたFAQの作成
1つずつ見ていきましょう。
議事録の作成
社内ナレッジに生成AIを活用する方法の1つ目は、議事録の作成です。
生成AIを活用することで、Web会議や対面会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、議事録を作成できます。
従来の手動による議事録作成では、担当者が会議内容を聞きながらメモを取り、後から整理する必要がありました。
しかし、音声認識技術の向上により高精度な文字起こしができるようになったため、会議に参加している間にメモを取る必要はありません。生成AIを活用して自動化することで、大幅な時間短縮が可能です。
また、会話の流れを妨げずに本質的な議論を深められるため、より質の高い意思決定につながるでしょう。
さらに、議事録の形式や項目を事前に作成しておくことで、統一感のある読みやすい議事録を自動生成できるため、情報共有の質の向上も見込めます。
関連記事:【2025年版】AIで議事録作成をサポートするおすすめアプリ9選(無料で始められる)!
議事録からのタスク抽出
社内ナレッジに生成AIを活用する方法の2つ目は、議事録からのタスク抽出です。
会議中に決定した具体的な行動項目や担当者を自然言語処理技術を使って識別し、タスクリストとして出力することが可能です。
例えば、誰が何をいつまでに行うかといった情報を、AIが会議の内容から自動的に見つけ出して整理してくれます。
重要な決定事項やタスクの見落としを防ぐことができるため、チーム全体の業務の質が向上するでしょう。
会議が終わった後に「何を決めたのか思い出せない」という状況を避けられます。 また、生成AIから抽出したタスクは、自動でプロジェクト管理ツールに連携することも可能な場合があります。
社内で活用しているプロジェクトツールと連携させることで、複数のタスクを一元管理できます。プロジェクト全体の進捗状況を把握しやすくなり、チーム全体の生産性の向上にもつながるでしょう。
業務の引き継ぎや情報共有
社内ナレッジに生成AIを活用する方法の3つ目は、業務の引き継ぎや情報共有です。
従来の引き継ぎ方法では、前任者の記憶や個人的な経験に依存する傾向があり、属人的な解釈による認識のずれが課題となっていました。
例えば、業務手順の背景にある判断基準や、過去の意思決定プロセスが十分に伝達されないことも珍しくありません。
生成AIを活用すれば、業務プロセスや過去の対応事例、意思決定の経緯などを客観的かつ構造的に整理し、標準化された形式で記録できます。引き継ぎ期間の短縮と、業務の継続性が見込めるでしょう。
関連記事:生成AIの社内データ活用術!学習法・メリット・デメリットも紹介
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
アイデア出し
社内ナレッジに生成AIを活用する方法の4つ目は、アイデア出しです。
生成AIは、社内に蓄積した知識や過去の事例を活用して、業務の問題に対するさまざまな解決策を提案することも可能です。
過去の成功プロジェクトや、他の部署での解決方法、業界で効果的だった手法など、幅広い情報を組み合わせて新しいアプローチを提案してくれます。
例えば、営業部門で売上を伸ばしたい場合、過去の成功したキャンペーン施策の分析結果をもとに、新しい戦略を提案することも可能です。
また、生成AIは人間とは違う視点で分析するため、私たちが思いつかないような斬新なアイデアを見つけることもあります。
生成AIが会社の「知恵袋」として機能すれば、過去の経験や知識を最大限に活用して、新しい解決策を見つけ出せるでしょう。
関連記事:生成AIで壁打ちが劇的進化!おすすめツールとメリット・例・成功のコツまで解説
ナレッジを元にしたFAQの作成
社内ナレッジに生成AIを活用する方法の5つ目は、ナレッジを元にしたFAQの作成です。
生成AIは、社内のさまざまなデータから「よくある質問」を自動で見つけ出し、FAQ(よくある質問集)を作成することも可能です。これまでは、担当者が一つ一つ質問を集めて、答えを書く必要があり、手間も時間もかかる作業でした。
しかし、生成AIなら会話ログ、会議の記録、お客様からの問い合わせなどを自動で読み込んで、どのような質問が多いのかを見つけ出し、その回答も自動で生成できます。
さらに便利なのは、新しい質問が出てきたときも、AIが過去の情報から答えを探して回答を作ってくれることです。
例えば、社内で「有給休暇の申請方法は?」という質問が繰り返し寄せられている場合、AIが適切な回答とともにFAQを追加することも可能です。
FAQを最新の状態に保っておくことで、従業員は同じ質問に何度も答える必要がなくなり、本来の仕事に集中できるでしょう。質問する側も、すぐに答えが見つかるので待ち時間の減少が期待できます。
関連記事:生成AIでナレッジマネジメントが劇的進化!活用メリットと注意点も解説
社内ナレッジに生成AIを活用するメリット

ここでは、社内ナレッジに生成AIを活用するメリットについて、以下の3点を解説します。
- 検索の手間を減らして共有を迅速化できる
- ナレッジを整理して質を揃えられる
- 業務を効率化してコストを削減できる
1つずつ見ていきましょう。
検索の手間を減らして共有を迅速化できる
社内ナレッジに生成AIを活用するメリットの1つ目は、検索の手間を減らして共有を迅速化できることです。
生成AIを導入することで、必要な情報をすばやく検索・抽出でき、業務スピードが大幅に向上します。従来のキーワード検索では、適切な検索語を設定する必要がありました。
生成AIでは、自然言語処理により質問形式での検索が可能となり、より直感的に情報を探せます。
また、一度の検索で包括的な情報収集ができるため、複数のシステムを横断して情報を探す必要もありません。
長文の資料から重要なポイントを瞬時に把握できるため、意思決定のスピードアップにも貢献するでしょう。
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
ナレッジを整理して質を揃えられる
社内ナレッジに生成AIを活用するメリットの2つ目は、ナレッジを整理して質を揃えられることです。
生成AIを活用することで、従業員ごとの表現や形式のばらつきをなくし、ナレッジの質を均一化できます。
従業員が個々にナレッジベースに情報を書き込んでいると、個人の書き方や理解度によって資料の品質に差が生じることも珍しくありません。
生成AIを活用すれば、統一された形式やトーンで情報を整理することで、読みやすく理解しやすいナレッジベースが構築できます。
また、専門用語の説明や背景情報の補足を自動で追加する機能があるのも特徴です。異なる部署や経験レベルの従業員でも理解できる資料を作ることもできます。
定期的に生成AIを使って更新していくことで、組織全体の知識レベルの向上と属人化の防止が見込めるでしょう。
関連記事:生成AI活用によるナレッジベース作成法と成功のポイントを解説!
業務を効率化してコストを削減できる
社内ナレッジに生成AIを活用するメリットの3つ目は、業務を効率化してコストを削減できることです。
生成AIを導入することで、マニュアル作成や問い合わせ対応の自動化が実現し、人的コストや時間の大幅な削減が期待できます。
従来であれば専門知識を持つ担当者が個別に対応していた業務を、AIが24時間対応することで効率化が可能です。
また、繰り返し発生する質問に自動で回答できるため、従業員は本来の業務に集中できます。ナレッジを活用することで、新入従業員の教育期間の短縮も期待できます。
生成AIを活用することで、初期投資を上回るコスト削減と業務効率化が実現できるでしょう。
関連記事:コストを賢く削減する具体的な方法と手順・注意点を徹底解説!
社内ナレッジに生成AIを活用するときの注意点

ここでは、社内ナレッジに生成AIを活用するときの注意点について、以下の3点を解説します。
- 機密情報を守るセキュリティ対策
- 出力した内容を確認するチェック体制
- 社内研修を実施する
1つずつ見ていきましょう。
機密情報を守るセキュリティ対策
社内ナレッジに生成AIを活用するときの注意点の1つ目は、機密情報を守るセキュリティ対策です。
生成AIを社内ナレッジに活用するときには、機密情報や個人情報を含まないよう、厳格なセキュリティガイドラインの整備が不可欠です。
クラウド型のAIサービスを利用する場合、企業の重要な情報が外部のサーバーに送信されるリスクがあるため、データの暗号化や匿名化処理を徹底しましょう。
また、機密度に応じて情報の閲覧制限を設け、不正アクセスを防止することも大切です。定期的にセキュリティ監査や脆弱性の確認を実施し、最新の脅威に対応できる体制の整備も欠かせません。
自社に必要なセキュリティ対策を実施し、企業情報の漏洩リスクを最小限に抑えましょう。
出力した内容を確認するチェック体制
社内ナレッジに生成AIを活用するときの注意点の2つ目は、出力した内容を確認するチェック体制です。
生成AIの出力する内容には、誤りや不正確な情報が含まれる可能性があります。
そのため、人によるチェック体制の構築は欠かせません。AIが生成した文書や回答は、必ず担当者が内容を精査し、事実確認を行ってから公開・共有しましょう。
また、複数人によるダブルチェック体制を導入することで、見落としや主観的な判断によるミスを防止できます。そして、定期的にAIの出力精度を評価し、必要に応じて改善策を講じることも大切です。
チェック体制を強化することで、信頼性の高いナレッジベースの構築と運用が実現できます。
社内研修を実施する
社内ナレッジに生成AIを活用するときの注意点の3つ目は、社内研修を実施することです。
生成AIを効果的に活用するためには、全従業員が正しい使い方を理解し、適切に運用できるよう社内研修を実施しましょう。
生成AIの基本的な仕組みを理解してもらうことで、過度な期待や誤った使用方法を防止できます。
また、プロンプトの書き方や効果的な質問方法を習得することで、より精度の高い回答を得られるようになるでしょう。セキュリティリスクや倫理的な配慮事項についての教育も不可欠です。
定期的にフォローアップ研修会や事例共有会を開催することで、組織全体のAIリテラシー向上を図りましょう。
関連記事:生成AIの活用で直面する7つの課題!解決のための施策も解説
社内ナレッジに生成AIを活用するときのポイント

ここでは、社内ナレッジに生成AIを活用するときのポイントについて、以下の3点を解説します。
- 目的を明確化する
- 段階的に取り入れる
- 運用ルールを策定する
1つずつ見ていきましょう。
目的を明確化する
社内ナレッジに生成AIを活用するときのポイントの1つ目は、目的を明確化することです。
導入前に、業務効率化やナレッジ共有の強化、問い合わせ対応の自動化など、具体的な改善目標を設定しましょう。目的が明確になることで、AIツールの選定や必要な機能を特定できます。
また、各部署のニーズや課題を詳細に分析し、優先度の高い領域から段階的に導入することも重要です。
明確な目的を設定することで、組織全体でAI活用の方向性を共有し、一貫した取り組みを推進できるでしょう。
関連記事:AIアシスタントの使い方ガイド!成功するポイントや活用例をわかりやすく解説
関連記事:生成AIを仕事で活用!おすすめの使い方10選を事例とともに解説
段階的に取り入れる
社内ナレッジに生成AIを活用するときのポイントの2つ目は、段階的に取り入れることです。
生成AIの導入は、小規模な範囲から試験的に開始し、段階的に全社展開することで導入リスクを最小限に抑えることが可能です。
まずは、特定の部署やプロジェクトでパイロット運用を実施し、実際の効果や課題を検証しましょう。
この段階で得られた知見をもとに、運用方法の改善やツールの調整を行えば、より効果的な活用方法を確立できます。
各段階での成果を社内で共有し、全社展開をスムーズに進められるようにしましょう。
関連記事:生成AIビジネス利用のコツ!メリット・リスク・成功ポイントも詳しく紹介
運用ルールを策定する
社内ナレッジに生成AIを活用するときのポイントの3つ目は、運用ルールを策定することです。
効果的なAI活用を実現するためには、利用対象やプロンプト例、禁止事項などを明記した詳細なガイドラインを策定することが重要です。
具体的な使用方法を明文化することで、従業員が迷うことなく適切にAIを活用できます。例えば、どの情報をAIに入力してよいか、どのような質問形式が効果的かといったルールを策定しましょう。
また、セキュリティの要件や品質基準を明確に定義することも重要です。定期的に運用ルールの見直しを行うことで、リスク管理と継続的な改善を両立できるでしょう。
社内のコミュニケーションをAIでナレッジとして活用できるツール「CrewWorks」
CrewWorks(クルーワークス)は、チャット・タスク管理・Web会議・ファイル共有・プロジェクト管理といった仕事に必要な機能を1つにまとめた、統合型のコミュニケーションプラットフォームです。社内で行われるあらゆるコミュニケーションを一元的に管理し、生成AIを活用して蓄積された情報を「ナレッジ」として活用することが可能です。
特に注目すべきは、AIアシスタント機能です。過去のチャットや会議の記録、タスク履歴などをもとに、「この案件はどうなっているのか」「あの会議で何が決まったのか」といった質問に対して、AIが自然な言葉で答えてくれます。
まるで知識豊富な同僚に聞くような感覚で、必要な情報を素早く手に入れられるでしょう。
CrewWorksの特長
- AIアシスタントによる自動回答機能
- コミュニケーション記録の一元管理
- 参照情報への1クリックアクセス
詳細はこちら: https://crewworks.net/
まとめ

今回は、社内ナレッジ管理における生成AIの活用方法やメリット、注意点、活用時のポイントについて詳しく解説しました。
生成AIを社内ナレッジ管理に活用することで、議事録作成の自動化やタスク抽出、FAQ作成といった業務の改善が可能です。
一方で、セキュリティ対策やチェック体制の構築が必要になることも把握しておかなければなりません。
社内ナレッジ管理の課題を抱えている企業は、まず小規模な範囲から生成AIの試験導入を検討し、段階的に活用範囲を拡大してみてはいかがでしょうか。