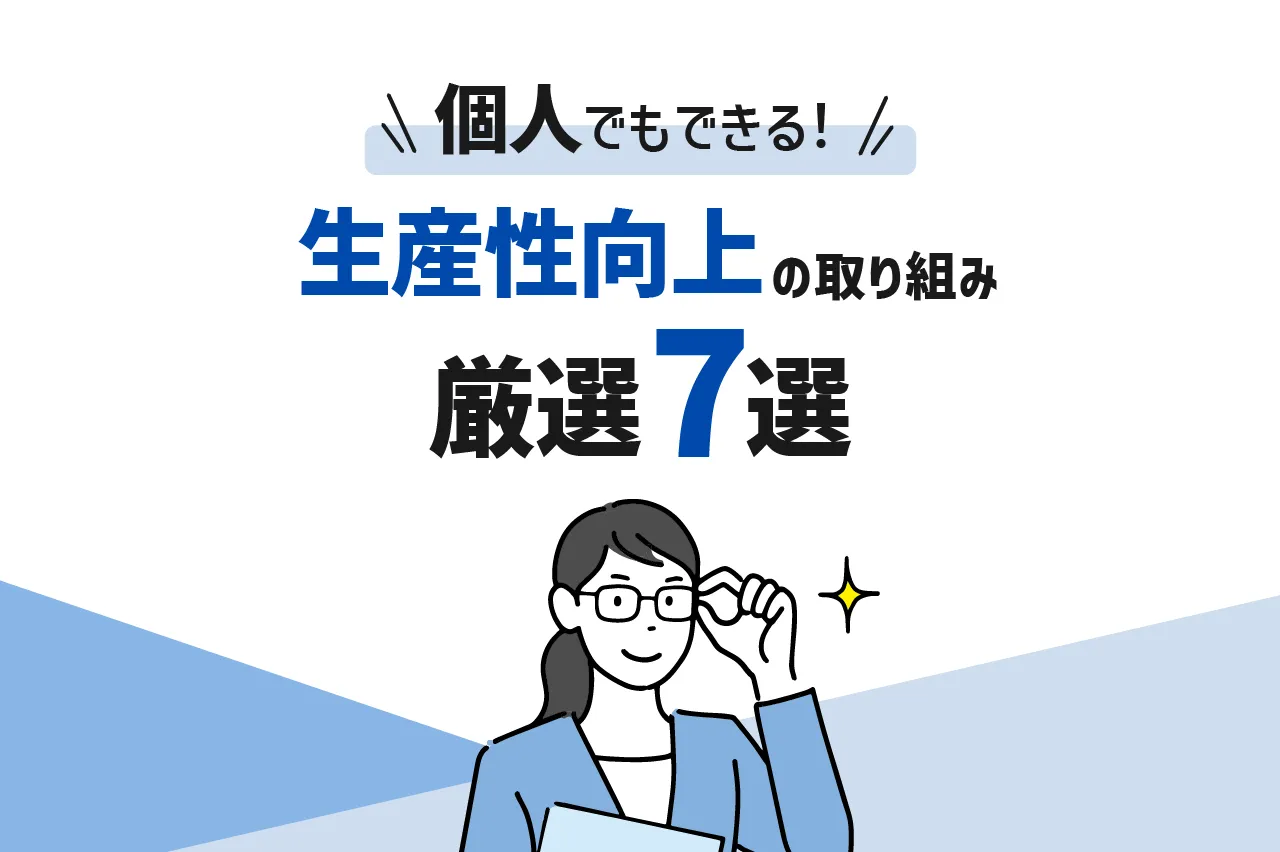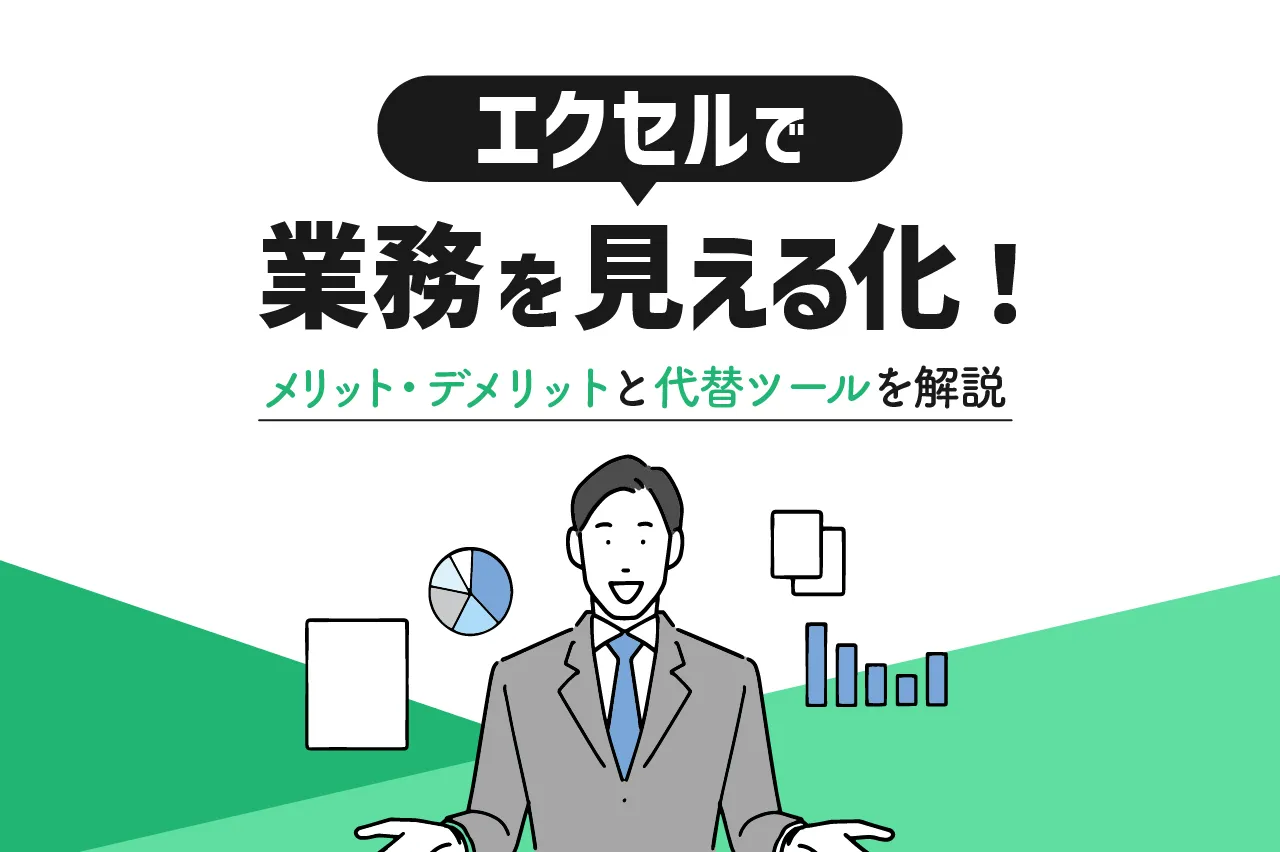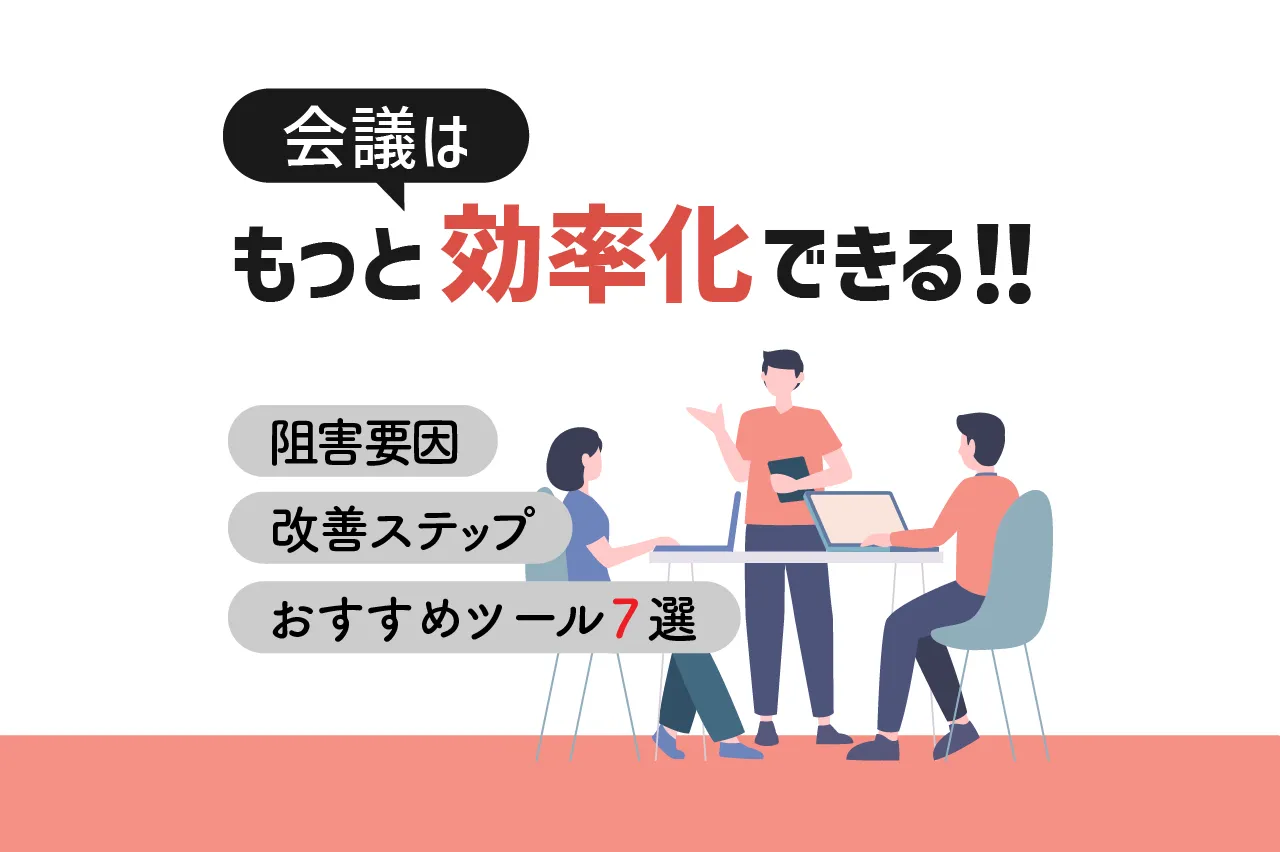全部管理しきれない!複数ツール連携による負担を減らすには
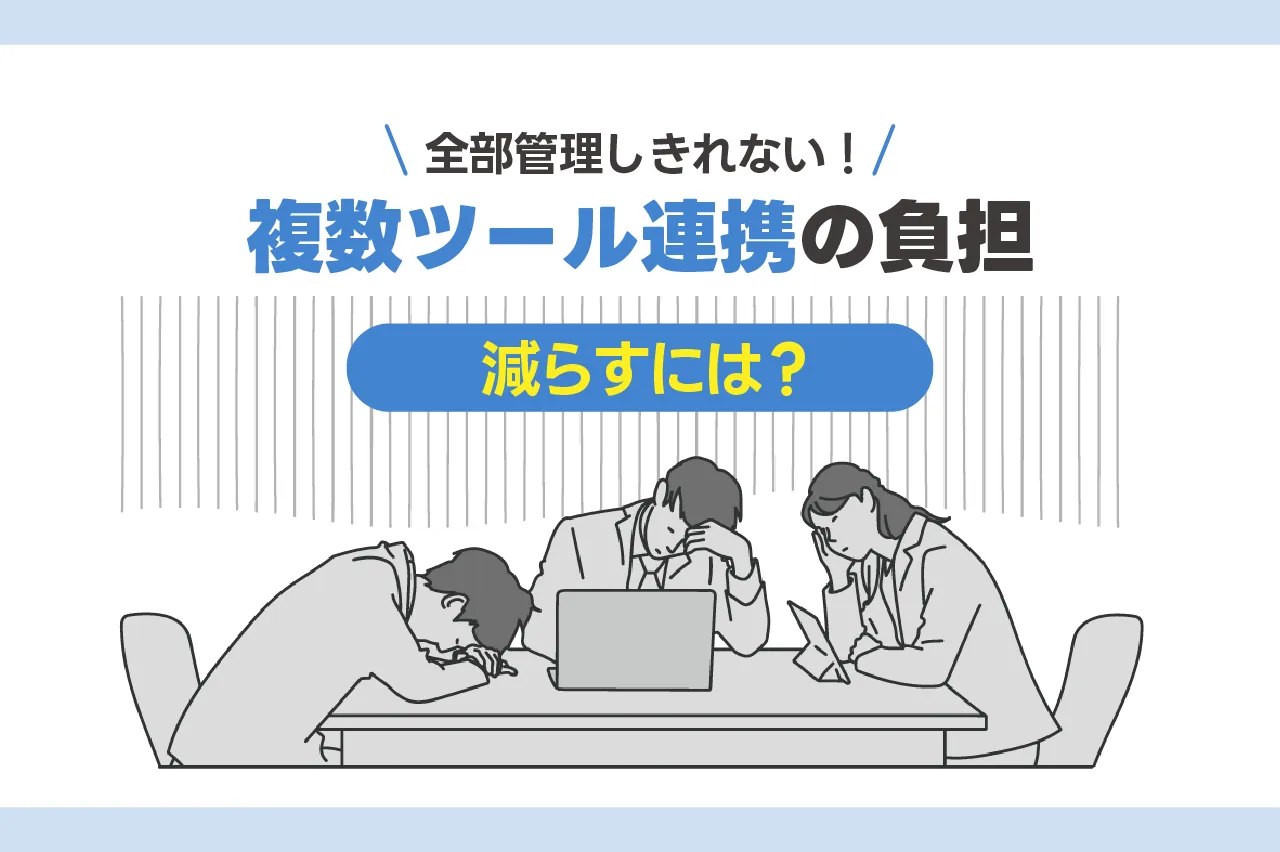
ただ、これらのツールは便利ではあるものの、情報が社内で散在する原因になり、情報活用を阻害することにもなりかねません。
情報の散在を防ぐ手段として有効なのが、ツール連携です。
ツール連携で情報の一元化を促進できますが、ツール連携にも課題があるので注意しましょう。
そこで今回は、ツール連携を行う理由や課題に加えて、よく使われるツール連携手法やそのポイントについて解説します。
【目次】
ツール連携を行う理由
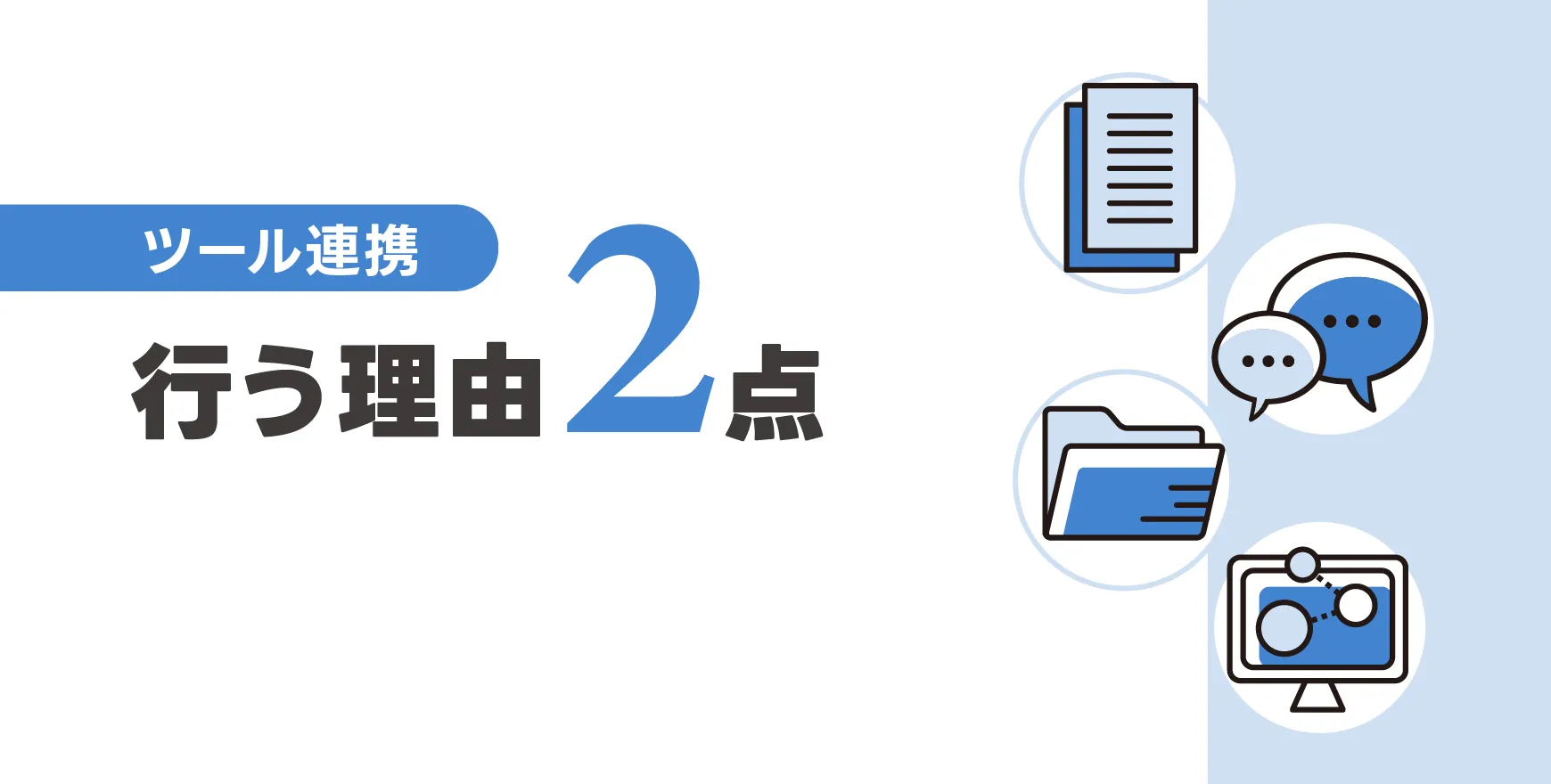
ここでは、ツール連携を行う理由について、以下の2点を解説します。
- 社内の現状把握を行う
- 情報の信頼性をアップさせる
1つずつ見ていきましょう。
社内の現状把握を行う
ツール連携を行う理由の1つ目は、社内の現状把握を行うことです。
ETLツールなどでシステム連携を進めることで、リアルタイムでの経営データ分析が可能となり、従来どおり手作業でデータ集計をせずとも、簡単にデータ分析ができます。
これにより、変動費の即時集計や棚卸資産の状況把握など、管理会計や予実管理の効率化が可能です。
また、データドリブンな経営判断を迅速に行うことができ、企業の意思決定プロセスも大幅に改善できるでしょう。
情報の信頼性をアップさせる
ツール連携を行う理由の2つ目は、情報の信頼性をアップさせることです。
ツール間の連携不足があると、企業の情報管理において深刻な課題を引き起こします。例えば、異なるシステムでデータが分散管理されると、データが最新かつ正確である保証がありません。
また、システムメンテナンスを怠れば、古いデータや誤ったデータが混ざり込む可能性が高まるでしょう。さらに、複数システム間でデータを手作業で転記すると、転記ミスで正確な情報を残せないケースがあります。
これらの課題を解決するためには、ETLツールなどを活用したデータの一元管理が不可欠で、それが結果的に組織の情報品質を向上させます。
ツール連携でよくある課題
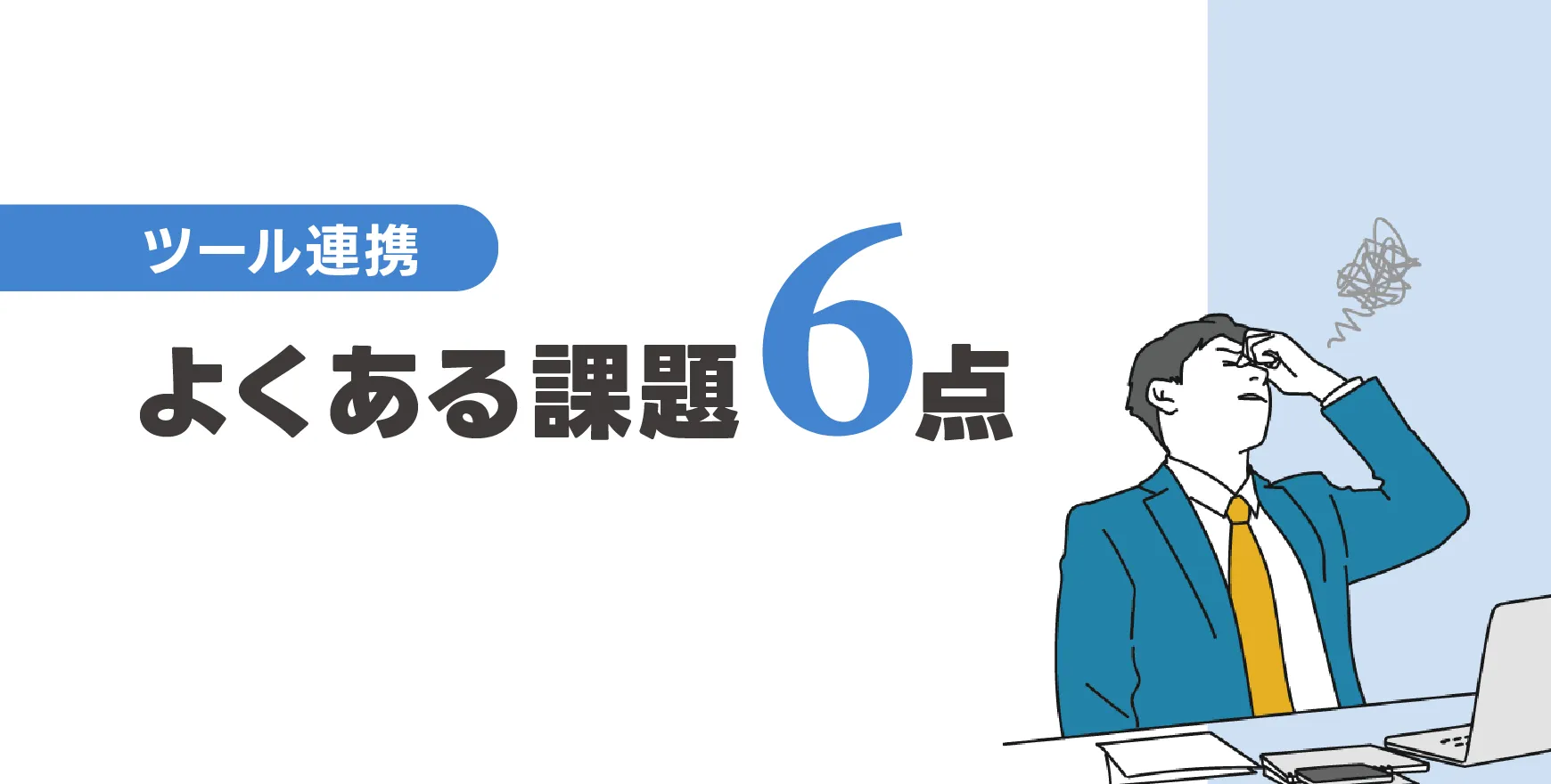
ここでは、ツール連携でよくある課題について、以下の6点を解説します。
- 連携作業中にデータ損失・不具合が発生する
- 連携作業中にツール運用に支障が出る
- 追加でコストがかかる
- 複雑なシステムではブラックボックス化する
- 連携したいサービスと連携できない
- クラウド・オンプレミス間ではさらに複雑になる
1つずつ見ていきましょう。
連携作業中にデータ損失・不具合が発生する
ツール連携でよくある課題の1つ目は、連携作業中にデータ損失・不具合が発生することです。
大規模にツール連携を行うには複雑なプロセスが必要で、情報の消失や漏えいのリスクが否めません。特に旧システムのデータが失われる可能性があるため、慎重な計画とテスト、適切なバックアップ対策が重要です。
連携作業中にツール運用に支障が出る
ツール連携でよくある課題の2つ目は、連携作業中にツール運用に支障が出ることです。
ツール連携作業中には、各種ツールが使えなくなり一時的に運用が中断する可能性があります。
また、新システムへの移行期間は業務プロセスが変更され、従来の運用方法が通用しないため、効率が低下するリスクもあるでしょう。
追加でコストがかかる
ツール連携でよくある課題の3つ目は、追加でコストがかかることです。
追加コスト・ランニングコストの増大も課題になるでしょう。システム統合には、打ち合わせ・設計・テストなど、膨大な工数が必要となるため、人的・時間的・費用的コストが大幅に増加する恐れがあります。
また、統合後の運用には新たな管理や保守が必要となり、継続的にコストが増加するかもしれません。
複雑なシステムではブラックボックス化する
ツール連携でよくある課題の4つ目は、複雑なシステムではブラックボックス化することです。
データ連携プログラムがブラックボックス化すると、特定の技術者以外プログラムを取り扱えず、深刻な問題となります。
TCP/IPによるファイル転送でデータ連携を行う場合、プロジェクトごとにフレームワークや開発言語が異なると、細かい作業が続いて作業が属人化しがちです。
そうなると、仕様変更時の対応や、トラブル発生時の迅速な解決が困難になります。
連携したいサービスと連携できない
ツール連携でよくある課題の5つ目は、連携したいサービスと連携できないことです。
特にブラックボックス化したプログラムでは、新たに連携したいサービスやアプリケーションとうまく連携できない可能性が高いでしょう。
また、連携を成功させるために余計なコストがかかることにもなりかねません。そのような事態を防ぐには、最初から新規サービスの追加を前提に、データ連携基盤を準備することが必要です。
クラウド・オンプレミス間ではさらに複雑になる
ツール連携でよくある課題の6つ目は、クラウド・オンプレミス間ではさらに複雑になることです。
企業の中には、既存のオンプレミスサービスとクラウドサービスを併用するケースも珍しくありません。
しかし、オンプレミスサービスは社内システムに応じて柔軟にカスタマイズしやすい分、新規のクラウドサービスとの連携が容易ではないケースがあります。その場合、連携に手間がかかる可能性が高まるでしょう。
ツール連携でよく使われる手法

ここでは、ツール連携でよく使われる手法について、以下の3点を解説します。
- ファイル転送
- メッセージ連携ツール
- Web API
1つずつ見ていきましょう。
ファイル転送
ツール連携でよく使われる手法の1つ目は、ファイル転送です。
ファイル転送は、サーバー間でCSVなどのファイルをFTPやSMBなどの通信方式で送受信する仕組みです。送信側のシステムが必要な情報をファイル出力し、受信側のシステムがそのファイルをインポートすることで連携を行います。
既存システムに情報の出力入力機能があれば、追加開発なしで比較的容易に連携できますが、連携したい情報が確実に扱えるかは既存システムの仕様によります。
大量データの連携には向いているものの、リアルタイム連携には向いていません。
そのため、多くの場合は一定間隔かつ定期的な連携に用いられます。FTPプロトコルを利用すれば、システムプログラムを変更する必要がなく、システム障害に強い点がメリットです。
ただ、サーバーが増えると処理速度が低下する点には注意しなければなりません。
メッセージ連携ツール
ツール連携でよく使われる手法の2つ目は、メッセージ連携ツールです。
メッセージ連携ツールは、メッセージキューを活用してアプリケーション間でデータをやり取りする方法です。送信されたデータは第三者のソフトウェアのキュー(データ領域)に一時保存され、受信者が自分のタイミングでデータを取り出せます。
メッセージがキューに保存された時点で送信完了となるため、受信処理を待つ必要がありません。そのため、特に非同期処理が求められるシステムに適しています。
受信側は柔軟なタイミングでデータを受け取れるため、システム負荷を分散させやすい点が特徴です。
Web API
ツール連携でよく使われる手法の3つ目は、Web APIです。
「Web API」は、HTTPやHTTPSの標準技術でアプリケーション連携を行う手法です。XMLなどの形式でメッセージをやり取りし、SOAPやRESTなどのプロトコルを使用します。
Web APIの大きな利点は、システム内部に精通していない人でもシステム連携が可能である点です。社外の関係者に社内システムのアプリケーションを提供でき、リモートワークの推進にも有用です。
SOAPは軽量なデータ交換プロトコルで、データ構造のみを規定しておりHTTP・SMTPに対応しています。
RESTは、Webの仕組みをそのまま利用できるアーキテクチャで、Webアプリケーションやソーシャルゲームなど幅広い分野で活用可能です。
ツール連携を確実に成功させるポイント
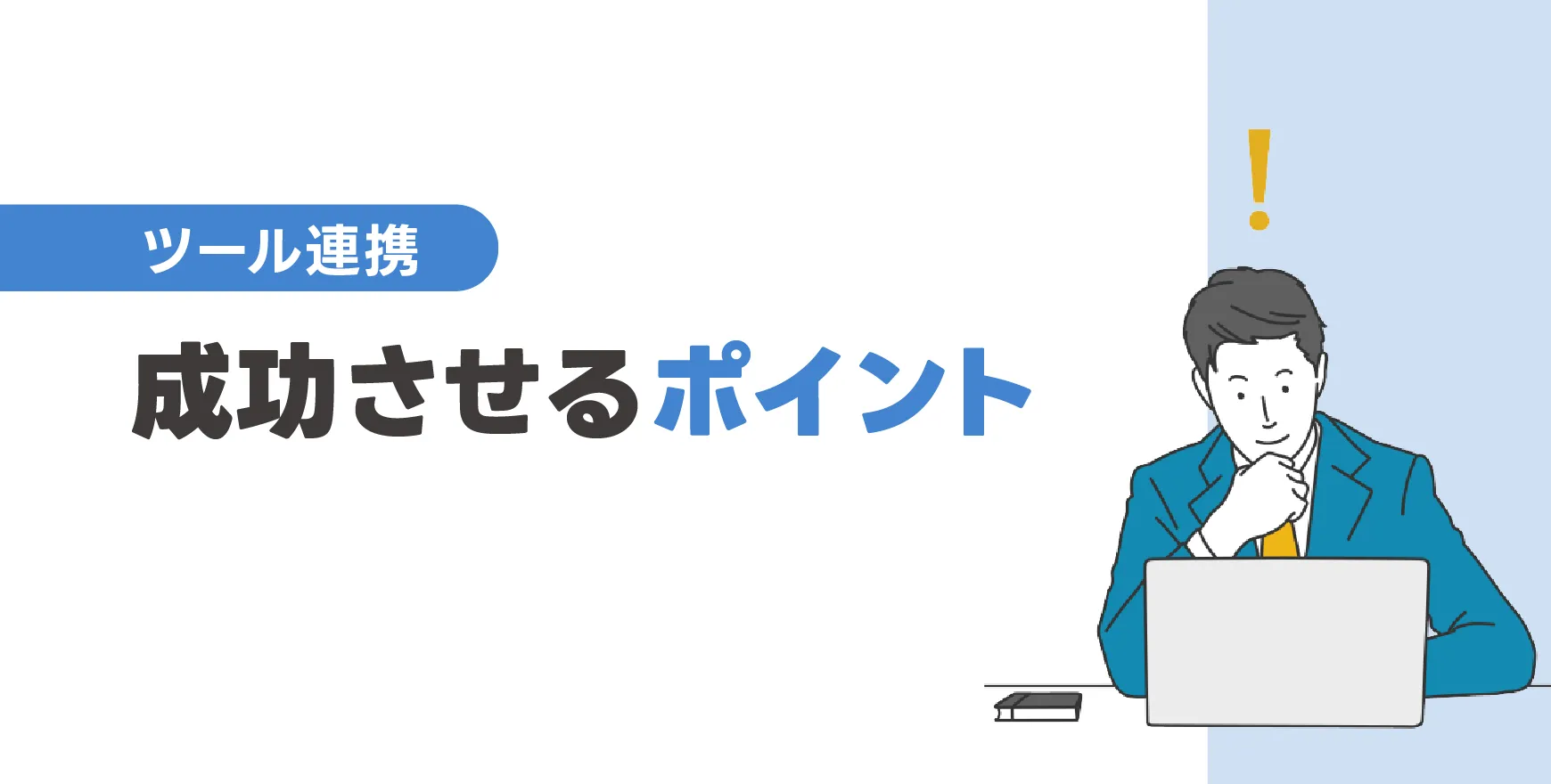
ここでは、ツール連携を確実に成功させるポイントについて、以下の6点を解説します。
- 導入目的を明確化する
- 適切な予算の範囲内でツール連携を行う
- 解決したい課題を洗い出す
- 使いやすいツールと連携する
- ツール管理体制を整備する
- 教育期間を確保する
1つずつ見ていきましょう。
導入目的を明確化する
ツール連携を確実に成功させるポイントの1つ目は、導入目的を明確化することです。
企業によって必要なツールは異なりますが、ツール連携で解決したい課題や期待する効果を目的として具体的に定義しましょう。必要な機能を洗い出してツール連携すれば、現場への定着も早まります。
適切な予算の範囲内でツール連携を行う
ツール連携を確実に成功させるポイントの2つ目は、適切な予算の範囲内でツール連携を行うことです。
優れたツールでも、導入の結果予算オーバーして資金繰りを圧迫してはなりません。まずは適切な予算の範囲内でツールを選び、その中で最大の成果を期待できる方法がおすすめです。
解決したい課題を洗い出す
ツール連携を確実に成功させるポイントの3つ目は、解決したい課題を洗い出すことです。
ツール導入担当者だけでなく、実際に業務を遂行する現場の声も十分聞き取り、ツール連携で解決したい課題を洗い出しましょう。
現場の要望や不満を特定し、それに優先順位をつければ自ずとツール導入で解決したい課題が見えてきます。
使いやすいツールと連携する
ツール連携を確実に成功させるポイントの4つ目は、使いやすいツールと連携することです。
ツールは毎日使うものが多く、どれだけ高機能なツールでも使いにくいと従業員に使ってもらえず、思うような効果を得られません。
そのため、ツールの使いやすさにも注目し、誰もが理解しやすく、操作が簡単なシステムを選びましょう。
ツール管理体制を整備する
ツール連携を確実に成功させるポイントの5つ目は、ツール管理体制を整備することです。
ツール連携の前後には多かれ少なかれトラブルが発生するもので、そのトラブルを未然に防止することと、トラブルが発生してもすぐに対処することが必要です。
そのため、管理体制の整備も忘れてはいけません。専門知識を持つ担当者の確保に加え、障害発生時の対応方法やセキュリティ対策を事前に検討しておきましょう。
教育期間を確保する
ツール連携を確実に成功させるポイントの6つ目は、教育期間を確保することです。
導入後の教育期間も十分確保しましょう。これは、全ての従業員が連携したツールを使いこなせないと、その効果は十分得られないためです。
全従業員がシステムを正しく使えるよう、部門ごとに代表者を決めて丁寧に教育することが必要です。これにより、スムーズな移行が可能となります。
複雑な連携作業不要のオールインワンツール「CrewWorks」
ここまでツール連携について解説してきましたが、最初から多機能のオールインワンツールを活用することも一手です。オールインワンツールは多数のベンダーが提供していますが、その中でもおすすめのツールがCrewWorks(クルーワークス)です。
ここでは、CrewWorksの強みについて、以下の3点を解説します。
- ビジネスに必要なツールをこれひとつで
- ツールの学習コスト削減
- 連携不要で管理者の手間もかからない
1つずつ見ていきましょう。
ビジネスに必要なツールをこれひとつで
CrewWorksの強みの1つ目は、ビジネスに必要なツールをこれひとつでカバーできることです。
CrewWorksは、タスク管理・Web会議・チャット・ファイル共有など、ビジネスシーンで役立つ様々な機能が用意されています。
そのためツール連携をしなくても、仕事に必要なツールをこれひとつに集約できると言えるでしょう。
ツールの学習コスト削減
CrewWorksの強みの2つ目は、ツールの学習コスト削減です。
CrewWorksには様々な機能がありますが、操作方法や画面については機能ごとに大差はありません。
また、シンプルで分かりやすい機能だけを集めているため、画面を見ただけで直感的に操作することも可能です。そのため、ツールの学習コスト削減に寄与します。
連携不要で管理者の手間もかからない
CrewWorksの強みの3つ目は、連携不要で管理者の手間もかからないことです。
CrewWorksを使えばビジネスに必要なツールをこれひとつでカバーできるため、外部ツールとの連携は不要です。また、複数のツールを利用する場合、それぞれ異なるセキュリティ設定を行う必要があります。
セキュリティ対策が不十分なツールが含まれると、情報漏洩などのセキュリティリスクも高まります。
各種ツールが統合されたCrewWorksは煩雑なセキュリティ管理は不要です。その分、管理者の手間もかかりません。
まとめ
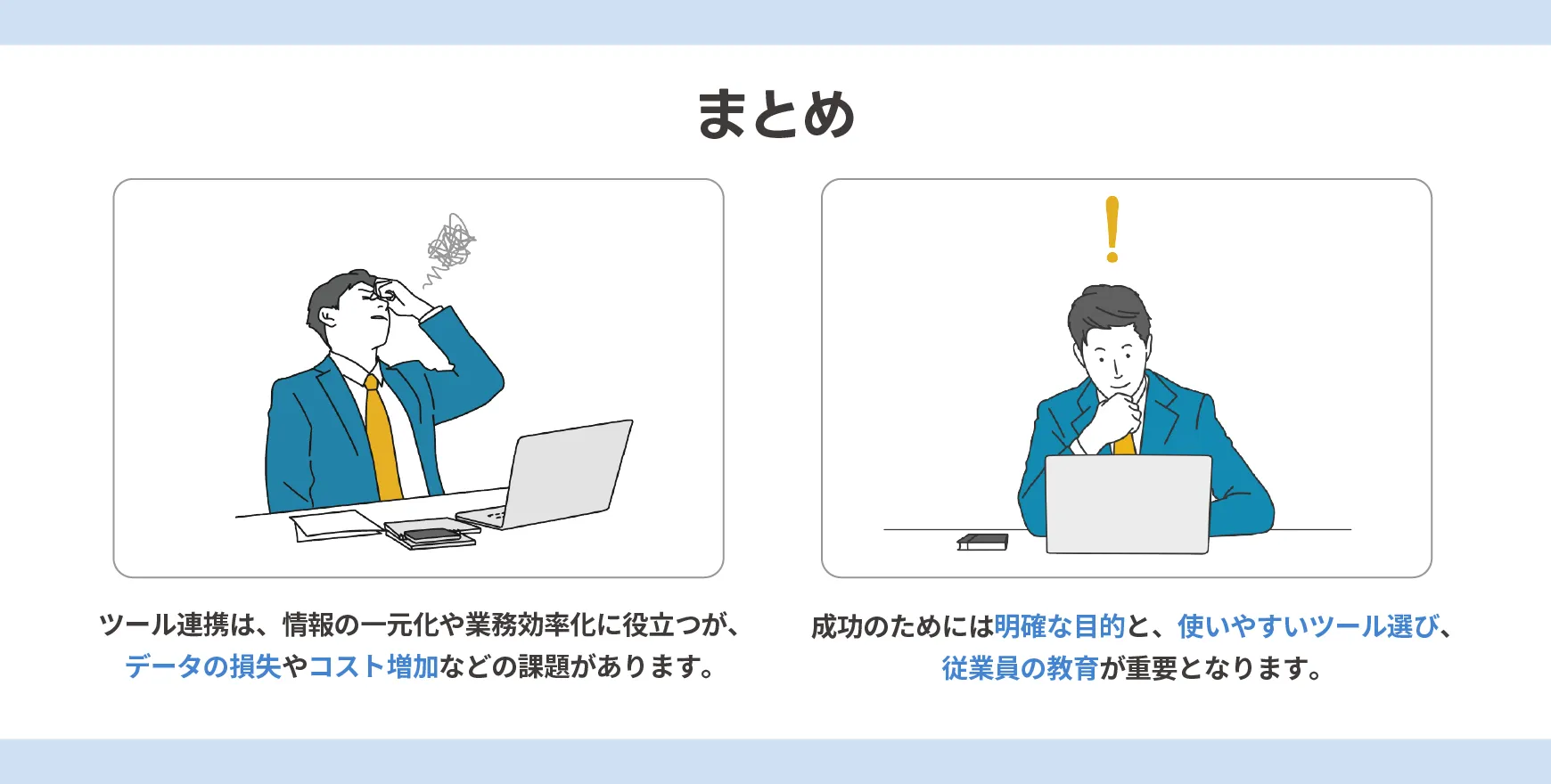
今回は、ツール連携を行う理由や課題に加えて、よく使われるツール連携手法やそのポイントについて解説しました。
ツールの連携は情報管理の観点では有用ですが、連携作業中にツール運用に支障が出るなど課題も少なくありません。 ツール連携では、ファイル転送などの方法を活用します。
また、導入目的を明確化し、教育期間を確保するなどポイントを抑えれば、成功する確率が高まるでしょう。
ただ、ツール連携は少なからず手間になることは事実です。そのような手間をなくすには、オールインワンツールの活用も検討しましょう。
オールインワンツールのCrewWorks(クルーワークス)は、50ユーザーまで無料のフリープランもあるのでお気軽にお試しください。