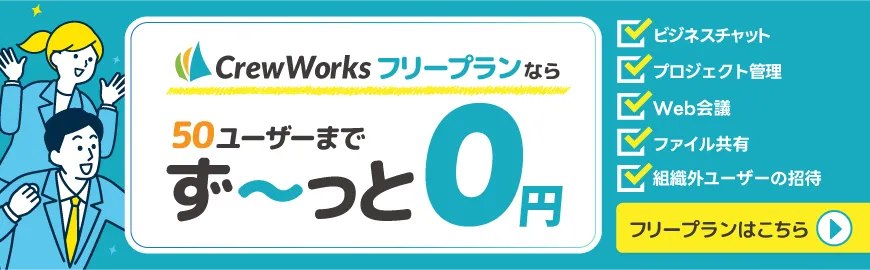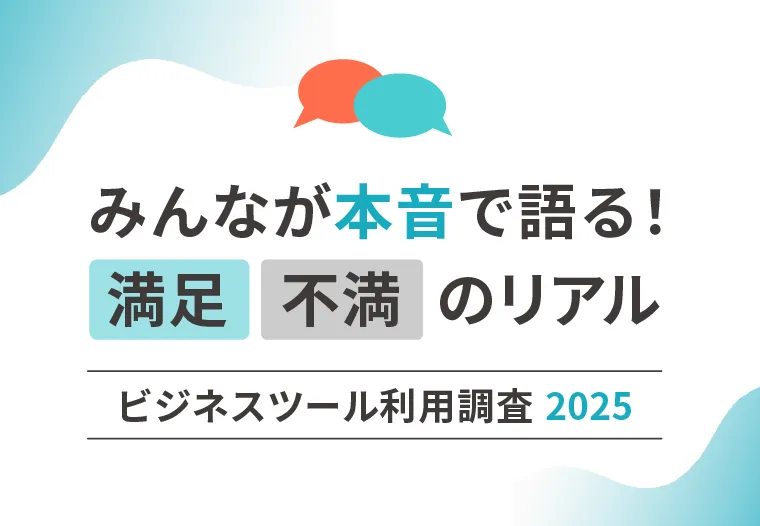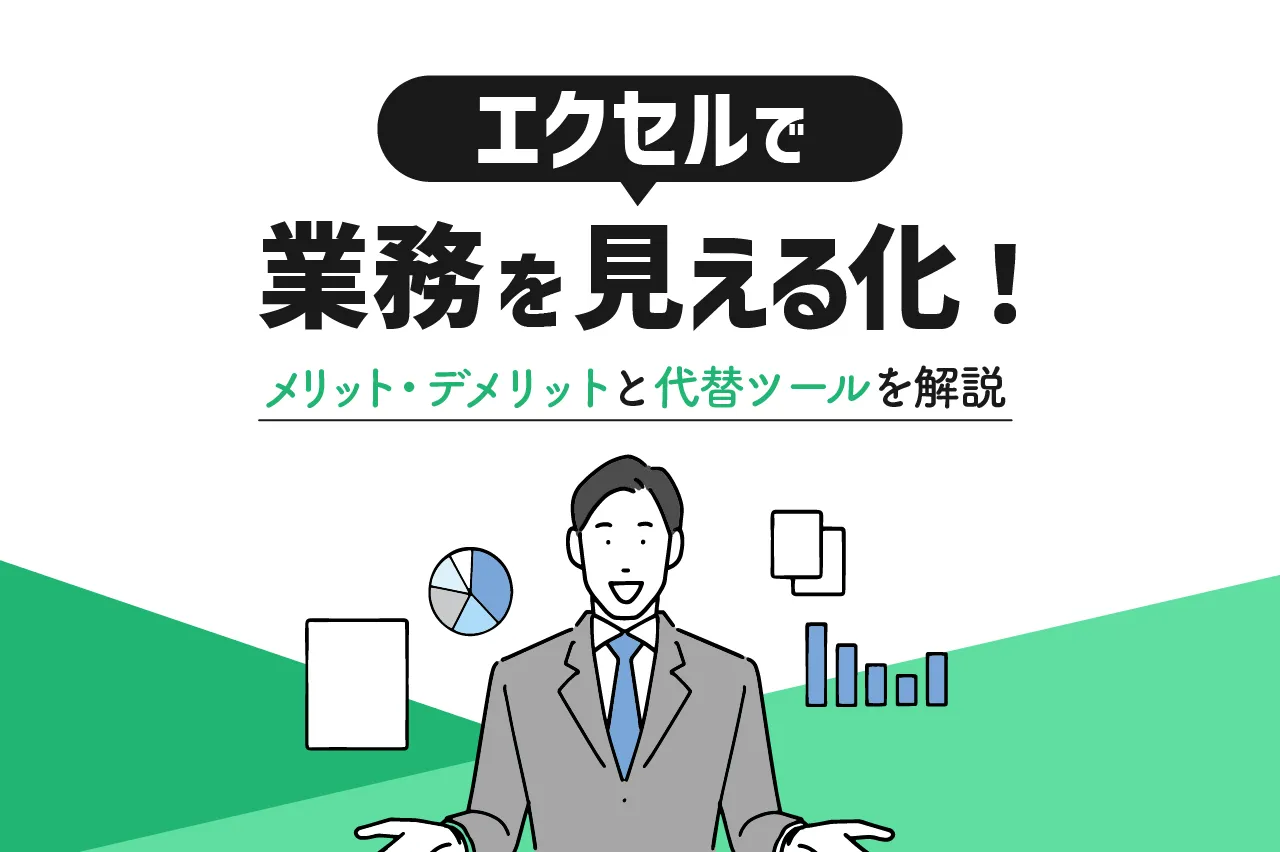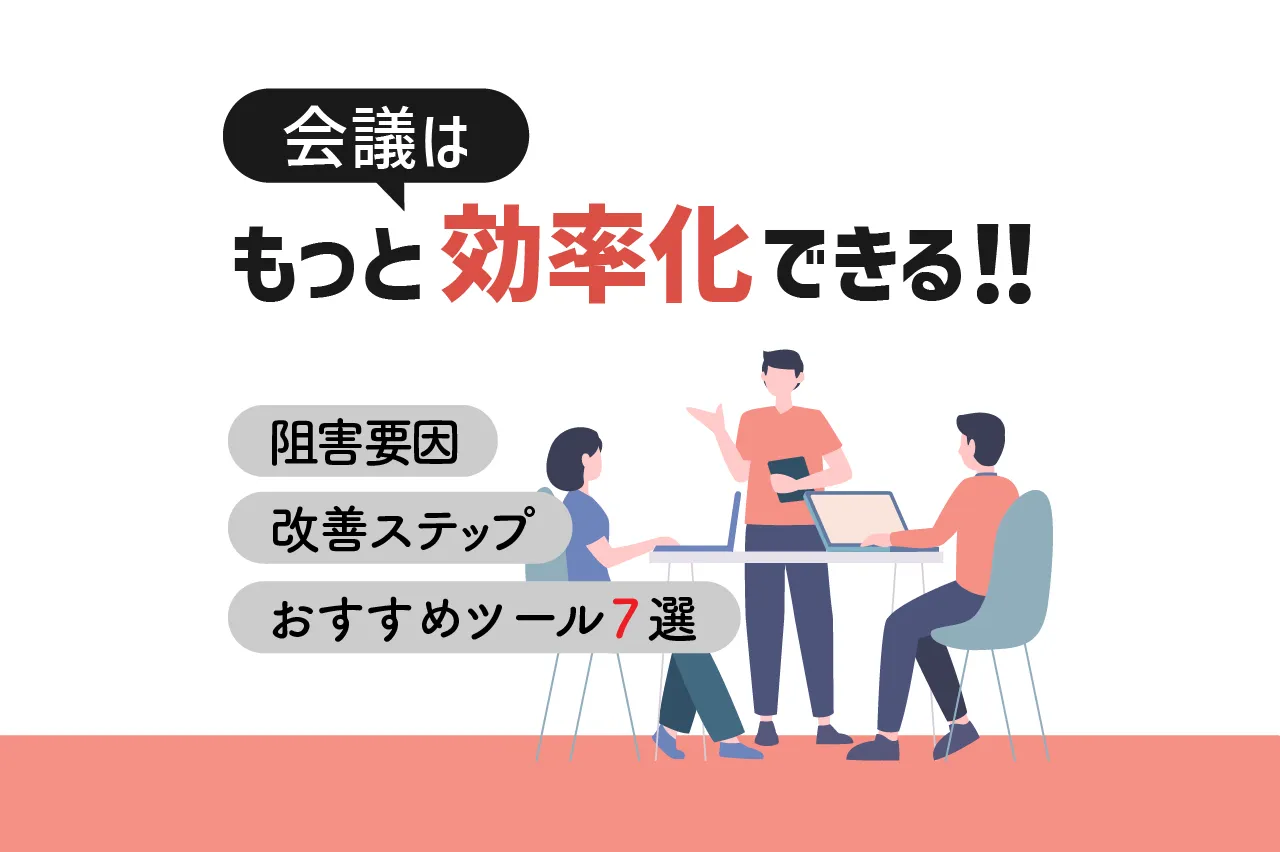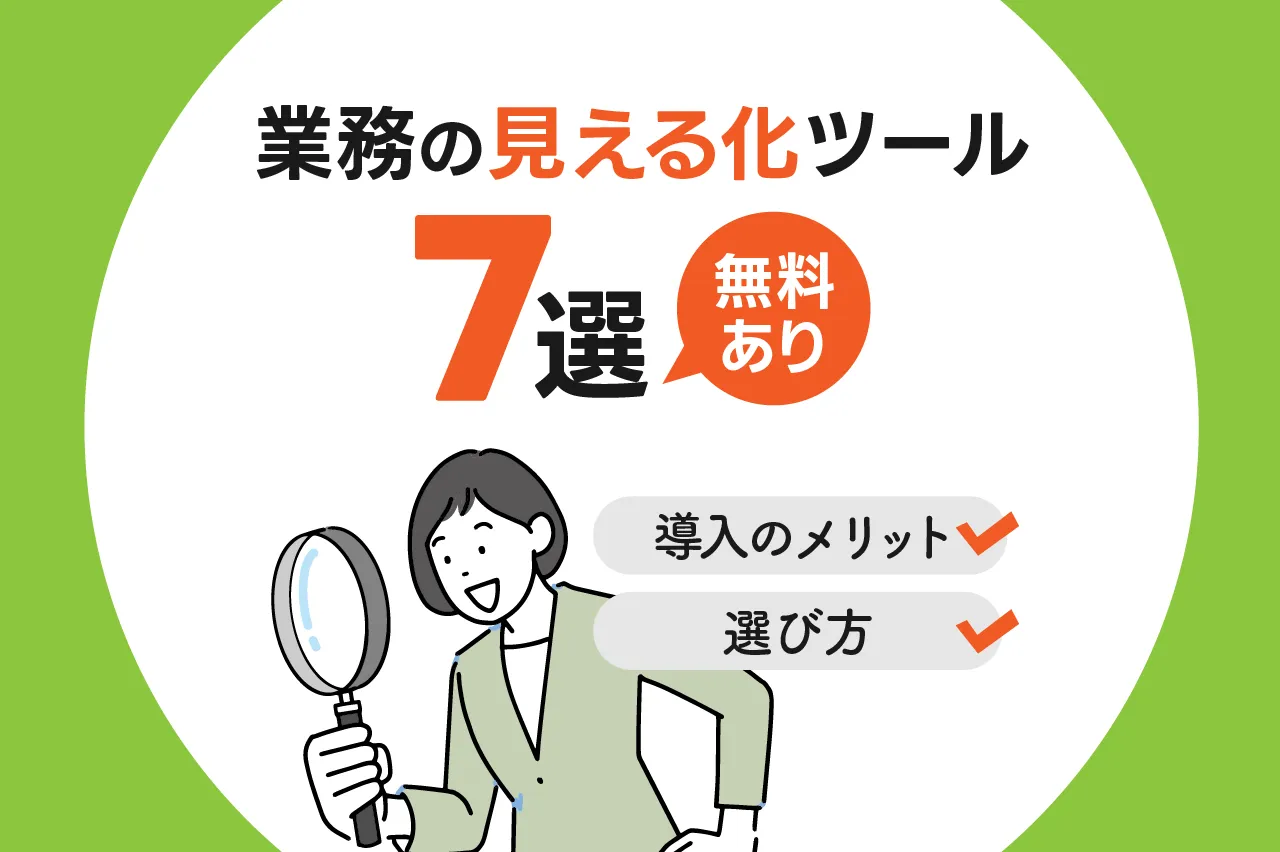平準化とは?標準化との違いや業務で実施するポイントをわかりやすく解説
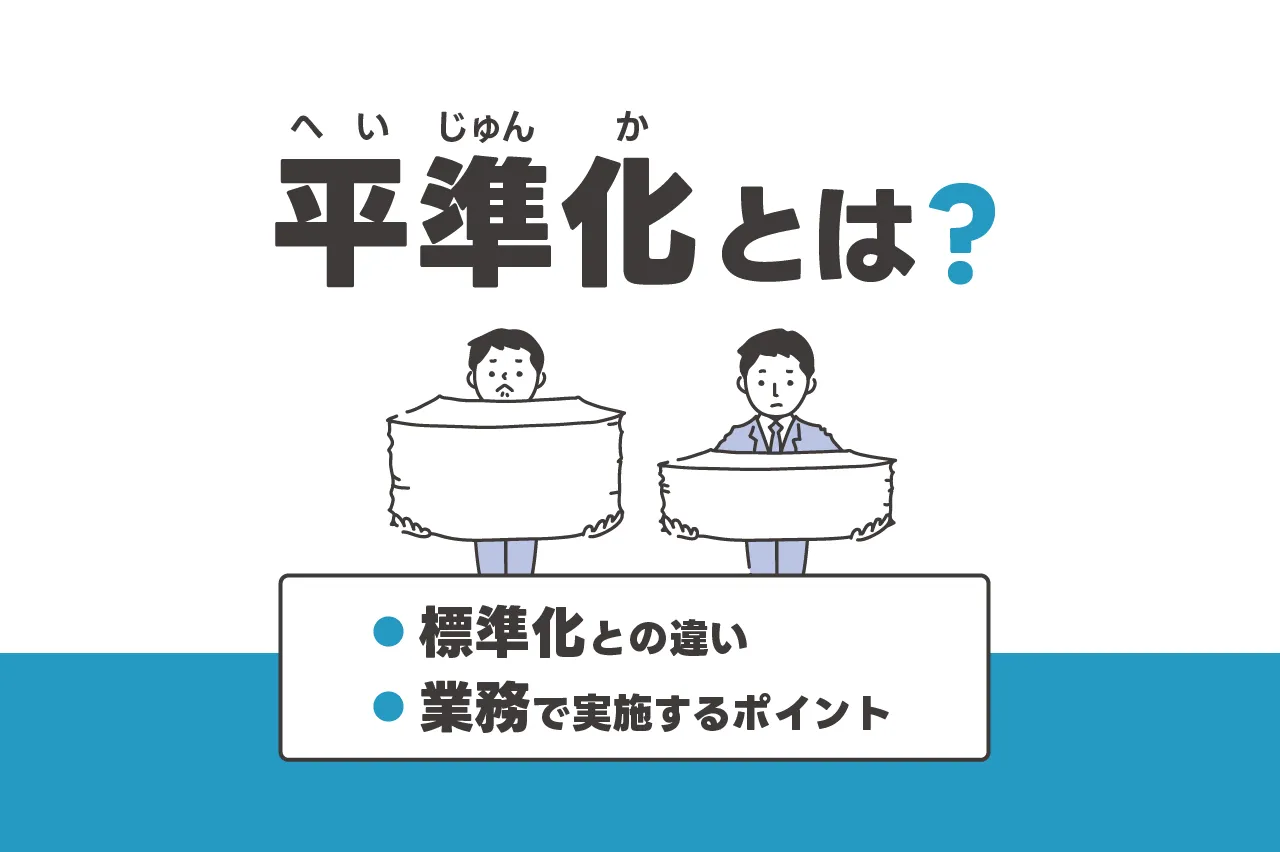
そこで重要な概念が「平準化」です。業務の平準化を進めることで、業務の属人化を防ぎ、業務の効率化やコストダウンにつなげられます。
ただし、平準化は正しい手順で進めないと思うように進められません。そのポイントを押さえておくことが重要です。
そこで今回は、平準化の意味や標準化との違い・手順などに加えて、業務平準化のポイントを解説します。
【目次】
■合わせて読まれている資料
利用者アンケートでビジネスツールの活用実態と課題を徹底調査しました!
利用者のリアルな声からツール選定や活用のヒントが見つかる資料です。
⇒「ビジネスツール利用調査2025」を無料ダウンロード
平準化とは

業務平準化とは、特定の期間やチームメンバーへの業務負担の偏りを是正することです。
特定の時期やメンバーに負担が偏る状況を改善し、作業量を均等に分散させることが目的で、企業全体の生産性向上と効率的なリソース活用を目指します。
▼平準化ができていない状態とは(主な例)
- 従業員の作業量に偏り
- 時期によって作業量にバラつき
- 業務が属人化
- 業務の定型化が不十分
ここでは、平準化に関する基礎知識について、以下の2点を解説します。
- 標準化との違い
- 平準化の必要性
標準化との違い
平準化に関する基礎知識の1つ目は、標準化との違いです。
業務の標準化と平準化は目的が異なります。 標準化は、作業手順や製品仕様を統一して業務効率化や品質向上を図ることが目的です。
一方、平準化は業務量の均一化でリソースを有効活用することを目的としています。 業務の標準化が不十分だと、従業員の仕事内容・業務量に偏りが生じ、平準化の達成が困難です。
平準化の必要性
平準化に関する基礎知識の2つ目は、平準化の必要性です。
ここでは、以下の3点を解説します。
- 業務の円滑な進行
- 業務属人化の防止
- コストダウンの促進
1つずつ見ていきましょう。
業務の円滑な進行
平準化の必要性の1つ目は、業務の円滑な進行です。
業務リソースが偏って配分されていると、プロジェクトの遅延原因になりかねません。これは、特定の時期や特定の人に業務が集中すると、処理能力を超える負荷がかかるためです。
業務平準化により作業負荷を均等に分散させることで、業務の流れがスムーズになり、遅延を防いで計画的な運営を実現できます。
業務属人化の防止
平準化の必要性の2つ目は、業務属人化の防止です。
特定のメンバーに業務が集中すると、他のメンバーが業務の詳細がわからずそのメンバーがいないと業務の品質が大きく低下しかねません。
また、不公平感やモチベーションの低下につながることもあるでしょう。 平準化によって業務を複数の従業員で分担し、特定のメンバーに依存しない体制を作ることで業務属人化を防止できます。
関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説
コストダウンの促進
平準化の必要性の3つ目は、コストダウンの促進です。
業務品質を低下させずにコストダウンを図るためにも、業務の平準化が重要です。一部のメンバーが手一杯になると、全体の業務フローが停滞し、次の工程のメンバーに待ち時間が発生することで無駄な人件費が発生しかねません。
業務の負荷を均等に分散すれば、効率的なリソース配分が可能になり、無駄な労働コストを削減してコストダウンにつながります。
関連記事:コストを賢く削減する具体的な方法と手順・注意点を徹底解説!
平準化の手順

ここでは、平準化の手順について、以下の4点を解説します。
- 目的の共有
- 業務内容の分類
- 業務フローの可視化
- 業務分担の決定
1つずつ見ていきましょう。
目的の共有
平準化の手順の1つ目は、目的の共有です。
まず現状の業務を可視化し、各メンバーや時期の業務内容とその量を明確化し、現場の課題を特定します。
その場合、作業時間の削減や品質向上、属人化の解消など具体的な目標を設定し、関係者全員で共有しましょう。
明確な目的を持つことで、取り組むべき範囲や方向性が明確になり、従業員のモチベーション向上と積極的な協力を促せます。
業務内容の分類
平準化の手順の2つ目は、業務内容の分類です。
各従業員に、他のメンバーもスムーズに作業できるように、業務を細かく分解して洗い出してもらいます。その後、洗い出した各業務を以下の3種類に分類しましょう。
▼業務の分類
|
感覚型 |
経験や知識に基づく判断が必要な業務 |
|
選択型 |
条件によって対応が変わる業務 |
|
単純型 |
マニュアル化しやすい定型業務 |
上記のうち、平準化が可能な業務は選択型と単純型です。また、一見感覚型に見えても、条件付けなど工夫次第では選択型や単純型に分類できるケースもあります。
業務フローの可視化
平準化の手順の3つ目は、業務フローの可視化です。
業務を前述の3種類に分類した後は、選択型と単純型の業務フローを整理しましょう。すべての業務フローを一度に整理することは困難なため、発生頻度が高いものから優先順位を付けて取り組むことがおすすめです。
業務手順を見直しながら、不要な業務の削減・効率化を図り、マニュアルやルールを再設定します。マニュアル作成時に誰もが手順を理解できるよう詳細に記載すれば業務属人化を防げます。
関連記事: プロジェクト管理でワークフローが活用される理由は?ツールの選び方も解説
関連記事:社内マニュアルの作成方法!メリット・デメリットと作成時のコツも解説
業務分担の決定
平準化の手順の4つ目は、業務分担の決定です。
業務の可視化で分担可能な業務が明確になっているため、従業員ごとの偏りを確認し、業務量の多い従業員に対する業務配分を見直しましょう。
特定の時期のみ発生する業務については、本当にその時期に行うべきかを検討し、可能であれば前倒しや分散も検討すべきです。
また、標準化が可能な業務は標準化が困難な業務を担うメンバーを避け、なるべく他のメンバーに割り振りましょう。さらに、RPAなどのツールで置き換えられないかの検討も必要です。
平準化のポイントとは

ここでは、平準化のポイントについて、以下の6点を解説します。
- スモールスタートが基本
- 作業計画の柔軟な立案
- 従業員の力量を踏まえた平準化
- 平準化自体は目的としない
- 長期的目線での取り組み
- 全体の作業量を正確に見積もる
1つずつ見ていきましょう。
スモールスタートが基本
平準化のポイントの1つ目は、スモールスタートが基本であることです。
最初は平準化をスモールスタートで始めることで、失敗時のリスクを最小限に抑えられ、計画の修正も容易になります。また、関わる人数が少なければ、チーム内での理解も早く進むでしょう。
その上で、一部の製品や業務の成功事例を作った後、徐々に組織全体に展開していく段階的なアプローチが効果的です。
作業計画の柔軟な立案
平準化のポイントの2つ目は、作業計画の柔軟な立案です。
平準化では需要変動への対応は不可欠で、現在の需要を正確に予測し、その予測データに基づき生産計画を策定することが求められます。
また、市場環境や顧客のニーズは常に変化するため、定期的な計画見直しも重要です。 短いサイクルで生産計画を更新し、需要変動に迅速に対応できる柔軟な体制を構築する必要があります。
関連記事:生産管理のすべてを解説!効率的な業務運営とシステム導入の秘訣とは
従業員の力量を踏まえた平準化
平準化のポイントの3つ目は、従業員の力量を踏まえた平準化です。
従業員間の技能格差を考慮し、各従業員の能力レベルに応じた無理のない生産計画を立てることで、現実的に平準化できます。
また、従業員教育の充実やマニュアルの整備により、作業の標準化を図ることも効果的です。 誰でも同じ品質とスピードで作業できる仕組みを作れば、属人化を防げます。
関連記事:引き継ぎマニュアルの作り方は5つの手順!わかりやすく作るポイントも解説
平準化自体は目的としない
平準化のポイントの4つ目は、平準化自体は目的としないことです。
平準化の実施に固執しすぎると、組織の現状に合わない施策を導入してしまい、かえってコストの増加や業務の品質低下を招きかねません。
平準化の目的は、人員配置の最適化や在庫管理の適正化を通じて、コスト削減と品質向上を実現することです。 企業や業界によって最適な手法は異なるため、自社に最も適した施策を見つけましょう。
長期的目線での取り組み
平準化のポイントの5つ目は、長期的目線での取り組みです。
平準化は短期間の取り組みだけで完了するものではなく、実施後も成果が現れるまでには時間を要します。そのため、短期的な結果を求めすぎないことが大切です。
焦って必要なプロセスを省略すると、現場に混乱が生じる原因になりかねません。
全体の作業量を正確に見積もる
平準化のポイントの6つ目は、全体の作業量を正確に見積もることです。
全体の作業量を正確に把握できていないと、適切にタスクを配分できません。作業量の見積もりには、かんばん方式のタスク管理手法が効果的です。
付箋やかんばん方式のタスク管理ツールなどを用いることで、各メンバーの作業量を可視化しましょう。
関連記事:タスク管理にもかんばん方式が使える!?便利なツール4選も紹介
関連記事:工数管理とは?生産性向上のためのメリットと効果的な手順
まとめ

今回は、平準化の意味や標準化との違い・手順などに加えて、業務平準化のポイントを解説しました。 業務平準化とは、特定の期間やチームメンバー間の業務負担の偏りを是正することです。
これにより、業務の円滑な進行や業務属人化の防止などを図ります。目的の共有から業務分担の決定まで、正しく手順を踏んで行いましょう。
業務の平準化を進めるには、まずはスモールスタートで始めて、長期的目線で取り組んでいくことがおすすめです。
また、作業計画の柔軟な立案や従業員の力量を踏まえた平準化も、成功のために欠かせません。
作業量の可視化には、タスク管理ツールがおすすめです。「【2025年版】無料のタスク管理ツールおすすめ個人・仕事向け計15選を徹底比較!」では、無料で使えるタスク管理ツールを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
|
ビジネスツール利用調査2025
ビジネスコミュニケーションツールの活用実態と課題を徹底調査しました。
|