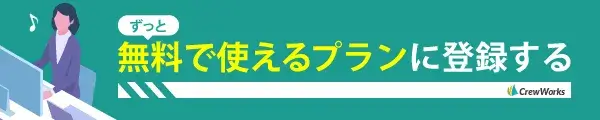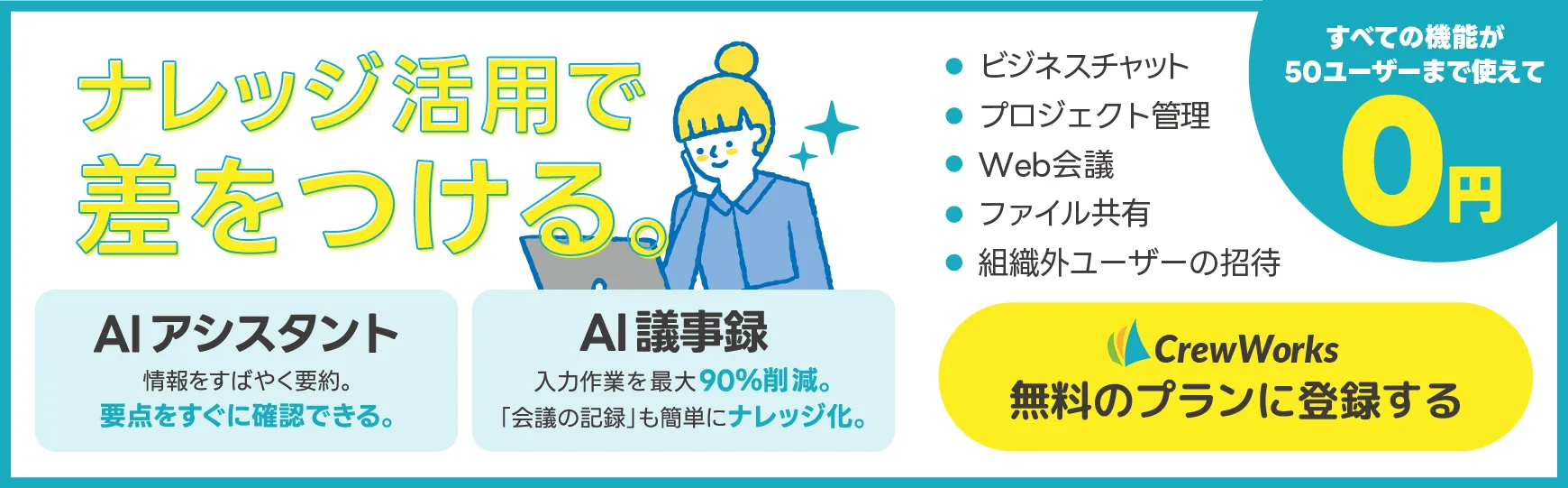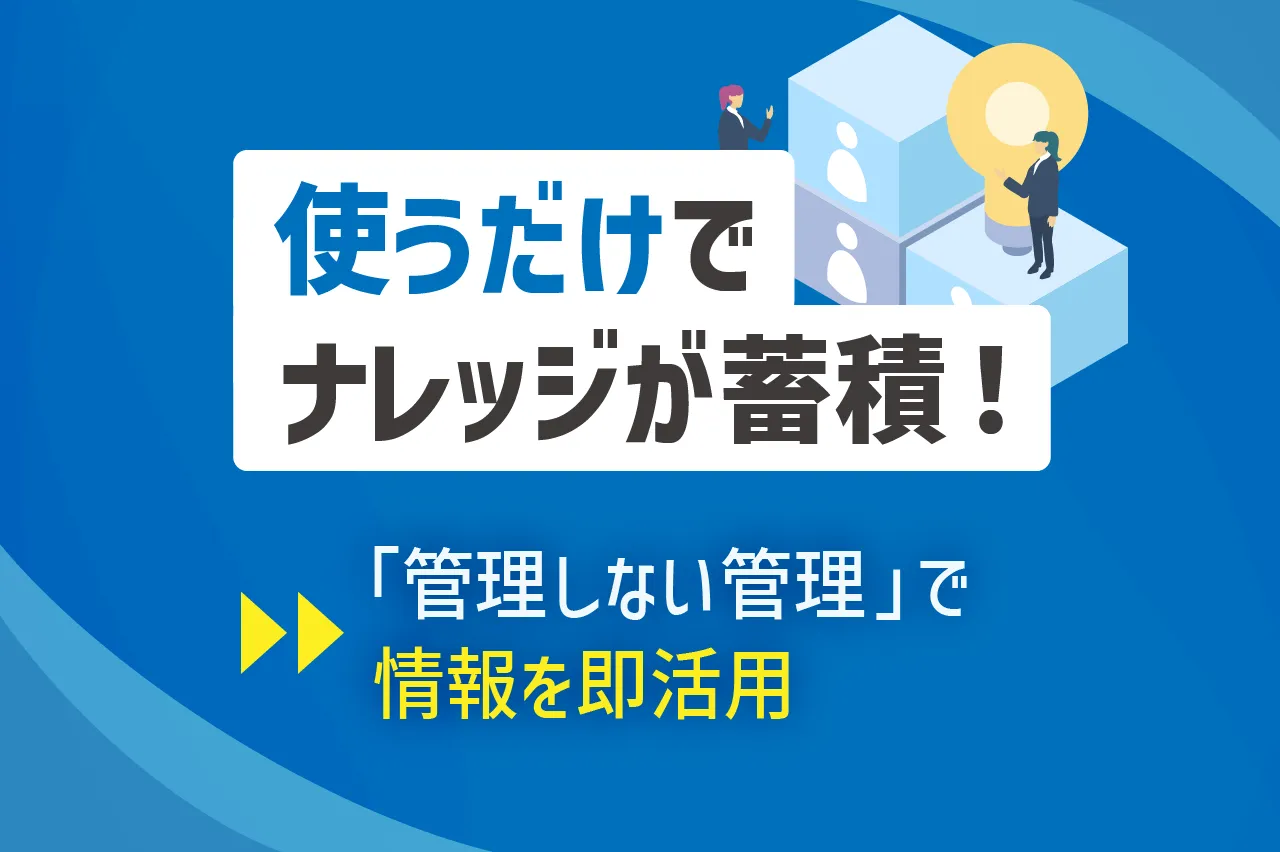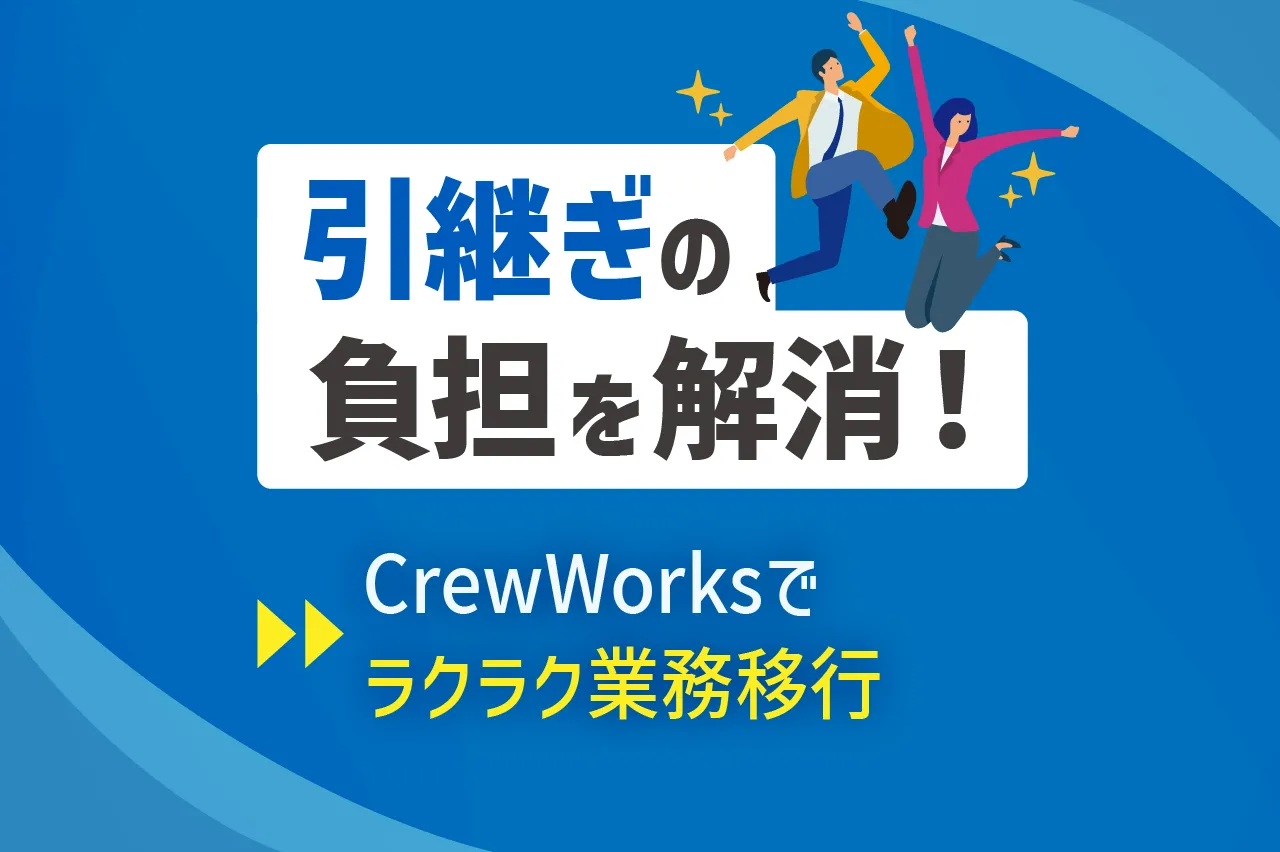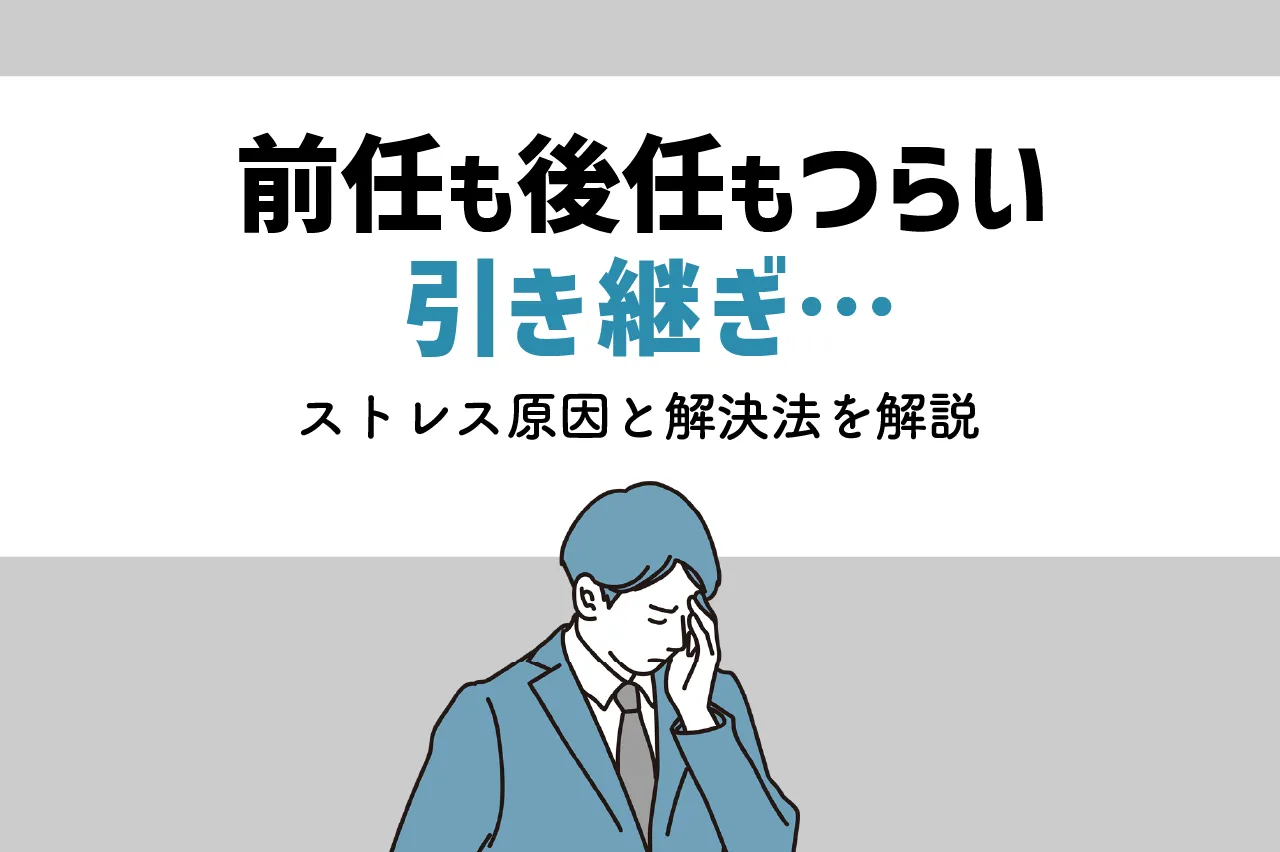引き継ぎがうまくいかない5つの理由!失敗しないための対処法を解説
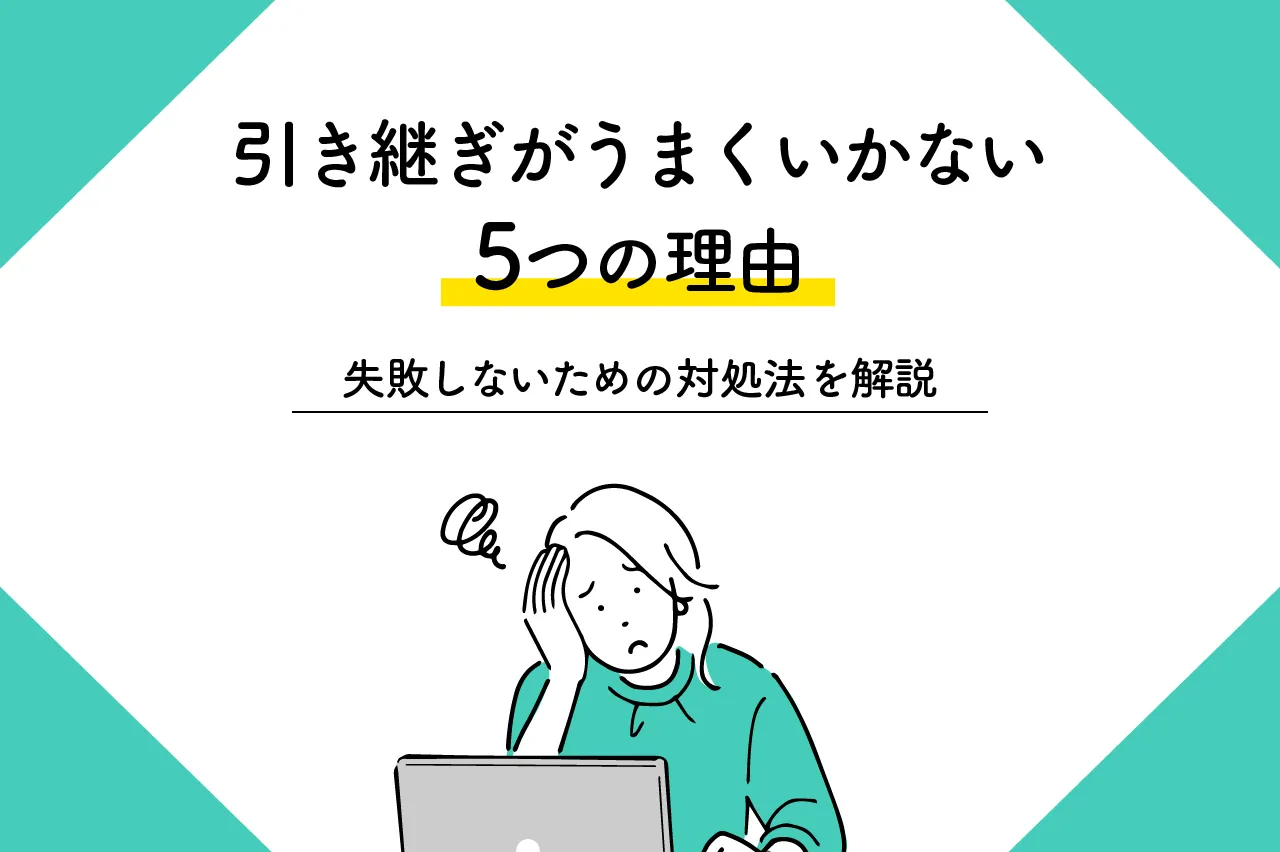
しかし、さまざまな理由で引き継ぎがスムーズに進まず、業務に支障をきたすことも珍しくありません。
いざ自分が引き継ぎを担当する立場になると、「何から始めればいいのか分からない」「どうすればうまく引き継ぎができるのか見当がつかない」と感じることもあるでしょう。
そこで今回は、引き継ぎがうまくいかない主な理由と、失敗を防ぐための具体的な対処法について詳しく解説します。
引き継ぎに不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
■おすすめの効率的な引き継ぎができるツール
無料で最大50ユーザーまで、生成AIを活用した引き継ぎができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
引き継ぎがうまくいかない5つの理由
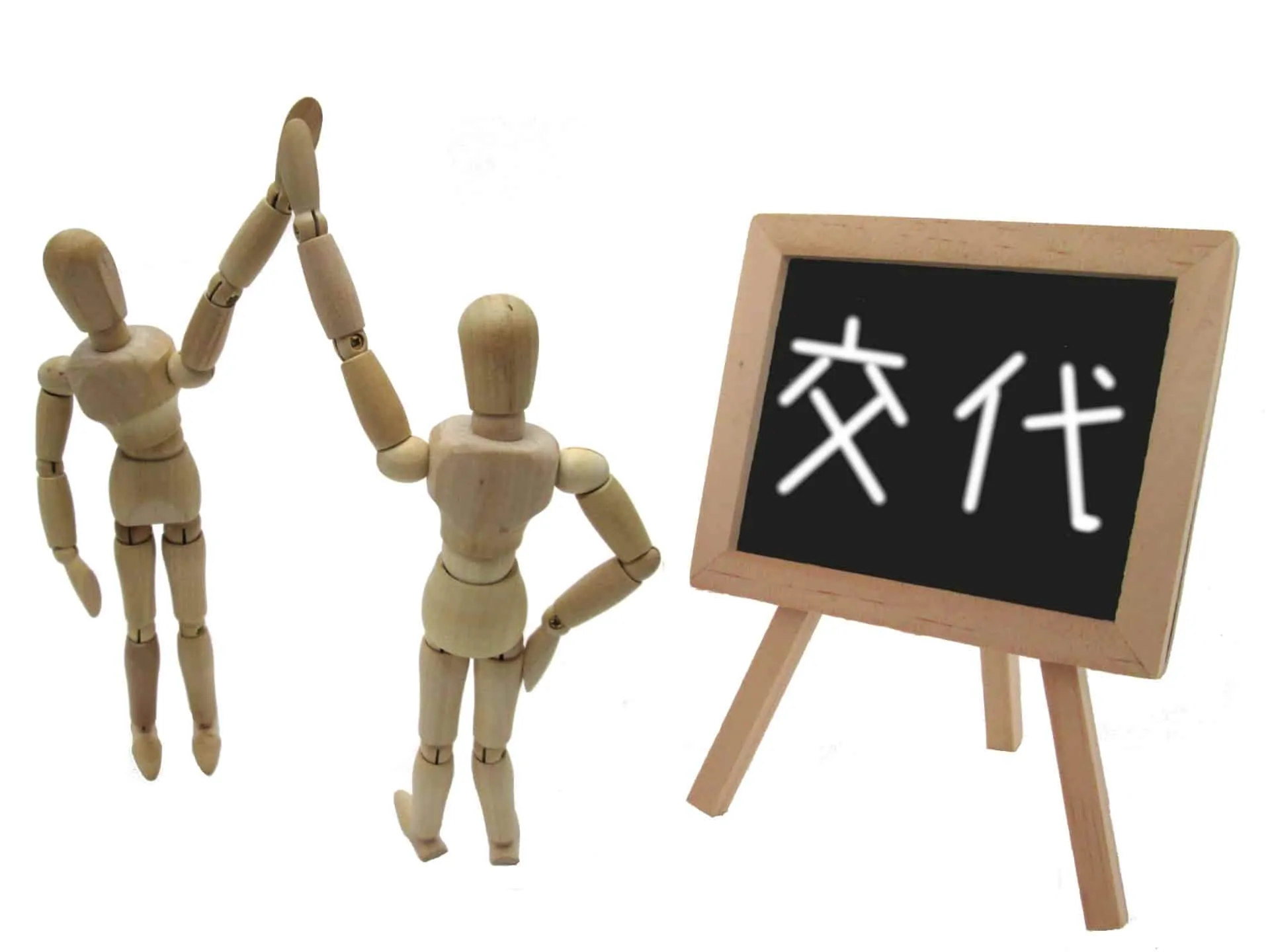
ここでは、引き継ぎがうまくいかない理由について、以下の5点を解説します。
- スケジュールに無理がある
- 方法がわからない
- 引き継ぎ先がいない
- マニュアルが整備されていない
- コミュニケーションが取りにくい
1つずつ見ていきましょう。
スケジュールに無理がある
引き継ぎがうまくいかない理由の1つ目は、スケジュールに無理があることです。
退職日や異動日が迫っているにも関わらず、十分な引き継ぎの時間が取れないと、失敗することがあります。
繁忙期と重なった場合などは、通常業務に追われて引き継ぎの準備を後回しにしてしまうこともあるでしょう。
また、後任者が既存の業務を抱えている場合には、新しい業務の引き継ぎに十分な時間を割くことができません。
表面的な情報の伝達だけではなく、業務の本質的な部分やノウハウを引き継ぐためにも、時間を確保することが大切です。
関連記事:仕事引き継ぎでイライラが限界!原因・影響・対処法をわかりやすく解説
関連記事:ノウハウとは?ビジネスにおける意味や類語、使い方と活用メリットをわかりやすく解説
方法がわからない
引き継ぎがうまくいかない理由の2つ目は、方法がわからないことです。
「何を」「どこまで」引き継ぐべきかの判断基準がないと、担当者の経験や感覚にやり方が依存するため、うまくいかないことがあります。
引き継ぎのフォーマットが統一されていなければ、情報の漏れや重複が起きることもあるでしょう。
詳細な資料を作成する担当者がいる一方で、別の担当者は口頭での説明のみで済ませてしまうなど、品質にばらつきが生じることもあります。
組織全体で引き継ぎの標準的な手順を策定し、共有することが不可欠です。
関連記事:前任者も後任者もつらい…仕事の引き継ぎで起こるストレスの原因と解消法を解説
引き継ぎ先がいない
引き継ぎがうまくいかない理由の3つ目は、引き継ぎ先がいないことです。
特に、専門性の高い業務や特殊なスキルが必要な業務は、後任者を見つけることが困難な場合があります。
また、組織の再編や事業の縮小により、業務自体が他部門に移管されたり、複数の担当者に分散されたりするケースもあります。このような状況では、引き継ぎ先が複雑になり、誰に何を引き継いで良いかがわかりません。
結果として、重要な業務が宙に浮いた状態になり、顧客対応や業務継続に深刻な影響を与える可能性があります。
マニュアルが整備されていない
引き継ぎがうまくいかない理由の4つ目は、マニュアルが整備されていないことです。
長年同じ担当者が業務を担ってきた結果、その人だけが知っている暗黙知やノウハウが蓄積されている状態であることも珍しくありません。
業務手順が文書化されていても、実際の運用と乖離していたり、更新が滞っていたりするケースがあります。
特に、システムの操作方法や取引先との細かな取り決め、過去のトラブル対応事例などは、マニュアルに記載されにくい情報です。
必要な情報が共有されないまま引き継ぎが行われると、後任者は同じ失敗を繰り返す可能性があります。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
関連記事:「あの人にしかできない仕事」は危険!属人化によるストレスと職場の崩壊リスク
コミュニケーションが取りにくい
引き継ぎがうまくいかない理由の5つ目は、コミュニケーションが取りにくいことです。
画面共有やWeb会議では伝わりにくい細かな作業手順や、実際の業務の雰囲気などは、対面での説明が効果的です。
また、部門間の壁や組織文化の違いにより、質問しづらい雰囲気が生まれている場合もあります。特に、他部門に引き継ぐ場合には、専門用語などが分かりづらく、十分な説明が行われないことがあります。
さらに、引き継ぎを受ける側が遠慮してしまい、分からないことがあっても質問できずに進んでしまうケースもあるでしょう。
対面での説明の機会を設けたり、質問しやすい雰囲気づくりを意識したりすることが大切です。
関連記事:もう業務の引き継ぎで悩まない!事前準備からトラブル防止まで徹底解説
引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスク
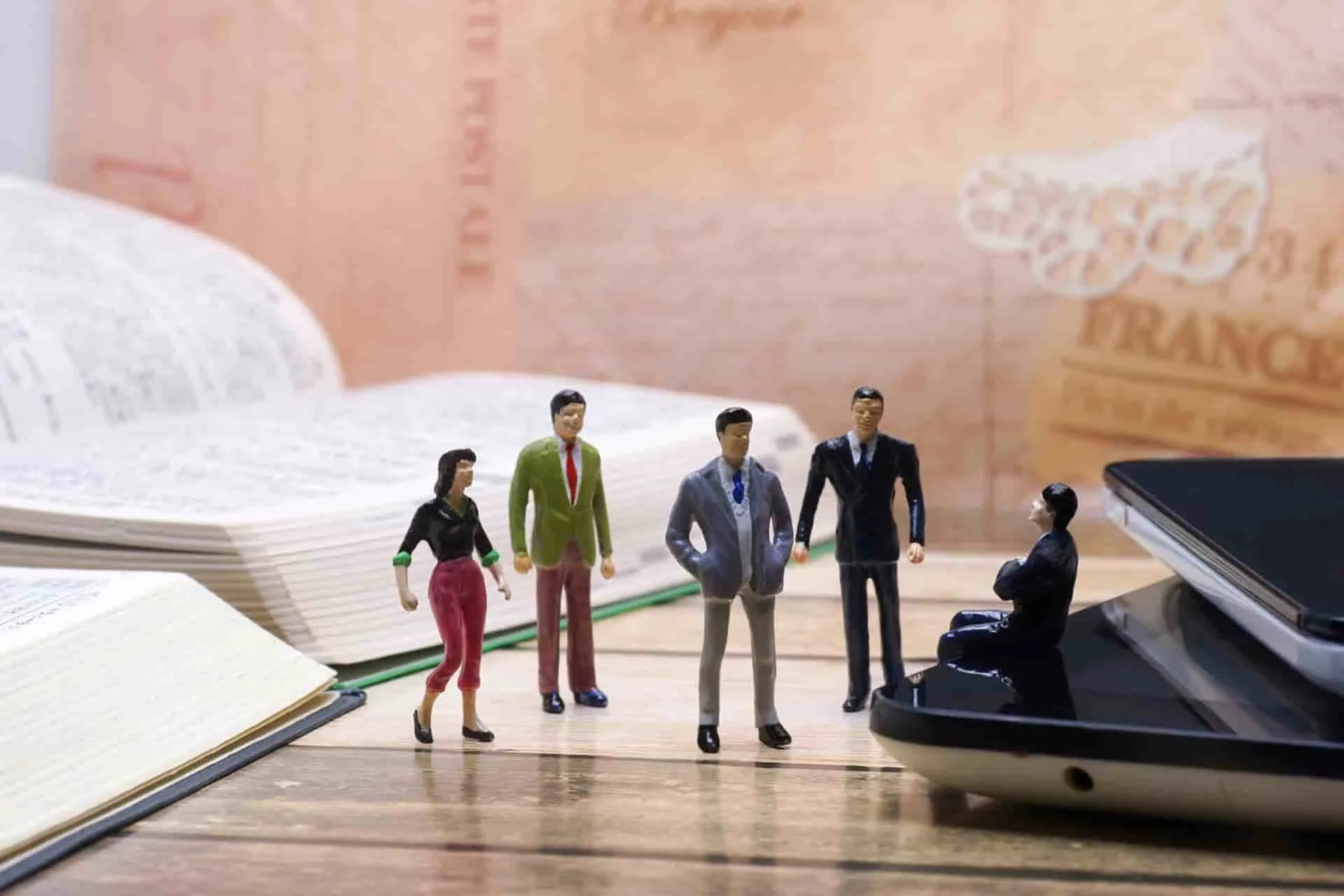
ここでは、引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスクについて、以下の4点を解説します。
- 取引先からの信頼を失う
- 社内のナレッジが失われる
- 後任者の負担が大きくなる
- 業務効率が低下する
1つずつ見ていきましょう。
取引先からの信頼を失う
引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスクの1つ目は、取引先からの信頼を失うことです。
担当者変更の連絡が適切に行われなかったり、過去の約束事や特別な配慮事項が引き継がれないと、取引先からの問い合わせに対して的確な回答ができません。
状況が長引くと、取引先からは「対応力が低い企業」「信頼できない企業」と見なされてしまいます。長年築いてきた信頼関係が崩れることのないよう、必要な情報を引き継いでいくことは重要です。
関連記事:ナレッジの継承は企業活動で必要になる!うまくいかない要因や方法などを解説
社内のナレッジが失われる
引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスクの2つ目は、社内のナレッジが失われることです。
経験に基づく知識は暗黙知と呼ばれ、一度失われると再現が非常に困難です。
過去のトラブル事例やその対処法、効率的な業務の進め方、顧客の細かな要望など、業務を円滑に進めるために必要な情報は複数あります。
引き継ぎがうまくいかないと、後任者は一から試行錯誤を繰り返すことになります。その結果、同じミスを何度も繰り返したり、業務が非効率になることもあるでしょう。
競合他社に対する優位性の喪失にもつながるため、引き継ぎを円滑に進めていかなければなりません。
関連記事:暗黙知とは?ナレッジマネジメントで形式知化すべき理由・役立つツールも解説
関連記事:ナレッジ活用で組織力を最大化!失敗しない進め方とツールの選び方を解説
後任者の負担が大きくなる
引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスクの3つ目は、後任者の負担が大きくなることです。
業務の全体像が把握できない状態で着任するため、後任者は常に不安を抱えながら業務を進めることになります。
分からないことがあっても質問する相手がいない場合、インターネットで調べたり、関係者に個別に確認したりする必要があり、通常の何倍もの時間がかかってしまいます。
場合によっては、残業や休日対応が増加し、後任者の心身への負担が大きくなることもあるでしょう。
ストレスが蓄積することで、新たな退職者を生み出しかねないため、引き継ぎができる体制を整えることは重要です。
関連記事:キャパオーバーのサインに要注意!仕事の負担を軽減する方法
関連記事:業務の引き継ぎで悩まない!スムーズに行うための事前準備や効果的な方法を徹底解説
業務効率が低下する
引き継ぎがうまくいかないことで起こるリスクの4つ目は、業務効率が低下することです。
後任者が業務に慣れるまでの間、作業スピードが遅くなるのは避けられません。しかし、適切な引き継ぎが行われていれば、慣れるまでの期間を最小限に抑えることが可能です。
一方で、引き継ぎが不十分だと手戻りやダブルチェックが頻繁に発生し、本来不要な作業に時間と手間を取られてしまいます。
また、不明点を確認するための会議や調査に時間を取られ、他の業務にも影響を及ぼしかねません。品質管理にかかる時間とコストを削減するためにも、引き継ぎは適切に行う必要があります。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
引き継ぎがうまくいかないときの対処法

ここでは、引き継ぎがうまくいかないときの対処法について、以下の5点を解説します。
- 業務内容を整理する
- 引き継ぎのスケジュールを決める
- マニュアル・資料を作成する
- 引き継ぎを実施する
- フォローを行う
1つずつ見ていきましょう。
業務内容を整理する
引き継ぎがうまくいかないときの対処法の1つ目は、業務内容を整理することです。
日常的に行っている定型業務から、月次・四半期・年次で発生する業務まで、時系列で整理していくことが重要です。
各タスクの優先度や他業務との依存関係を可視化し、どの業務から引き継ぎを始めるべきかを明確にしましょう。
業務の洗い出しでは、表面的な作業だけでなく、判断が必要な場面や例外的な対応についても詳細に記録します。
特に、緊急時の対応方法や重要な期限、チェックポイントなどは、後任者が混乱しやすい部分のため、丁寧に整理しておくことが大切です。
関連記事:仕事効率アップ!タスク洗い出しのメリット・流れ・おすすめ無料ツール8選
引き継ぎのスケジュールを決める
引き継ぎがうまくいかないときの対処法の2つ目は、引き継ぎのスケジュールを決めることです。
一般的には、退職や異動の2~3ヶ月前から準備を開始し、十分に余裕を持った計画を立てることが重要です。引き継ぎ期間は業務の複雑さや量に応じて調整しますが、最低でも2週間程度は確保したいところです。
スケジュールは、資料作成期間・説明期間・実践期間・フォロー期間などに区分し、各段階での完了目標を設定するのもおすすめです。
特に、重要な業務については、複数回、実践する機会を設けることで、後任者の理解度を深めることができます。
関連記事:スケジュール管理ツールで時間を制す!おすすめ個人・ビジネス向け計8選と選び方を紹介
マニュアル・資料を作成する
引き継ぎがうまくいかないときの対処法の3つ目は、マニュアル・資料を作成することです。
マニュアルは、業務の目的・手順・注意点・関係者情報などを体系的に整理し、後任者が一人でも業務を進められることを目標に、明確に記載します。
特に効果的なのは、スクリーンショットや動画を活用した視覚的な説明です。システムの操作方法や複雑な手順については、実際の画面を見ながら学習できるため、理解度が大幅に向上するでしょう。
また、後任者の不安を軽減するために、よくある質問やトラブル事例、その対処法についてもFAQ形式でまとめておくのも方法の1つです。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
関連記事:引き継ぎマニュアルの作り方は5つの手順!わかりやすく作るポイントも解説
引き継ぎを実施する
引き継ぎがうまくいかないときの対処法の4つ目は、引き継ぎを実施することです。
最も効果的な方法は、OJT(On-the-Job Training)形式で、実際の業務に同行しながら説明することです。マニュアルだけでは伝わりにくい業務の雰囲気や判断のポイントを、実践の中で伝えることができます。
引き継ぎは段階的に進め、まずは簡単な業務から始めて、徐々に複雑な業務に移行していきます。後任者が実際に作業を行い、その場で疑問点を解消できる環境を作ることが重要です。
また、取引先や関係部門への紹介も忘れずに行い、人脈の引き継ぎも同時に進めましょう。
フォローを行う
引き継ぎがうまくいかないときの対処法の5つ目は、フォローを行うことです。
移行後の1~2ヶ月間は、定期的な面談やチャットでのサポートを提供し、後任者が困った時にすぐに相談できる体制を維持しておきます。
フォロー期間中は、新たに発生した疑問点や想定外の状況を共有し、必要に応じてマニュアルの更新も行いましょう。
また、業務の進捗状況や品質をモニタリングし、問題があれば早期に対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。
フォローアップすることで、後任者の不安が軽減され、スムーズに業務を移行していけるでしょう。
関連記事:マニュアル管理ができていない職場は危ない?導入ステップ・おすすめツールを解説
引き継ぎがうまくいかないというお悩みに最適なナレッジマネジメントツール「CrewWorks」
引き継ぎの課題を根本的に解決するためには、日頃から情報共有と知識を管理しておくことが大切です。
CrewWorks(クルーワークス)は、仕事に必要な機能が一つにまとまっているため、仕事上のコミュニケーションを一元管理できるツールです。
チャット・タスク管理・ファイル共有・ナレッジベースなどの機能が統合されているため、業務に関するあらゆる情報を一箇所で管理できます。
特筆すべきは、CrewWorksにAIアシスタント機能があることです。AIアシスタント機能を使うと、CrewWorks上で質問するだけで、システム内のすべてのコミュニケーション記録をもとに、AIが分かりやすく回答してくれます。
回答のもととなった参照情報も1クリックで確認できるため、詳細な情報を迅速に探し出せるでしょう。社内のデータ収集や分類を行わなくとも、効率的にナレッジを活用できます。
過去のやり取りや決定事項を簡単に検索・共有できるため、引き継ぎするときにも便利に活用でき、業務の属人化を防ぐことができます。
CrewWorksの特長
- 質問に対して過去のチャットやタスク等をもとに回答するAIアシスタント機能
- チャット・タスク・会議・ファイルの情報を一元管理できる統合型プラットフォーム
- 50ユーザーまで無料のフリープランあり
詳細はこちら: https://crewworks.net/
まとめ

今回は、引き継ぎがうまくいかない5つの理由と、失敗を防ぐための対処法について解説しました。
引き継ぎ先の不在やコミュニケーション不足といった課題を解決するためには、個々の課題にあった解決策を実践していく必要があります。
引き継ぎは、組織の継続性と成長にとって不可欠な要素です。ぜひ今回ご紹介した方法を参考に、自社の引き継ぎ業務を見直してみてください。