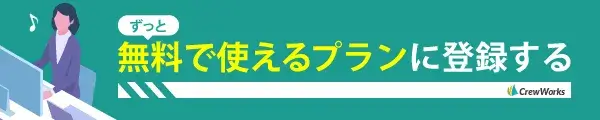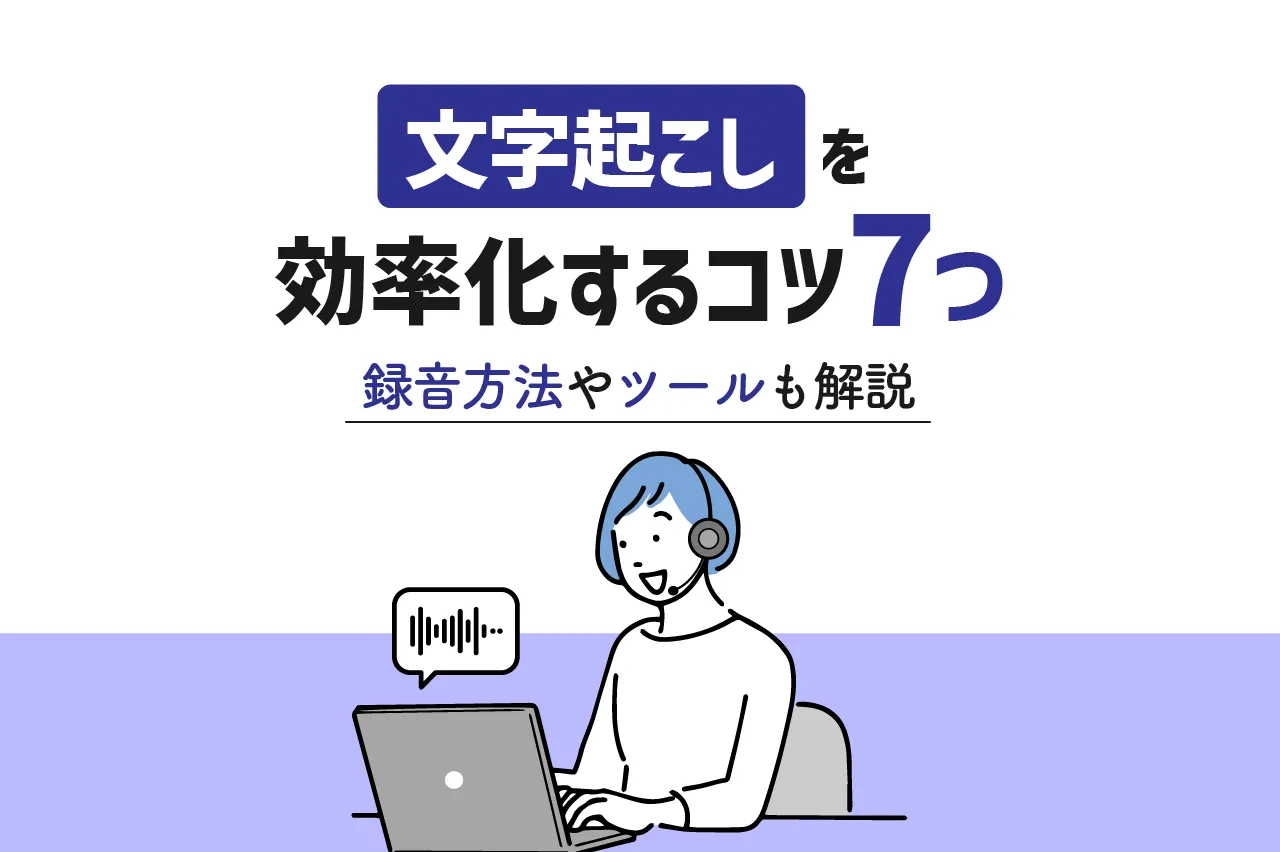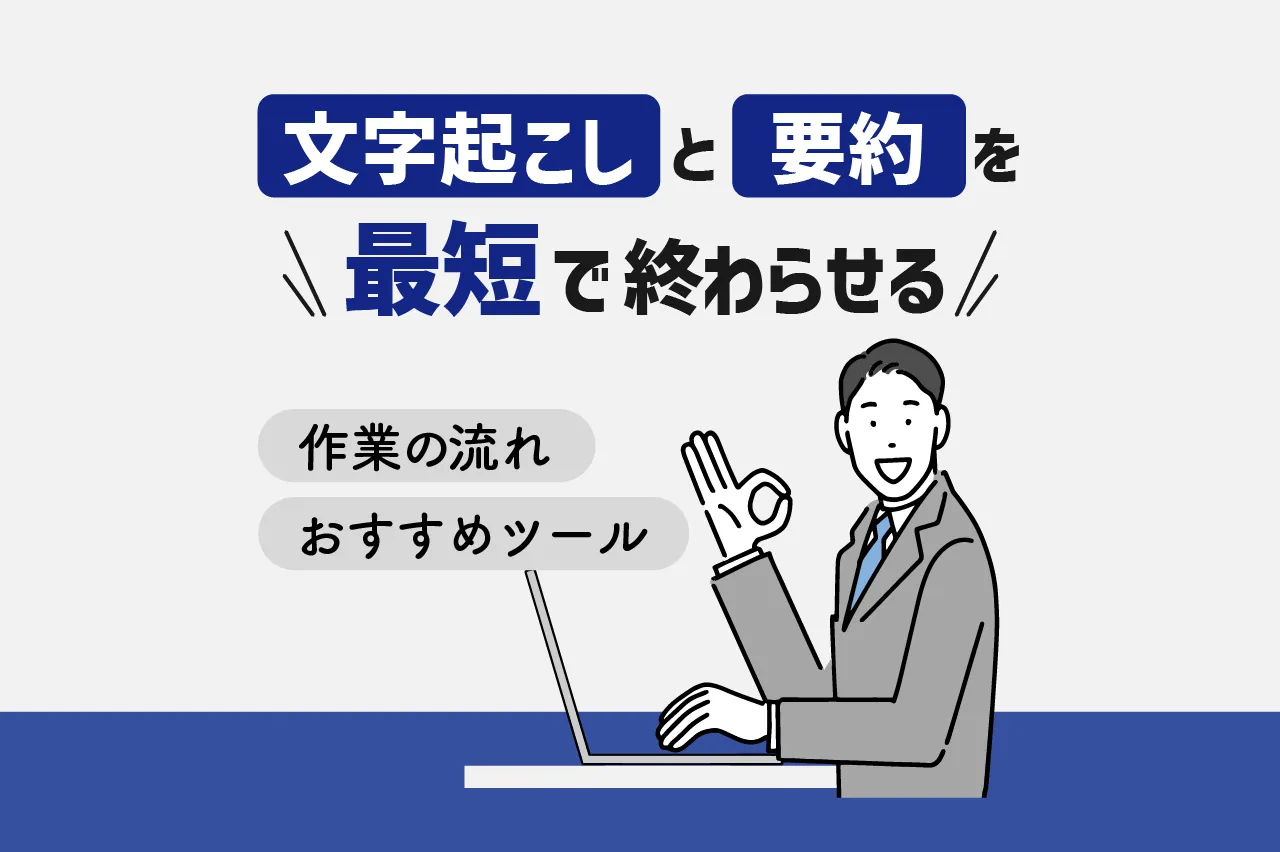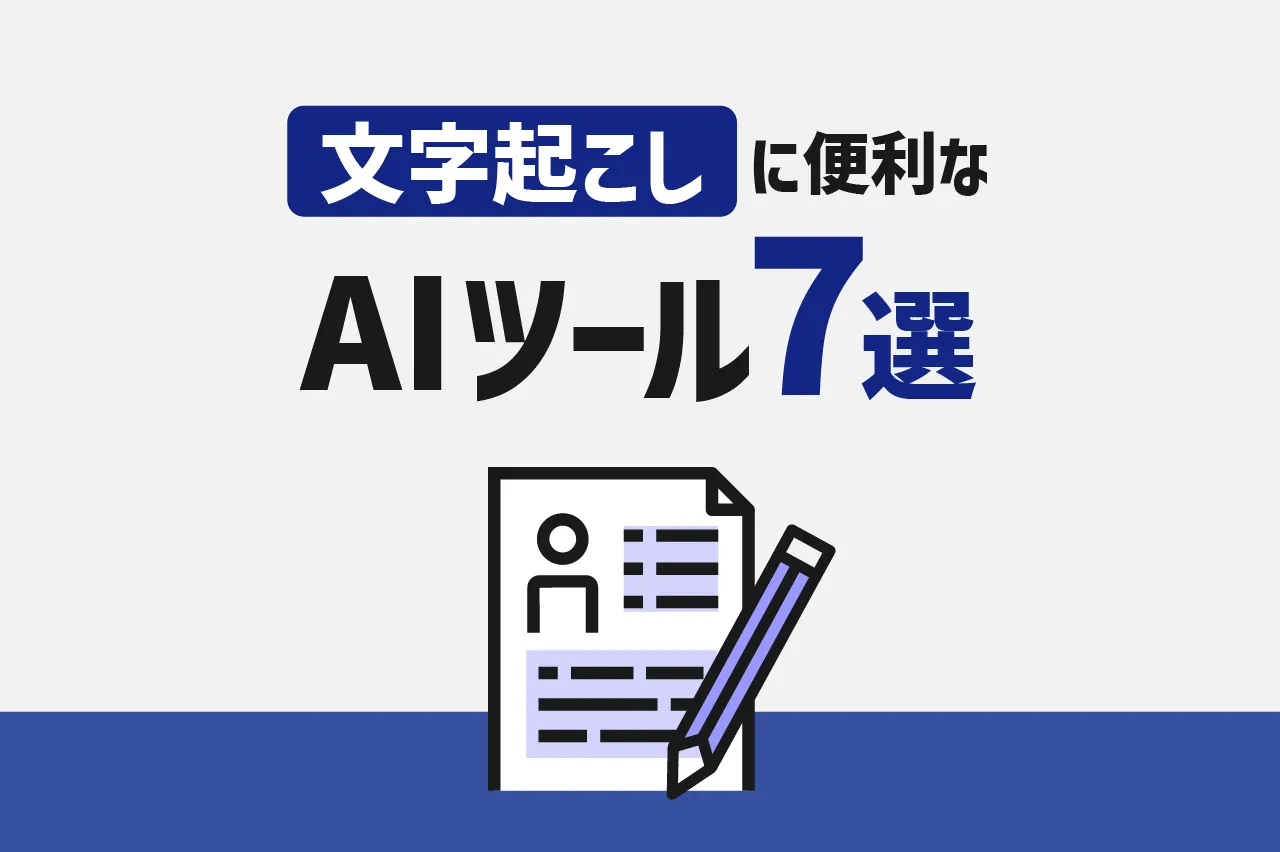文字起こしのやり方と効率化のコツ!おすすめツールも紹介
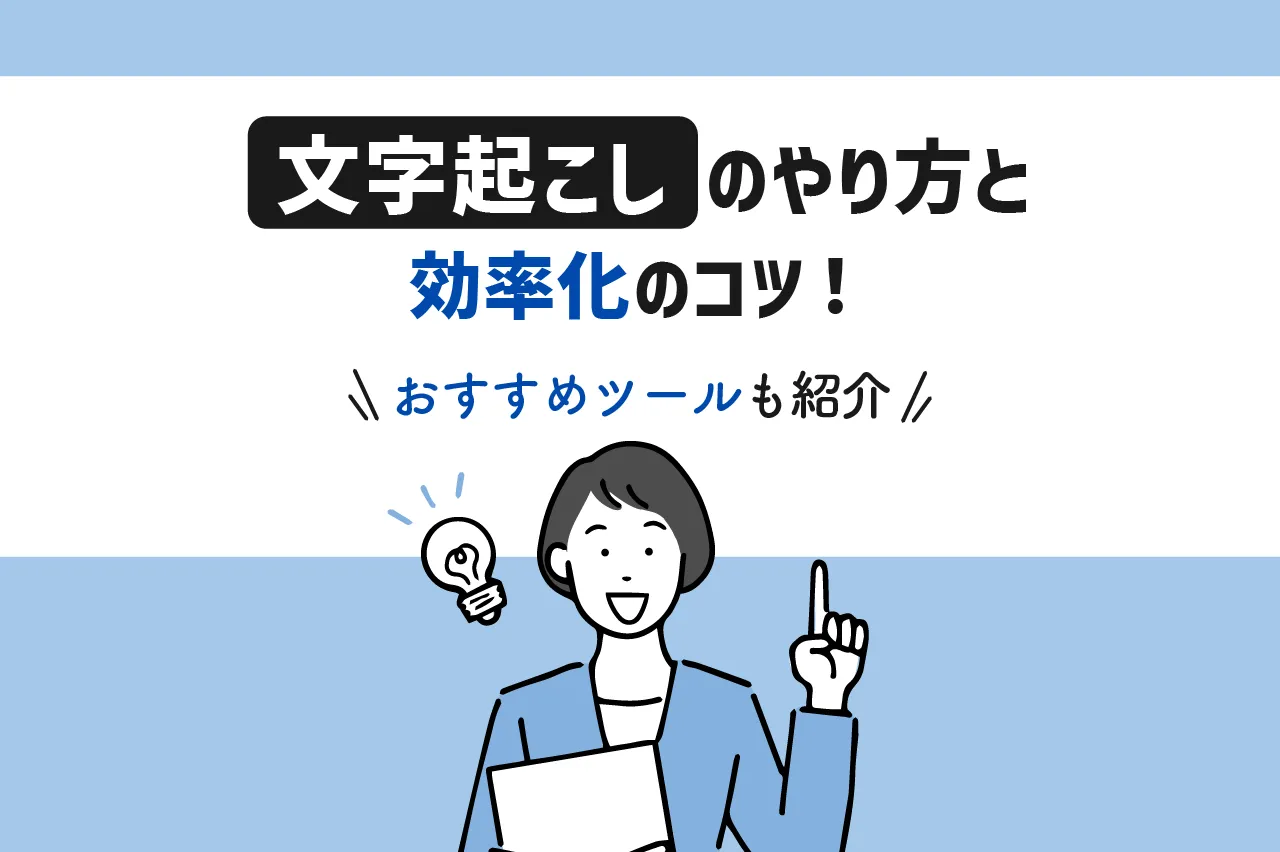
しかし、長時間の音声データを一字一句起こすのは大変な作業であり、時間や労力がかかってしまうのが実情ではないでしょうか。
特に業務の合間に手作業で進めると効率が悪く、精度やスピードの両立に悩む方も少なくありません。
そこで今回は、文字起こしの基本的なやり方から、効率的に進めるための実践的なコツ、おすすめの文字起こしツールも紹介します。
導入して、社内の情報共有や会議の生産性向上につなげていきましょう。
【目次】
■おすすめの文字起こしツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的な文字起こしができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
文字起こしはやり方で変わる!

ここでは、文字起こしはやり方で変わる!について、以下の2点を解説します。
- 文字起こしとは
- 文字起こしの種類
1つずつ見ていきましょう。
文字起こしとは
文字起こしとは、会議・インタビュー・講演・動画などで話された音声を文章に変換する作業のことを指します。
口頭でのやり取りは記録が残りにくく、聞き逃しや解釈の違いが生じやすいため、文字起こしによって正確な情報を共有できることがメリットの一つです。
手作業で一字一句書き起こす方法もあれば、AIや専用ソフトを用いて自動的に文章化する方法もあり、用途や精度の求め方によってどのツールを選ぶか選択肢が変わります。
また、必要に応じて「ケバ取り」(語尾の調整や言いよどみの削除)や「整文」(文法を整えて読みやすくする作業)を加えることで、読み手にとって理解しやすい文章に仕上げることも可能です。
近年はAI技術の進化により、効率的で高精度な文字起こしが身近になり、業務効率化や情報共有の手段として注目されています。
関連記事:Wordで文字起こしはここまでできる!使い方・注意点・おすすめツール紹介
関連記事:Teamsの会議内容を文字起こし!メリットや操作方法を解説
文字起こしの種類
文字起こしにはいくつか種類があり、目的に応じた使い分けが重要です。
まず「素起こし」とは、話された内容をそのまま忠実に書き起こす方法です。
言いよどみや「あー」「えー」といったフィラー(無意味なつなぎ言葉)も含めて記録するため、発言のニュアンスや話し方を正確に残したい研究や調査に向いています。
次に「ケバ取り」は、発言内容を損なわない範囲で不要なフィラーや重複表現を省く方法です。読みやすさが向上するため、会議の議事録や社内共有資料などに適しています。
「整文」は、口語表現を文章として自然に読めるように整える方法です。助詞の補足や語順の調整を行い、読み手にとって理解しやすい形に仕上げます。
素起こし・ケバ取り・整文の特徴を理解して適切に選びましょう。
関連記事:議事録作成時には文字起こし!おすすめツール4選(無料あり)や比較ポイントも紹介
■おすすめの文字起こしツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的な文字起こしができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
文字起こしのやり方

ここでは、文字起こしのやり方について、以下の7点を解説します。
- 環境と機材を整える
- 音声を収録する
- 録音データを整理する
- 文字起こしを実行する
- 出力されたテキストを整える
- 固有名詞や専門用語を確認する
- 最終チェック・保存・共有
1つずつ見ていきましょう。
環境と機材を整える
文字起こしのやり方の1番目は、環境と機材を整えることです。
周りの雑音や反響が多い環境では音声が不明瞭になり、後から文字に起こす時に聞き取りづらくなります。
会議室や個室など外部の音を遮断できる場所を確保するだけで、文字起こしの精度は大きく変わります。
録音する時には高性能のマイクやICレコーダーなどの録音機器を準備しておくことも効果的です。
PC内蔵マイクやスマートフォンだけでも録音は可能ですが、専用機材の使用により音質が安定し、細かな声の抑揚や複数人の発言もクリアに記録できるでしょう。
さらに、録音前にテストを行い音量やマイク位置を調整すれば、後の作業負担を大幅に軽減できます。「環境」と「機材」を整えることで、スムーズで精度の高い文字起こしができるでしょう。
関連記事:文字起こしを効率化する7つのコツ!録音方法やツールも解説
音声を収録する
文字起こしのやり方の2番目は、音声を収録することです。
会議やインタビューの場では、全ての内容をその場でメモに残すのは難しく、聞き逃しや記録漏れのリスクがあります。
そこで、録音機器やスマートフォン、Web会議ツールの録画機能を活用して、発言を丸ごと記録しておくことが有効です。
録音をしておけば、後から落ち着いて再生しながら正確に文字起こしができ、聞き取りにくかった部分も繰り返し確認できます。
また、録音だけに頼らず、必要に応じて簡単なメモを取っておくのもポイントです。重要なキーワードや発言者の意図をメモしておけば、文字起こし作業の時にスムーズに補足でき、内容理解が深まります。
録音とメモを組み合わせることで、正確性と効率を両立でき、文字起こしの品質を高められるでしょう。
関連記事:議事録を作成しているときにメモが追いつかない!その要因と対処法を解説
関連記事:議事録作成は録画で効率化!メリット・注意点・おすすめツール6選も紹介
録音データを整理する
文字起こしのやり方の3番目は、録音データを整理することです。
文字起こしを効率的に進めるためには、文字起こし前に録音データを整理しておきましょう。長時間の会議やインタビューでは、雑談や本題と関係のない部分も含まれることが多いです。
不要な部分は文字起こし前にカットすることが大切です。
また、録音状況によっては発言者ごとに音量が異なることがあり、そのままでは聞き取りにくさの原因になります。
音量を均一に整えたり、不要なノイズを軽減したりすることで、音声がクリアになり、精度の高い文字起こしが可能です。
こうした編集作業は一見手間に思えますが、後から聞き返す回数を減らし、全体の作業効率を大幅に改善する効果があります。
関連記事:対面会議・録画ファイルにもAI議事録が使える!?すべての会議の議事録作成の負担を軽減する方法を解説!
文字起こしを実行する
文字起こしのやり方の4番目は、文字起こしを実行することです。
録音データを整えたら、いよいよ文字起こしを実行していきます。従来は一字一句入力する手作業が一般的でしたが、現在ではツールを活用して効率的に進める方法が主流です。
専用ソフトやクラウドサービスを利用すれば、音声を自動でテキスト化でき、膨大な作業時間を大幅に削減できます。
特にAIによる自動文字起こしは精度が高く、話者分離や専門用語の認識にも対応するサービスが増えており、会議やインタビューなどビジネスシーンでも十分活用可能です。
もちろん完全に正確というわけではなく、固有名詞や聞き取りにくい部分は修正が必要ですが、人手による負担は格段に減るでしょう。
関連記事:初心者でも迷わない!文字起こしツール無料版のメリット・注意点・おすすめツールも紹介!
関連記事:文字起こしに便利なAIツールおすすめ7選
出力されたテキストを整える
文字起こしのやり方の5番目は、出力されたテキストを整えることです。
文字起こしツールで起こしたテキストは、「あのー」「えっと」といった不要なつなぎ言葉や言いよどみも含まれてしまうことが多いため、そのままでは読みにくくなります。
まずはそうした不要な表現を削除し、内容をすっきりと整理することが大切です。
さらに、口語のままでは文が長く途切れがちになるため、適切に句読点を加えたり、段落を分けたりして文章構造を整えましょう。
必要に応じて助詞を補ったり語順を調整したりすることで、読み手にとって理解しやすい文に仕上げられます。
関連記事:文字起こしと要約を最短で終わらせよう!流れとおすすめツールを紹介
固有名詞や専門用語を確認する
文字起こしのやり方の6番目は、固有名詞や専門用語を確認することです。
AIによる自動文字起こしは便利ですが、人名や会社名、業界特有の専門用語は誤認識されやすく、そのままでは誤った情報が伝わってしまう可能性があります。
特に、同音異義語やカタカナ用語は誤変換が多いため注意が必要です。例えば「佐藤」と「加藤」のように、似た発音が別の単語として出力されることも珍しくありません。
そのため、出力後には必ずテキストを見直し、発言内容や文脈に照らして正しい表記へ修正しましょう。
また、事前に業界用語や関係者名を辞書登録しておけば、自動変換の精度を高めることも可能です。こうした確認作業を徹底することで、正確で信頼性の高い文字起こしを完成できます。
最終チェック・保存・共有
文字起こしのやり方の7番目は、最終チェック・保存・共有です。
まず、出力されたテキストを全体的に読み直し、誤字脱字や文法の不自然な部分を修正します。この段階で内容が正確に伝わるか、読みやすさに問題がないかを確認しましょう。
その後、用途に応じて適切な形式で保存します。例えば、議事録ならWordやPDF、データベースに蓄積する場合はテキストファイルなど、活用目的に合った形で管理するのが効果的です。
さらに、必要に応じて関係者へ速やかに共有することで、情報の透明性や業務のスピードを高められます。共有時にはアクセス権限や機密性にも配慮し、誤送信を防ぐ工夫も欠かせません。
最終的なチェックと適切な保存・共有を行うことで、文字起こしは単なる記録ではなく、組織にとって価値ある情報資産として残り、次の活用へとつながります。
関連記事:【保存版】議事録を共有する手段5選!おすすめツールと注意点も解説
関連記事:アプリで議事録作成・共有を効率化!おすすめ11選も紹介(無料あり)
■おすすめの文字起こしツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的な文字起こしができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
文字起こしを効率よく進めるやり方

ここでは、文字起こしを効率よく進めるやり方について、以下の4点を解説します。
- 音声を一通り聞いておく
- 音声データを最適化する
- 辞書登録
- ツールの活用
1つずつ見ていきましょう。
音声を一通り聞いておく
文字起こしを効率よく進めるやり方の1つ目は、音声を一通り聞いておくことです。
作業を始める前に最初から最後まで音声を確認することで、会話や発言の全体像を把握でき、内容の流れや重要なポイントを掴めます。
事前に流れを理解していれば、どこで強調すべきか、どの部分に専門用語や固有名詞が出てくるかを予測できるため、文字起こし中に立ち止まる回数が減り、効率的に進められるのです。
また、録音状態の良し悪しや聞き取りにくい箇所も把握でき、後で重点的に確認する時の目安になります。
さらに、音声のテンポや話者の特徴を事前に掴めるため、実際の作業時に文字起こししやすくなるのもメリットでしょう。
音声データを最適化する
文字起こしを効率よく進めるやり方の2つ目は、音声データを最適化することです。
録音した音声には、周囲の雑音やマイクの位置による異なる音量が含まれている場合が多く、そのまま自動文字起こしツールにかけると誤認識が増えてしまいます。
そこで、雑音を除去したり、音量を均一に整えたりといった前処理を行うことで、AIによる文字起こしの精度を大幅に高められます。
特に、複数人が発言する会議録音では、発言者ごとの声の大きさが異なるため、事前に調整しておくと聞き取りやすくなるでしょう。
準備をしっかりとすることでしておけば、後から修正する手間も減り、全体の作業効率が向上します。
辞書登録
文字起こしを効率よく進めるやり方の3つ目は、辞書登録です。
自動文字起こしツールや音声入力機能を利用する時、専門用語や人名などは誤認識されやすく、毎回修正するのは大きな手間です。
そこで、よく使う業界用語・会社名・製品名・担当者名などを事前に辞書登録しておくことで、変換ミスを大幅に減らせます。
例えば「クラウドサービス名」や「特定のプロジェクト名」などを登録しておけば、自動的に正しい表記が反映され、修正の手間を省けます。
辞書登録は一度設定すれば継続的に活用できるため、作業効率アップだけでなく精度向上にもつながるでしょう。
ツールの活用
文字起こしを効率よく進めるやり方の4つ目は、ツールの活用です。
従来のように音声を聞きながら一字一句を手作業で入力していく方法は、時間も労力もかかり、集中力も長く続きにくいものです。
そこで役立つのが、文字起こし機能が含まれたツールの選択です。ツールを使えば、録音データを自動でテキスト化でき、手作業に比べて大幅な時間短縮が可能です。
最近はAI技術の進化により、話者ごとの区別や専門用語の認識精度も向上しているツールも多く、会議やインタビューといったビジネスシーンでも十分活用できるでしょう。
もちろん誤認識が発生することはありますが、文字起こししたデータがある状態で人手で整文や修正を行えば、効率がアップするのです。
関連記事:対面会議・録画ファイルにもAI議事録が使える!?すべての会議の議事録作成の負担を軽減する方法を解説!
関連記事:【2025年版】議事録作成ツールおすすめ12選(無料あり)選び方も紹介
文字起こしなら「CrewWorks」がおすすめ
CrewWorks(クルーワークス)は、タスク管理やビジネスチャット、会議の記録などを一元化できるオールインワンツールで、社内の情報を効率的に統合・共有できます。会議の議事録作成や情報整理をスムーズに進められるだけでなく、タスクやチャットと連携することで、発言内容をそのまま業務に反映できるのも大きな魅力です。最近では外部ファイルの取り込みにも対応し、録音データや動画から自動で文字起こしを行う機能が追加されました。文字起こしと業務管理を同時に効率化できる点で、企業担当者にとって頼れるツールでしょう。
CrewWorksの特長
- 生成AIを使ってWeb会議の録画データ等から文字起こしが可能
- 導入社数3,000社を突破
- 30日間無料トライアル有
詳細はこちら: https://crewworks.net/
関連記事:対面会議・録画ファイルにもAI議事録が使える!?すべての会議の議事録作成の負担を軽減する方法を解説!
まとめ

今回は、文字起こしの基本的なやり方から効率化のコツ、おすすめツールまでを解説しました。
文字起こしの知識である、素起こし・ケバ取り・整文などを理解して、目的に応じて使い分けることで、読みやすく実用性の高い文章に仕上げられます。
さらに、辞書登録や自動文字起こしツールを活用することで、効率化と精度向上の両立も可能です。
会議やインタビューを正確に記録するためには、録音環境を整え、データを最適化し、効率的に文字起こしを行えるツールの活用がおすすめです。
日々の業務を効率化し、情報共有をスムーズに進めたい企業担当者にとって、文字起こしツールは大きな武器となるでしょう。