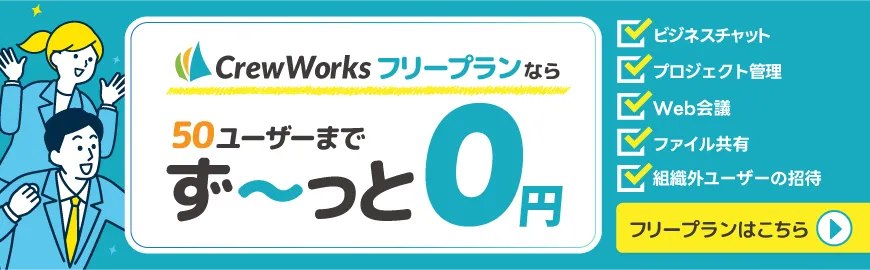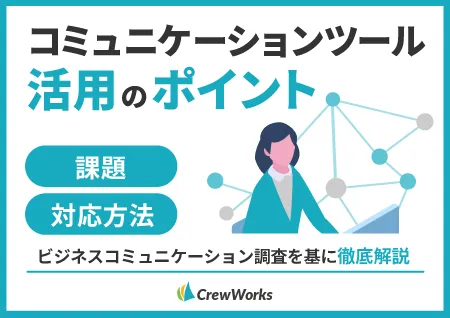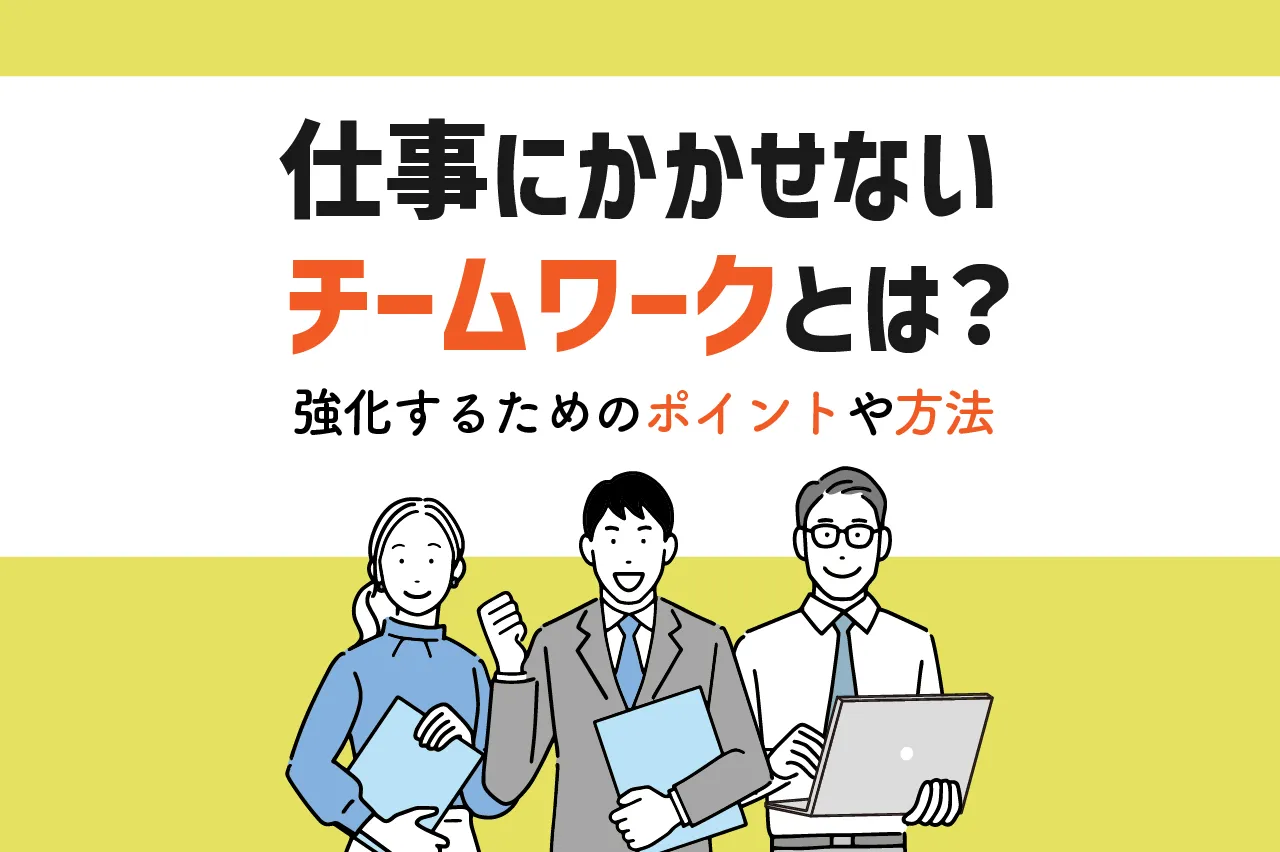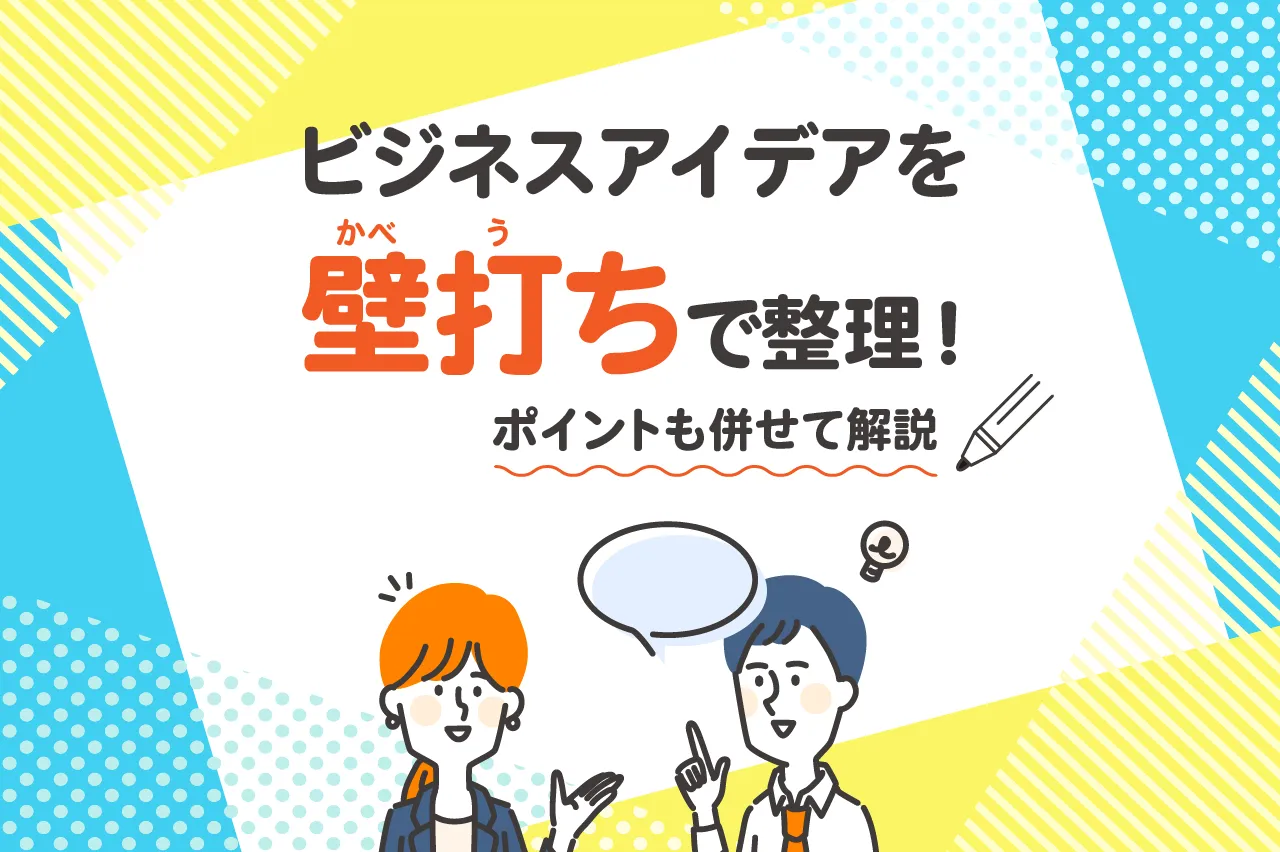業務の引き継ぎで悩まない!スムーズに行うための事前準備や効果的な方法を徹底解説
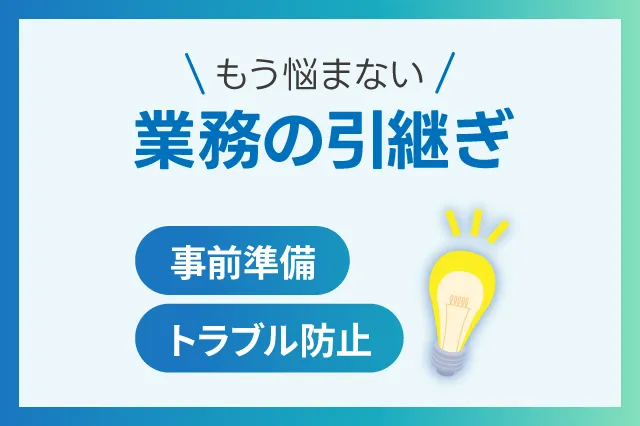
業務の引き継ぎは後任者がスムーズに仕事を進められるようにするために欠かせないものです。
しかし、急いで準備をするとミスや漏れが発生することもあります。
さらに、引き継ぎ資料の作成や適切なコミュニケーションも、意外と手間がかかるものです。
そこで今回は、失敗しないための引き継ぎのコツや事前準備の方法を具体的に解説します。
【目次】
■合わせて読まれている資料
あなたの会社ではコミュニケーションツールを使いこなせていますか?
・アンケートから分かるコミュニケーションの課題
・他社のツール利用状況と利用時の課題
を学べる資料です。
⇒コミュニケーションツール活用のポイントを徹底解説した資料を無料ダウンロードする
業務の引き継ぎが重要な理由

ここでは、業務の引き継ぎが重要な理由について、以下の4点を解説します。
- 業務の継続性を保つ
- 知識やノウハウの伝承
- トラブル防止とリスク管理
- 社内の信頼関係の構築
1つずつ見ていきましょう。
業務の継続性を保つ
業務の引き継ぎが重要な理由の1つ目は、業務の継続性を保つためです。
異動や休職・転職、また長期休暇により担当者がいなくなる場合でも、業務が滞らず進行することは大切です。
引き継ぎを通して後任者がスムーズに業務を進められる環境を整えることで、業務の遅延やクオリティの低下を防ぐことができます。
また、引き継ぎがしっかり行われていることで、後任者も安心して業務に取り組むことができるため、全体のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。
組織全体としても、業務の継続性を保つことは信頼性向上に寄与し、安定した組織運営が可能になります。
知識やノウハウの伝承
業務の引き継ぎが重要な理由の2つ目は、知識やノウハウの伝承です。
担当者が業務を通して培ってきた知識や効率的な進め方・現場での工夫などは、企業にとって貴重な財産です。
これらを引き継ぐことで、後任者は一から学ぶ手間が省け、業務に速やかに対応できるようになります。
また、知識やノウハウの伝承は企業全体の生産性向上にも繋がり、企業の持続的な発展を支えます。
特に専門性が高い業務や独自のスキルを要する業務においては、引き継ぎが組織の競争力維持にも貢献します。ノウハウの共有は、個人に依存しない強い組織づくりのために極めて重要です。
関連記事:ノウハウ共有ツールで情報管理を効率化!選び方のポイントとおすすめ7選
トラブル防止とリスク管理
業務の引き継ぎが重要な理由の3つ目は、トラブル防止とリスク管理です。
引き継ぎが不十分な場合、業務の進行中に思わぬトラブルが発生し、後任者が対応に困る場面も少なくないでしょう。
重要なポイントや業務の進行上の注意事項を正確に伝えておくことで、後任者が適切な対処をしやすくなり、トラブルを未然に防げます。
また、引き継ぎをしっかり行うことは、リスク管理の観点からも重要で、組織全体として安定した業務運営を実現します。
引き継ぎのときにリスク要因を共有しておくことで、会社全体でリスクに備える体制を整えることができます。
関連記事:プロジェクト管理のカギを握る「リスク管理」を徹底解説!
社内の信頼関係の構築
業務の引き継ぎが重要な理由の4つ目は、社内の信頼関係の構築です。
引き継ぎを丁寧に行うことで、後任者が安心して業務に臨むことができるため、自然と社内の信頼関係が生まれます。
先任者が引き継ぎに注力し、業務に必要な情報をしっかりと共有することで、後任者も自信を持って業務に取り組むことができます。
これにより、部署内やチーム内での人間関係が良好になり、組織全体の協力体制が強化されます。
また、信頼関係が構築されることで業務を進める上でのコミュニケーションも円滑に行われ、職場の雰囲気もよくなります。人と人との信頼関係は、組織における大切な基盤です。
▼引き継ぎ資料の情報が古くなり役に立たない…何度も更新する手間がめんどう…
ナレッジの陳腐化を防ぎ、最大限にナレッジを活用したい方は、こちらをご覧ください。
ナレッジ活用における課題と最大限にナレッジ活用するためのツールの選び方とは?
業務の引き継ぎを行わないことによるリスク

ここでは、業務の引き継ぎを行わないことによるリスクについて、以下の4点を解説します。
- 業務効率や生産性の低下
- 顧客や取引先からの信頼を損なう
- ノウハウやナレッジが継承されない
- 後任者がストレスを抱える
1つずつ見ていきましょう。
業務効率や生産性の低下
業務の引き継ぎを行わないことによるリスクの1つ目は、業務効率や生産性の低下です。
業務の引き継ぎが適切に行われないと、後任者は業務の進め方がわからず、結果として業務効率や生産性が大幅に低下するリスクがあります。
例えば、必要な情報が不足しているために、後任者が自分で一から調べたり、上司や関係者に何度も質問したりすることになり、本来の業務に集中できない状況が発生するのです。
特に、前任者が退職してしまっている場合や、新たな業務に忙殺されている場合は、質問できる相手が限られるため、後任者はより一層の負担を抱えることになります。
業務の全体像や細かい手順が不明瞭なままだと、後任者は不安やストレスを抱えやすくなり、これが業務の停滞や質の低下を引き起こす悪循環となるのです。
顧客や取引先からの信頼を損なう
業務の引き継ぎを行わないことによるリスクの2つ目は、顧客や取引先からの信頼を損なうことです。
顧客や取引先は、担当者個人だけでなく、企業全体を信頼して商品やサービスを利用しているため、担当者が変わったことで業務上のミスや滞りが生じると、企業への不信感につながる可能性があるのです。
これにより、顧客満足度が低下し、最悪の場合、顧客離れや契約解除といった事態に発展し、企業の業績に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
このようなリスクを回避するためには、担当者の変更は企業都合であることを認識し、取引先や顧客に不利益が生じないよう、前任者が築いた信頼関係を維持するための丁寧な引き継ぎが不可欠です。
具体的には、重要な取引先や顧客に対しては、後任者をきちんと紹介し、これまでの関係性や経緯について詳細に伝えることが求められます。
ノウハウやナレッジが継承されない
業務の引き継ぎを行わないことによるリスクの3つ目は、ノウハウやナレッジが継承されないことです。
業務マニュアルだけでは伝えきれない、実践を通して得られた「暗黙知」と呼ばれるノウハウや、経験に裏打ちされた知識(ナレッジ)が、引き継ぎが不十分なことで失われてしまう可能性が高いです。
特に、長年同じ業務を担当していたベテラン社員の場合、その知見が属人化しており、退職や異動の際に引き継ぎがうまくいかないと、貴重なノウハウが社内に蓄積されず、消失する恐れがあります。
ノウハウやナレッジが継承されないことは、中長期的に見て組織にとって大きな損失です。 こうした事態を防ぎ、企業の競争力を維持するためには、属人化しやすいノウハウを可視化し、組織全体で共有する仕組みを整えることが不可欠です。
効率的なノウハウ継承は、個人のスキルを組織全体の力へと高め、企業の持続的な成長を支える上で欠かせません。
関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説
後任者がストレスを抱える
業務の引き継ぎを行わないことによるリスクの4つ目は、後任者がストレスを抱えることです。
業務の進め方が不明瞭なままだと、後任者は不安や焦りを感じ、「何から手をつければ良いかわからない」という状況に陥ることがあります。
特に、マニュアルの不備や口頭での説明が断片的な場合は、業務全体の把握が難しく、混乱を招きかねません。このような状況が続くと、後任者は業務へのモチベーションを失い、最悪の場合、離職につながるリスクも考えられます。
スムーズな引き継ぎと後任者の負担軽減のためには、十分な時間確保と情報の漏れがない丁寧な引き継ぎが不可欠です。
関連記事:仕事引き継ぎでイライラが限界!原因・影響・対処法をわかりやすく解説
業務の引き継ぎのスムーズな進め方

ここでは、業務の引き継ぎをスムーズに進めるためのステップについて、以下の4点を解説します。
- 業務内容の棚卸と整理
- 引き継ぎスケジュールの作成
- 引き継ぎ資料の作成と共有
- ミーティングの実施とフォローアップ
1つずつ見ていきましょう。
業務内容の棚卸と整理
業務の引き継ぎをスムーズに進めるためのステップの1つ目は、業務内容の棚卸と整理です。
スムーズな引き継ぎには、まず業務内容の棚卸と整理が不可欠です。現在担当している業務内容を全て洗い出し、重要度や優先度をしっかりと分類しましょう。
具体的には、日常的な業務・期間限定の業務・特別なスキルを要する業務などに整理すると分かりやすくなります。
この作業によって後任者に引き継ぐべき業務範囲が明確になるだけでなく、引き継ぎの漏れを防ぎ、重要業務が滞ることを防ぐことができます。
また、業務内容が整理されていると、後任者も業務全体の把握がしやすくなるため、スムーズな移行が可能です。
引き継ぎスケジュールの作成
業務の引き継ぎをスムーズに進めるためのステップの2つ目は、引き継ぎスケジュールの作成です。
棚卸した業務の一覧表を基に、引き継ぎのスケジュールを作成しましょう。計画的に引き継ぎを進めることで、後任者が準備や質問の時間を確保できるようにします。
まず、退職日や異動日、引き継ぎ業務量や難易度から逆算して、引き継ぎ完了までの期間を把握しましょう。
その後、段階ごとの目標を立て、優先順位の高い業務から順に引き継いでいきます。 また、後任者の通常業務の都合や負担も考慮し、引き継ぎの進捗確認のための時間を設けるとよいでしょう。
計画的なスケジュール作成によって、引き継ぎの無駄を減らし、効率よくスムーズに進めることができます。
関連記事:スケジュール管理ツールで時間を制す!おすすめ8選と選び方を紹介
引き継ぎ資料の作成と共有
業務の引き継ぎをスムーズに進めるためのステップの3つ目は、引き継ぎ資料の作成と共有です。
後任者が業務内容を理解しやすいように、口頭のみにせずマニュアルとなる引き継ぎ資料を分かりやすく作成し、文書化して共有することも重要です。
資料には、業務の目的や詳細な手順・やり方、よくある問題とその対処方法などを記載し、後任者が困ったときに参考にできるようにしましょう。
また、関連書類の保管場所や、問い合わせ先なども添えておくと便利です。資料を適切に共有することで、後任者が自分で確認しながら業務に取り組めるようになり、引き継ぎの負担も軽減されます。
オンラインで共有できる環境があれば、更新も容易で効率的です。
ミーティングの実施とフォローアップ
業務の引き継ぎをスムーズに進めるためのステップの4つ目は、ミーティングの実施とフォローアップです。
直接的なミーティングを行い、対面またはオンラインで後任者に業務内容を共有しながら引き継ぎを行いましょう。
ミーティングでは、引き継ぎ資料に記載しきれない詳細な説明を加えたり、後任者の質問にその場で回答したりすることで、理解度を深めます。
また、重要部署の場合や対外業務が含まれる場合は、取引先や他部署への同行も検討しましょう。
引き継ぎ後も、後任者が困ったときに気軽に相談できる環境を整えることが大切です。フォローアップによって、引き継ぎ完了後はスムーズに業務を開始できるでしょう。
分かりやすい業務引き継ぎ資料の作成方法
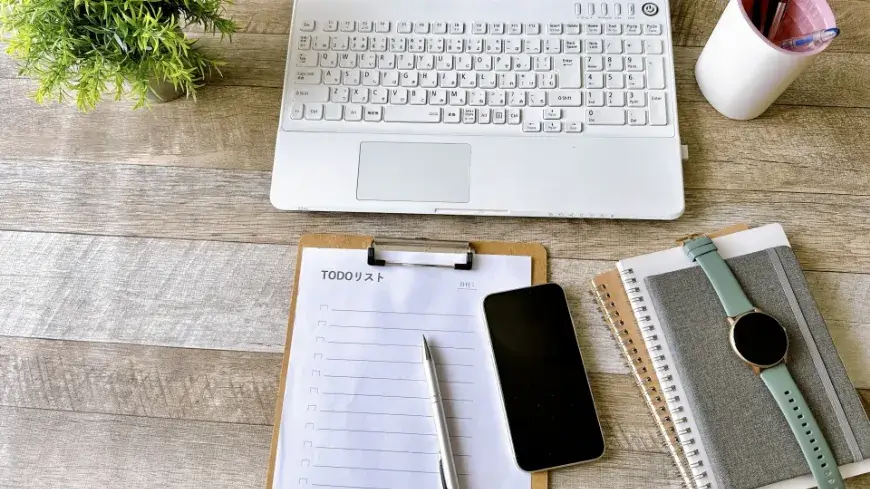
ここでは、分かりやすい業務引き継ぎ資料を作成するためのポイントを3点解説します。
- 後任者が理解しやすい資料作成のコツ
- 引き継ぎ資料に盛り込むべき項目
- 引き継ぎ資料のテンプレートと活用法
1つずつ見ていきましょう。
後任者が理解しやすい資料作成のコツ
後任者が引き継ぎ資料を見て業務を理解しやすくするためには、簡潔で明確な表現と、項目ごとに整理された情報提供が大切です。
業務内容を分かりやすく見出しや項目ごとに分類し、複雑な内容については図や表を用いて視覚的に伝えるよう工夫しましょう。
特に、後任者がその業務に初めて関わる場合は、専門用語の簡単な解説や、過去の事例を交えることで、より実感を伴った理解が可能になります。
こうした工夫により、後任者が迷わず業務を進めるための道筋が示され、引き継ぎがスムーズに進む効果が期待できます。
関連記事:引き継ぎマニュアルの作り方は5つの手順!わかりやすく作るポイントも解説
引き継ぎ資料に盛り込むべき項目
引き継ぎ資料には、担当業務の全体的な概要・具体的な手順や流れ・関係者や関係部門の連絡先・業務の優先度・定期的なスケジュールに加え、想定される問題点とその対処法を網羅することが求められます。
これらの項目を盛り込むことで、後任者が業務の内容を安心して把握できるだけでなく、突発的な問題が発生しても適切に対応できるようになります。
特に、業務の要所やリスクの高い場面を明記することで、後任者が意識して取り組むことができ、結果的に円滑な業務の継続に寄与するでしょう。
引き継ぎ資料のテンプレートと活用法
引き継ぎ資料の作成には、効率的で統一感のあるテンプレートを活用することが推奨されます。
テンプレートには、必要な基本項目があらかじめ設定されているため、情報を漏らさずに記入することが可能です。
テンプレートを利用することで、後任者も情報を確認しやすく、また内容を理解しやすくなります。
さらに、営業支援システムやコミュニケーションツールなどのデジタルツールを活用すれば、資料の共有がスムーズになり、即座に最新情報を更新することも可能です。
企業全体で統一したテンプレート導入を検討することで、引き継ぎ業務の効率向上が期待できます。
関連記事:ビジネスチャットとは?おすすめツール7選と活用のメリットや主な機能を比較解説
▼引き継ぎ資料の情報が古くなり役に立たない…何度も更新する手間がめんどう…
ナレッジの陳腐化を防ぎ、最大限にナレッジを活用したい方は、こちらをご覧ください。
ナレッジ活用における課題と最大限にナレッジ活用するためのツールの選び方とは?
業務引き継ぎ時の注意点と失敗しないためのポイント

ここでは、業務引き継ぎ時の注意点と失敗しないためのポイントについて、以下の6点を解説します。
- チェックリストの活用
- コミュニケーションの重要性
- 過去のトラブルやクレームを必ず伝える
- 後任者の理解度に合わせる
- 完了後のフォローアップ
- 閑散期に資料を作成しておく
1つずつ見ていきましょう。
チェックリストの活用
業務引き継ぎ時の注意点の1つ目は、チェックリストの活用です。
引き継ぎのときに業務内容が漏れないように、チェックリストを作成しておくことで、確実な引き継ぎが可能になります。
チェックリストには、引き継ぐべき業務項目や必要な情報を詳細に記載し、特に重要なタスク・連絡先・関連書類の場所なども網羅しておくと安心です。
また、リストを定期的にチェックし、必要な項目が漏れなく引き継がれているか確認することも大切です。
こうしたリストの活用によって、引き継ぎ時の不安が減り、安心して後任者に業務を引き継ぐことができます。
コミュニケーションの重要性
業務引き継ぎ時の注意点の2つ目は、コミュニケーションの重要性です。
引き継ぎをスムーズに進めるためには、後任者との円滑なコミュニケーションが欠かせません。
具体的には、業務内容を詳細に解説し、後任者が不明点を気軽に質問できる環境を整えることが重要です。
また、定期的に進捗確認を行い、引き継ぎが順調に進んでいるか、後任者が業務内容を十分に理解しているかを把握することで、トラブルの未然防止にも繋がります。
良好なコミュニケーションを保つことで、引き継ぎの質が向上し、後任者が安心して業務を進めることができます。
関連記事:職場のコミュニケーションを活性化させるためには?重要性とポイントを解説
過去のトラブルやクレームを必ず伝える
業務引き継ぎ時の注意点の3つ目は、過去のトラブルやクレームを必ず伝えることです。
過去のトラブルやクレームに関する内容は、後任者へ漏れなく伝えることが非常に重要です。共有する内容がなければ、同じようなトラブルやクレームが再度発生するリスクが高まります。
これにより、企業の信頼を損ねるだけでなく、大きな課題へと発展する可能性も考えられます。
そのため、トラブルの具体的な経緯や、それに対してどのような対応を行ったのか、そしてその後にどのような影響があったのかを詳細に引き継ぎ資料に記載しておく必要があります。
さらに、後任者が将来的に同様の状況に直面した際に参考にできるよう、未解決の課題や改善策についても明記することが求められます。
これにより、後任者は過去の事例から学び、適切な対応を取ることが可能になります。
後任者の理解度に合わせる
業務引き継ぎ時の注意点の4つ目は、後任者の理解度に合わせることです。
引き継ぎの過程で、後任者が業務内容を十分に理解しないまま進んでしまうと、業務の円滑な移行が難しくなります。
このような失敗を防ぐためには、できるだけ難しい専門用語などは使わずに業務内容を分かりやすく文書化し、逐次確認を行いながら引き継ぎを進めることが重要です。
また、後任者が業務に取り組むときに上司や同僚などのサポート体制を整えることで、不明点があっても迅速に解消でき、スムーズな移行が可能となります。
こうした対策により、引き継ぎの失敗を防ぎ、後任者が自信を持って業務に取り組むことができます。
関連記事:引き継ぎがうまくいかない5つの理由!失敗しないための対処法を解説
完了後のフォローアップ
業務引き継ぎ時の注意点の5つ目は、完了後のフォローアップです。
引き継ぎが完了した後も、後任者が業務に慣れるまではフォローアップが必要です。
具体的には、定期的な確認や不明点のヒアリングを行い、後任者が安心して業務に取り組める環境を整えましょう。
フォローアップは、後任者の不安を軽減し、業務のスムーズな移行を支えるだけでなく、後任者が自立して業務を遂行できるまでのサポートを提供します。
フォローアップを行うことで、引き継ぎが円滑に進み、組織全体の業務の質向上にも貢献します。
閑散期に資料を作成しておく
業務引き継ぎ時の注意点の6つ目は、閑散期に資料を作成しておくことです。
転勤や異動が決まってから急いで引き継ぎ資料を作成すると、焦りから情報が漏れる恐れや、内容が不十分になる可能性があります。
そのため、業務が比較的落ち着いているときに、事前に引き継ぎ資料を作成しておくことが重要です。こうしておけば、引き継ぎが決まったときにも余裕を持って対応できます。
担当者が急な病気や怪我で業務を一時的に離れる場合も、周りのフォローがスムーズに進むため、安心して業務を引き継ぐことができます。事前準備が、スムーズな引き継ぎを実現します。
関連記事:ナレッジの効果的な共有方法とは?具体例も含めてわかりやすく解説
まとめ

今回は、業務引き継ぎをスムーズに進めるためのポイントと注意点について解説しました。
業務の棚卸しや詳細な引き継ぎ資料の作成、そして後任者との丁寧なコミュニケーションとフォローアップが重要です。
また、事前にチェックリストやテンプレートを活用することで引き継ぎ漏れを防ぎ、必要に応じてサポート体制を整えることで、後任者が自信を持って業務を進められる環境を作りましょう。
効率的な引き継ぎのために、オンラインでの情報共有やコミュニケーションツールの導入もぜひ検討しましょう。
▼引き継ぎ資料の情報が古くなり役に立たない…何度も更新する手間がめんどう…
ナレッジの陳腐化を防ぎ、最大限にナレッジを活用したい方は、こちらをご覧ください。
ナレッジ活用における課題と最大限にナレッジ活用するためのツールの選び方とは?
|
コミュニケーションツール活用のポイント
コミュニケーションツールを導入し利用しているものの、うまくコミュニケーションが取れないと感じていませんか?
|