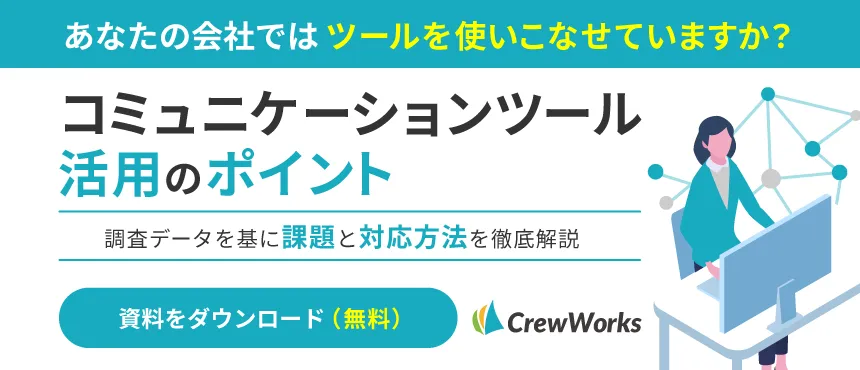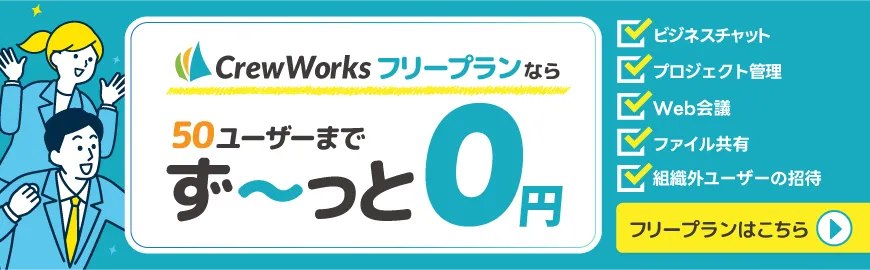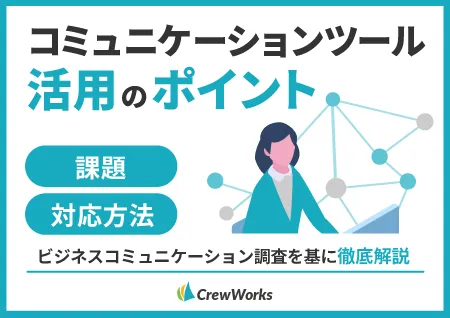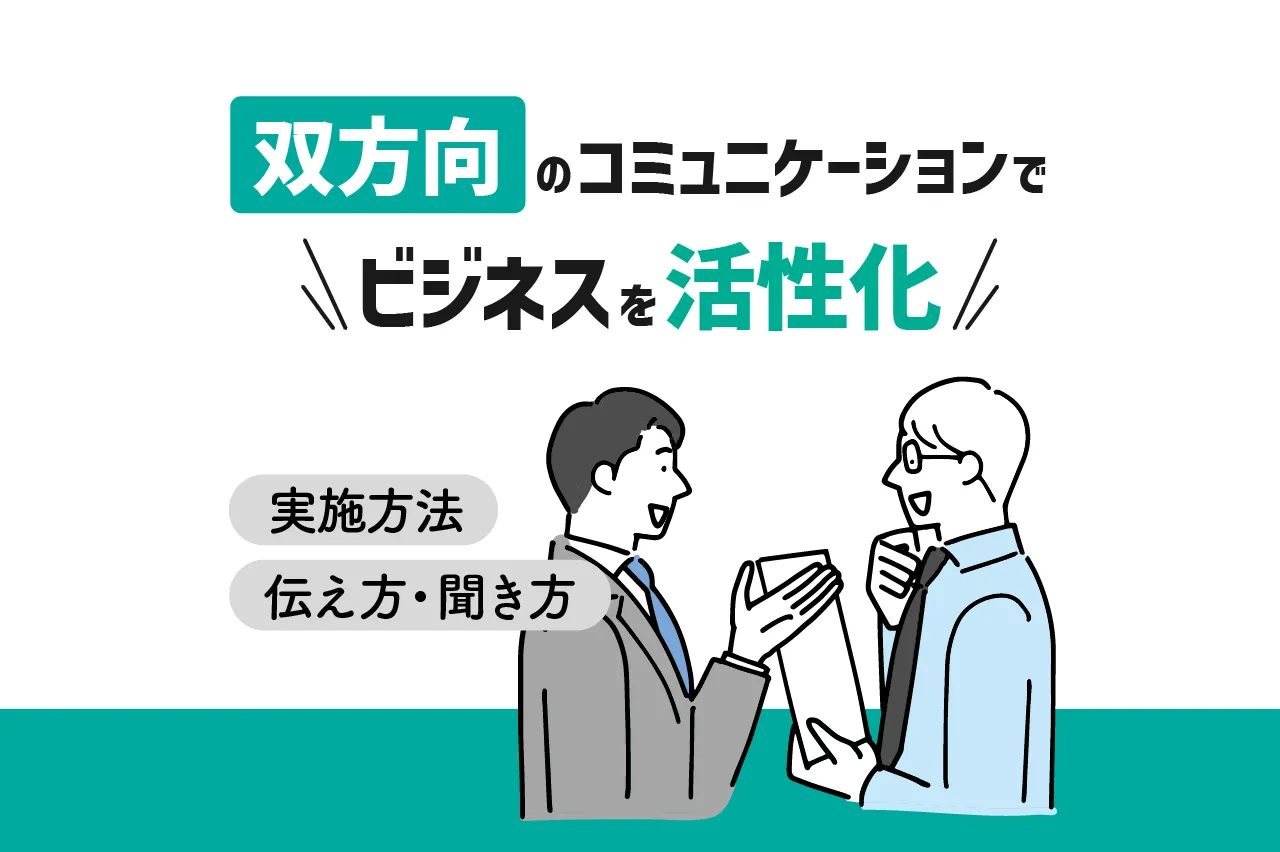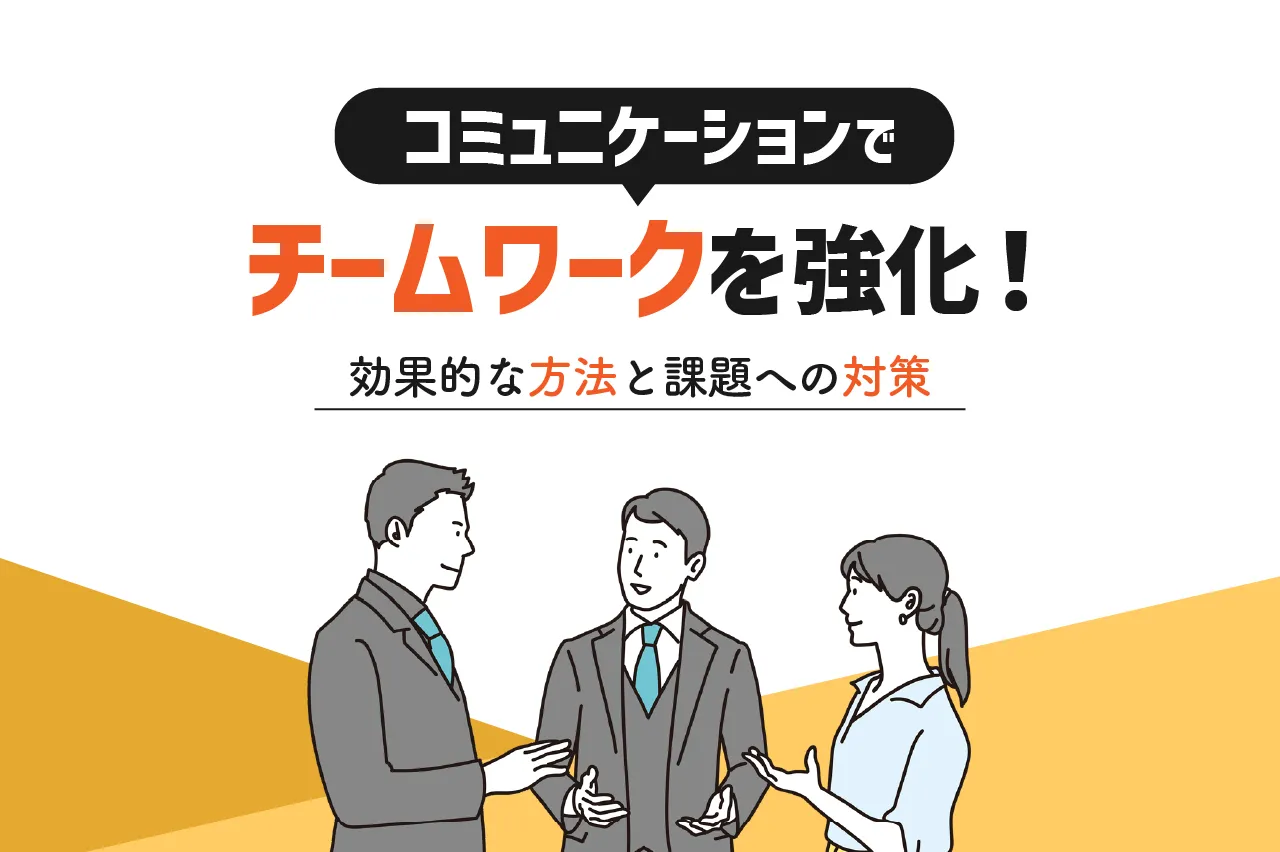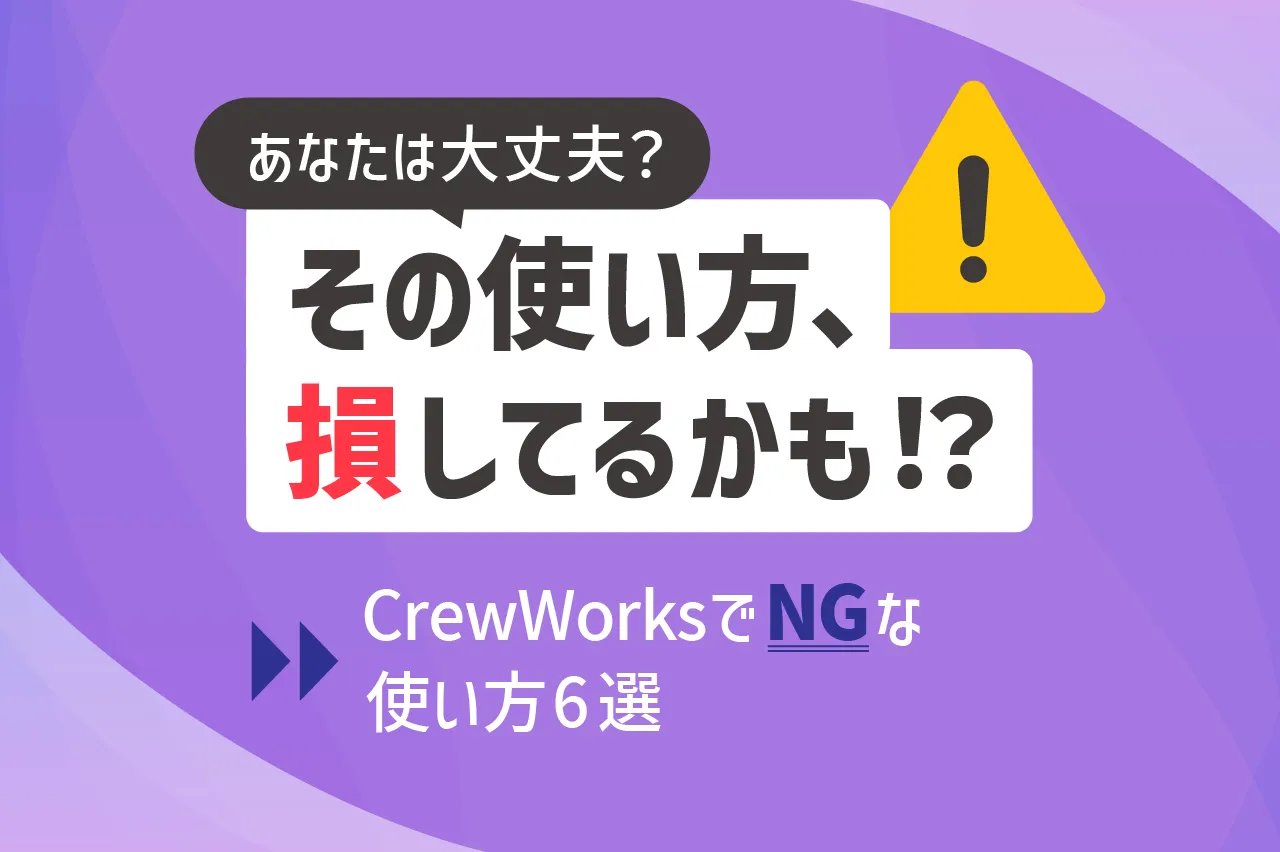コミュニケーションコストが高い!問題点と個人・組織の削減方法を解説
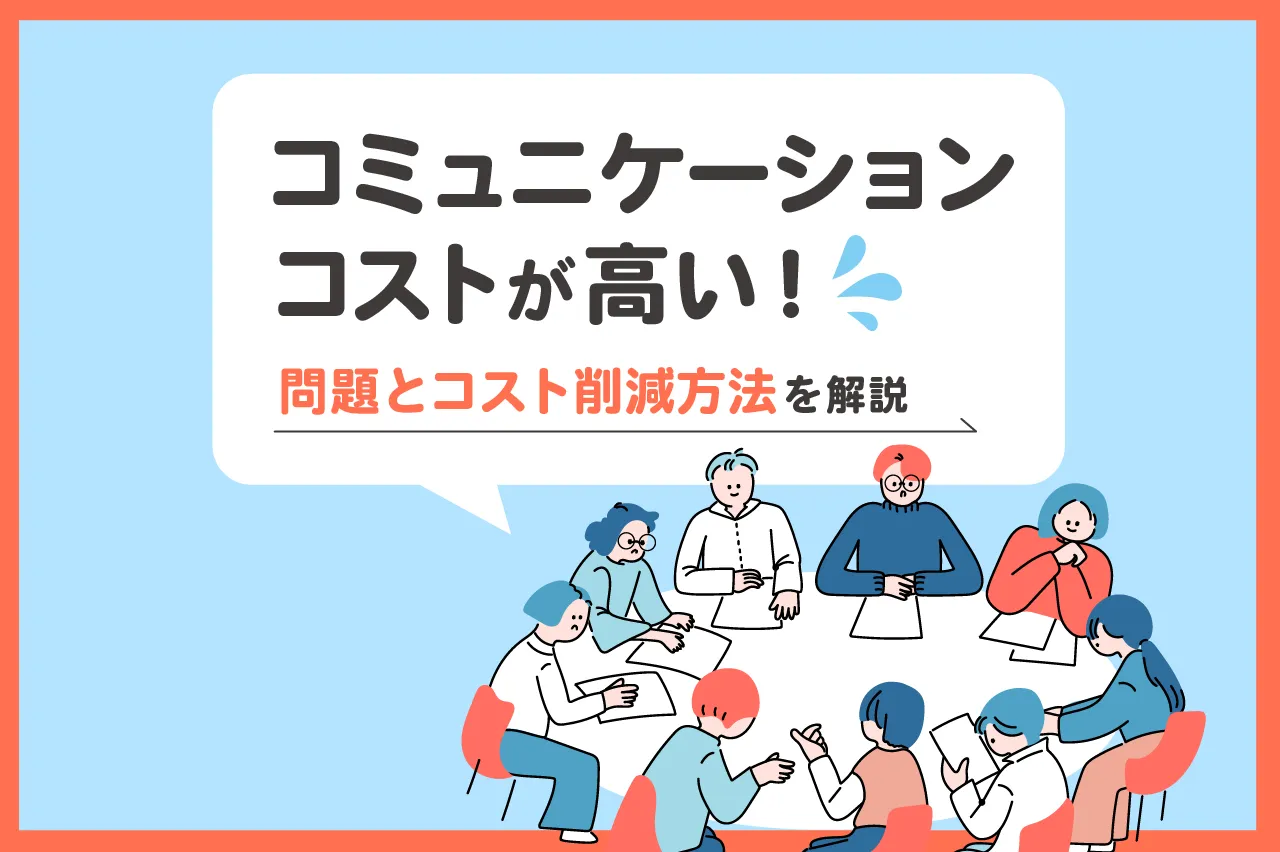
ただ、コミュニケーションに余計な手間がかかると、業務に支障が出ることもあるでしょう。
そこで重要なのが、「コミュニケーションコスト」です。
詳細な内容は後述しますが、ブルックスの法則によると、メンバーが多くなるほどコミュニケーションコストが増大する傾向にあります。
また、コミュニケーションコストが高い人の特徴や下げる方法について把握していると、コミュニケーションコストが課題になっている場合でも的確に対処できます。
そこで今回は、コミュニケーションコストの意味や高いことによって生じる問題に加え、その下げ方を解説します。
【目次】
コミュニケーションコストとは

コミュニケーションコストとは、職場での情報共有や意思疎通に必要な時間や労力です。ビジネスを進める過程では、社内外の関係者とのコミュニケーションが必ず発生します。
ただ、そのコミュニケーションに手間がかかりすぎると業務に支障が出かねません。
ここでは、コミュニケーションコストに関する基礎知識について、以下の2点を解説します。
- ブルックスの法則
- コミュニケーションコストの計算方法
1つずつ見ていきましょう。
ブルックスの法則
コミュニケーションコストに関する基礎知識の1つ目は、ブルックスの法則です。
ブルックスの法則とは、「チームメンバーが増加するほどコミュニケーションに必要な時間や手間が膨らみ、かえってプロジェクトの完了が遅れる」とする法則です。
この法則に沿って考えると、単純に人手を増やせば作業が早く終わるとは限りません。むしろ調整や情報共有の負担が重くなることで、全体の効率が悪化する可能性もあるでしょう。
関連記事:プロジェクトマネジメントはチームで仕事を行うときに必須!運営のポイントやアイデアも解説
コミュニケーションコストの計算方法
コミュニケーションコストに関する基礎知識の2つ目は、コミュニケーションコストの計算方法です。
ブルックスの法則では、人数増加に伴いコミュニケーションコストが増大すると先ほど解説しました。具体的には、コミュニケーションにかかる負担は関係人数の2乗に比例して増加すると言われています。
例えばメンバーが3倍になれば、情報共有や調整にかかる時間は9倍になります。
作業を細分化して分担することには限界があり、全員が同じレベルで内容を理解できるよう、説明や調整は避けられないからです。
関連記事:社内コミュニケーションの問題点と主な原因、解決策を徹底解説
関連記事:労働時間の57%はコミュニケーション!?情報共有を効率化してコミュニケーションコストを削減する方法とは?
コミュニケーションコストが高い人の特徴

ここでは、コミュニケーションコストが高い人の特徴について、以下の3点を解説します。
- 情報内容の把握に時間がかかる
- 役割を理解できていない
- 話がよく脱線する
1つずつ見ていきましょう。
情報内容の把握に時間がかかる
コミュニケーションコストが高い人の特徴の1つ目は、情報内容の把握に時間がかかることです。
コミュニケーションコストが高いと、他の人と比べて情報を理解するまで多くの時間を要します。通常であれば簡潔な説明で済む内容でも、背景や経緯を含めた詳細な説明が欠かせません。
話の前提となる情報から順序立てて説明しなければならないため、結果的にやり取りに多くの時間と労力がかかるでしょう。
ただし、口頭でのやり取りが苦手でも文章なら理解しやすいなど、コミュニケーション方法を工夫することで改善できるケースもあります。
役割を理解できていない
コミュニケーションコストが高い人の特徴の2つ目は、役割を理解できていないことです。
自分が組織でどのような役割を期待されているか把握していなければ、上司への報告や部下への指示が必要以上に複雑になり、コミュニケーションコストが増大しかねません。
例えば、営業担当者であれば商談結果や受注量などの成果を報告すべきところを、出社してから呼ばれるまでの経緯を長々と説明してしまうこともあるでしょう。
このように、報告内容に余分な情報が含まれることで会話が長引き、他の従業員よりもコミュニケーションに時間がかかります。
話がよく脱線する
コミュニケーションコストが高い人の特徴の3つ目は、話がよく脱線することです。
話がよく脱線して、会話の中で自分の話題を優先する人や、無駄話を挟むことが多い人も、コミュニケーションコストがかかります。
そのような場合は円滑な意思疎通が困難で、関係ない話が先に出てきて、必要な情報を得るまでに余計なやり取りが生じるためです。
コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題

ここでは、コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題について、以下の4点を解説します。
- 業務効率が低下する
- チーム同士でうまく連携できない
- 意思決定が遅延する
- 従業員がストレスで疲弊する
1つずつ見ていきましょう。
業務効率が低下する
コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題の1つ目は、業務効率が低下することです。
コミュニケーションコストが膨らむと、本来の業務に割くべき時間やエネルギーまでコミュニケーションにかけなければなりません。
特に、過度な会議や不要な確認作業が増えると、生産性を大幅に損なうことになるでしょう。
業務効率の低下は、実質的な労務費の増大にも直結しかねません。本来必要な人員よりも多くの人員を配置しなければならない状況が発生するなど、金銭的なコスト増大にもつながりる問題と言えるでしょう。
関連記事:仕事効率化に役立つアイデア16選!実行する手順や事例も解説
関連記事:労働時間の57%はコミュニケーション!?情報共有を効率化してコミュニケーションコストを削減する方法とは?
チーム同士でうまく連携できない
コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題の2つ目は、チーム同士でうまく連携できないことです。
コミュニケーションコストが高いと、部署間の調整やチーム内連携に余計な時間と労力が必要になります。
例えば、会社の自部署では既に導入済みのツールと同機能のシステムについて、他部署が重複して検討することもあるでしょう。
これは縦割り組織特有の情報共有不足が原因で、本来避けられるはずの重複投資や作業効率の悪化につながりかねません。
関連記事:情報共有がチームワークを高める!具体的な手段やコツを解説
意思決定が遅延する
コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題の3つ目は、意思決定が遅延することです。
組織の意思決定には現場状況の正確な把握が欠かせませんが、コミュニケーションコストが高いと情報収集だけで多大な時間が必要です。
さらに、部署間での意思疎通にも時間がかかると、最終的な判断が大幅に遅れます。
その結果、限られた時間内で下せる決定数が制限されるため、事業やプロジェクト全体の進捗に深刻な影響を与え、競争力の低下につながりかねません。
従業員がストレスで疲弊する
コミュニケーションコストが高い組織に生じる問題の4つ目は、従業員がストレスで疲弊することです。
コミュニケーションコストが高い組織では、従業員が過度なストレスを抱えやすく、疲弊する傾向にあります。
情報伝達に無駄な時間や労力がかかり、自身の意見が伝わらない、あるいは理解してもらえないと感じることが増えるためです。
このような状況は、従業員の心身に大きな負担となり、精神的なストレスにつながります。コミュニケーションの質を見直し、ストレスを軽減するための対策を講じることが重要です。
コミュニケーションコストが高い要因

ここでは、コミュニケーションコストが高い要因について、以下の5点を解説します。
- コミュニケーション手法が統一されていない
- 不要な情報まで発信している
- 非効率な手法を活用している
- コミュニケーションがオープンになっていない
- 前提条件が共有されていない
1つずつ見ていきましょう。
コミュニケーションロスの原因と対策については、以下の記事で解説しています。
関連記事:もう悩まない!コミュニケーションロスの原因と対策を具体例付きで紹介
コミュニケーション手法が統一されていない
コミュニケーションコストが高い要因の1つ目は、コミュニケーション手法が統一されていないことです。
組織内でコミュニケーション手段が統一されていないと、情報伝達時に無駄な時間とコストが発生しかねません。
例えば、上司への報告でチャットとメールが混在しており使い分けも明確でないと、情報の見落としやタイムラグの原因になります。
また、既に報告済みの内容を再度伝える必要が生じたり、重要な情報が散逸したりするリスクも高まるでしょう。
関連記事:労働時間の57%はコミュニケーション!?情報共有を効率化してコミュニケーションコストを削減する方法とは?
不要な情報まで発信している
コミュニケーションコストが高い要因の2つ目は、不要な情報まで発信していることです。
情報を十分整理せず、不要な情報まで発信していると、余計な情報までやり取りする分コミュニケーションコストが増大します。
典型例は、複数の担当者が同じ内容を重複して報告することや、必要以上に詳細な情報を共有することです。
このような場合、情報発信側に余計な負担がかかる上、受信側も要点の把握に時間を要するため、全体的な業務効率が著しく低下します。
非効率な手法を活用している
コミュニケーションコストが高い要因の3つ目は、非効率な手法を活用していることです。
例えば体質が古い組織では、今でも紙媒体によるやり取りが珍しくありません。
しかし、デジタル上だけで十分情報のやり取りが可能な内容についても紙に印刷していると、情報共有効率が低下し、コミュニケーションコストがかかります。
また、Web会議システムや電話で十分な話でも対面での対話にこだわると、移動が必要な分余計なコミュニケーションコストがかかるでしょう。
関連記事:社内でペーパーレス化を促進!メリット・デメリットやポイントを解説
コミュニケーションがオープンになっていない
コミュニケーションコストが高い要因の4つ目は、コミュニケーションがオープンになっていないことです。
コミュニケーションがオープンでなければ、情報の偏りが発生します。
具体的には、少人数のミーティング内容が部署全体に共有されないケースや、1対1の連絡手段に依存するケースでは、特定の人だけが重要な情報を把握することになりかねません。
このように情報格差が発生すると、組織全体の連携が阻害されて、結果的に無駄な確認作業や重複業務を招くでしょう。
関連記事:サイロ化とは?意味や引き起こす要因・生じる問題などをまとめて解説
関連記事:職場の空気を変える!オープンコミュニケーションがもたらすメリットや方法を解説
前提条件が共有されていない
コミュニケーションコストが高い要因の5つ目は、前提条件が共有されていないことです。
組織固有の価値観や前提情報が共有されていない状態では、相手が伝えたい内容を正しく解釈してくれないリスクが高まります。
例えば、新商品開発時に企業理念が浸透していないと、各担当者が独自の解釈で会議に臨むため議論がまとまらないことになりかねません。
その結果、無駄な話し合いが増えて意思決定の遅延を招くでしょう。
コミュニケーションコストを下げる方法

ここでは、コミュニケーションコストを下げる方法について、以下の2点を解説します。
- 個人のコミュニケーションコストを下げる方法
- 組織のコミュニケーションコストを下げる方法
1つずつ見ていきましょう。
個人のコミュニケーションコストを下げる方法
まずは、個人のコミュニケーションコストを下げる方法について、以下の3点を解説します。
- 役割を明確にする
- 相手の話を傾聴する
- 5W1Hで話を整理する
1つずつ見ていきましょう。
役割を明確にする
個人のコミュニケーションコストを下げる方法の1つ目は、役割を明確にすることです。
まず組織における自身の役割や期待されていること、そしてその目的やミッションを明確にすることが重要です。
短期的な目標だけでなく、中長期的に目指すべき方向性まで理解することで、与えられた役割を果たすための行動が具体的になります。
自身の役割を正確に認識すると、それに必要なコミュニケーションの種類や頻度、内容が明確になり、無駄なやり取りを削減できるでしょう。
関連記事:プロジェクト管理におけるチームの全体像!各ポジションの役割を解説
相手の話を傾聴する
個人のコミュニケーションコストを下げる方法の2つ目は、相手の話を傾聴することです。
コミュニケーションの無駄なやり取りを削減するには、まず相手が伝えたい内容を正確に把握することが重要です。
相手の話に積極的に耳を傾け、必要に応じて質問を投げかけながら、相手の意図を深く理解するよう努めましょう。
これにより、認識の齟齬を防ぎ、的確な回答を返すことができるため、スムーズな意思疎通につながります。
5W1Hで話を整理する
個人のコミュニケーションコストを下げる方法の3つ目は、5W1Hで話を整理することです。
相手の話をヒアリングする際には、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して情報を整理することが効果的です。
このフレームワークを活用すると、相手が伝えたい内容を体系的に理解しやすくなり、認識のずれを防ぐことにつながります。
結果として、質問の回数を減らし、無駄なやり取りを削減できるでしょう。
組織のコミュニケーションコストを下げる方法
次に、組織のコミュニケーションコストを下げる方法について、以下の6点を解説します。
- 企業理念を浸透させる
- 部署ごとの役割や目的・機能を明確にする
- 社内教育の仕組みを整える
- マニュアルを作成する
- オープンなコミュニケーションを図る
- コミュニケーションの手段を統一する
1つずつ見ていきましょう。
企業理念を浸透させる
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の1つ目は、企業理念を浸透させることです。
社員一人ひとりが企業の目指す方向性や価値観を深く理解することで、業務における判断基準が統一され、認識のずれによる無駄なやり取りを削減できます。
これにより、日常業務での意思疎通がスムーズになり、効率的な情報共有が促進されるでしょう。
部署ごとの役割や目的・機能を明確にする
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の2つ目は、部署ごとの役割や目的・機能を明確にすることです。
各部署が果たすべき役割と目的、機能が明確であれば、メンバーそれぞれが必要な情報や把握すべき範囲を容易に理解できるようになります。
これにより、無用な質問や相談が減り、より有益な情報発信や交換が促進されるでしょう。結果として、組織全体の業務効率向上にもつながります。
社内教育の仕組みを整える
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の3つ目は、社内教育の仕組みを整えることです。
社員が自社の理念や価値観、行動規範を学ぶ機会を設けることで、組織全体での共通理解が深まります。
これにより、同じ目的意識を持って業務に取り組むことができ、より円滑なコミュニケーションが図れるでしょう。
一度きりの研修ではなく、定期的に実施することで、社員の理解をさらに深めることができます。
マニュアルを作成する
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の4つ目は、マニュアルを作成することです。
頻繁に寄せられる質問や定型業務についてマニュアルを整備することで、従業員は自己解決できるようになり、同じ内容の質問を繰り返す手間を省くことができます。
これにより、質問対応に費やしていた時間を主要業務に充てることが可能になります。
また、マニュアルがあることで、仮に質問が発生した場合でも、マニュアルを基に回答できるため、コミュニケーションにかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
関連記事:マニュアル管理ができていない職場は危ない?導入ステップ・おすすめツールを解説
関連記事:社内マニュアルの作成方法!メリット・デメリットと作成時のコツも解説
オープンなコミュニケーションを図る
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の5つ目は、オープンなコミュニケーションを図ることです。
特定の人だけが情報を把握する状況を避け、関係者全員が会話の内容を確認できる仕組みを整えることが重要になります。
これにより、情報の偏りをなくし、不要な確認作業や重複業務の発生を抑えることが可能になります。
関連記事:コミュニケーションでチームワークを変える!不可欠な理由と活かし方・課題と対策も紹介
コミュニケーションの手段を統一する
組織のコミュニケーションコストを下げる方法の6つ目は、コミュニケーションの手段を統一することです。
情報の見落としや伝達ミスを防ぎ、無駄なやり取りを削減する上で非常に重要です。
電話やメールだけでなく、ビジネスチャットやプロジェクト管理ツールといったデジタルツールを活用することで、会話形式の手軽な情報共有が可能となり、情報伝達にかかる時間と手間を大幅に削減できます。
これにより、従業員間の情報格差をなくし、より迅速な意思決定を促進できるでしょう。
関連記事:ビジネスチャットとは?おすすめツール7選と活用のメリットや主な機能を比較解説
関連記事:【2025年版】プロジェクト管理ツールおすすめ16選を徹底比較!5つの確認ポイントも紹介
まとめ

今回は、コミュニケーションコストの意味や高いことによって生じる問題に加え、その下げ方を解説しました。 コミュニケーションコストとは、職場での情報共有や意思疎通に必要な時間や労力です。
コミュニケーションコストがかかる人の特徴には、情報内容の把握に時間がかかることや、役割を理解できていないことなどがあります。
また、コミュニケーションコストが高いと、チーム同士の連携や業務進捗などにも支障が出かねません。
コミュニケーションコストが高い場合は、コミュニケーション手法や共有されている情報について見直しましょう。また、雰囲気づくりや仕組みづくりも重要です。
コミュニケーションコストを下げるおすすめのツールとして 「CrewWorks(クルーワークス)」があります。
CrewWorksにはビジネスに必要な機能が揃っており、業務上の情報共有をスムーズにし、コミュニケーションを円滑化する仕組みづくりに最適です。
コミュニケーションコストを効率的に下げたいと考えている企業担当者の方は、ぜひ導入を検討してみてください。
|
コミュニケーションツール活用のポイント
コミュニケーションツールを導入し利用しているものの、うまくコミュニケーションが取れないと感じていませんか?
|