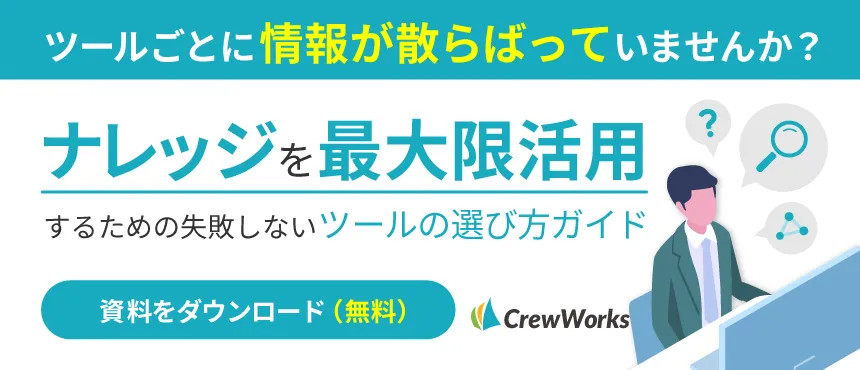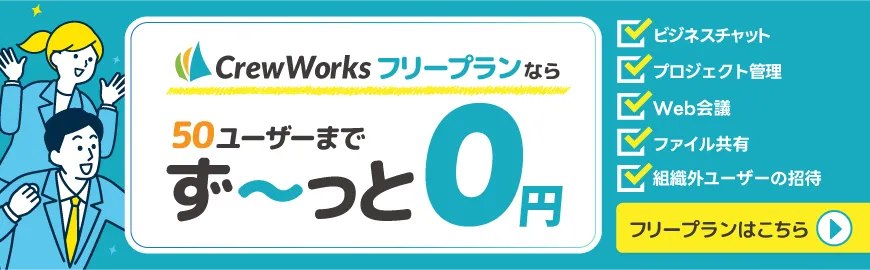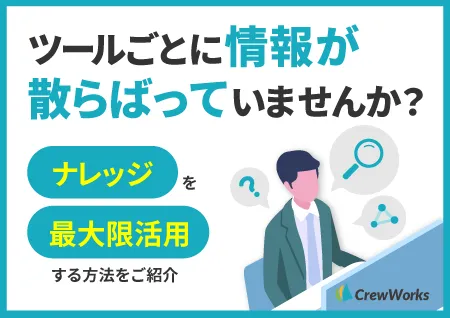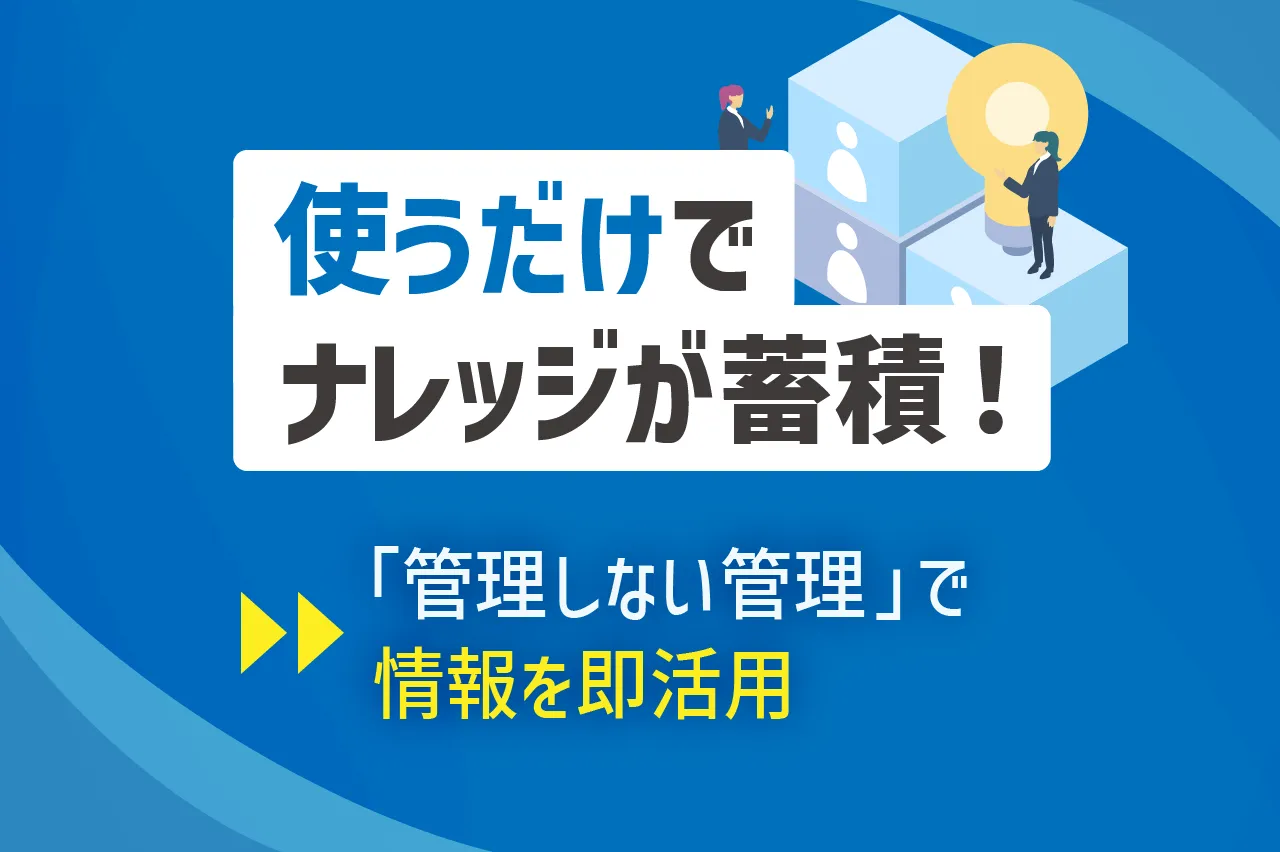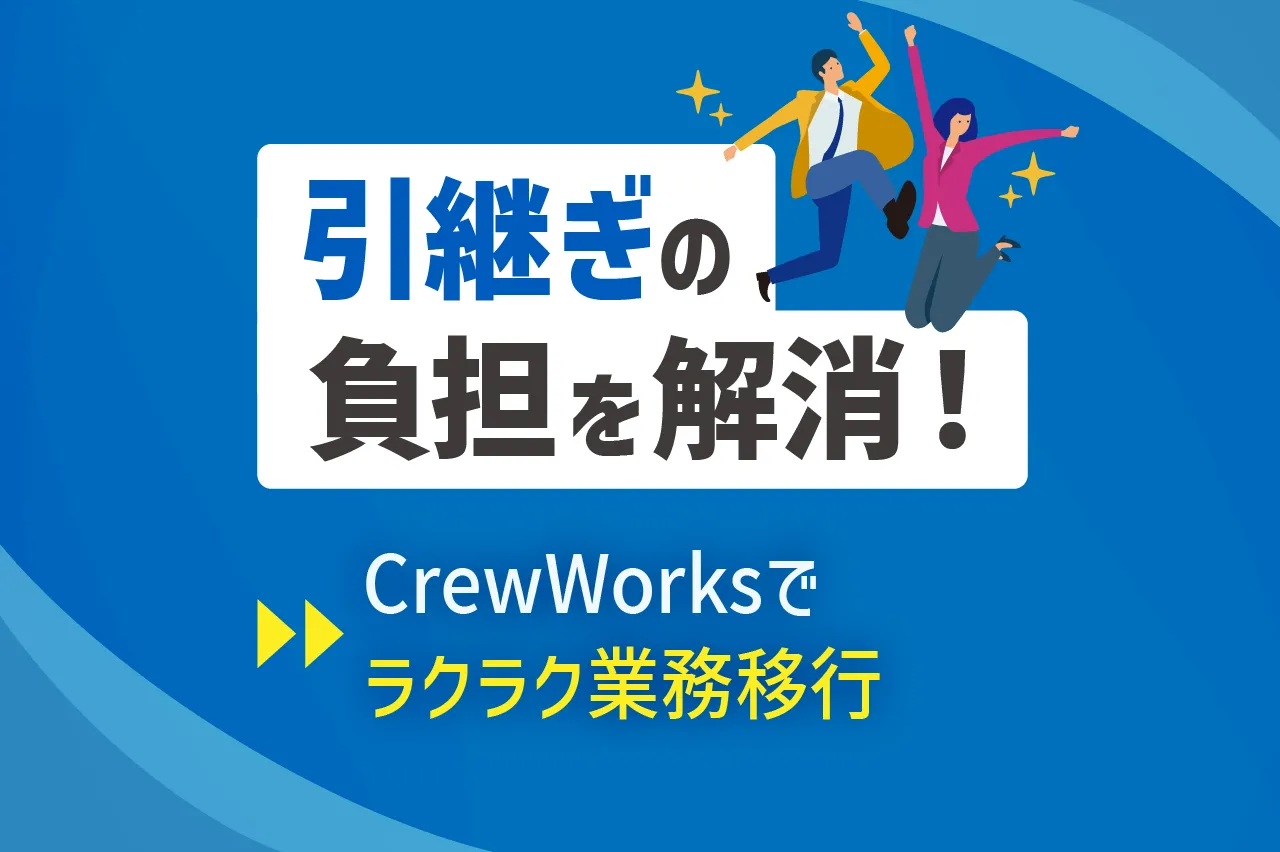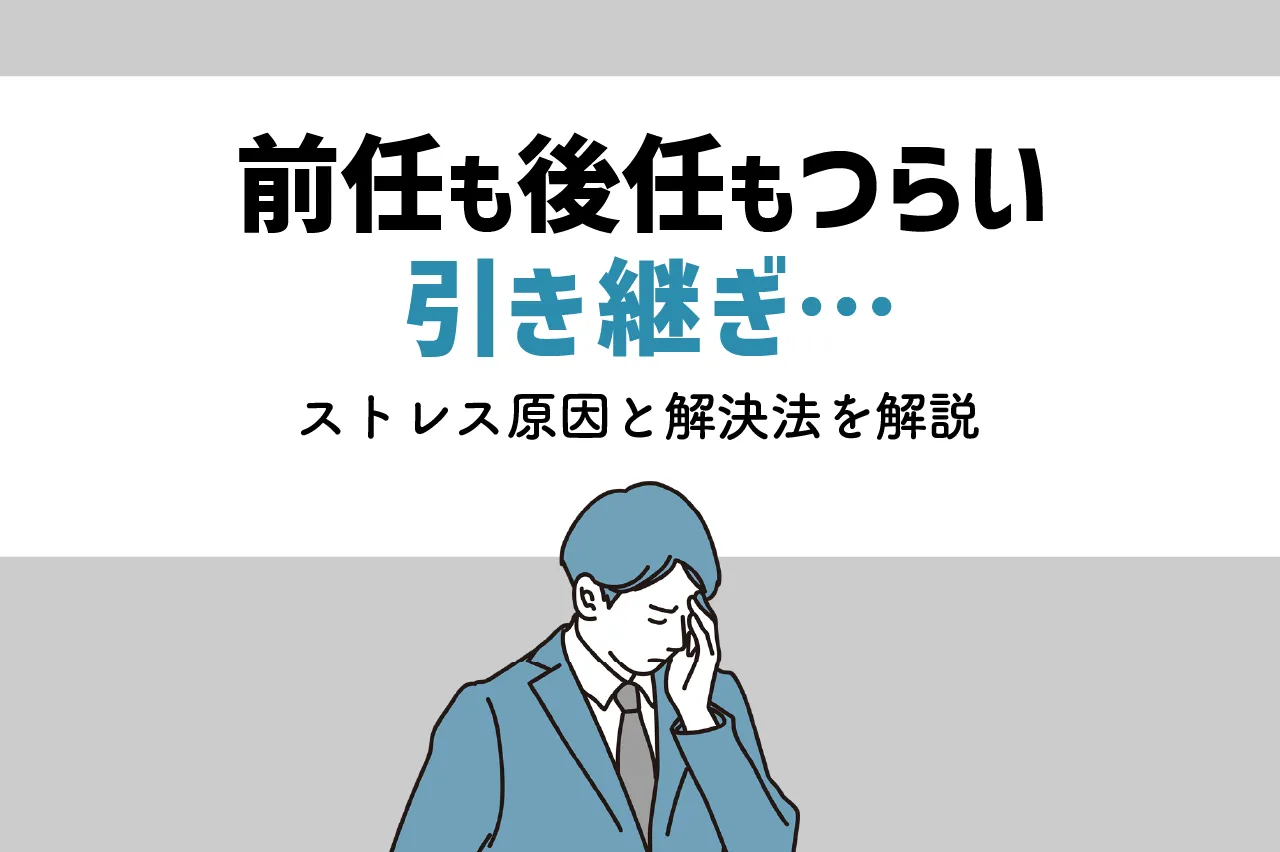サイロ化とは?意味や引き起こす要因・生じる問題などをまとめて解説
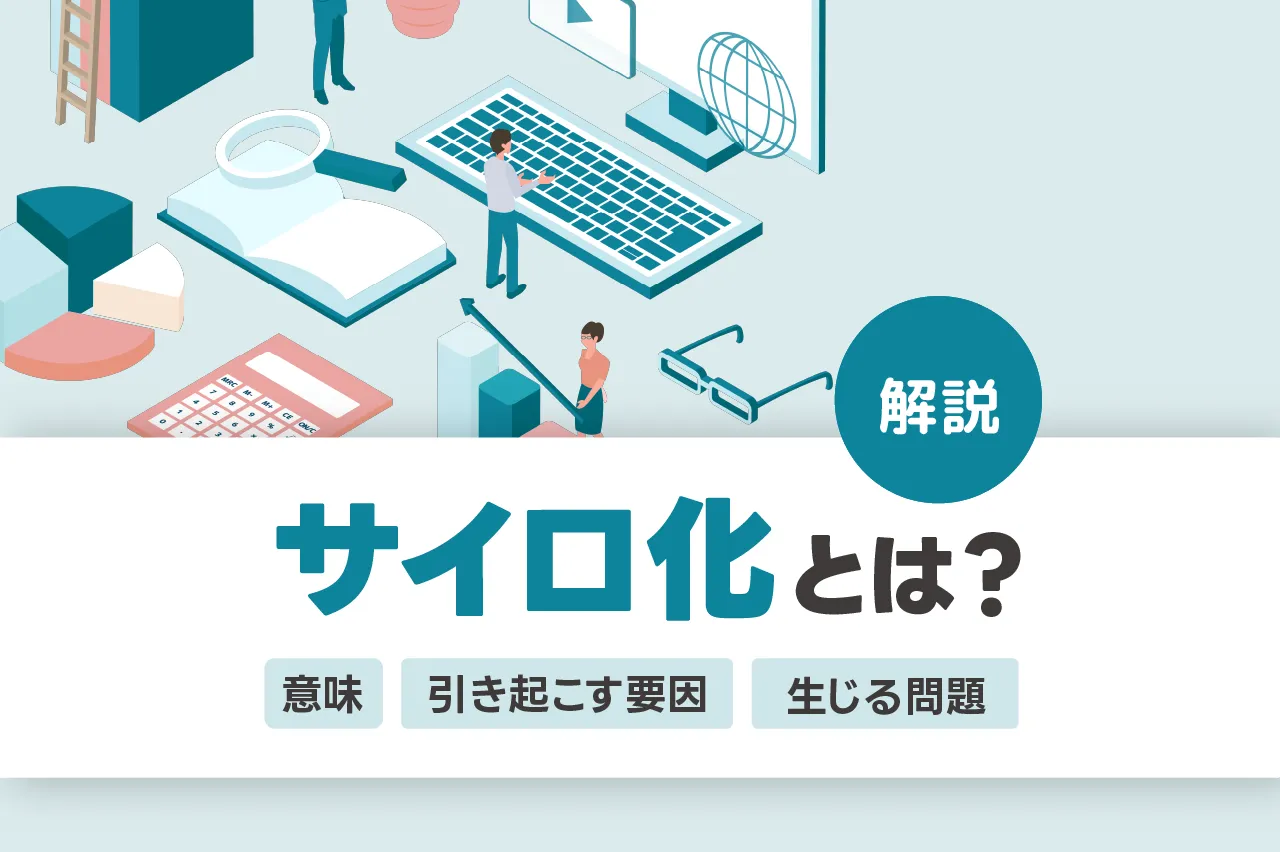
情報の活用が進まない要因はいくつか考えられますが、その中の1つが「サイロ化」です。
サイロは、工業や農業などでは資材を貯蔵する円筒型の倉庫を意味しますが、ビジネスではシステムやデータが社内で十分連携できていない状態を、サイロ化と言います。
これが起こると、業務の効率低下などの問題を引き起こす要因になりかねません。
そこで今回は、サイロ化の意味や要因に加え、それに伴う問題や解消する手法について解説します。
【目次】
サイロ化とは?ビジネスのデータ活用に関係する意味を解説

サイロ化は、企業内のシステムやデータが部門ごとに分かれており、互いに連携していない状態です。
例えば、営業部と開発部でそれぞれ異なるシステムを使っているケースや、同じ種類のデータを別形式で管理している場合はサイロ化の恐れがあります。
詳細は後述しますが、サイロ化が発生すると社内の業務にさまざまな悪影響が生じるため、速やかに対処しなければなりません。
ここでは、サイロ化の種類について、以下の2点を解説します。
- 組織のサイロ化
- データのサイロ化
1つずつ見ていきましょう。
組織のサイロ化
サイロ化の種類の1つ目は、組織のサイロ化です。 組織のサイロ化は、各部門がそれぞれ独立して活動することで、他の部門との連携が不足している状態を意味します。
部門間のコミュニケーション不足や、部門ごとに異なる業務プロセスやシステムを採用していることが主要因です。
データのサイロ化
サイロ化の種類の2つ目は、データのサイロ化です。 これは、データが複数のシステムやツールに分散して保存されており、それらが連携されていない状態を意味します。
部門ごとに異なるシステムを使用していることや、データのフォーマットが統一されていないことが要因です。
関連記事:データのサイロ化を今すぐ解消!組織が抱える課題と解決法を徹底紹介!
サイロ化を引き起こす要因とは
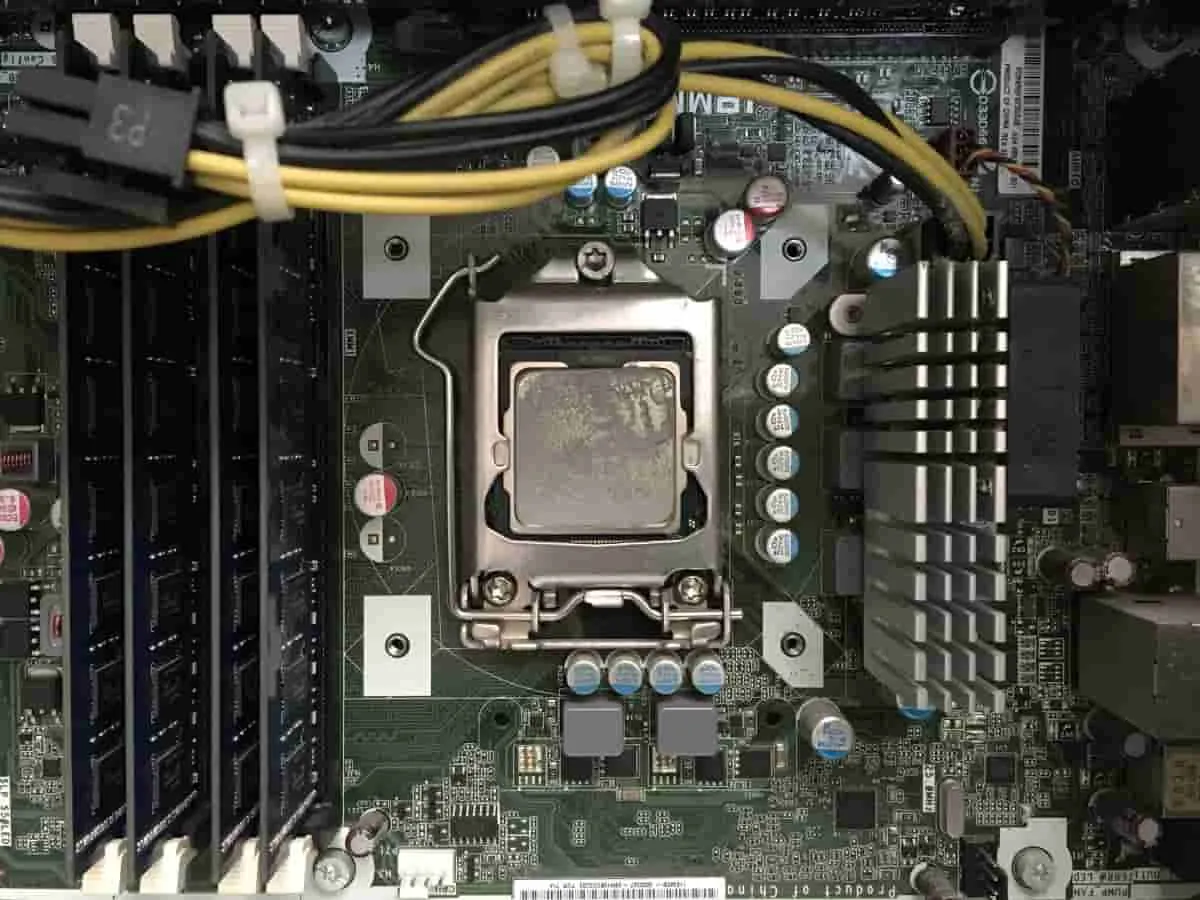
ここでは、サイロ化を引き起こす要因について、以下の4点を解説します。
- 独立採算制
- 縦割り組織
- システム連携の不足
- 部分最適化されたシステム
1つずつ見ていきましょう。
独立採算制
サイロ化を引き起こす要因の1つ目は、独立採算制です。
昨今では、部署ごとの独立採算制を採用する企業も増えてきました。独立採算制では、部署や事業部ごとに組織を切り分けて独自に利益を生み出すことを目指しています。
権限委譲で意思決定を加速し、各部署の自主性を高めることや経営効率を向上することが狙いです。
一方で、各部署の独立心が強まりすぎると、自分たちの利益ばかりにとらわれて部門間の連携不足が発生する恐れもあります。その結果、サイロ化が発生しかねません。
縦割り組織
サイロ化を引き起こす要因の2つ目は、縦割り組織です。
縦割りの組織構造では、部署同士で互いの従業員が交流することが少なくなり、その分部門間の連携が阻害されてサイロ化が起こりやすくなります。
各部門で独自のルールやシステムが誕生すると、ますます情報共有が困難になって組織全体の効率が低下するでしょう。
さらに、部署ごとにライバル心が芽生えると部署間の競争が激化し、協力体制が築きにくくなるかもしれません。上記の独立採算制も、その点では縦割り組織になりやすい体制です。
システム連携の不足
サイロ化を引き起こす要因の3つ目は、システム連携の不足です。
システム同士には相性があり、中にはうまくシステム同士を連携できないケースもあります。部門ごとに異なるシステムが導入されている場合、システム同士の相性が悪いためデータの連携が困難でサイロ化が生じるかもしれません。
システム間の連携をしやすくするためシステムのチューニングや刷新を行う場合も、コストや時間がかかります。
さらに、各システムで異なるデータフォーマットが使用されている場合は、データの統合も困難です。
部分最適化されたシステム
サイロ化を引き起こす要因の4つ目は、部分最適化されたシステムです。
各部門ごとに、会計・人事・生産管理などさまざまな目的でシステムを導入することもあるでしょう。
もちろん、ある程度は部署ごとに最適化することも必要ですが、あまりに部分最適化をしすぎると、そのシステムに特化したデータが蓄積され、他部門とのデータ共有が困難になるかもしれません。
その結果、部門間の連携が阻害されれば、サイロ化が進みます。
サイロ化で生じる問題とは
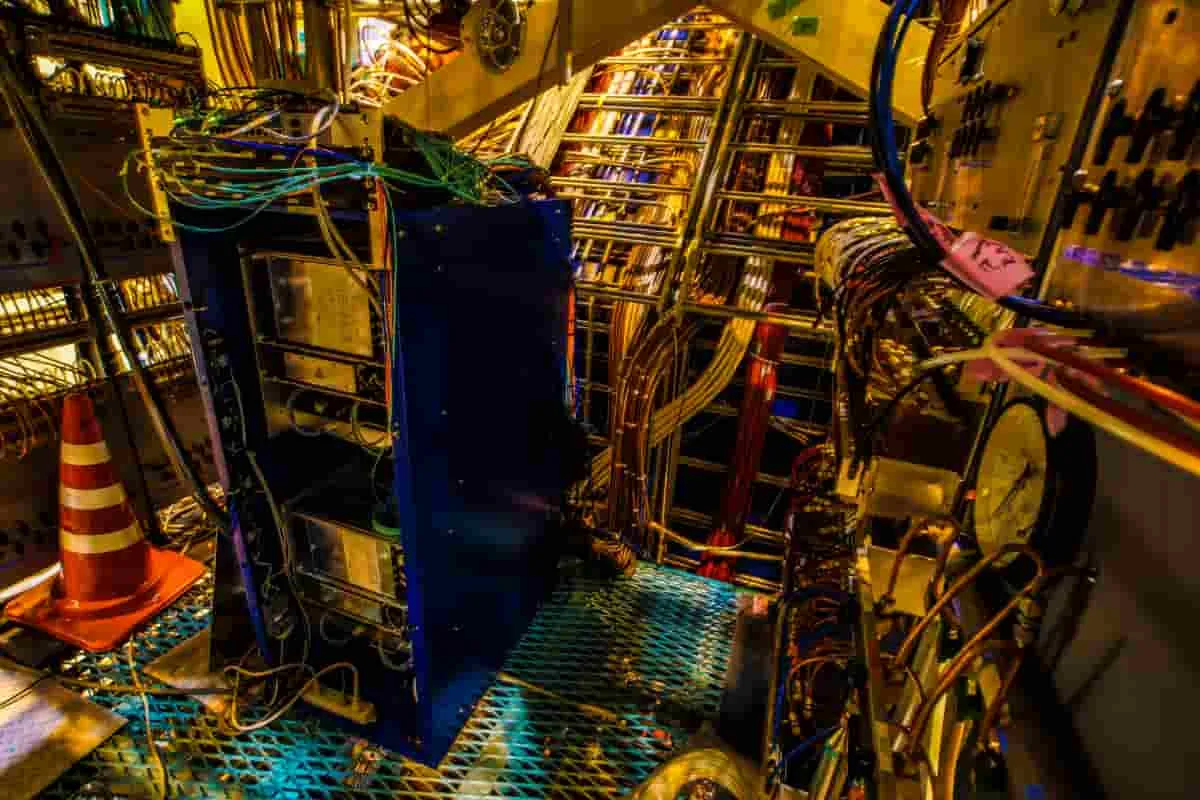
ここでは、サイロ化で生じる問題について、以下の3点を解説します。
- 業務の効率低下
- ビッグデータ活用の阻害
- DX推進の阻害
1つずつ見ていきましょう。
業務の効率低下
サイロ化で生じる問題の1つ目は、業務の効率低下です。
情報がサイロ化すると、同じデータが複数のシステムに入力されることがあります。すると、二重入力が原因で時間と労力の無駄が生じかねません。
また、データが部門やシステムごとで管理されると、それぞれのデータの整合性が取れなくなり誤った判断が下される場面もあるでしょう。
さらに、各システムの運用・保守コストが増加し、企業全体のITコストが増大することにもつながりかねません。
関連記事:業務効率化ツールとは?おすすめツール7選・種類・選び方を解説
ビッグデータ活用の阻害
サイロ化で生じる問題の2つ目は、ビッグデータ活用の阻害です。
企業には、顧客データ・生産データ・技術データなど、多種多様かつ貴重なデータが保存されています。
これらのデータは、ビッグデータとして活用され、マーケティングや商品開発などさまざまな場面で用いられるケースが増えてきました。
しかし、これらのデータが部門ごとに散在していると、社内全体でビッグデータとして活用することは困難です。
DX推進の阻害
サイロ化で生じる問題の3つ目は、DX推進の阻害です。
DXを推進するには、新たなデジタルテクノロジーの導入が欠かせません。しかし、システムがサイロ化された状態では、既存システムとの連携が難しくその導入は困難です。
また、推進のため社内のシステムをまとめて更新することも、コストや所要時間を考えると簡単には実現できません。
関連記事:社内DXとは?進め方や事例・阻害要因などをまとめて解説
関連記事:DX推進は「見える化」から!メリットと実践ステップを解説
サイロ化を解消する手法とは

ここでは、サイロ化を解消する手法について、以下の4点を解説します。
- 専門外の知識を研修で学ぶ
- 責任者同士の連携
- 他部署との交流
- データ統合システムの活用
1つずつ見ていきましょう。
専門外の知識を研修で学ぶ
サイロ化を解消する手法の1つ目は、専門外の知識を研修で学ぶことです。
各部署の業務においては、多かれ少なかれ専門知識が必要になります。しかし、特定の従業員しか知らない専門知識が増えると、情報共有が抑制されてサイロ化が促進されるかもしれません。
また、ナレッジが共有されても他部署のメンバーにはわからない専門知識があると、他部署のメンバーがそのナレッジを実務で使いこなせない恐れがあります。
そこで、従業員に対して専門外の知識を研修で学ぶよう推奨しましょう。専門外の知識を知ることで、他部署の業務内容やナレッジを理解できます。
また、専門外の知識を応用して、自らの業務に活用できるシーンもあるでしょう。
関連記事:ナレッジを蓄積する目的は?活用までの4ステップとコツ
責任者同士の連携
サイロ化を解消する手法の2つ目は、責任者同士の連携です。
部門やプロジェクトの責任者は、チームにおいて少なからず影響があります。そのため、責任者同士が連携して、チームを超えた情報共有が推進されれば、自ずとサイロ化は解消されていくでしょう。
また、責任者同士でサイロ化解消に向けた共通目標をもつことも欠かせません。他部署の施策やその実施状況を逐次共有することで、より効果的にサイロ化を解消するための施策を実行できます。
責任者が率先してサイロ化解消に取り組む姿勢を見せることで、従業員に影響を与えて全社的にサイロ化解消に向けた取り組みが行われるでしょう。
関連記事:社内の情報共有は課題解決に必須!役立つツールの種類や促進成功事例も解説
他部署との交流
サイロ化を解消する手法の3つ目は、他部署との交流です。
他部署との交流が多いと、部署を超えた情報交換が活発になるためサイロ化が起こりにくくなるでしょう。他部署との交流には、イベントや勉強会などだけでなくグループウェアや社内SNSなどのツールを活用することもおすすめです。
また、部門横断型のプロジェクトチームを組成し、従業員同士が直接交流すると互いの業務内容を理解する機会が増えます。
このように、さまざまな方法で他部署との交流を促進することで、全社的に情報共有が活発になるためサイロ化を解消できるでしょう。
関連記事:情報共有を効率化するコツ!仕組みの作り方やツールの選び方も解説
データ統合システムの活用
サイロ化を解消する手法の4つ目は、データ統合システムの活用です。
データ統合システムを導入すれば、部署ごとに散在していたデータを一元化し、情報共有を円滑化できるためサイロ化を解消できます。
また、部署ごとにデータが散在している状態では、部署ごとに独自のフォーマットでデータを管理するため、データの整合性を取るために手間がかかるでしょう。
しかし、データ統合システムで全社の情報を一元管理すれば、統一されたフォーマットでデータを管理できるためデータの正確性と信頼性を担保できます。
そのため、容易にデータ分析ができ、業務運営の効率化が可能です。
まとめ

今回は、サイロ化の意味や要因に加え、それに伴う問題や解消する手法について解説しました。
サイロ化はシステムやデータが社内で十分連携できていない状態を指し「組織のサイロ化」と「データのサイロ化」に大別されます。
サイロ化は縦割り組織やシステム連携の不足などが要因で、ビッグデータ活用の阻害やDX推進の阻害などさまざまな問題の要因になりかねません。
データ統合システムの活用や責任者同士の連携などで、速やかに対処しましょう。
|
ナレッジを最大限活用するための失敗しないツールの選び方ガイド
コミュニケーション・ナレッジマネジメントツールを個別に導入し、情報が散在し必要な情報が見つけられなくて困った経験はありませんか?
|