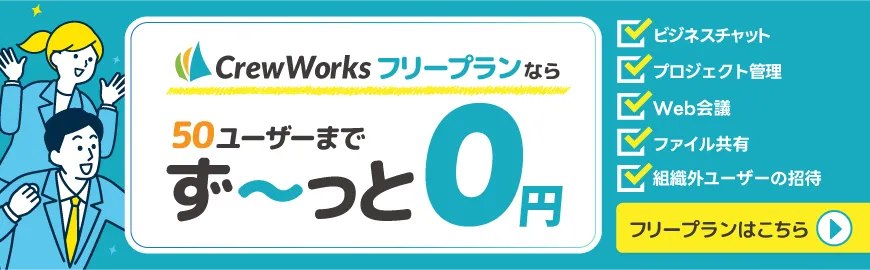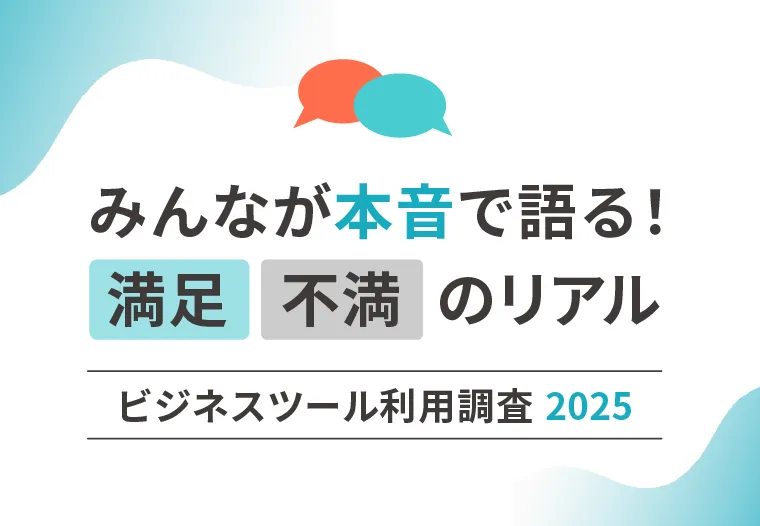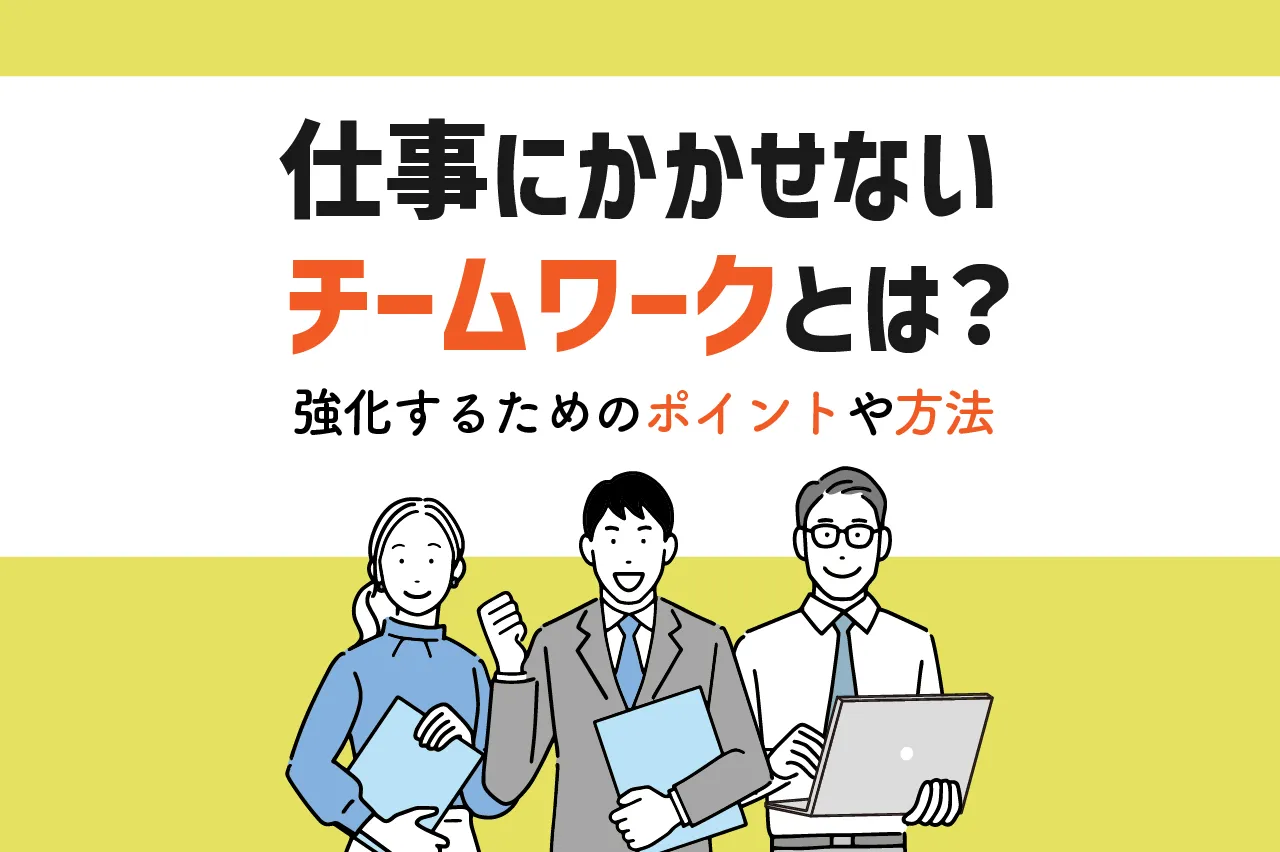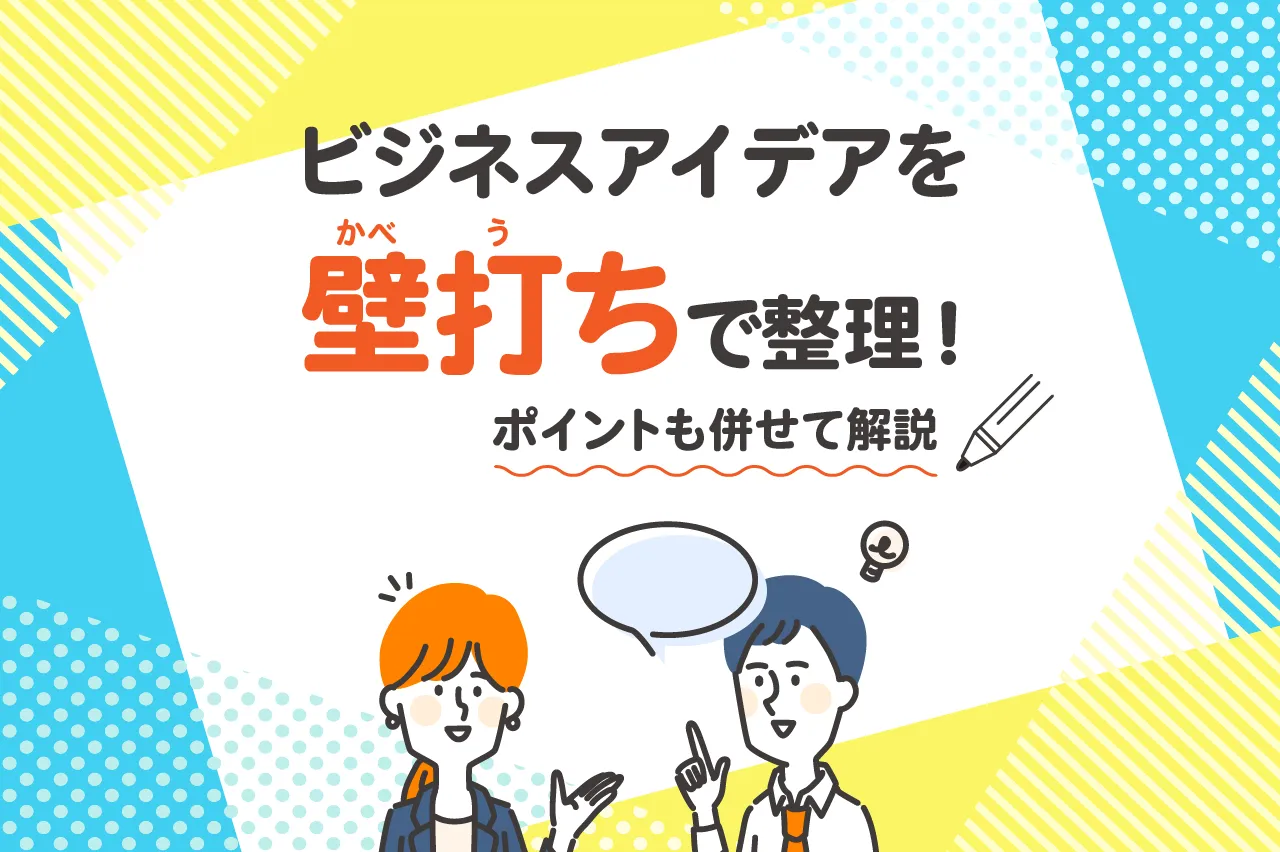コンセンサスとは?意味や使い方・例文・類語などビジネスに役立つ知識を解説

「コンセンサス」の意味をしっかり理解していなければ齟齬が起こり、仕事上でトラブルが起こってしまうこともあります。
そこで今回は、コンセンサスの意味・使い方、ビジネスシーンでの例文を解説します。
【目次】
■合わせて読まれている資料
利用者アンケートでビジネスツールの活用実態と課題を徹底調査しました!
利用者のリアルな声からツール選定や活用のヒントが見つかる資料です。
⇒「ビジネスツール利用調査2025」を無料ダウンロード
コンセンサスとは?

ここでは、コンセンサスについて、以下の4点を解説します。
- コンセンサスの正しい意味
- コンセンサスの重要性
- アグリーメントとの違い
- オーソライズとの違い
1つずつ見ていきましょう。
コンセンサスの正しい意味
コンセンサスとは、集団の中で意見が一致すること、または共通の認識を持つことを指します。英単語の「consensus」からできたカタカナ語です。
主に、ビジネスシーンで決定を下すときに、全員もしくは大多数の同意や合意が得られた状態を表現する言葉として用いられます。
また、コンセンサスは複数人だけではなく、個人の同意や合意を得る場合も使われます。
コンセンサスの重要性
ビジネスシーンにおいて、コンセンサスは意見の多様化が進む現代社会でその重要性が増しています。多様な背景を持つ組織では、意思決定の迅速化が求められる中、コンセンサスの形成は不可欠です。
関係者全員が納得できる合意形成をすることは、プロジェクトの円滑な進行や組織全体のパフォーマンス向上に直結します。
例えば、新しい業務を依頼する際に、単に指示を出すだけでは、相手は納得しにくいかもしれません。
その業務の背景や意図を丁寧に説明することで、相手の理解と納得を得られ、主体的な行動を引き出すことができます。
事前に情報共有を徹底し、関係者間で認識の齟齬がないようにすることが、スムーズなコンセンサス形成には不可欠と言えるでしょう。
アグリーメントとの違い
コンセンサスと似た言葉に、アグリーメントがあります。どちらも意見の一致や合意を示す言葉ですが、ニュアンスや使われ方が異なります。
前述した通り、コンセンサスは集団の中で意見や考え方が一致した状態を指します。
これは、単純に多数意見に同意するだけでなく、参加者のほとんどが納得している状態であることが重要です。
そのため、コンセンサスを取る過程では、参加者全員の意見を十分に聞き、理解し合う必要があります。
アグリーメントは、英語の「agreement」からきているカタカナ語で、「同意」という意味があります。
コンセンサスは、主に会議など複数人の参加者との間で同意をとることを指しますが、アグリーメントは一対一の場面でも使えます。
たとえ同意を得る相手が一人であっても「アグリーメントが得られる」などの文脈で使用できるのが、コンセンサスとの違いです。
オーソライズとの違い
コンセンサスと似た言葉に、オーソライズがあります。
オーソライズは権限付与や承認を意味し、責任者や上位者が「許可」や「承認」を与える行為を指します。これはトップダウンのロジックが働きやすいのが特徴です。
一方、コンセンサスは関係者全員の意思決定プロセスを重んじ、上下関係に依存しません。
上司からの承認という一方向の流れではなく、全員が横並びで話し合い、同意を形作っていく点に大きな違いがあります。
コンセンサスの使い方・例文

では、実際にどのような場面で「コンセンサス」という言葉は使えるのでしょうか。
ここでは、コンセンサスの使い方や例文について、以下の2点を解説します。
- コンセンサスを得る
- コンセンサスを取る
1つずつ見ていきましょう。
コンセンサスを得る
「コンセンサスを得る」という表現は、自分の意見や主張を伝え、他の人から合意を得るという意味で使われます。
【例文】
- 新しいプロジェクトの方向性について、全チームメンバーからコンセンサスを得ることができた
- 彼は、会議で提案されたアイディアに対して、部署内でのコンセンサスを得るための追加提案をした
- コンセンサスを得るためには、各ステークホルダーの意見や懸念を十分に聞き入れる必要がある
コンセンサスを取る
「コンセンサスを取る」は、他の人の意見や考えを聞き出し、交渉してから合意を得たときに使われます。
また、公の場で議論をする前に事前に交渉しておく、根回しをするといった意味合いでも使われることがあります。
【例文】
- 新方針を実施する前に、関係者全員とコンセンサスを取るべきだ
- 彼は、全体会議の前に経理部のコンセンサスを取っていた
関連記事:成功する社内調整の極意!若手からベテランまで使えるスキルと対策を徹底解説
コンセンサスのメリット

ここでは、コンセンサスのメリットについて、以下の3点を解説します。
- 組織やチームの団結力を強くする
- 主体性が育まれる
- 少数派の意見を拾いやすくなる
1つずつ見ていきましょう。
組織やチームの団結力を強くする
コンセンサスのメリットの1つ目は、組織やチームの団結力を強くすることです。
全員の意見を加味して決定を行うため、メンバーそれぞれが納得感を得やすくなります。
結果として、意思決定後の行動に移す際のモチベーションが高まり、チーム全体が目標に向かって進みやすくなります。
また、合意内容を共有するプロセス自体がコミュニケーションを活性化し、チームの一体感を強化するきっかけにもなります。
関連記事:コミュニケーションでチームワークを変える!不可欠な理由と活かし方・課題と対策も紹介
主体性が育まれる
コンセンサスのメリットの2つ目は、主体性が育まれることです。
誰かの指示をただ受けるだけでなく、メンバー自身が考えや意見を出し合うことで合意形成に参加します。その結果、「自分が携わった」という感覚が芽生え、責任感が増します。
メンバー同士の対話を通じて互いの役割や得意分野を理解するため、一人ひとりの主体性が高まり、チームワークの質を高めることにもつながります。
関連記事:チームワークを高めるにはどうすればいい?必要性や具体的手法を解説
少数派の意見を拾いやすくなる
コンセンサスのメリットの3つ目は、少数派の意見を拾いやすくなることです。
コンセンサスのプロセスでは、多数意見で一気に決定するのではなく、少数意見にも丁寧に耳を傾ける必要があります。
これにより見過ごされがちなリスクや新しいアイデアを取り入れる可能性が高まります。
多様性が認められることで組織が得られる恩恵は大きく、最終的な結論のクオリティも向上しやすくなります。
コンセンサスのデメリット

ここでは、コンセンサスのデメリットについて、以下の2点を解説します。
- 全員の合意を得るためにエネルギーが必要
- 相手の意見に譲歩する必要がある
1つずつ見ていきましょう。
全員の合意を得るためにエネルギーが必要
コンセンサスのデメリットの1つ目は、全員の合意を得るためにエネルギーが必要なことです。
多様な価値観が存在するほど、さまざまな考えや意見のすり合わせには時間とエネルギーが必要です。
ときには妥協点の模索に長時間が費やされ、プロジェクト全体のスケジュールが押してしまうリスクもあります。
効率化を図るには、事前のアジェンダ設定や関係者の役割分担など、準備段階の工夫が大切です。
関連記事:会議前にはアジェンダを用意!必要な理由や作成ポイントも解説
相手の意見に譲歩する必要がある
コンセンサスのデメリットの2つ目は、相手の意見に譲歩する必要があることです。
コンセンサス形成には、各メンバーの意見をある程度すり合わせる作業が伴います。自分の主張をすべて通すことは難しく、どこかで譲歩や妥協をする必要が出てきます。
譲れないポイントに関しては事前に共有し、意見が対立した場合でもどう解決するか明確にしておくことで、無用な摩擦を最小限に抑えられます。
会議で使われるコンセンサス方式とは

ここでは、会議で使われるコンセンサス方式について、以下の2点を解説します。
- コンセンサス方式
- ネガティブ・コンセンサス方式
1つずつ見ていきましょう。
議事録やWeb会議システムについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:議事録の基本を解説!社内会議から法定の様式まで押さえておくべきポイントを紹介
関連記事:【2025年版】Web会議システムおすすめ10選!無料利用可能
コンセンサス方式
コンセンサス方式とは、会議や議論が全会一致で可決される手法のことです。
多数決で決まるのではなく、全員が納得する結論や方針を探求していきます。
コンセンサス方式の会議では、意見の相違や懸念点を明確にし、お互いの意見を尊重しながら解決策を探していくことが重要です。
コンセンサス方式を採るメリットは、参加者全員が結果に納得感が持てるため、実行時には参加者の意欲が高まることです。
一方、多数決と比較して時間がかかることや、完全な一致を得るのが難しい場合もあるというデメリットもあります。
ネガティブ・コンセンサス方式
ネガティブ・コンセンサス方式は、全員が反対する場合のみ否決とする方式のことです。
賛成する人が一人でもいれば、可決されます。ネガティブ・コンセンサス方式を採るメリットは、多様な意見や提案に対して都度承認を求めるよりも、効率的に意思決定を進められることです。
特に、迅速に決定して物事を進める必要がある場合や、反対意見が少ない場合に向いています。
しかし、参加者が提案内容を十分に理解していなかった場合、適切な反対意見が出ないことがあるため注意が必要です。場合によっては、情報共有や議論を深める必要があるでしょう。
関連記事:情報共有を活性化させるメリットは?具体的な手順とポイントも解説
コンセンサスの言い換え・類語

ここでは、コンセンサスの言い換え・類語について、以下の3点を解説します。
- 合意を得る
- 共通認識を持つ
- 根回しをしておく
1つずつ見ていきましょう。
合意を得る
ビジネスや議論の場においてコンセンサスを取る場合、参加者全員が納得のいく答えや方針を共有し、一致することを指します。
言い換えると「合意を得る」となり、特定の提案や方針に対して共通の理解や承認を得ることを意味します。
共通認識を持つ
コンセンサスは、多様な意見を一つの共通の理解や認識にまとめ上げるときにも使えるため、「共通認識を持つ」と言い換えることができます。
例えば、チームや組織内で意見が分かれている場面で、全員の考えを一つにまとめるときにふさわしい表現です。
根回しをしておく
「根回しをしておく」は、事前に関係者や関心を持つ人々との間で話し合いを行い、後の会議や議論でスムーズに進めるための下準備をする概念です。
根回しは、ある種の「事前のコンセンサス」を形成するための手法と捉えることができます。
公の場で議論する前に、個別に話し合いをすることで、異論や対立を最小限に抑え、スムーズに合意を得たいときに使われます。
■コンセンサス形成を円滑にするおすすめツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的なコミュニケーションができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
業界別のコンセンサスの使われ方

ここでは、業界別のコンセンサスの使われ方について、以下の5点を解説します。
- 市場コンセンサス
- 医学的コンセンサス
- コンセンサスゲーム
- コンセンサスアルゴリズム
- 国民のコンセンサス
1つずつ見ていきましょう。
市場コンセンサス
市場コンセンサスは、株式取引の場で、証券アナリストたちが持つ共通の見解のことを指します。
また、「コンセンサス予想」とは、複数のアナリストが出す特定の会社の業績予想を集計し、平均した結果のことを指します。
医学的コンセンサス
医療の分野では、専門家たちが議論すべき事項の「総意」として見解を発表するときに「医学的コンセンサス」と表現します。
医学的コンセンサスは、その時点での先進的な医学的知識や根拠に基づき、専門家グループが出す公式な声明のことです。
医療従事者から患者に対して、信頼性の高い医学情報の提供を行うことができ、医療の質向上と安全性が確保されます。
コンセンサスゲーム
コンセンサスゲームは、特定の課題をチーム内で討議し、全体としての合意を求めるゲームのことです。
チーム内で合意を得ることの難しさを体感するために行われます。ビジネス研修やチームビルディングの活動として、取り入れられることが多いでしょう。
関連記事:チームビルディングとは、効果的な目的と実践例で結束力を高める秘訣
コンセンサスアルゴリズム
コンセンサスアルゴリズムは、仮想通貨業界における「データの正確さを確保するためのルール」のことです。
また、どのマイナーの計算結果が正確であるかを決めるルールを、「コンセンサスアルゴリズム」と呼びます。
国民のコンセンサス
政治の場で「国民のコンセンサス」という言葉は、特定の政策や方針について国民全体の総意や合意が得られている状態を指します。
政策決定の際には、国民がその政策に賛成しているか、広く支持されているかを確認することが重要です。
これは、国民の意見を反映し、信頼性の高い政策運営を行う上で不可欠な要素と言えます。
ビジネスでコンセンサスを形成するポイント

ここでは、ビジネスでコンセンサスを形成するポイントについて、以下の4点を解説します。
- 論点を明確にする
- 率直に意見を伝える
- 相手の意見にしっかりと耳を傾ける
- 前向きに擦り合わせて落とし所を作る
1つずつ見ていきましょう。
論点を明確にする
ビジネスでコンセンサスを形成するポイントの1つ目は、論点を明確にすることです。
まず、議論の主題や目的、解決すべき課題を明確にしておきましょう。
参加者全員が同じ認識や方向性を持たなければ、意見が合わず、合意ができなくなってしまいます。具体的には、課題を定義し、参加者との間で目的の共有を図っていきます。
また、論点を明確にするときには認識の違いを避けるために、言葉の定義や用語を確認し説明しておくことも重要です。
率直に意見を伝える
ビジネスでコンセンサスを形成するポイントの2つ目は、率直に意見を伝えることです。
コンセンサスを取るには、メンバー全員が自分の考えや意見、懸念を隠さずに共有する必要があります。
また、素直に意見を表明することで、他のメンバーも自分の考えをオープンにしやすくなり、深い議論をしやすくなります。
ただし、意見を言う場合は、相手の立場や感情を尊重し、攻撃的な言い方は避けておいたほうが無難です。建設的なコミュニケーションを心がけることで、円滑に合意に近づくことができるでしょう。
関連記事:アサーションとは?現代のコミュニケーションスキルの基礎知識
相手の意見にしっかりと耳を傾ける
ビジネスでコンセンサスを形成するポイントの3つ目は、相手の意見にしっかりと耳を傾けることです。
自分の意見をただ伝えるだけでなく、他者の意見や感じていることを真摯に受け止めましょう。
相手の意見をしっかり聞くことで、新しい視点や情報を得ることができ、より良い決定を下せるようになります。
また、他者の意見を尊重し、背景や理由を理解することで、信頼関係を築くことができます。
信頼関係が築けることで、コンセンサス形成がスムーズに進むだけでなく、将来的な協力関係も見込めるでしょう。
前向きに擦り合わせて落とし所を作る
ビジネスでコンセンサスを形成するポイントの4つ目は、前向きに擦り合わせて落とし所を作ることです。
ビジネスの議論や交渉では、批判的な意見が出たり参加者の意見が一致しないことも珍しくありません。
参加者間で意見を擦り合わせ、双方が納得できる中間地点を見つけて歩み寄る姿勢を持つことが重要です。
落とし所を作るときには、各々の企業の要望やルールを理解し、共通の目標やビジョンに照らし合わせ、最適な解決策を探求していきましょう。
また、最終的に採用されなかった意見については、発言者に理由をフィードバックすることで、モチベーションの低下や不満の解消にもつながるでしょう。
関連記事:イニシアチブとは?イニシアチブの類義語・活用例やイニシアチブを取る方法までを詳しく解説
■コンセンサス形成を円滑にするおすすめツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的なコミュニケーションができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
まとめ

今回は、コンセンサスの意味・使い方・例文や類語を解説しました。
コンセンサスの使い方について正しい知識を持つことで、ビジネスシーンで相手の話が理解でき、自分も「コンセンサス」という言葉が使えるようになります。
また、会議やプレゼンテーション、日常業務でも、コンセンサスを得ておくことでスムーズな意思決定や協力的な関係構築が期待できるでしょう。
そして、社内でコンセンサスを形成するには、普段からコミュニケーションを取っておくことが大切です。
従業員同士のコミュニケーションを円滑にするためにも、CrewWorks(クルーワークス)を導入してみませんか。使いやすいUIで誰でも簡単に活用でき、ビジネスチャットやWeb会議がしやすくなるでしょう。
コンセンサス形成を円滑にするおすすめツール「CrewWorks」
CrewWorks(クルーワークス)は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などを備えたビジネスコミュニケーションツールです。コミュニケーションツールが統合されていることで情報を一元管理することができ、社内の円滑な情報共有のみならず、業務プロセス全体の効率化を図ることができます。シンプルな画面構成で直感的に操作が可能です。
CrewWorksの特長
- スマートフォンアプリによるマルチデバイス対応
- オールインワンツール導入によるコスト削減が見込める
- 最大50ユーザーまでずっと無料のフリープランあり
|
ビジネスツール利用調査2025
ビジネスコミュニケーションツールの活用実態と課題を徹底調査しました。
|