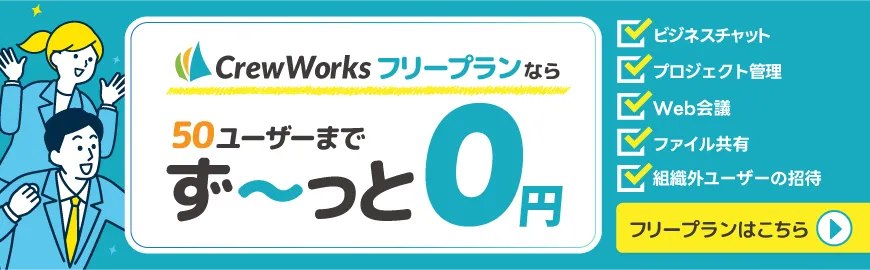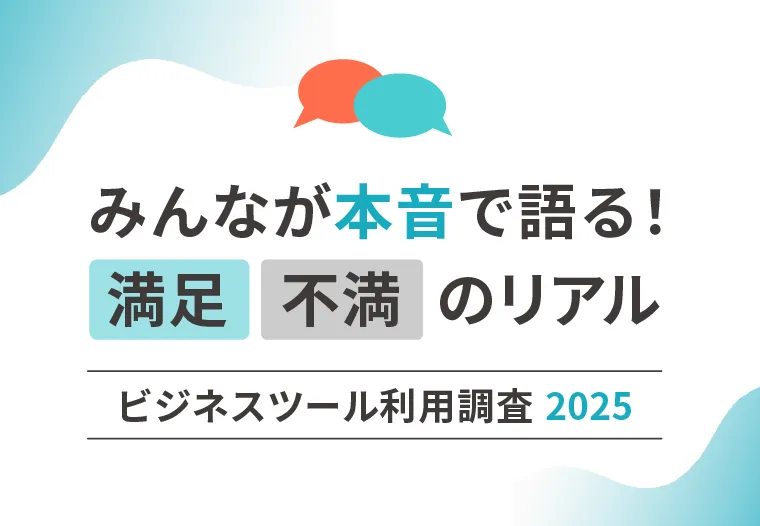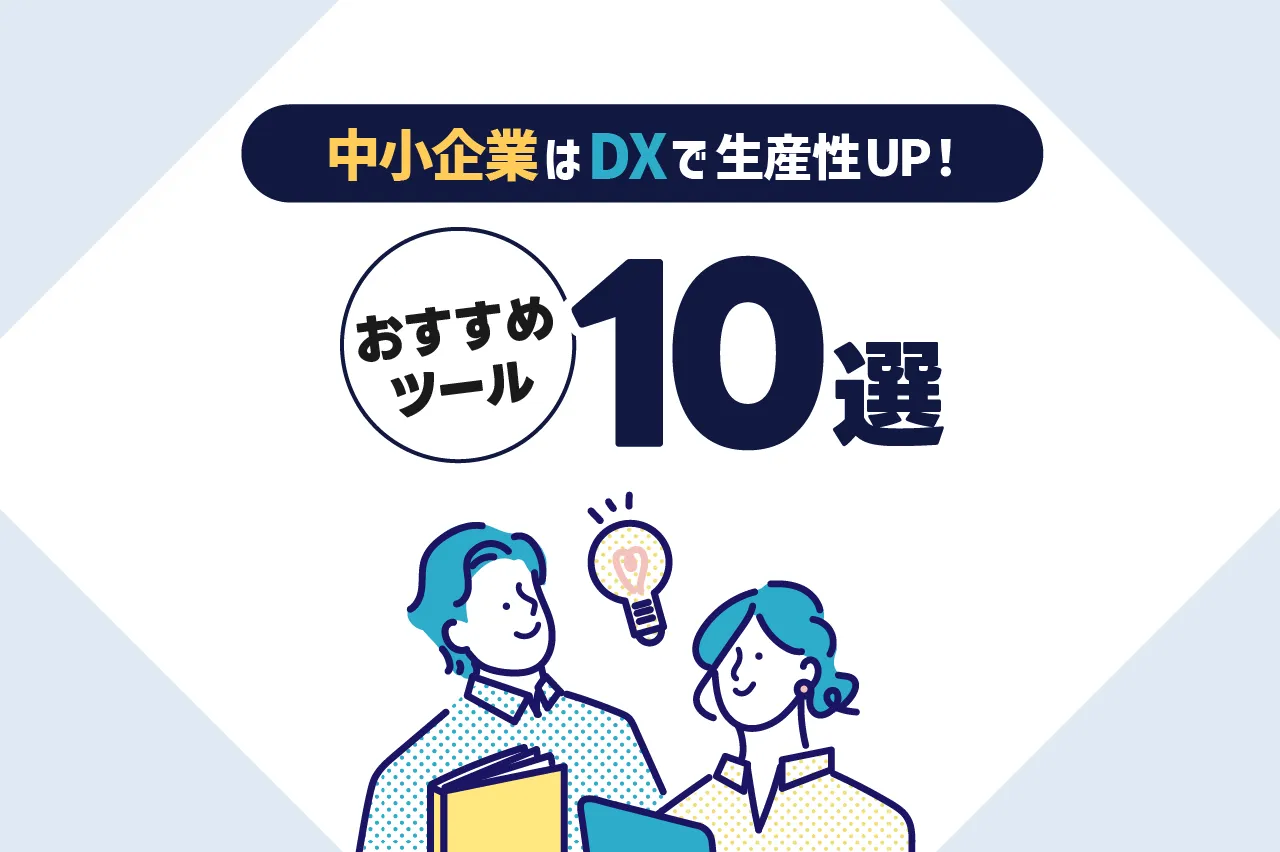社内でペーパーレス化を促進!メリット・デメリットやポイントを解説
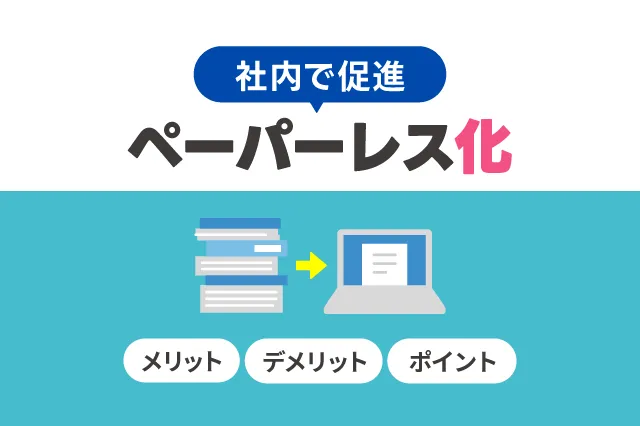
ペーパーレス化を行うことで、業務効率化や文書管理の負担軽減など多くのメリットが期待できます。
一方で、ペーパーレス化を実現するためにはいくつかのハードルがあり、思うように進まない企業もあるかもしれません。
また、社内のペーパーレス化の流れをきちんと把握していなければ、適切にペーパーレス化は実現できないでしょう。
そこで今回は、社内でペーパーレス化を行うメリットやそれを阻む要因と、ペーパーレス化の流れを解説します。
【目次】
■合わせて読まれている資料
利用者アンケートでビジネスツールの活用実態と課題を徹底調査しました!
利用者のリアルな声からツール選定や活用のヒントが見つかる資料です。
⇒「ビジネスツール利用調査2025」を無料ダウンロード
社内文書のペーパーレス化が進んでいる

ペーパーレス化とは、紙書類を電子データなどに変換・保存することで紙文書の使用をなくすことです。
ペーパーレス化により、業務効率化やコスト削減などが図れます。ペーパーレス化は、スキャンや電子ファイル作成などの方法で実現可能です。
ここでは、文書のペーパーレス化に関する基礎知識について、以下の2点を解説します。
- ペーパーレス化の現状
- 関連する法律
1つずつ見ていきましょう。
ペーパーレス化の現状
文書のペーパーレス化に関する基礎知識の1つ目は、ペーパーレス化の現状です。
2024年にペーパーロジック株式会社が行ったアンケートによると、2023年にペーパーレス化推進を「積極的に行った企業」は11.2%でした。
また「ある程度行った企業」は43.9%にのぼり、半数以上の企業がペーパーレス化に取り組んだと回答しています。
ワークフローや見積請求書発行で、特にペーパーレス化が推進されていると推察されます。
関連記事:ペーパレス化とは?メリット・デメリットと進め方を解説
関連する法律
文書のペーパーレス化に関する基礎知識の2つ目は、関連する法律です。ここでは、以下の2つを解説します。
- 電子帳簿保存法
- e-文書法
電子帳簿保存法
関連する法律の1つ目は電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、国税に関する帳簿や書類の電子データ保存を認める法律です。
国税関係の書類を電子化するには、電子帳簿保存法に従って保存しなければなりません。
同法によると、国税関係帳簿書類の電子保存には、以下3つの方法があります。
|
電子帳簿等保存 |
電子データで作成した帳簿をそのまま保存する方法 |
|
スキャナ保存 |
紙の書類をスキャンして画像データとして保存する方法 |
|
電子取引データ保存 |
電子取引でやり取りしたデータを保存する方法 |
e-文書法
関連する法律の2つ目はe-文書法です。
e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)は、様々な法定文書について電子保存を認める法律です。
国税関係書類・医療関係書類・建築関係図書など、多くの文書が対象になります。e-文書法に基づき文書保存を行う場合は、検索性・機密性・完全性・見読性の4要件を満たさなければなりません。
関連記事:文書管理の電子化とは?実施方法からメリット・注意点まで詳しく解説
社内のペーパーレス化を行うメリット
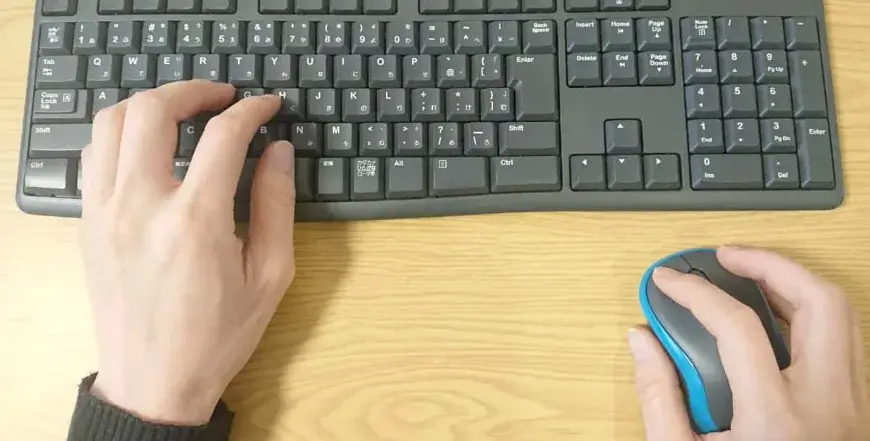
ここでは、社内のペーパーレス化を行うメリットについて、以下の7点を解説します。
- 業務効率化
- 属人化防止
- テレワーク推進
- 紙関係のコスト削減
- 文書の紛失リスク軽減
- 文書管理の負担軽減
- 企業イメージ向上
1つずつ見ていきましょう。
業務効率化
社内のペーパーレス化を行うメリットの1つ目は、業務効率化です。
ペーパーレス化で文書を電子化して、ストレージサービスに保存することで、書類の検索性が高まります。これにより、業務に必要な情報に素早くアクセスできるようになるでしょう。
また、内部決裁の承認プロセスや取引先とのやり取りも効率化されるため、従業員の負担軽減やヒューマンエラー防止にもつながります。
関連記事:仕事効率化に役立つアイデア16選!実行する手順や事例も解説
属人化防止
社内のペーパーレス化を行うメリットの2つ目は、属人化防止です。
文書をペーパーレス化し、クラウドストレージなどで保存・共有することで、誰でも必要な情報にアクセス可能になります。これにより、業務に必要な情報の属人化防止を図れるでしょう。
一部の従業員しか業務に必要な情報を知らない状態を防げるため、組織のレベルアップや業務品質の安定化に寄与します。
関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説
関連記事:「あの人にしかできない仕事」は危険!属人化によるストレスと職場の崩壊リスク
テレワーク推進
社内のペーパーレス化を行うメリットの3つ目は、テレワーク推進です。
ペーパーレス化によってオンライン上で資料のやりとりや決裁を行えるようにすることで、テレワークを推進できます。
テレワークは、コロナ禍のような緊急事態だけでなく従業員の多様な働き方のニーズに対応するためにも、導入を進めたい働き方です。
関連記事:テレワークとは?今さら聞けない基本概要から効果・導入のポイントまで徹底解説
紙関係のコスト削減
社内のペーパーレス化を行うメリットの4つ目は、紙関係のコスト削減です。 オフィスで紙の文書を作成すると、以下のコストが必要になります。
- コピー機のランニングコスト
- 用紙代
- トナー代
- 収入印紙費用
- 資料保管室の管理コスト
ペーパーレス化して紙の使用量を減らせば、上記のコストを軽減できるのです。また、空いたオフィススペースの有効活用もできるため、従業員にとって働きやすいオフィス環境作りも期待できます。
関連記事:コストを賢く削減する具体的な方法と手順・注意点を徹底解説!
文書の紛失リスク軽減
社内のペーパーレス化を行うメリットの5つ目は、文書の紛失リスク軽減です。
文書を電子化して、クラウドサーバー上などに文書データを保存すれば、文書の紛失リスクを軽減できます。
しかも、災害などのトラブル時にオフィス外から文書データにアクセス可能です。 文書データへのアクセス権を制限することで、文書の廃棄・改ざんなどのリスクも防止でき、セキュリティを強化できます。
文書管理の負担軽減
社内のペーパーレス化を行うメリットの6つ目は、文書管理の負担軽減です。
文書を電子データで残すことで、閲覧履歴や修正履歴を容易に管理できるようになります。
そのため、文書改ざんのリスクも低減できるでしょう。また、文書決裁の承認プロセスが明確になるため、承認漏れや承認経路の間違いを防止することにもつながります。
関連記事:文書管理とは?概要や注目の理由・電子化に向けたツールについて解説
企業イメージ向上
社内のペーパーレス化を行うメリットの7つ目は、企業イメージ向上です。
ペーパーレス化で紙の使用量を削減することで、環境問題への意識をアピールできます。環境問題への積極的な取り組み姿勢が、企業イメージ向上につながるでしょう。
▼社内文書をDX化して生産性を向上したい方は、以下の記事をご覧ください。
社内情報共有はDX化のはじめの一歩に最適!コミュニケーションコストを簡単に削減できるおすすめツールとは?
社内のペーパーレス化を阻む要因

ここでは、社内のペーパーレス化を阻む要因について、以下の4点を解説します。
- 初期コストの重さ
- ペーパーレス化に消極的な従業員がいる
- ITリテラシーの低さ
- システム障害を不安視
1つずつ見ていきましょう。
初期コストの重さ
社内のペーパーレス化を阻む要因の1つ目は、初期コストの重さです。
ペーパーレス化には、システム導入や環境整備などの初期費用が重い負担となります。
しかし、長期的に見れば、紙代や人件費の削減につながるため、高い費用対効果が期待できます。長期的目線でのメリットに着目できるかが、ペーパーレス化成功のポイントです。
ペーパーレス化に消極的な従業員がいる
社内のペーパーレス化を阻む要因の2つ目は、ペーパーレス化に消極的な従業員がいることです。
今までのやり方で問題ないと考える従業員が多ければ、ペーパーレス化の妨げになります。
しかし、デジタル化推進が求められている中でペーパーレス化の必要性が高まっていることも事実です。そのことを組織全体に広め、ペーパーレス化のメリットについて従業員の理解を促す必要があります。
ITリテラシーの低さ
社内のペーパーレス化を阻む要因の3つ目は、ITリテラシーの低さです。
ITリテラシーに自信がない従業員がいると、導入の妨げになります。ベテラン社員の中には、ペーパーレス化に抵抗感がある人が多いかもしれません。
その場合は、直感的に操作できるシステムを活用することで電子化への抵抗感を軽減できるでしょう。
システム障害を不安視
社内のペーパーレス化を阻む要因の4つ目は、システム障害を不安視することです。
災害や停電でシステム障害が発生したときに、文書データが紛失することに不安を感じる方もいるでしょう。
文書データが紛失するリスクは、クラウド上にデータを保存してバックアップを取ることで回避可能です。むしろ紙媒体の方が、災害などで紛失するリスクが大きいともいえるでしょう。
社内のペーパーレス化を実行する流れ
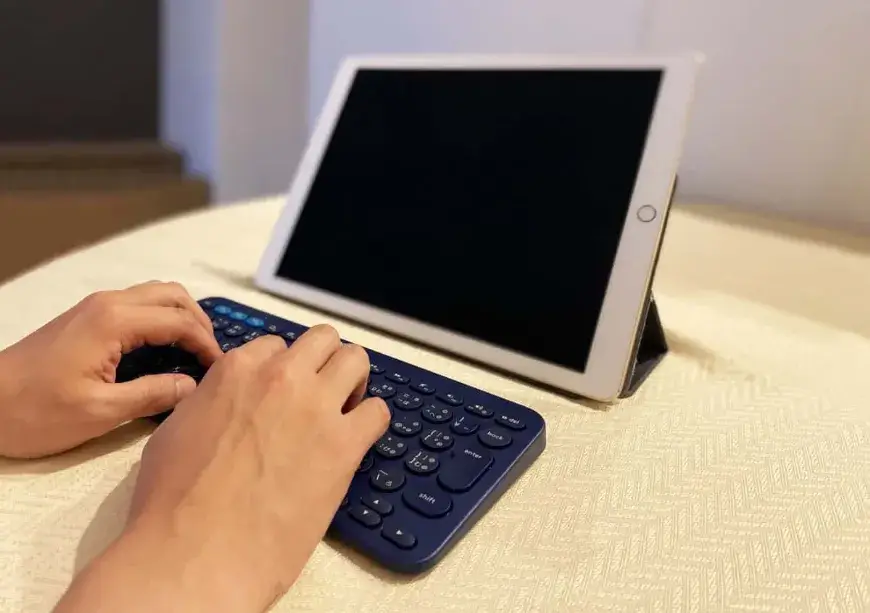
ここでは、社内のペーパーレス化を実行する流れについて、以下の7点を解説します。
- ペーパーレス化の目的・目標を設定
- 電子化範囲・優先順位の決定
- 文書保存のルール設定
- 使用ツールの選定
- テスト運用
- 業務フロー・ルールの見直し
- 従業員教育
1つずつ見ていきましょう。
ペーパーレス化の目的・目標を設定
社内のペーパーレス化を実行する流れの1つ目は、ペーパーレス化の目的・目標を設定することです。
目的意識がなくただペーパーレス化を推進しようとしても、うまくいかない可能性が高いでしょう。
現場へのヒアリングなどを通じ、自社にどのような課題があるかを明確にすることで、ペーパーレス化の目的が見えてきます。
ペーパーレス化の主な目的は、次の4点です。
- 業務の効率化
- コスト削減
- セキュリティ対策
- 人為的ミスの防止
電子化範囲・優先順位の決定
社内のペーパーレス化を実行する流れの2つ目は、電子化範囲・優先順位の決定です。
社内の文書すべてを電子化することは現実的ではありません。 以下の点に留意して、どの文書を優先的に電子化するか事前に決めておきましょう。
- 業務の頻度
- 発生するコスト
- 情報漏洩のリスク
- 従業員の抵抗感
- 業務フローへの影響
関連記事:仕事の優先順位が付けられない!優先順位の付け方や仕事の進め方について解説
文書保存のルール設定
社内のペーパーレス化を実行する流れの3つ目は、文書保存のルール設定です。
法令に基づき、電子化された文書は一定期間適切な方法で保存しなければなりません。 基本的に、法令に定められている内容に従って文書保存のルールを設定しましょう。
|
契約書 |
種類により異なるが、7〜10年程度保管 |
|
請求書 |
法人の場合、原則7年間保管 |
|
領収書 |
法人の場合、原則7〜10年保管 |
電子保存する場合は、改ざん防止や復元性確保のため、電子署名やタイムスタンプなどを活用することも検討しましょう。
関連記事:文書管理を行うときに気を付けるべき保存期間について徹底解説
使用ツールの選定
社内のペーパーレス化を実行する流れの4つ目は、使用ツールの選定です。
ペーパーレス化に役立つツールは、多くのベンダーが提供しています。以下の選定ポイントを考慮して、自社にとって最適なツールを選定しましょう。
|
機能 |
必要な機能がすべてそろっているか |
|
操作性 |
従業員が使いやすいインターフェースか |
|
セキュリティ |
データの安全性を確保できるか |
|
導入コスト |
初期費用とランニングコストはどの程度か |
|
サポート体制 |
導入後のサポートが充実しているか |
関連記事:ESMとは?業務効率化に与える効果やITSMとの違いも解説
テスト運用
社内のペーパーレス化を実行する流れの5つ目は、テスト運用です。 ツール・システムの導入前にテスト運用することで、以下の内容を確認できます。
- 期待通りの機能を実現できるか
- 従業員がスムーズに操作できるか
- 既存システムとの連携に問題はないか
テスト運用の結果に基づき、ツール・システムの設定調整や、業務フローの見直しを行えば、ツール・システムを運用しやすくなります。
デモや無料トライアルの活用がおすすめです。
業務フロー・ルールの見直し
社内のペーパーレス化を実行する流れの6つ目は、業務フロー・ルールの見直しです。
ペーパーレス化に伴い既存の業務フローを見直し、新しいルールを策定しましょう。 例えば、以下のような見直しが必要です。
▼見直し内容の例
|
業務フロー可視化 |
現在の業務フローを可視化し、無駄な作業を特定 |
|
ルール明確化 |
電子文書の保存場所・アクセス権限・共有方法など、具体的なルールを策定 |
|
マニュアル作成 |
従業員がスムーズに業務を行えるよう、マニュアル作成 |
関連記事:DX推進は「見える化」から!メリットと実践ステップを解説
関連記事:社内マニュアルの作成方法!メリット・デメリットと作成時のコツも解説
従業員教育
社内のペーパーレス化を実行する流れの7つ目は、従業員教育です。
ペーパーレス化に向けてツールを導入しても、それを使う従業員が使いこなせなければ意味がありません。
以下の内容で、ペーパーレス化に関する従業員教育を行いましょう。
|
導入目的の周知 |
ペーパーレス化の目的やメリットを周知 |
|
操作研修の実施 |
ツールの使い方を指導 |
|
Q&Aセッション |
従業員の疑問点や不安点を解消 |
また、定期的にペーパーレス化の実施状況を把握し、改善を行うことも欠かせません。
▼社内文書をDX化して生産性を向上したい方は、以下の記事をご覧ください。
社内情報共有はDX化のはじめの一歩に最適!コミュニケーションコストを簡単に削減できるおすすめツールとは?
まとめ

今回は、社内でペーパーレス化を行うメリットやそれを阻む要因と、ペーパーレス化の流れについて解説しました。
近年社内のペーパーレス化が進んでおり、関連法律も整備されています。
社内のペーパーレス化により、テレワーク推進や文書の紛失リスク軽減などのメリットがあります。 ただ、初期コストの重さやシステム障害が要因で、ペーパーレス化が進まないケースもあるでしょう。
社内でペーパーレス化を進めるには、まず目的を設定することが欠かせません。
そこから、電子化の優先順位付けやツールの選定などを着実に行いましょう。また、従業員教育も行って、社内全体でペーパーレス化の機運を高めることも必要です。
▼社内文書をDX化して生産性を向上したい方は、以下の記事をご覧ください。
社内情報共有はDX化のはじめの一歩に最適!コミュニケーションコストを簡単に削減できるおすすめツールとは?
|
ビジネスツール利用調査2025
ビジネスコミュニケーションツールの活用実態と課題を徹底調査しました。
|