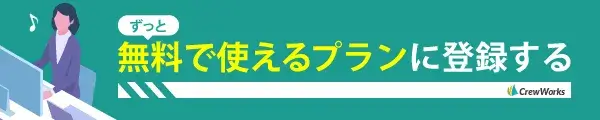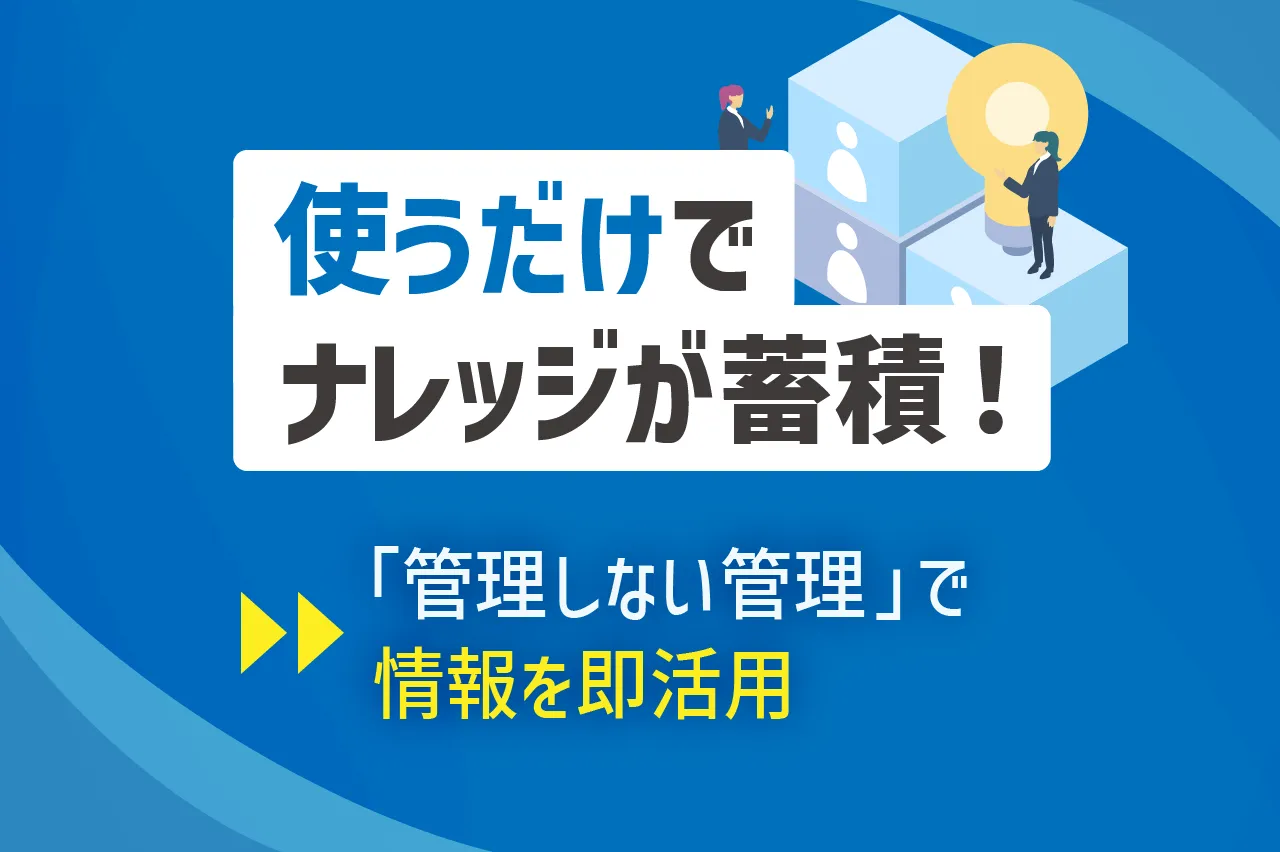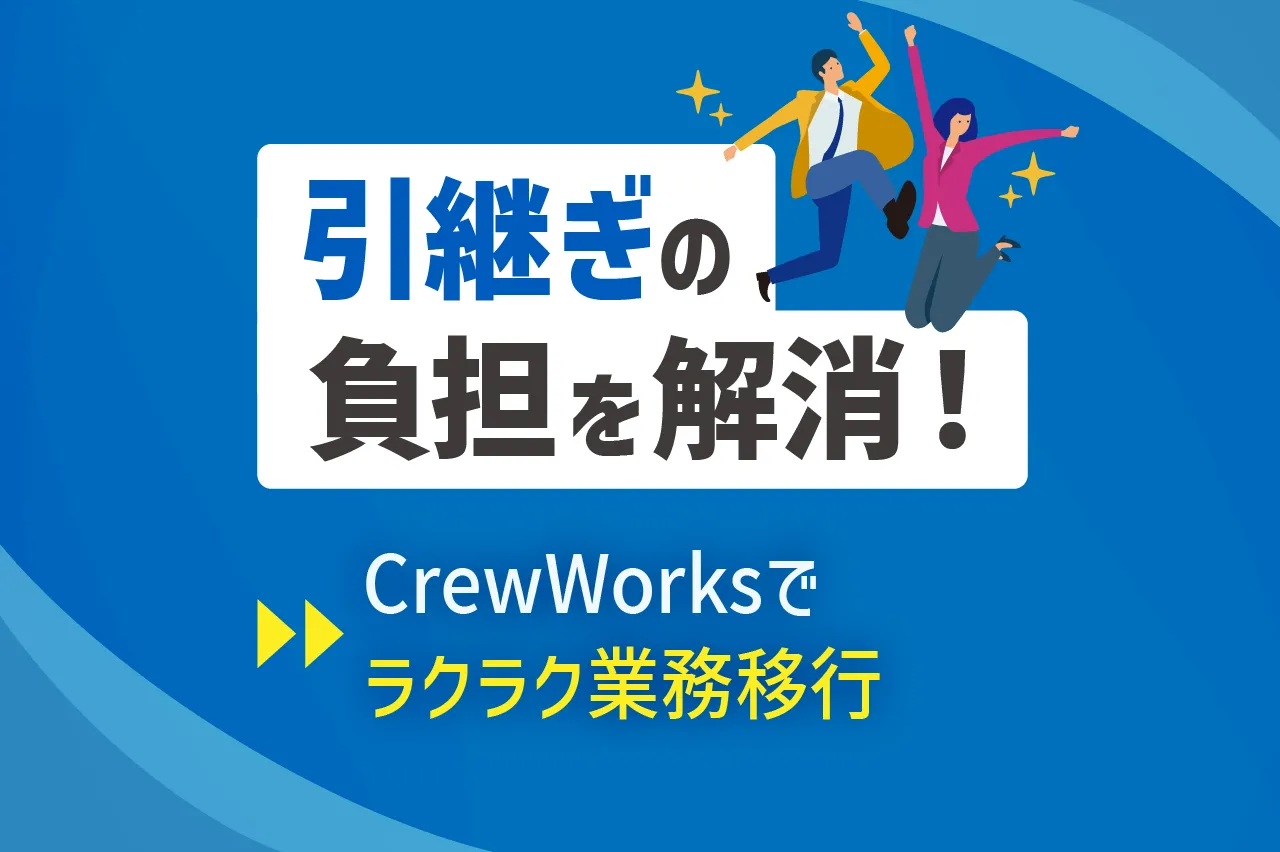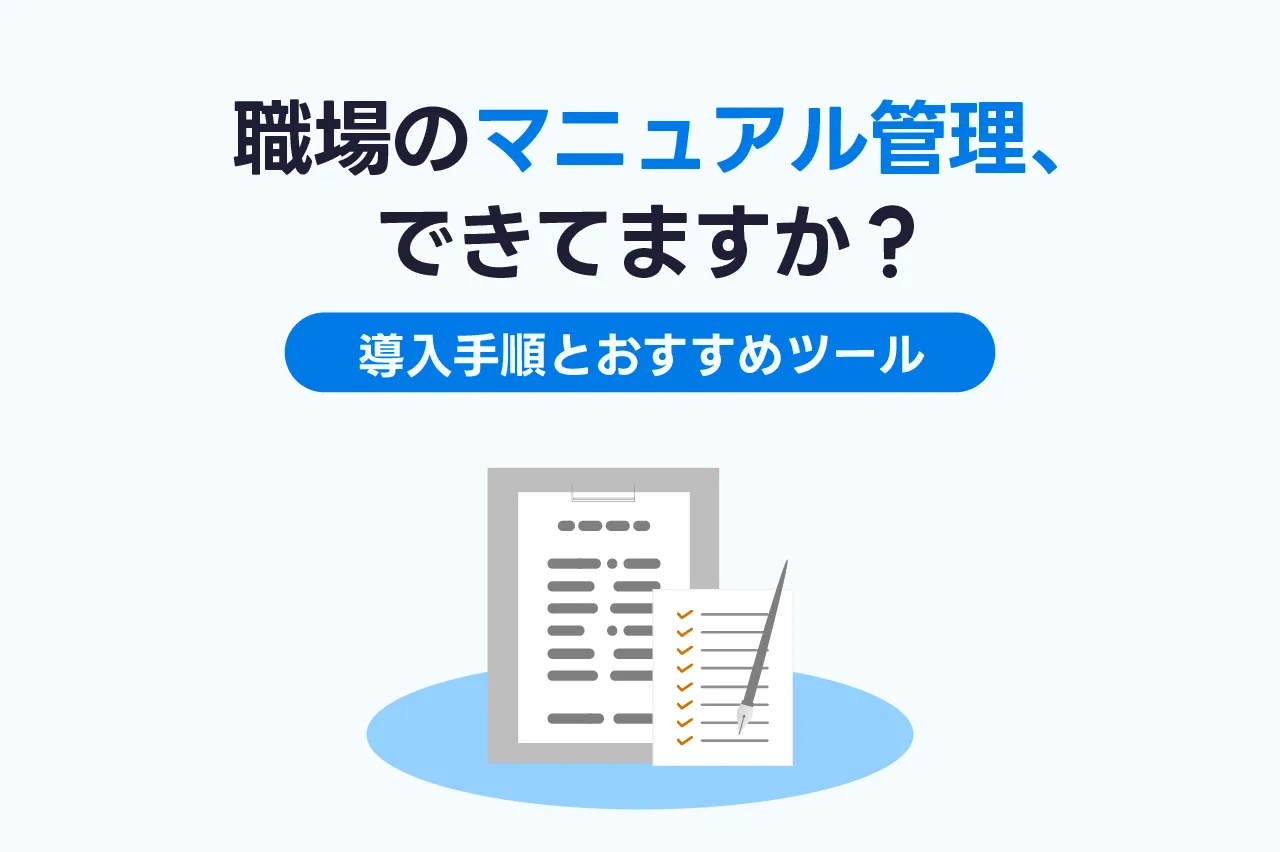前任者も後任者もつらい…仕事の引き継ぎで起こるストレスの原因と解消法を解説
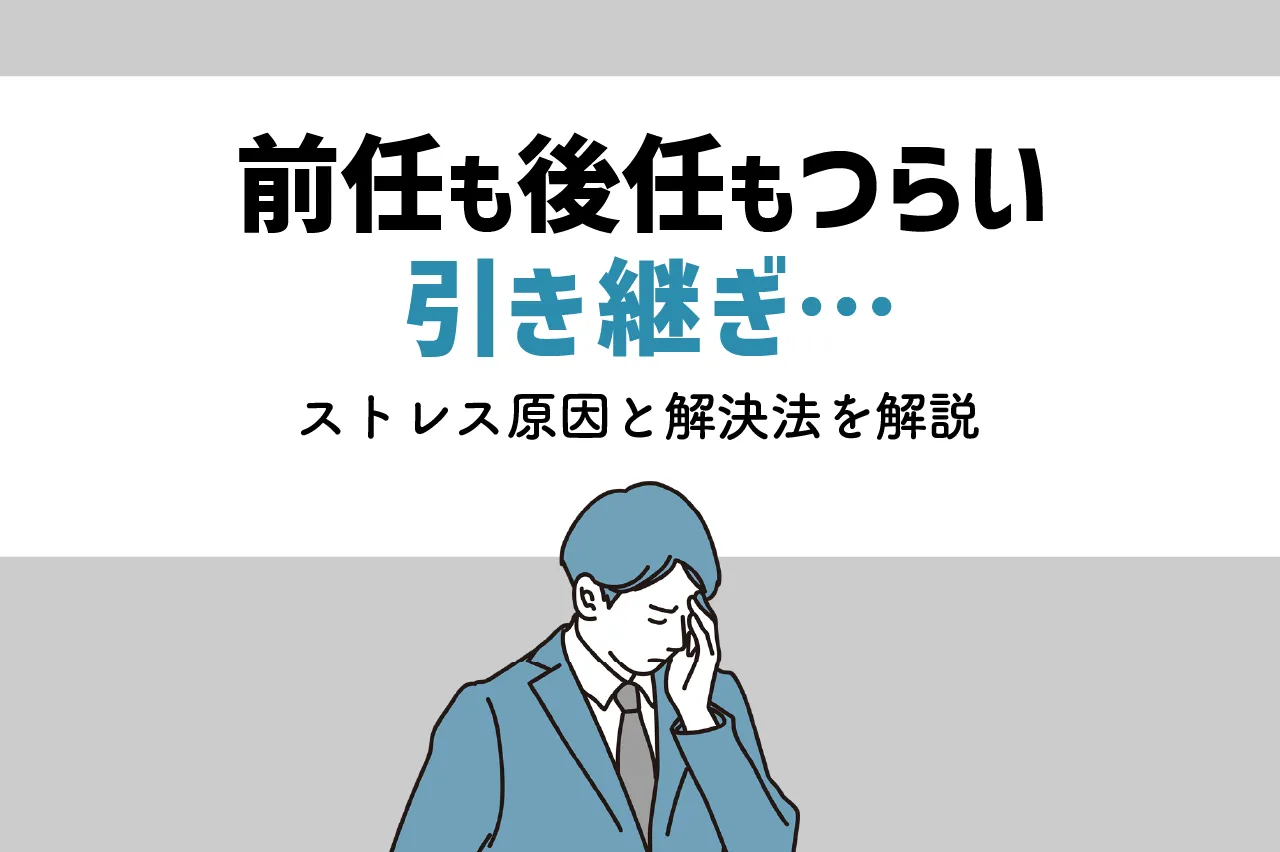
「うまく伝わっているのだろうか」「理解できているのだろうか」といった不安や、限られた時間の中での情報共有の難しさに悩む方も多いのではないでしょうか。
特に重要な業務や工程が複雑な業務の引き継ぎは、担当者の負担が大きくなりがちです。
そこで今回は、仕事の引き継ぎでストレスを感じる主な原因、スムーズに仕事の引き継ぎを進めるための方法について詳しく解説します。
【目次】
■引き継ぎの仕事の負担やストレスを減らすおすすめのツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的に引き継ぎのストレスの軽減ができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
仕事の引き継ぎでストレスを感じる主な原因

ここでは、仕事の引き継ぎでストレスを感じる主な原因について、以下の2点を解説します。
- 前任者の場合
- 後任者の場合
1つずつ見ていきましょう。
前任者の場合
ここでは、仕事の引き継ぎでストレスを感じる前任者の主な原因について、以下の3点を解説します。
- メモを取らない
- マニュアルを読んでもらえない
- 話を聞いているかわからない
1つずつ見ていきましょう。
メモを取らない
仕事の引き継ぎでストレスを感じる前任者の主な原因の1つ目は、後任者がメモを取らないことです。
重要な情報を伝えても後任者がメモを取らないと、後で確認や振り返りができません。記録がないと同じ内容を何度も説明しなければならず、前任者の負担が大きくなってしまいます。
引き継ぎが始まるときに、後任者に「重要な点はメモを取ってください」と明確に伝え、適宜メモの時間を設けましょう。
マニュアルを読んでもらえない
仕事の引き継ぎでストレスを感じる前任者の主な原因の2つ目は、後任者にマニュアルを読んでもらえないことです。
せっかく準備した資料が十分に活用されず、結局は口頭での説明に頼ることになると、効率的な引き継ぎができません。準備にかけた時間や労力が無駄に感じられ、負担につながります。
そのため、引き継ぎ前にマニュアルを事前に渡し、目を通す期限をあらかじめ決めておきましょう。
その上で、内容をしっかり理解できているかを確認するために、簡単な質疑応答の時間を設けるのがおすすめです。
話を聞いているかわからない
仕事の引き継ぎでストレスを感じる前任者の主な原因の3つ目は、後任者が話を聞いているかわからないことです。
後任者に話しかけても返答や質問がないと、内容を理解しているのか判断できません。一方的に話すだけの状況となり、本当に伝わっているのか不安を感じながら引き継ぎを進めることになります。
この場合は、定期的に「ここまでで、何か質問はありますか」と確認を取ると効果的です。重要なポイントでは、相手に要約してもらうことで理解度を確認できるでしょう。
後任者の場合
ここでは、仕事の引き継ぎでストレスを感じる後任者の主な原因について、以下の3点を解説します。
- 引き継ぎの時間がない
- マニュアルが整っていない
- 実際の業務と引き継ぎ資料が異なる
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぎの時間がない
仕事の引き継ぎでストレスを感じる後任者の主な原因の1つ目は、引き継ぎの時間がないことです。
前任者の退職直前に急いで引き継ぎを行ったり、短期間で多くの業務を覚えなければならなかったりする状況では、大きな心理的負担がかかります。
十分に理解できないまま業務を始めると、不安や焦りを抱えながら進めることになり、ミスが起きることもあるでしょう。
あらかじめ十分な引き継ぎ期間を設け、業務の重要度に応じて段階的に引き継ぐスケジュールを作成しておくことが大切です。
マニュアルが整っていない
仕事の引き継ぎでストレスを感じる後任者の主な原因の2つ目は、マニュアルが整っていないことです。
業務手順がそもそも文書化されていない場合、引き継ぎは口頭での説明に頼るしかありません。
説明を聞きながらメモを取っても、全てを正確に記録するのは難しく、後で確認できない状態で業務を進めることになります。
その結果、必要な情報を再度確認するたびに前任者や周囲に質問しなければならず、業務効率が下がるだけでなく心理的な負担も増加してしまいます。
少なくとも、基本的な業務手順や対応フローを箇条書きでまとめた資料を作成し、引き継ぎ前に後任者が目を通せるように準備しておくことが重要です。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
実際の業務と引き継ぎ資料が異なる
仕事の引き継ぎでストレスを感じる後任者の主な原因の3つ目は、実際の業務と引き継ぎ資料が異なることです。
資料に書かれている手順が実際の業務フローと一致していない、またはシステム画面・操作方法の変更が反映されていないことがあります。
誤った資料を参照しても実務では対応できず、後任者が混乱したり不安を感じたりしてしまうことがあるでしょう。
前任者は、引き継ぎ前に実際の業務を一度確認し、資料と内容を照らし合わせておくことが大切です。相違点があれば、事前に資料を修正するか、補足説明を加えておきましょう。
関連記事:仕事引き継ぎでイライラが限界!原因・影響・対処法をわかりやすく解説
引き継ぎのストレスが仕事に与える影響

ここでは、引き継ぎのストレスが仕事に与える影響について、以下の3点を解説します。
- 引き継ぎが完全に終わらない
- 周囲の業務にも悪影響が及ぶ
- 後任者が離職する
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぎが完全に終わらない
引き継ぎのストレスが仕事に与える影響の1つ目は、引き継ぎが完全に終わらないことです。
ストレスが蓄積した状況では、前任者と後任者の間でコミュニケーションが円滑に進まず、重要な情報の伝達漏れが発生します。
結果として、前任者が退職した後も後任者から質問や確認の連絡が続き、完全な業務移行が実現できません。
このような状況は、前任者の新しい職場での業務にも支障をきたし、組織全体の生産性低下につながります。
また、不完全な引き継ぎは、顧客対応や重要なプロジェクトの進行に遅れを生じさせる可能性もあるため注意が必要です。
関連記事:引き継ぎがうまくいかない5つの理由!失敗しないための対処法を解説
周囲の業務にも悪影響が及ぶ
引き継ぎのストレスが仕事に与える影響の2つ目は、周囲の業務にも悪影響が及ぶことです。
引き継ぎが不十分だと、後任者は日々の業務で同僚や上司に何度も質問やサポートを求める必要が出てきます。その結果、他のメンバーの作業時間が削られ、チーム全体の効率が下がりかねません。
さらに、後任者が業務内容を正しく理解できていないと、ミスや作業の遅れが発生し、関連する部署やプロジェクトにも影響が広がります。
特に、顧客対応や外部との重要な取引でトラブルが起きると、信頼性を失う可能性があるため、対策は不可欠です。
後任者が離職する
引き継ぎのストレスが仕事に与える影響の3つ目は、後任者が離職することです。
引き継ぎが不十分なまま責任だけが押し付けられると、後任者は強いストレスや不安を感じてしまいます。サポート体制が整っていない職場では、孤立感や無力感が深まり、「ここではうまくやっていけない」と感じることもあるでしょう。
その結果、せっかく採用した人材が早期に退職し、再び採用や引き継ぎにコストと労力がかかってしまいます。
関連記事:業務の引き継ぎで悩まない!スムーズに行うための事前準備や効果的な方法を徹底解説
■引き継ぎの仕事の負担やストレスを減らすおすすめのツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的に引き継ぎのストレスの軽減ができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップ

ここでは、ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップについて、以下の5点を解説します。
- 引き継ぐ業務を洗い出す
- スケジュールを決める
- 資料を作成する
- 引き継ぎをする
- フォローアップを行う
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぐ業務を洗い出す
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップの1つ目は、引き継ぐ業務を洗い出すことです。
まず、自分が担当している業務をすべてリストアップし、それぞれの重要度・難易度・頻度を整理しましょう。
日常の定型業務から、月次・年次の特別な業務、イレギュラーな対応まで、漏れなく洗い出すことが重要です。
並行して、業務で関わる人たちや関係者、使用しているシステムやツール、資料の保管場所なども整理しておきます。
引き継ぐ前に業務の全体像を可視化することで、後任者が理解しやすい引き継ぎの土台を作れるでしょう。
関連記事:仕事効率アップ!タスク洗い出しのメリット・流れ・おすすめ無料ツール8選
スケジュールを決める
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップの2つ目は、スケジュールを決めることです。
業務の洗い出しが完了したら、引き継ぎに必要な期間を算出し、前任者の退職日や後任者の着任日を考慮した、現実的なスケジュールを策定します。
重要度の高い業務から優先的に引き継ぎを行い、複雑な業務については十分な時間を確保することが大切です。
また、後任者の理解度や習熟度に応じて、スケジュール調整可能な余裕を持たせておきましょう。
バッファがあることで、焦りや不安を軽減できます。スケジュールは書面で共有し、関係者全員が同じ認識を持てるようにすることも重要なポイントです。
関連記事:プロジェクト管理ではスケジュールの管理が必須!おすすめツール6選も紹介
資料を作成する
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップの3つ目は、資料を作成することです。
口頭説明だけでは限界があるため、業務手順書やマニュアル、チェックリストなどの文書を整備しておきましょう。
業務の目的や背景、注意点、よくあるトラブルとその対処法などを含めた包括的な資料を作成することで、後任者が一人でも業務を進められる環境を整えられます。
また、関係者の連絡先やシステムのアクセス権限、重要なファイルの保存場所なども明記しておくことが大切です。視覚的に理解しやすいよう、フローチャートや図表を活用することも効果的です。
明確な引き継ぎ資料があることで、前任者と後任者の安心感が高まります。
関連記事:社内マニュアルの作成方法!メリット・デメリットと作成時のコツも解説
引き継ぎをする
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップの4つ目は、引き継ぎをすることです。
準備した資料をベースに、実際の引き継ぎを実施します。一方的な説明ではなく、後任者の理解度を確認しながら進めることが重要です。
実際の業務を一緒に行いながら説明する時間を設け、後任者が実践的なスキルを身につけられるようサポートしましょう。
また、質問しやすい雰囲気を作り、疑問点や不安な点があれば遠慮なく聞けるよう配慮することも大切です。
説明の途中で理解度チェックを行い、必要に応じて繰り返し説明し、知識の定着を図りましょう。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
フォローアップを行う
ストレスなく進めるための仕事の引き継ぎステップの5つ目は、フォローアップを行うことです。
引き継ぎが終わった後も、しばらくはサポート体制を残しておくことが重要です。実際に後任者の業務が始まると、新たな疑問や課題が出てくることも珍しくありません。
すぐに相談できる環境を整えておきましょう。また、定期的に確認の場を設けて、業務の進み具合や困っている点を把握することも効果的です。
フォローアップがあることで、後任者の不安が軽減され、スムーズに業務を進行できるようになります。
仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法

ここでは、仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法について、以下の4点を解説します。
- 引き継ぎの時間を十分に確保する
- 標準のマニュアルを作成する
- コミュニケーションを図る
- ツールを活用する
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぎの時間を十分に確保する
仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法の1つ目は、引き継ぎの時間を十分に確保することです。
急な人事異動や退職でない限り、引き継ぎには2週間から1ヶ月程度の期間を設けましょう。複雑な業務や専門性の高い職種では、さらに長期間が必要になる場合もあります。
時間を十分に取ることで、前任者は焦ることなく丁寧な説明ができます。また、後任者も理解が足りていない部分を質問したり、実際に業務を体験したりする余裕が生まれます。
そして、引き継ぎ期間中の業務分担を調整し、両者が引き継ぎに集中できる環境を整備しておきましょう。
標準のマニュアルを作成する
仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法の2つ目は、標準のマニュアルを作成することです。
事前に業務内容を整理したマニュアルを用意しておくと、細かな説明に時間を取られず、実践的な指導やサポートに集中できます。
後任者にとっても、マニュアルがあれば自分のペースで内容を確認でき、理解が深まりやすいでしょう。
また、文書化されていることで、引き継ぎ時に抜け漏れや認識の食い違いが見つけやすくなり、トラブル防止にも有効です。
スムーズでストレスの少ない引き継ぎを実現するためには、標準マニュアルを整備し、定期的に内容を見直しましょう。
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
関連記事:引き継ぎマニュアルの作り方は5つの手順!わかりやすく作るポイントも解説
コミュニケーションを図る
仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法の3つ目は、コミュニケーションを図ることです。
引き継ぎ期間中は、前任者と後任者が定期的に話し合い、進捗状況や課題を共有することが大切です。一方的な情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを心がけることで、不安を解消できます。
また、業務に関連する他部署のメンバーや外部関係者への紹介も含めて、人間関係の引き継ぎも進めていきましょう。
関連記事:コミュニケーションの円滑化は重要?理由・メリット・ポイントをやさしく解説
ツールを活用する
仕事の引き継ぎ時のストレスを軽減する方法の4つ目は、ツールを活用することです。
例えば、プロジェクト管理ツールを使うと、引き継ぎのタスクと進捗の可視化が可能です。ナレッジ共有プラットフォームでは、業務情報を体系的に整理できます。
また、チャットツールを使えば、引き継ぎ期間中の質問対応もスムーズに行えます。適切なツールを活用して、引き継ぎを効率よく進めましょう。
関連記事:【2025年版】プロジェクト管理ツールおすすめ16選を徹底比較!5つの確認ポイントも紹介
関連記事:無料で使えるビジネスチャットサービス8選!選び方も解説
■引き継ぎの仕事の負担やストレスを減らすおすすめのツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的に引き継ぎのストレスの軽減ができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
引き継ぎの仕事の負担やストレスを減らす「CrewWorks」
CrewWorks(クルーワークス)は、引き継ぎで起こりがちな「マニュアルの情報が古い」「必要な資料が見つからない」といった問題を解決できるコミュニケーションツールです。AIアシスタントを活用すれば、過去のチャットやファイルから必要な情報をすぐに検索でき、参照元にもワンクリックでアクセスできます。さらに、Web会議の録画から自動で文字起こしと議事録を作成できるため、手作業でのまとめ作業も削減可能です。CrewWorksを活用することで、情報の抜け漏れや認識のズレを防ぎながら、新任担当者へのスムーズな情報共有が実現するでしょう。
CrewWorksの特長
- 情報が一元管理できるタスク・チャット機能
- 過去のチャットや会議、ファイルを瞬時に検索可能なAIアシスタント機能
- Web会議の録画から自動で文字起こしや議事録を作成
詳細はこちら: https://crewworks.net/
仕事の引き継ぎ時のストレスに関してよくある質問

ここでは、仕事の引き継ぎ時のストレスに関してよくある質問について、以下の3点を解説します。
- 仕事の引き継ぎは何ヶ月くらいかかる?
- 業務の引き継ぎでよくある課題は?
- 引き継ぎをうまく行うコツは?
1つずつ見ていきましょう。
仕事の引き継ぎは何ヶ月くらいかかる?
引き継ぎにかかる期間は、一般的な事務業務であれば2週間から1ヶ月程度、専門性の高い技術職や管理職では1ヶ月から3ヶ月程度が目安です。
ただし、重要なプロジェクトを担当している場合や、外部との重要な関係性がある場合は、長期化することもあります。
完全な引き継ぎを目指すよりも、後任者が一人で業務を遂行できるレベルまでサポートすることを目標に、現実的な期間を設定しましょう。
業務の引き継ぎでよくある課題は?
引き継ぎでよくある課題は、暗黙知の伝達が難しいことです。 長年の経験で身についたコツや判断基準は言語化が難しく、多くの場合マニュアルだけでは伝えきれません。
そのため、ドキュメント化だけでなく、実際の業務プロセスや判断の背景を共有するコミュニケーションが大切です。
引き継ぎをうまく行うコツは?
引き継ぎをうまく行うコツは、後任者の立場に立って考えることです。
自分だけが知っている前提や判断基準を丁寧に言語化し、疑問点をその場で解消できる環境を作ることが重要です。
業務の背景や判断の理由も併せて伝えることで、単なる作業手順だけでなくスムーズな業務遂行につながるでしょう。
まとめ

今回は、仕事の引き継ぎで発生するストレスの原因と効果的な解消法について詳しく解説しました。
引き継ぎ時のストレスは、十分な引き継ぎ期間が取れない、マニュアルが整備されていないなど、さまざまな要因から発生します。
業務内容を段階的に引き継ぐ計画を立て、基本手順をまとめたマニュアルを用意し、実務に即した情報更新を行うことが重要です。
また、タスク・チャット・ファイルを一元管理できるツールを活用するのも効果的です。
本記事を参考に、自社でも円滑で負担の少ない引き継ぎ体制を構築し、組織の継続性と生産性の向上を実現しましょう。