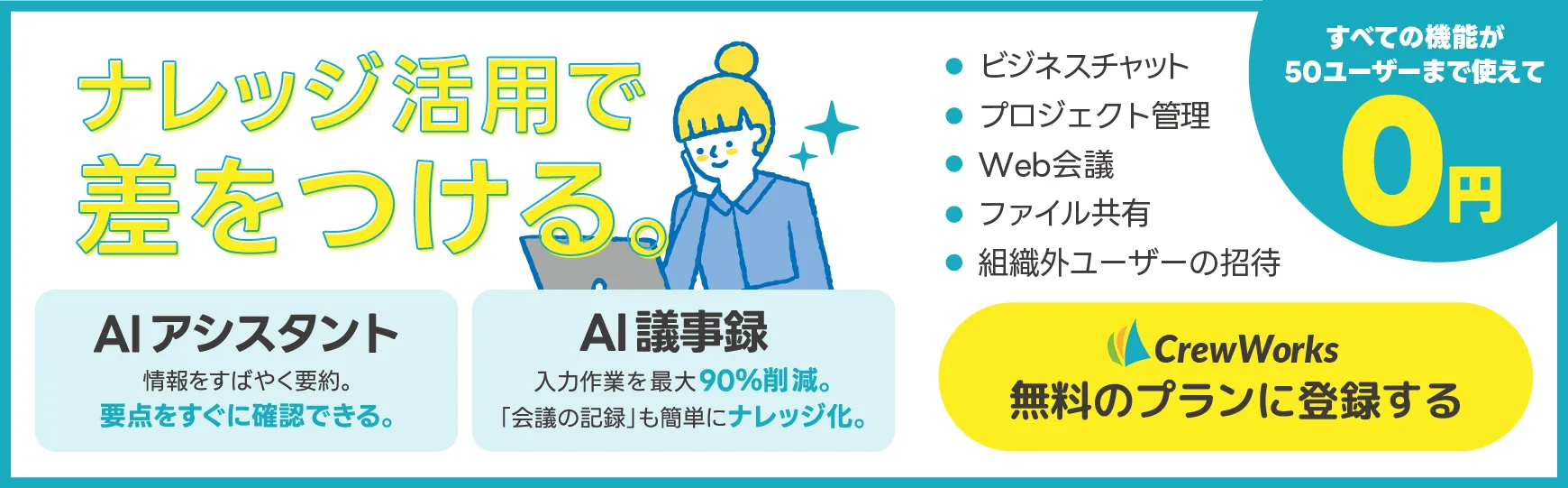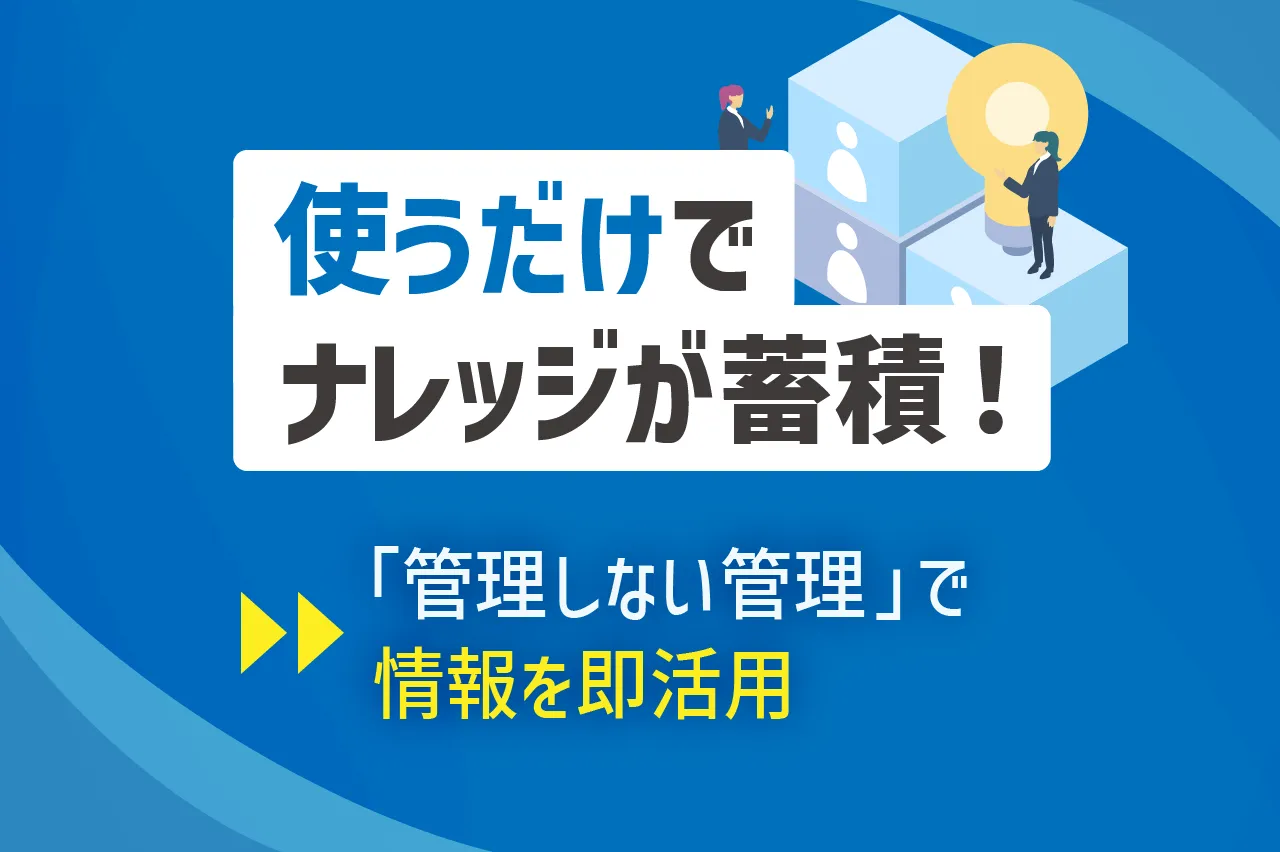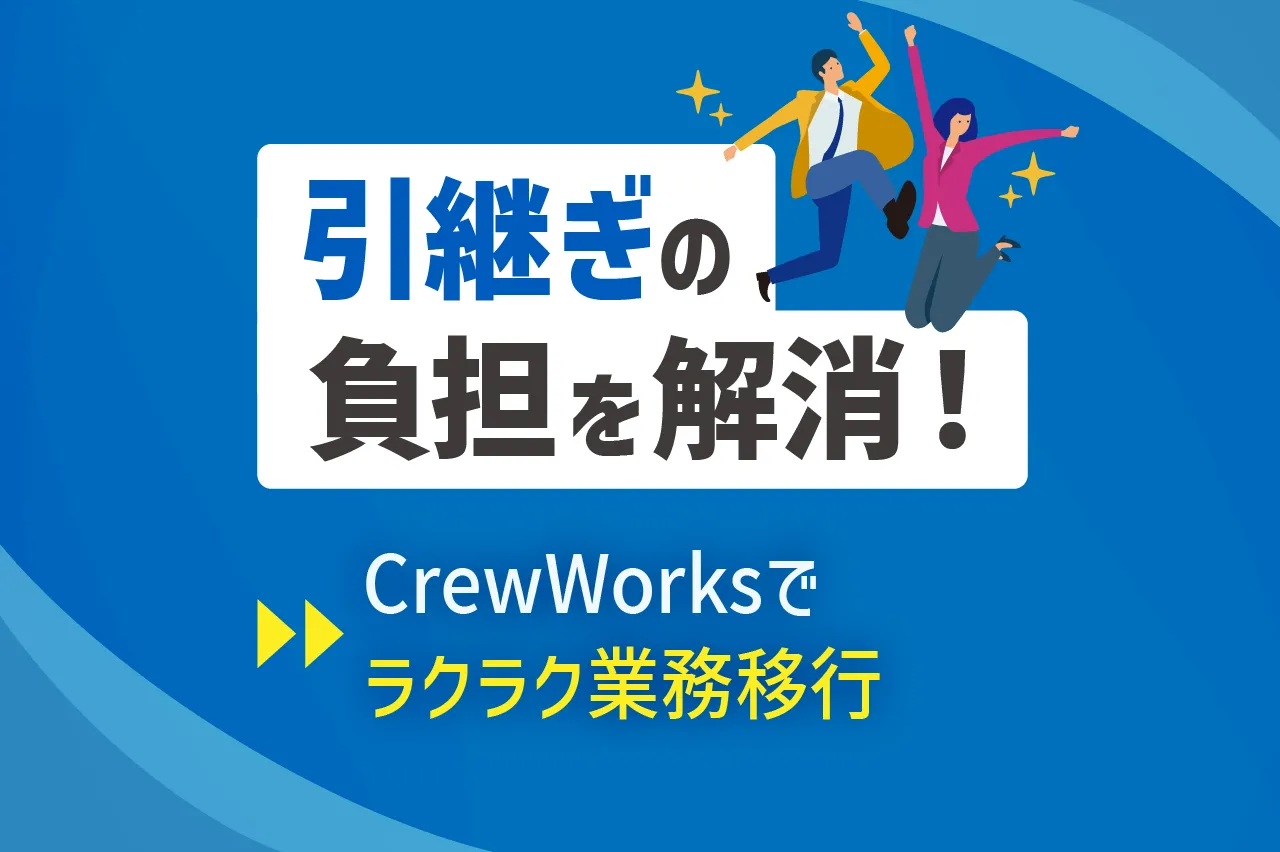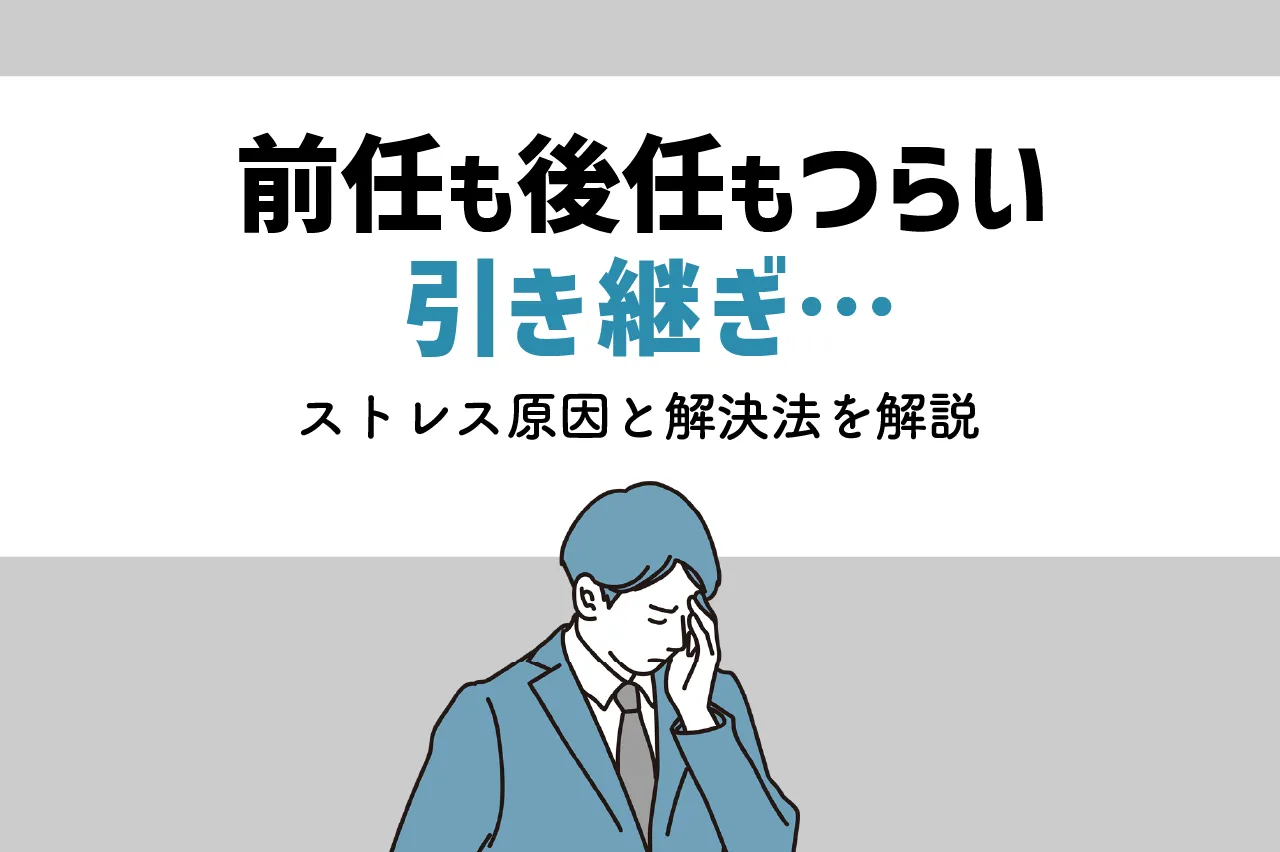仕事の引き継ぎあるある7選!克服のポイントも解説

退職や異動などその理由はさまざまですが、いずれにしても仕事の引き継ぎは確実に生じます。
しかし、引き継ぎがうまくいかず、後任者が苦労することは珍しくありません。
それを防ぐには、「仕事の引き継ぎあるある」を把握した上で、その対策を十分に講じることが有効です。
これにより、仕事の引き継ぎを滞りなく行えれば、社内業務がスムーズに行える上に顧客の印象を損ねるリスクも低減できるでしょう。
そこで今回は、仕事の引き継ぎあるある7選に加えて、仕事の引き継ぎに関する基礎知識や克服ポイントを解説します。
【目次】
仕事の引き継ぎは組織運営に欠かせない
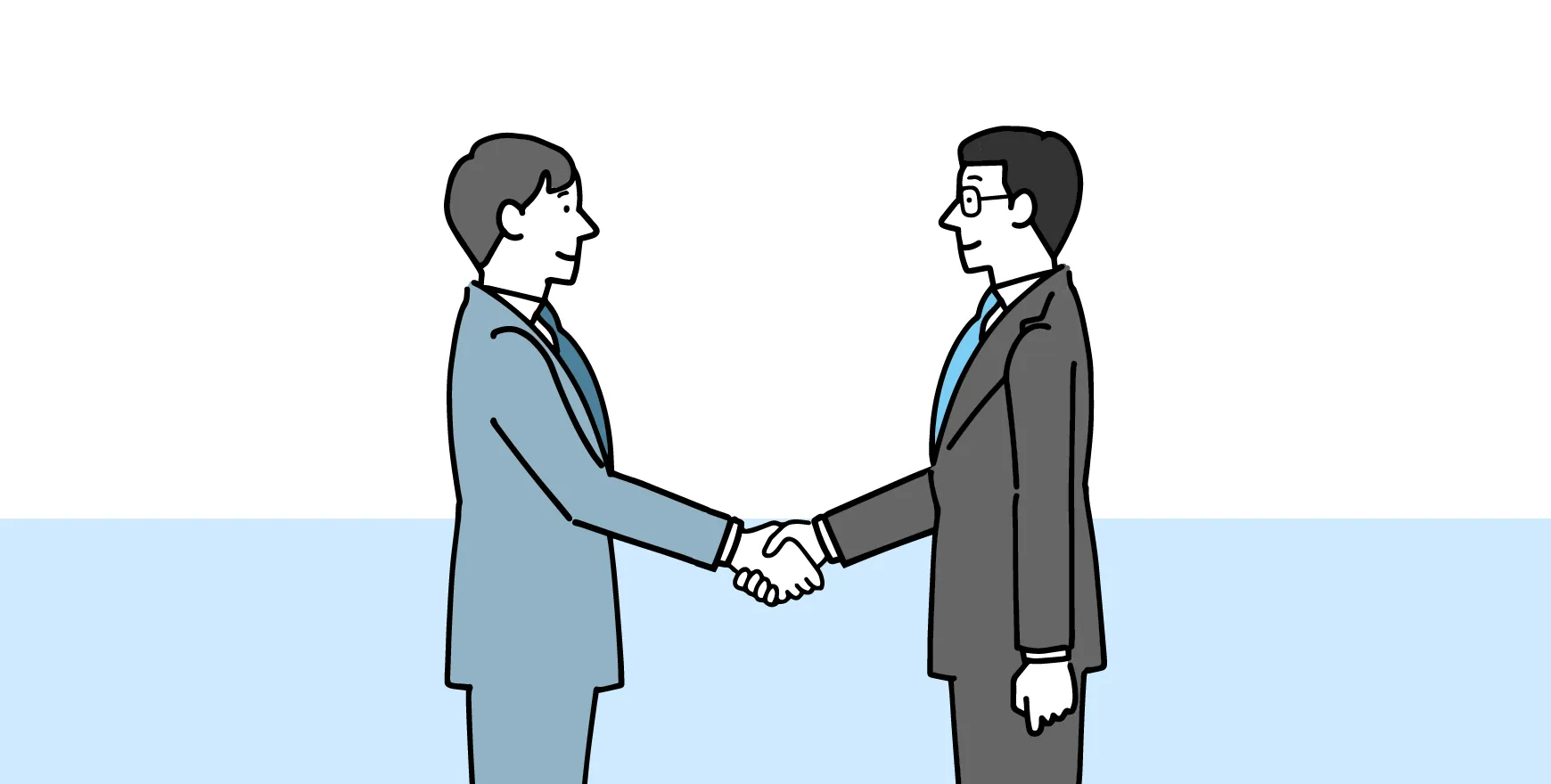
仕事の引き継ぎとは、担当者の異動や退職時に、現在の業務内容や進め方を後任者へ伝達するプロセスです。
引き継ぎが不十分だと、後任者は業務の進め方がわからず、顧客対応や取引先との関係に支障をきたす恐れがあります。
また前任者への問い合わせが頻発し、双方の業務効率が著しく低下することから、永続的な組織運営に引き継ぎは欠かせません。
関連記事:もう業務の引き継ぎで悩まない!事前準備からトラブル防止まで徹底解説
ここでは、仕事の引き継ぎに関する基礎知識について、以下の2点を解説します。
- 引き継ぎがうまくいかないとどうなる?
- 引き継ぎが発生するシーン
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぎがうまくいかないとどうなる?
仕事の引き継ぎに関する基礎知識の1つ目は、仕事の引き継ぎがうまくいかない場合のリスクです。
ここでは、以下の4点を解説します。
- 生産性の低下
- 信頼性の低下
- ナレッジの喪失
- 後任者への負担増加
1つずつ見ていきましょう。
生産性の低下
仕事の引き継ぎがうまくいかない場合のリスクの1つ目は、生産性の低下です。
適切に引き継ぎが行われないままに前任者の異動や退職が発生すると、後任者はこれまで行われてきた業務の進め方や手順がわかりません。
後任者は手探り状態で業務を進めることを余儀なくされ、その結果作業効率や生産性の大幅な低下を招きかねません。
上司や同僚に対し、業務に関して質問する必要がひんぱんに生じると、周囲の業務にも影響を与えるでしょう。
関連記事:生産性向上が企業活動で求められている!取り組み方や成功のポイントも解説
信頼性の低下
仕事の引き継ぎがうまくいかない場合のリスクの2つ目は、信頼性の低下です。
顧客や取引先との信頼関係は、前任者が長期にわたって関わってきたからこそ築き上げられます。
しかし、仕事の引き継ぎが不十分だと、担当者が変更になったことで業務に支障が出て、相手方に混乱や不便をかけかねません。
これでは、今まで構築されてきた信頼関係が損なわれる危険性があり、最悪の場合企業全体の信用問題に発展し、業績悪化につながる恐れもあります。
関連記事:引き継ぎがうまくいかない5つの理由!失敗しないための対処法を解説
ナレッジの喪失
仕事の引き継ぎがうまくいかない場合のリスクの3つ目は、ナレッジの喪失です。
実際の業務には、文書化されたマニュアルだけでは十分伝えきれない経験則やコツが存在することも珍しくありません。
それらを引き継ぐには、マニュアルだけでなく直接前任者との引き継ぎを行うことが有効です。
しかし、引き継ぎが不完全だと、前任者が長年かけて蓄積してきた貴重なノウハウや知識が組織から消失し、企業の競争力にも影響を与えかねません。
関連記事:ナレッジとは?ビジネスにおける関連用語やノウハウとの違いを徹底解説
関連記事:ナレッジの継承は企業活動で必要になる!うまくいかない要因や方法などを解説
後任者への負担増加
仕事の引き継ぎがうまくいかない場合のリスクの4つ目は、後任者への負担増加です。
引き継ぎが不十分だった場合、、業務がうまく進まず関係者にも迷惑をかけるため、後任者は心理的な負担を強いられます。
また、前任者との比較や業務評価の低下が発生すると、余計にストレスが蓄積して最悪の場合離職につながりかねません。
関連記事:キャパオーバーのサインに要注意!仕事の負担を軽減する方法
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
引き継ぎが発生するシーン
仕事の引き継ぎに関する基礎知識の2つ目は、引き継ぎが発生するシーンです。
仕事の引き継ぎは、以下に示すとおりさまざまなシーンで発生する可能性があります。
▼仕事の引き継ぎが発生するシーン(例)
- 人事異動
- 担当者の退職
- 担当者の休職
- 既存プロジェクトへの新規合流
- 既存プロジェクトからの離脱
- 新任者の加入
社外からは担当者の変更や引き継ぎがあるか不明なことも多いでしょう。業務品質や顧客満足の確保を実現するためにも、適切な引き継ぎが欠かせません。
仕事の引き継ぎあるある7選

ここでは、仕事の引き継ぎあるあるについて、以下の7点を解説します。
- 仕事に必要な資料・情報の不足
- 内容がわかりづらい引き継ぎ資料
- 引き継ぎ時の内容と実務で相違
- 前任者以外への情報共有が不十分
- データの所在が不明瞭
- テレワークで対面による引き継ぎが困難
- 情報共有にかかる時間不足
1つずつ見ていきましょう。
仕事に必要な資料・情報の不足
仕事の引き継ぎあるあるの1つ目は、仕事に必要な資料・情報の不足です。
前任者が必要な資料や重要な情報を十分に準備しないまま、後任者に業務を引き継ぐケースは珍しくありません。
そのため、後任者は業務の全体像や具体的な手順を把握しきれず、大きな困難に直面することもあるでしょう。
関連記事:マニュアル管理ができていない職場は危ない?導入ステップ・おすすめツールを解説
内容がわかりづらい引き継ぎ資料
仕事の引き継ぎあるあるの2つ目は、内容がわかりづらい引き継ぎ資料です。
引き継ぎ資料があっても、内容が体系化されておらず理解しにくいケースもあります。
引き継ぎ資料の情報が散在している場合や業務の全体像が把握しにくい場合は、後任者は正しく業務内容を理解することが困難です。
また、具体性に欠けた内容や古い情報が多い場合も、業務遂行に必要な情報を得られずに混乱を招きかねません。
関連記事:仕事引き継ぎでイライラが限界!原因・影響・対処法をわかりやすく解説
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
引き継ぎ時の内容と実務で相違
仕事の引き継ぎあるあるの3つ目は、引き継ぎ時の内容と実務で相違があることです。
引き継ぎで意外に多く発生するトラブルが、引き継ぎで共有された情報が実際の業務内容と異なっているケースです。
前任者が伝えた作業手順がすでに変更されているケースや、参照すべき資料の保存場所が変わっているケースがあります。
このように、引き継ぎ時の内容と実務で相違があり、後任者が誤った方法で業務を進めると、顧客からのクレームや納期遅延などの問題につながりかねません。
業務に関する変化が多い職場では、特に注意しましょう。
関連記事:前任者も後任者もつらい…仕事の引き継ぎで起こるストレスの原因と解消法を解説
前任者以外への情報共有が不十分
仕事の引き継ぎあるあるの4つ目は、前任者以外への情報共有が不十分であることです。
前任者の業務が属人化していた結果、他の同僚や上司が業務内容を把握していないケースも多く見られます。
その場合、後任者が業務についてわからないことを周りに質問しても、同じ部署の誰も答えられないこともあるでしょう。
特に、取引先ごとの個別事情や、従業員や部署ごとの特殊事情などが引き継がれないと、後任者に大きな負担をかけることになりかねません。
関連記事:今さら聞けない情報共有を徹底解説!~注目の理由からスムーズに行うためのポイントまで~
データの所在が不明瞭
仕事の引き継ぎあるあるの5つ目は、データの所在が不明瞭であることです。
業務に必要なマニュアルや資料の管理が不十分だと、業務に必要なデータがどこに保存されているのかわからなくなることもあるでしょう。
その場合、前任者は引き継ぎに必要な情報を集めるため、多大な時間がかかります。
また、引き継ぎ後も資料の場所が不明だと、後任者が必要な情報を探す手間がかかるため生産性の低下を引き起こしかねません。
関連記事:サイロ化とは?意味や引き起こす要因・生じる問題などをまとめて解説
テレワークで対面による引き継ぎが困難
仕事の引き継ぎあるあるの6つ目は、テレワークで対面による引き継ぎが困難であることです。
テレワークで業務を行っている場合、オフィスなどに出向いて対面で引き継ぎすることが困難なケースもあります。
この場合、言葉だけでは伝えにくい業務の細かいニュアンスや手順の背景理解が不足しがちで、相手の反応も見えにくいため認識のずれを生むこともあるでしょう。
関連記事:テレワークとは?今さら聞けない基本概要から効果・導入のポイントまで徹底解説
関連記事:テレワーク時代のコミュニケーションとは?課題の克服とチーム活性化の工夫
情報共有にかかる時間不足
仕事の引き継ぎあるあるの7つ目は、情報共有にかかる時間不足です。
異動や退職が決まってから急いで引き継ぎに向けた準備を開始すると、通常業務と並行して引き継ぎの準備を進めなければならず、情報共有にかかる時間不足が発生しかねません。
その結果、十分に資料を作り込んでわかりやすく口頭で説明することが困難になり、後任者が業務に対し多くの疑問を抱えることになるでしょう。
最悪の場合、顧客対応にも支障をきたし会社の信頼を損なうリスクも考えられます。
関連記事:情報共有を効率化するコツ!仕組みの作り方やツールの選び方も解説
仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイント

ここでは、仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイントについて、以下の4点を解説します。
- 引き継ぎ用マニュアルの作成
- 十分な引き継ぎ期間の確保
- 継続的なナレッジマネジメント
- ツールの有効活用
1つずつ見ていきましょう。
引き継ぎ用マニュアルの作成
仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイントの1つ目は、引き継ぎ用マニュアルの作成です。
口頭説明や簡単なメモだけで引き継ぎを行うと、情報の漏れや誤解が生じやすいため、体系的な引き継ぎマニュアルを作成しましょう。
マニュアルの作成時には、誰が読んでも理解できるよう業務に関する情報を整理すれば、後任者は業務の全体像を正確に把握できます。
また、一度マニュアルやそのテンプレートを作成すれば、将来的な引き継ぎにも継続して活用できるでしょう。
関連記事:引き継ぎマニュアルの作り方は5つの手順!わかりやすく作るポイントも解説
関連記事:マニュアル作成の負担を軽減し、ストレスゼロの引き継ぎを実現する方法とは?
十分な引き継ぎ期間の確保
仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイントの2つ目は、十分な引き継ぎ期間の確保です。
どれほど優れたマニュアルを作成しても、後任者が業務を完全に習得するには一定の時間が必要です。
そのため、引き継ぎ期間が不足すると、マニュアルを読んだだけで実践的なスキルや現場での判断力が身につかないまま業務を担当することになります。
理想的には一定期間OJT形式で引き継ぎたいところですが、業務の複雑さや後任者の経験レベルを考慮し、余裕があるスケジュールを組みましょう。
関連記事:プロジェクトの成功にはスケジュール管理が必須!手順やポイント・おすすめツール6選も紹介
継続的なナレッジマネジメント
仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイントの3つ目は、継続的なナレッジマネジメントです。
業務の属人化が発生すると、スムーズな引き継ぎは期待できません。
これを解決するには、組織全体で継続的にナレッジマネジメントを実施し、誰でもアクセス可能な形で業務に関する情報を蓄積できる仕組み作りが必要です。
経験や勘などの暗黙知も含め、可能な限り多くのナレッジをマニュアルやチェックリストなどの形式知として残し、組織全体で共有しましょう。
関連記事:暗黙知とは?ナレッジマネジメントで形式知化すべき理由・役立つツールも解説
関連記事:成功した企業に学ぶ!ナレッジマネジメントの成功事例4選とコツを解説
ツールの有効活用
仕事の引き継ぎあるあるを克服するポイントの4つ目は、ツールの有効活用です。
専用のマニュアル作成ツールを活用すると、引き継ぎマニュアルの作成・運用を大幅に効率化できます。
テンプレート機能を使えば、一目でわかりやすいマニュアルを簡単に作成でき、内容決定や構成検討などの作業にかかる手間を軽減できるでしょう。
また、編集機能が充実しているツールを活用すれば、視覚的にわかりやすいマニュアルの作成や、マニュアルの更新にも有利です。
関連記事:ナレッジマネジメントシステムとは?導入メリット・デメリットと選び方
関連記事:ナレッジツールおすすめ13選を紹介!
まとめ
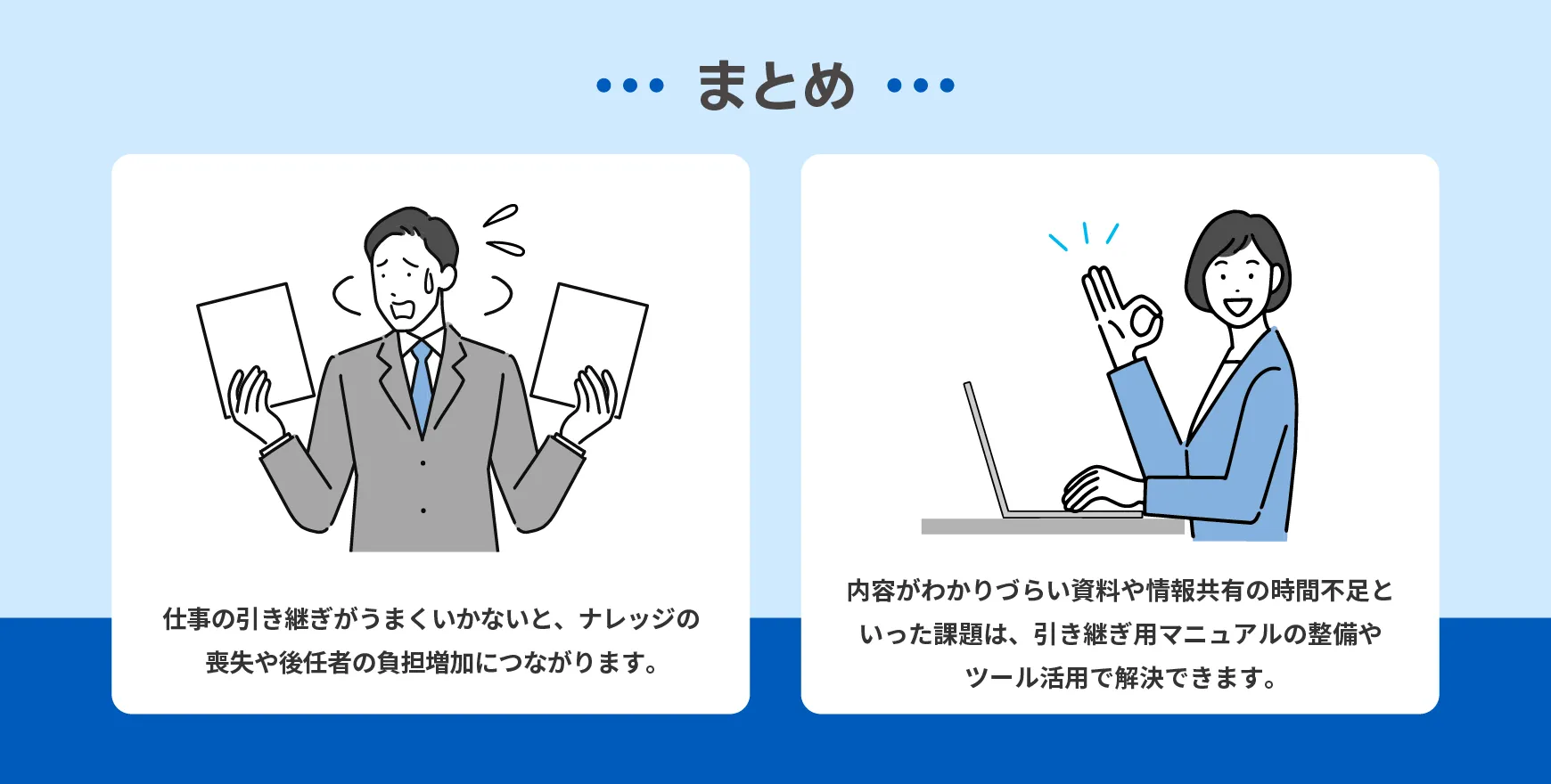
今回は、仕事の引き継ぎあるある7選に加えて、仕事の引き継ぎに関する基礎知識や克服ポイントを解説しました。
人事異動や退職などさまざまな場面で仕事の引き継ぎが必要ですが、それがうまくいかないと、ナレッジの喪失や後任者への負担増加などを引き起こしかねません。
仕事の引き継ぎあるあるには、内容がわかりづらい引き継ぎ資料や情報共有にかかる時間不足などがあります。これらを克服するには、引き継ぎ用マニュアルの作成やツールの有効活用などがおすすめです。
CrewWorks(クルーワークス)を活用することで、業務の見える化やナレッジの蓄積を効率的に行うことができ、スムーズな引き継ぎと組織全体の生産性向上を後押しすることができるでしょう。
サービスサイトはこちら: https://crewworks.net/
無料で最大50ユーザーまで利用できるフリープランがありますので、ぜひご活用ください。
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
また、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする