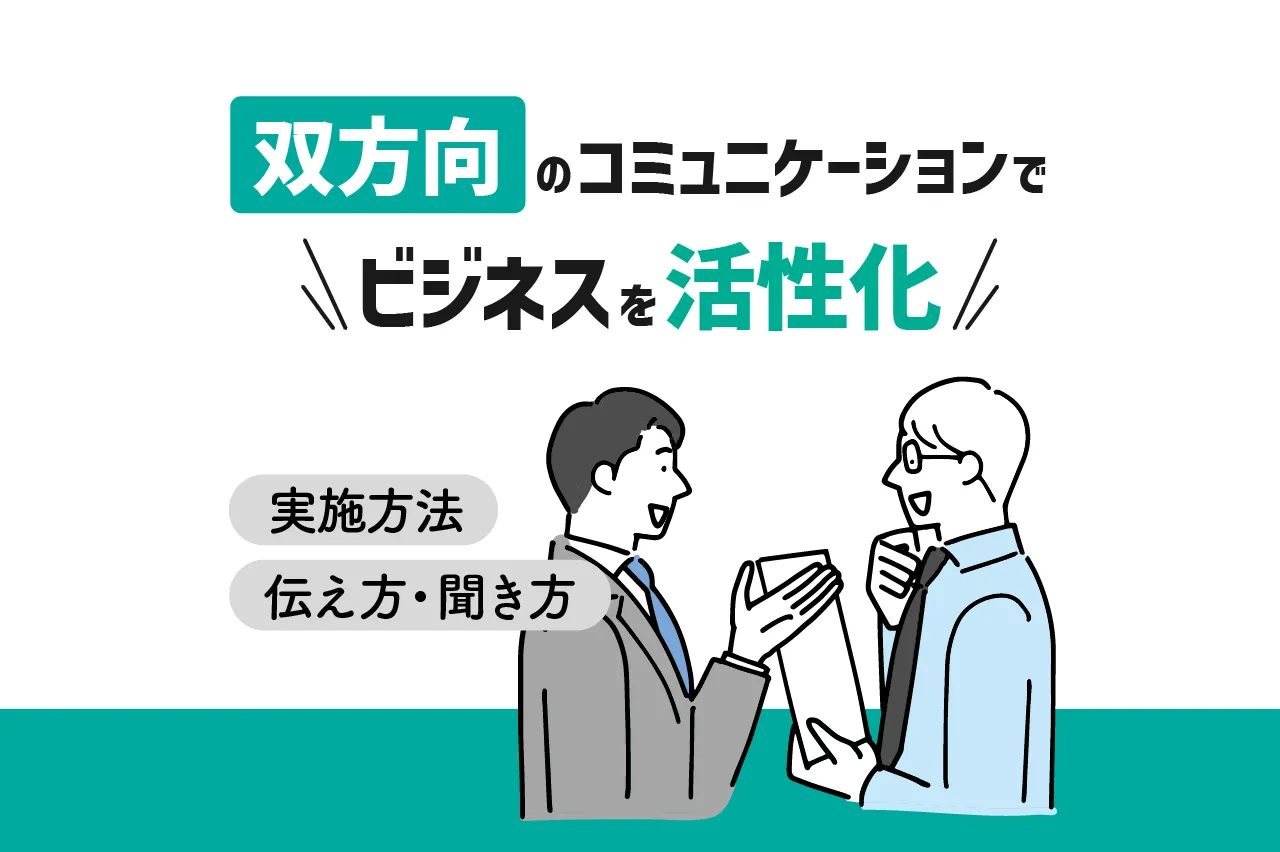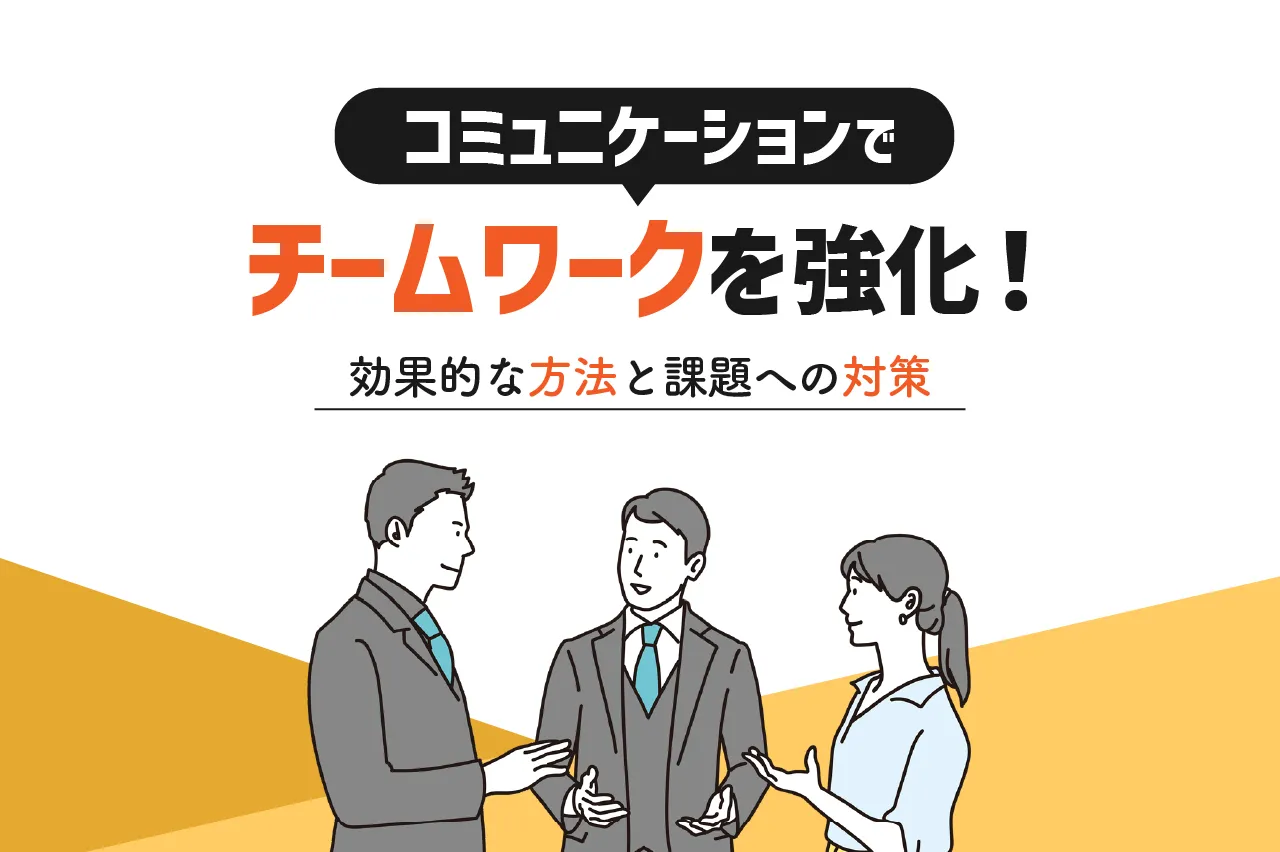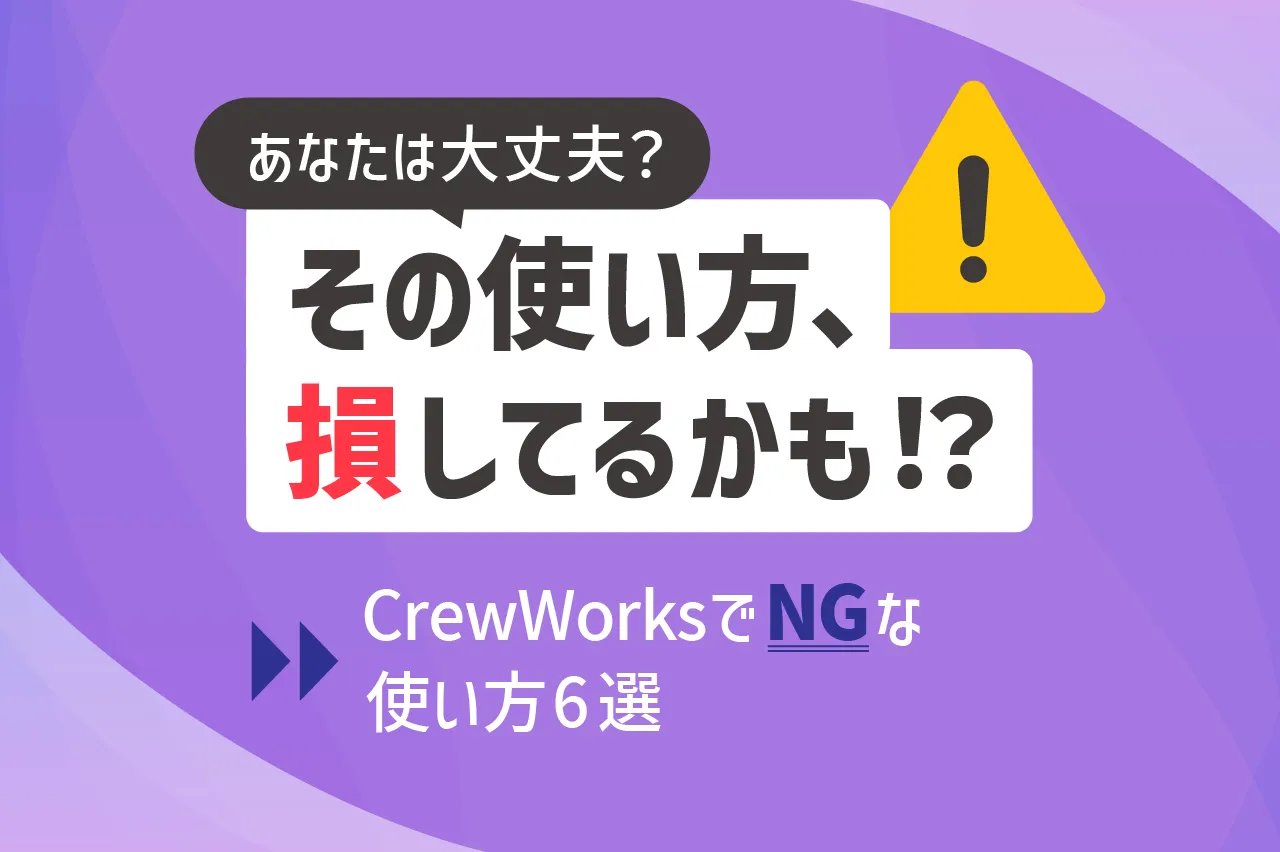同期と非同期コミュニケーションの違いとは?メリット・デメリットと使い分けを解説!
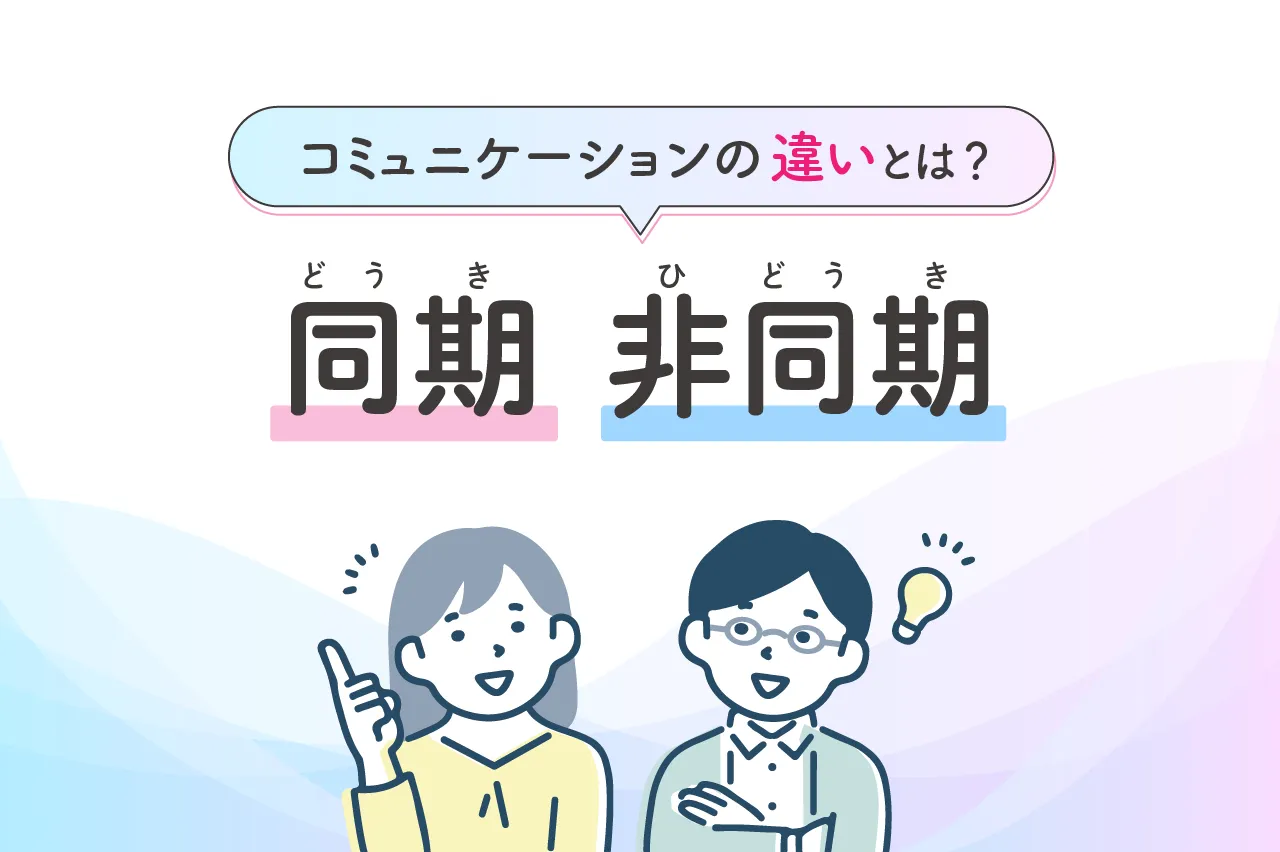
プロジェクトの進行やタスク管理を円滑に進めるためには、同期コミュニケーションと非同期コミュニケーションの使い分けを知っておくことが重要です。
しかし、具体的にどちらのコミュニケーション方法が適しているのか迷うこともあるでしょう。
そこで今回は、同期と非同期コミュニケーション、それぞれのメリット・デメリットとシーンに応じた使い分けのコツを解説します。
【目次】
■同期・非同期の両方のコミュニケーションができるツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的なコミュニケーションができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
同期コミュニケーションとは

ここでは、同期コミュニケーションについて、以下の2点を解説します。
- 同期コミュニケーション
- 非同期コミュニケーション
1つずつ見ていきましょう。
同期コミュニケーション
同期コミュニケーションとは、相手と同じタイミングで行われるコミュニケーションの形式のことです。
例えば、対面や電話での会話・オンラインミーティングなどを通じたコミュニケーションが該当します。
同期コミュニケーションでは、メッセージを送った瞬間に返答を受けることができ、迅速な意思疎通が可能です。
関連記事:今さら聞けないWebミーティングとは?開催する理由とおすすめのアプリ7選!
非同期コミュニケーション
非同期コミュニケーションは、相手と同じタイミングでのやり取りが必要ない形式のコミュニケーションのことです。
相手から連絡がきてもすぐに返信する必要はなく、各自の都合の良いタイミングでメッセージを確認したり、対応することができます。
代表的な例として、メール、ビジネスチャット、プロジェクト管理ツールのタスク共有、Googleドキュメントでの共同編集、録画されたビデオメッセージなどが挙げられます。
同じタイミングでの応答ではなく、相手の都合に関係なく情報をやり取りできる点が特徴です。そのため、異なるタイムゾーンで働くチームや、深い集中を要する作業を行う人にとって有効な手段です。
チームの生産性向上のために、同期・非同期のバランスを意識することが重要です。
関連記事:ビジネスチャットとは?おすすめツール7選と活用のメリットや主な機能を比較解説
関連記事:【2025年版】プロジェクト管理ツールおすすめ16選を徹底比較!5つの確認ポイントも紹介
関連記事:タスク管理とは?効率的な実施方法からおすすめのツール8選をまとめて比較・解説
▼同期・非同期の両方のコミュニケーション履歴をナレッジとして活用したい方は、ぜひこちらをご覧ください。
同期・非同期の両方のコミュニケーション全てを記録し、最大限にナレッジとして活用するための課題と使うべきツールとは?
同期コミュニケーションのメリット

ここでは、同期コミュニケーションのメリットについて、以下の3点を解説します。
- 即時性がある
- 誤解を減らせる
- チームの一体感を高める
1つずつ見ていきましょう。
即時性がある
同期コミュニケーションのメリットの1つ目は、即時性があることです。
相手と同じタイミングでやり取りができるため、質問や相談をその場で解決しやすく、意思決定のスピードが向上します。特に、業務上のトラブル対応や緊急の判断が必要な場面では、迅速なコミュニケーションが欠かせません。
非同期コミュニケーションでは、即座の対応を前提とせず、返信までに一定の時間がかかることがあります。そのため、急を要する場面でメッセージを送っても、すぐに相手と連絡が取れないケースが十分考えられます。
連絡が滞った場合、その後の業務進行に影響を及ぼし、スケジュールの遅れにつながる可能性もあるでしょう。
対面での会話やオンライン会議・電話などの手段を活用すれば、すぐに回答を得られます。
誤解を減らせる
同期コミュニケーションのメリットの2つ目は、誤解を減らせることです。
会議や電話、オンラインミーティングなどの同期コミュニケーションでは、直接話しながら詳細な説明ができ、疑問があればその場で解決しやすいという利点があります。
一方で、メールやチャットのみのやり取りでは、微妙なニュアンスが伝わりにくく、表現の仕方や受け取り方の違いによって認識のずれが生じることも少なくありません。
その結果、意図が十分に伝わらず、誤解が生まれる可能性があります。
リアルタイムでのやり取りが可能な同期コミュニケーションを活用することで、相手の反応を見ながら適切に補足説明を加えたり、必要に応じて言い換えることも可能です。
また、その場で質問し合うことで、双方の認識をすり合わせながら話を進められるため、情報の食い違いや誤解を未然に防げるでしょう。
関連記事:ビジネスチャットと電話はビジネスシーンでどう使い分ける?メリット・デメリットより整理
チームの一体感を高める
同期コミュニケーションのメリットの3つ目は、チームの一体感を高めることです。
リアルタイムでのやり取りを通じて、メンバー同士の関係を築きやすくなり、協力しながら業務を進める環境が整います。
例えば、対面の会議やオンラインミーティングでは、直接意見を交わしながら意思決定を行えるため、チームの結束力が強まります。
また、ビデオ通話や電話を活用することで、リモートワークでもコミュニケーションの機会を増やし、孤立を防ぐことが可能です。
雑談やカジュアルなやり取りがあれば、心理的な距離が縮まり、信頼関係が構築されやすくなるという効果もあります。
関連記事:テレワーク時代のコミュニケーションとは?課題の克服とチーム活性化の工夫
■同期・非同期の両方のコミュニケーションができるツール
無料で最大50ユーザーまで、効率的なコミュニケーションができるツール「CrewWorks(クルーワークス)」
⇒使える機能を確認して、フリープランを使ってみる
まず、CrewWorksの概要や実現できること・導入事例を確認したい方は、ぜひ3分で分かるサービス紹介資料をご覧ください。
⇒3分でわかるCrewWorksのサービス紹介資料を無料ダウンロードする
同期コミュニケーションのデメリット

ここでは、同期コミュニケーションのデメリットについて、以下の2点を解説します。
- スケジュールを合わせる必要がある
- 即時の対応を求められる
1つずつ見ていきましょう。
スケジュールを合わせる必要がある
同期コミュニケーションのデメリットの1つ目は、スケジュールを合わせる必要があることです。
同じタイミングでのやり取りを前提とするため、関係者全員の都合を調整しなければならず、時間の確保が難しい場合があります。
特に、複数の拠点にメンバーがいる場合や、リモートワーク環境下では、異なるタイムゾーンや勤務時間の違いが影響し、全員が同時に参加できないこともあるでしょう。
また、急な会議の設定や即時対応を求められることが増えると、個々の業務に集中できる時間が削られ、生産性の低下につながる可能性があります。
そのため、同期コミュニケーションを活用するときには、会議の必要性を慎重に判断し、重要度の低い内容は非同期コミュニケーションで対応するなど、適切なバランスを取ることが重要です。
関連記事:スケジュール管理が苦手で困っている!よくある悩みや克服方法を解説
即時の対応を求められる
同期コミュニケーションのデメリットの2つ目は、即時の対応を求められることです。
同期コミュニケーションは、相手の都合に関係なく対応を求められることがあるため、業務の中断を引き起こす可能性があります。
例えば、会議やオンラインミーティング、内線電話などが頻繁に発生すると、個々の作業時間が細切れになり、集中力が途切れることもあるでしょう。
また、即座に返答を求められることで、十分に考えを整理する時間が取れず、不完全な回答をしてしまうリスクもあります。
特に、リモートワークやフレックスタイム制の環境では、勤務時間が異なるメンバーがいるため、即時対応を前提にすると業務負担が増す可能性があります。
対応のルールを設け、非同期コミュニケーションと組み合わせることで、ストレスを軽減しながら効率的な業務運営を実現することが大切です。
同期コミュニケーションが向く場面

ここでは、同期コミュニケーションが向く場面について、以下の4点を解説します。
- 緊急時やトラブル対応
- 重要な意思決定や議論
- チームの結束を高めるミーティングや1on1
- 研修やプレゼンテーション
1つずつ見ていきましょう。
緊急時やトラブル対応
同期コミュニケーションが向く場面の1つ目は、緊急時やトラブル対応です。
迅速な判断と対応が求められる状況では、同期コミュニケーションは有効です。
例えば、システム障害やクレーム対応など、即座に解決しなければならない問題が発生したとき、メールやチャットのような非同期コミュニケーションでは対応が遅れ、被害が拡大する恐れがあります。
その点、電話やオンライン会議を活用すれば、関係者が即時に状況を把握し、適切な対応策を協議できるでしょう。
また、緊急性の高い業務では、認識のズレが大きなトラブルにつながることもあります。
対面での会話やビデオ通話を通じて確認することで、誤解を防ぎ、迅速な問題解決につなげられます。緊急時やトラブル発生時には、同期コミュニケーションを積極的に活用することが重要です。
重要な意思決定や議論
同期コミュニケーションが向く場面の2つ目は、重要な意思決定や議論です。
リアルタイムでの対話を通じて、関係者がその場で意見を交わし、迅速に結論を出すことができます。
例えば、新規プロジェクトの方針決定や、経営戦略の策定、トラブル対応の意思決定など、複数の視点から議論しながら進める必要がある場面では、同期コミュニケーションが効果的です。
対面会議やオンラインミーティングを活用すれば、相手の表情や声のトーンからニュアンスを読み取り、誤解を防ぐこともできるでしょう。
また、意見のすり合わせがスムーズに行えるため、非同期コミュニケーションでは時間がかかる調整を短縮できる点も大きなメリットです。
特に、組織の方向性を左右するような重要な意思決定では、リアルタイムでの議論を行い、共通認識を深めることが重要です。
チームの結束を高めるミーティングや1on1
同期コミュニケーションが向く場面の3つ目は、チームの結束を高めるミーティングや1on1です。
例えば、定期的なチームミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、意見交換や課題の共有を行うことで、メンバー同士の連携を強化できます。
また、1on1ミーティングでは、上司と部下が直接対話することで、不安や悩みを解消し、モチベーション向上につなげることが可能です。
リモートワークが多い環境下では、同期コミュニケーションを活用することで、メンバーの孤立を防ぎ、組織全体のエンゲージメントを維持できます。
チームの結束を高める場面では、リアルタイムのコミュニケーションを積極的に取り入れることが重要です。
関連記事:チームビルディングとは、効果的な目的と実践例で結束力を高める秘訣
研修やプレゼンテーション
同期コミュニケーションが向く場面の4つ目は、研修やプレゼンテーションです。
リアルタイムでの対話ができることで、受講者や参加者の理解度を確認しながら進めることができ、効果的な情報伝達が可能になります。
例えば、新入社員研修やスキルアップ研修では、講師が参加者の反応を見ながら説明を調整できるため、より分かりやすい指導ができるでしょう。
また、プレゼンテーションでは、聞き手の疑問にその場で対応したり、双方向のやり取りを取り入れることで、説得力を高められます。
ワークショップやディスカッションを組み合わせることで、学びを深め、実践的なスキルを身につけることにも役立つでしょう。
特に、複雑な内容や即時の質疑応答が求められる場面では、同期コミュニケーションを活用することで、研修やプレゼンの効果を最大限に引き出しやすくなります。
▼同期・非同期の両方のコミュニケーション履歴をナレッジとして活用したい方は、ぜひこちらをご覧ください。
同期・非同期の両方のコミュニケーション全てを記録し、最大限にナレッジとして活用するための課題と使うべきツールとは?
非同期コミュニケーションが向く場面

ここでは、非同期コミュニケーションが向く場面について、以下の3点を解説します。
- じっくり考える必要がある議論やフィードバック
- 記録を残す必要がある業務
- 個々のペースで作業を進めたい場合
1つずつ見ていきましょう。
じっくり考える必要がある議論やフィードバック
非同期コミュニケーションが向く場面の1つ目は、じっくり考える必要がある議論やフィードバックです。
リアルタイムでのやり取りでは、即座に返答する必要があるため、十分に考えを整理できず、質の高い議論やフィードバックが難しくなることがあります。
例えば、プロジェクトの方向性について深く考える必要がある場合や、相手の成果物に対して丁寧なフィードバックを行う場合が該当します。
非同期のメールやコメント機能を活用すれば、時間をかけて適切な意見を伝えられるでしょう。
また、非同期コミュニケーションであれば受け取る側も落ち着いて内容を理解でき、必要に応じて資料を確認しながら対応可能です。
特に、クリエイティブな作業や戦略的な意思決定に関する議論では、非同期コミュニケーションが向いています。時間をかけて思考を深めた方が、より質の高いアウトプットができるでしょう。
記録を残す必要がある業務
非同期コミュニケーションが向く場面の2つ目は、記録を残す必要がある業務です。
非同期のやり取りでは、メールやチャット、プロジェクト管理ツールなどを通じて、コミュニケーションの内容を明確に記録し、後から参照することが可能です。
例えば、業務の引き継ぎを口頭や会議だけで行うと、記憶に頼ることになり、情報の抜け漏れや誤解が生じかねません。
非同期コミュニケーションを活用すれば、経緯をテキスト化し、関係者全員が後で確認できるため、スムーズな業務の移行が可能になります。
また、過去のやり取りを振り返ることで、ミスの防止や業務改善にもつながるでしょう。記録を残す必要がある場面では、非同期コミュニケーションが有効です。
個々のペースで作業を進めたい場合
非同期コミュニケーションが向く場面の3つ目は、個々のペースで作業を進めたい場合です。
非同期コミュニケーションはリアルタイムでの対応を求められないため、各自のスケジュールや集中力を考慮しながら、適切なタイミングで対応できるのが特徴です。
例えば、クリエイティブな作業や企画立案など、深く考える時間が必要な業務では、即時の応答を求められると集中力が削がれ、作業効率が低下することがあります。
しかし、非同期コミュニケーションを活用すれば、他の業務とバランスを取りながら、自分のペースで作業を進めることが可能です。
また、異なるタイムゾーンで働くメンバーやフレックスタイムを活用する従業員がいる場合、全員が同時に対応できないこともあるでしょう。
非同期での情報共有や意思決定を行うことで、業務の遅延を防ぎつつ、各メンバーが最適なタイミングで作業を進められます。
個人のペースで業務を進行する場合や、柔軟な働き方を実現したい場合に、非同期コミュニケーションが有効です。
同期・非同期の両方のコミュニケーションができるツール「CrewWorks」
業務の効率を高めるためには、リアルタイムでの迅速な意思決定と、じっくり考えて対応する柔軟なコミュニケーションの両方が求められます。
CrewWorks(クルーワークス)は、ビジネスチャット・タスク管理・プロジェクト管理・Web会議など同期・非同期のコミュニケーションをシームレスに組み合わせ、業務のスムーズな進行をサポートするツールです。
通常のチャットツールでは、情報が分散し、どこでどのような話をしたのかを探すのに時間がかかることも少なくありません。CrewWorksでは、プロジェクトやタスクごとにチャットが自動で紐づくため、すぐに必要な情報へアクセスできます。
また、CrewWorksでは関連情報が自動的に整理・蓄積されるため、チーム内のナレッジとして活用できます。会議の議事録やタスクの進捗状況、ファイルの更新履歴などが一元管理されるため、「どこに何の情報があったのか?」と探し回る必要がありません。
「業務に必要な情報とコミュニケーションを、ひとつのツールでまとめて管理したい」「リアルタイムと非リアルタイム、どちらのコミュニケーションも使い分けたい」といった課題を感じている企業・チームにとって、CrewWorksは最適です。
CrewWorksでは、無料で最大50ユーザーまで使えるフリープランを提供しています。ぜひご活用ください。
また、3分でわかる!CrewWorksのサービス資料は、こちらから無料ダウンロードください。
まとめ

今回は、同期と非同期コミュニケーション、それぞれのメリット・デメリットとシーンに応じた使い分けのコツを解説しました。
同期コミュニケーションは即時性が高く、迅速な意思決定や円滑な議論が可能ですが、スケジュール調整が必要で即時対応の負担が発生しやすいというデメリットもあります。
一方、非同期コミュニケーションは個々のペースで対応でき、記録を残しやすい利点がありますが、リアルタイム性に欠け、意思疎通に時間がかかることもあります。
業務の生産性を向上させるには、業務内容や目的に応じて、同期・非同期を適切に使い分けることが、大切です。
自社のコミュニケーション環境を見直し、適切なツールやルールを導入して、業務の効率化を進めましょう。
▼同期・非同期の両方のコミュニケーション履歴をナレッジとして活用したい方は、ぜひこちらをご覧ください。
同期・非同期の両方のコミュニケーション全てを記録し、最大限にナレッジとして活用するための課題と使うべきツールとは?