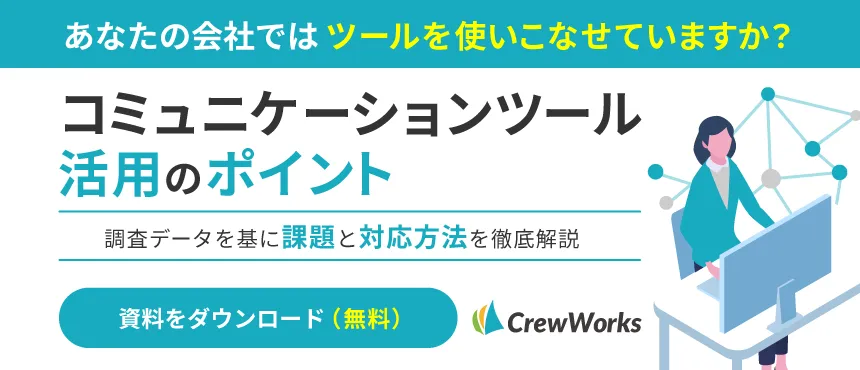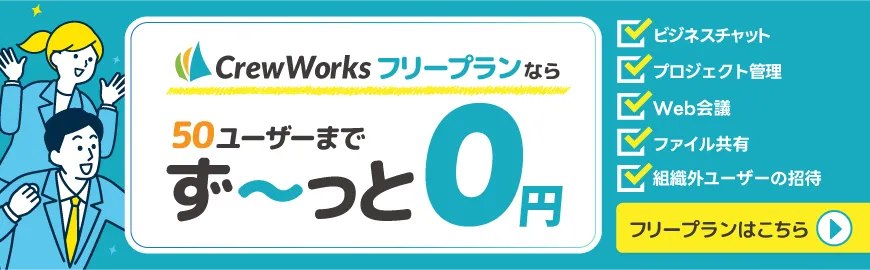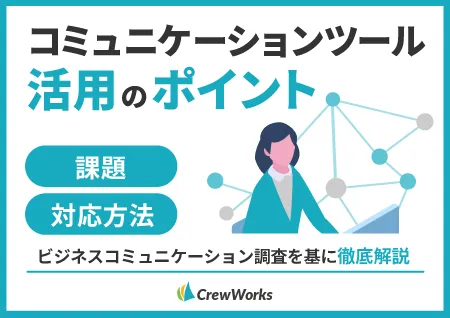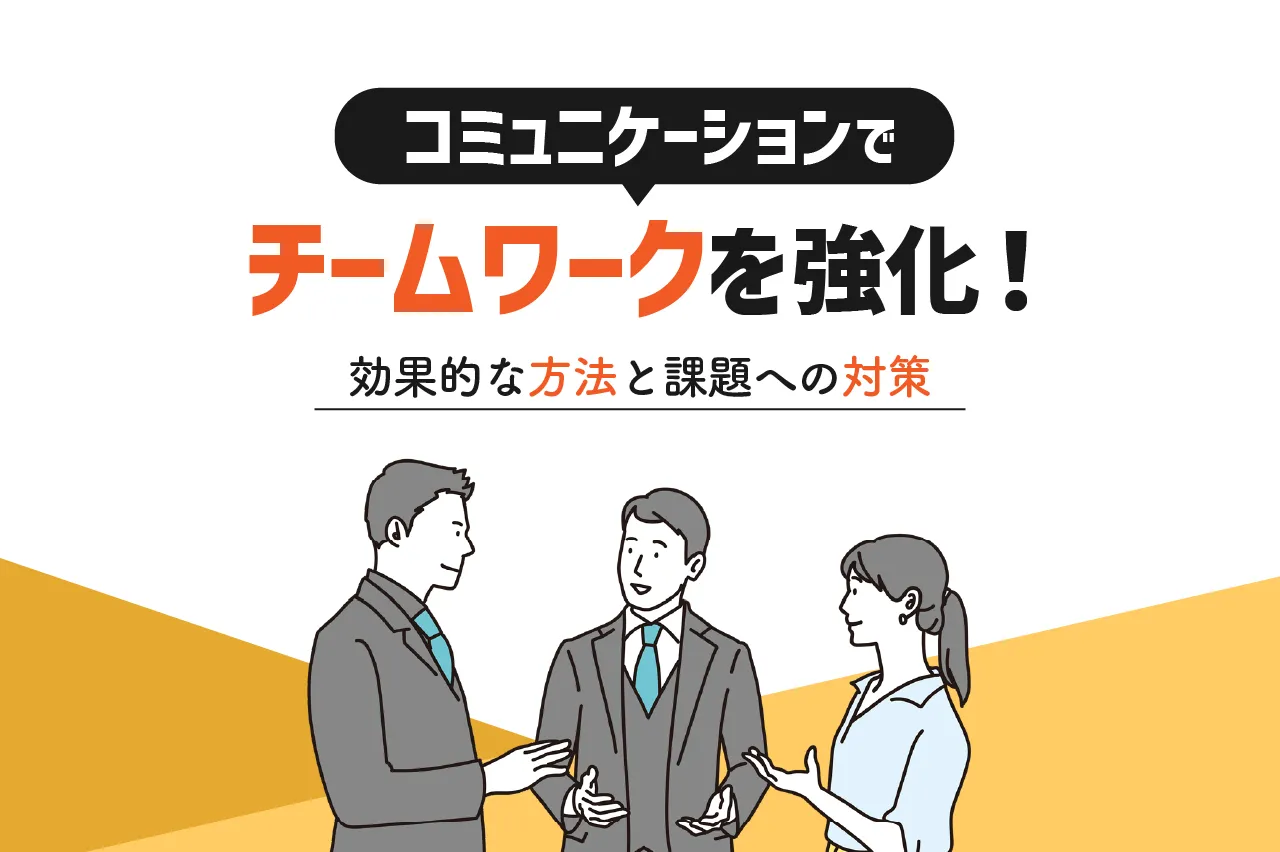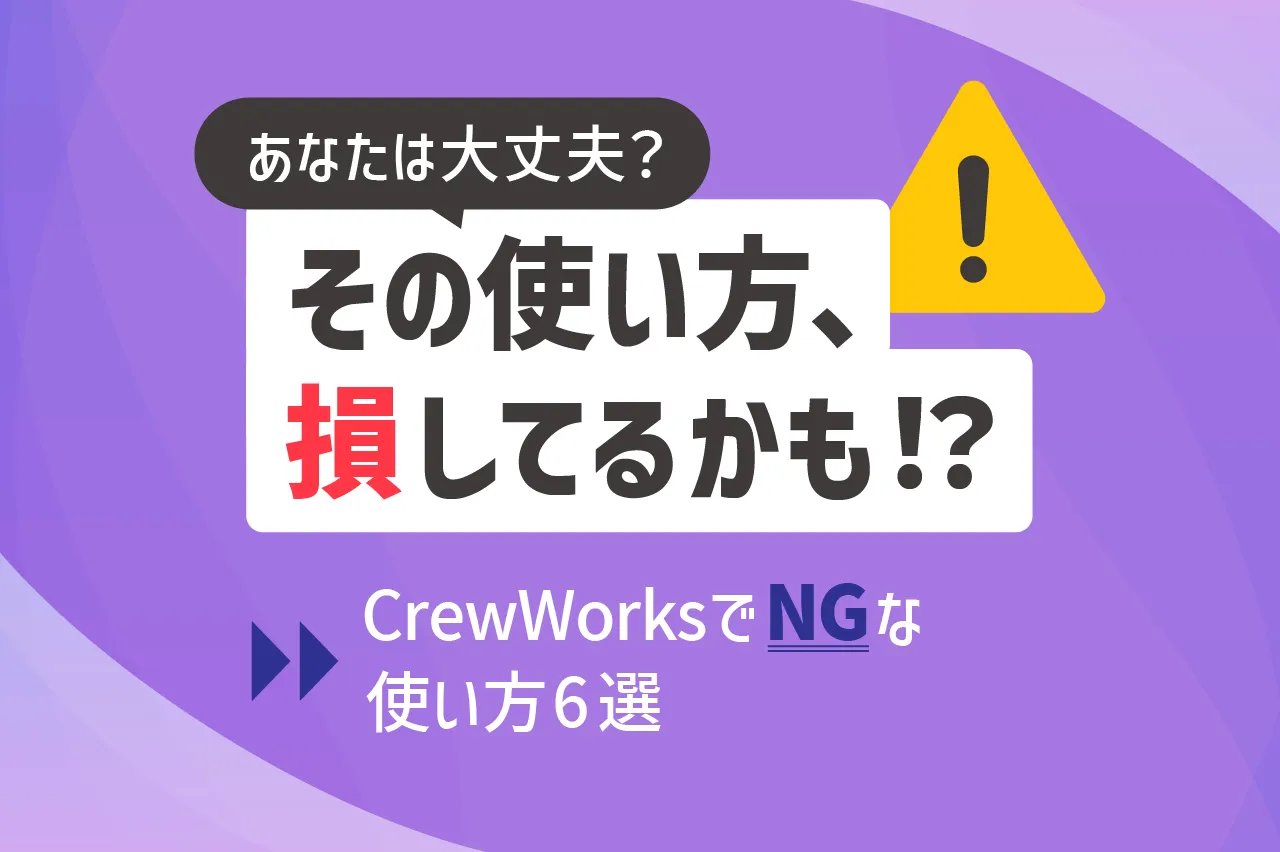社内コミュニケーションの課題とは?原因や解決策8選を解説!

チーム間の認識齟齬や情報伝達の遅れは、業務効率の低下を招くことがあります。
そこで今回は、よくある社内コミュニケーションの課題、社内コミュニケーションが発生する原因、解決策6選を解説します。
【目次】
社内コミュニケーションの重要性

組織やチームがスムーズに運営されるためには、従業員同士の円滑なやり取りが欠かせません。
社内コミュニケーションは業務上の情報連携や意思決定だけでなく、従業員同士の信頼関係を構築するうえでも重要な役割を担います。
うまくいっている職場では、情報が滞りなく流れて業務効率が高まり、新しいアイデアが生まれやすい環境を形成します。
また、部署の垣根を越えたコミュニケーションが促進されると、関係者全体の状況把握が容易になり、組織としての目標に向けて一致団結しやすくなります。
特に、業務内容が複雑化した現代では、個人に偏ったノウハウよりも組織全体で知識を共有することが求められます。
社内のコミュニケーションが円滑であれば、問題や課題が早期発見され、トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
情報連携がスピーディに行われることで、従業員一人ひとりが主体的に動きやすくなり、企業力の底上げにつながります。
関連記事:社内コミュニケーションの重要性と効果的な活用法、成功する秘訣を徹底解説
関連記事:職場のコミュニケーションを活性化させるためには?重要性とポイントを解説
社内コミュニケーション不足によって生じる課題とは?

ここでは、社内コミュニケーション不足によって生じる課題について、以下の11点を解説します。
- 情報共有の不足が発生している
- 信頼関係が構築できない
- ミスやトラブルが頻発する
- 属人化が起こる・ノウハウが蓄積されない
- 人材の育成に時間がかかる
- 精神的ストレスが増加する
- 革新的なアイデアが生まれない
- チームワークを強化できない
- 従業員がストレスを抱えやすい
- 離職する従業員が多い
- 従業員のモチベーションが低下する
1つずつ見ていきましょう。
情報共有の不足が発生している
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の1つ目は、情報共有の不足が発生していることです。
コミュニケーションがうまくいかないと業務に必要な情報発信がされず、トラブルが発生しやすくなります。
従業員同士が業務中に会話をする機会が少ないと、業務に関する質問や確認、相談が気軽にできなくなる可能性もあります。
問題が発生した場合でも報告が遅れ、大きなトラブルに発展してしまうこともあるため改善する必要があるでしょう。
関連記事:情報共有不足はなぜ起こる?原因と解決するためのツール5選
信頼関係が構築できない
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の2つ目は、信頼関係が構築できないことです。
コミュニケーション不足はお互いの考え方や状況を把握しづらくし、メンバー間の相互理解を妨げます。
どれだけ優秀な人材が集まっていても、信頼関係がないと協力体制を築けず、チーム力を向上させ成果を最大化することができません。
たとえば、会議や雑談の場が減ると、自分の思いや考えを伝えるタイミングが限定されるため、相互理解が進まないまま業務が進行します。結果として、人間関係の希薄化や悪化が職場全体のパフォーマンスを落とします。
信頼関係を強化するためには、定期的な対話や上司・部下間での1on1ミーティングなど、状況を共有できる取り組みが重要です。
関連記事:社内コミュニケーション不足にさよなら!原因と効果的な交流促進テクニック
ミスやトラブルが頻発する
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の3つ目は、ミスやトラブルが頻発することです。
コミュニケーションがうまくいかないと情報の伝達漏れや間違いが起こり、従業員間や部門間で意思の疎通がしづらくなります。
そうなると、誤解や齟齬が起こりミスやトラブルが発生してしまう恐れがあります。結果的に業務の効率性が下がり、生産性の低下を招く恐れがあるでしょう。
関連記事:もう悩まない!コミュニケーションロスの原因と対策を具体例付きで紹介
属人化が起こる・ノウハウが蓄積されない
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の4つ目は属人化が起こる・ノウハウが蓄積されないことです。
属人化とは、特定の人物だけが業務内容や進行方法を理解している状態を指します。
社内のコミュニケーションが少ないと、従業員同士で成功事例や失敗事例を共有する機会が減り、業務の進め方が属人化する恐れがあります。
特定の個人が全ての業務を単独で担当していると、他の従業員は業務手順や進捗状況などを把握できず、作業の重複や誤解が生じ、効率の低下につながるでしょう。
関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説
関連記事:ノウハウとは?ビジネスシーンにおける意味や使い方と活用メリットをわかりやすく解説
人材の育成に時間がかかる
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の5つ目は、人材の育成に時間がかかることです。
コミュニケーション不足により先輩社員から指導やサポートが行われない状態では、技術やスキルが新入社員・若手社員や中途採用の従業員に受け継がれなくなってしまい、人材育成が進みません。
従業員のスキル習得に時間がかかると、結果的に組織全体の成長にも影響を及ぼす恐れがあるでしょう。
精神的ストレスが増加する
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の6つ目は、精神的ストレスが増加することです。
相談や協力体制が不十分だと、従業員は業務上の不安や疑問を一人で抱え込んでしまいがちです。テレワーク環境では特に孤立感が強まり、心理的な負担が増すケースがあります。
また、気軽に雑談できる相手がいないと、ネガティブな感情を発散する機会も少なくなります。結果として、ストレスが蓄積されやすい状態が続くと、モチベーション低下や離職率の上昇につながる恐れがあります。
メンタルヘルスを維持するためにも、定期的に話し合える環境を整備し、声を掛けられる社風・雰囲気づくりを行うことが重要です。
関連記事:コミュニケーションの円滑化は重要?理由・メリット・ポイントをやさしく解説
革新的なアイデアが生まれない
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の7つ目は、革新的なアイデアが生まれないことです。
活発な意見交換や情報共有がないと、常に同じ視点や考え方に限定され、新しい発想が生まれにくくなります。組織のイノベーション創出を阻害し、他社との差別化が難しくなる要因にもなります。
会議でアイデアを出そうとしても、十分に意見を交わさなければ、多様性のある発想や具体性の高い提案には発展しません。
特に、リモート環境下では気軽なやり取りが減るため、雑談の中から生まれるひらめきが失われがちです。
こうした課題を解決するには、ビデオ会議システムを導入したりワークショップ、ブレーンストーミングの機会を確保するなど、自由に意見を出し合える仕組みづくりや関係性の強化が必要です。
チームワークを強化できない
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の8つ目は、チームワークを強化できないことです。
目標認識や役割分担の共有が曖昧だと、協力体制がうまく構築されずにプロジェクトが停滞しやすくなります。チームワークが発揮されないまま業務を進めると、お互いに助け合う姿勢が生まれにくくなるでしょう。
また、普段から対話の機会が少ないと、メンバー同士が得意分野を補い合えないため、成果の最大化が難しくなります。組織を横断する取り組みも進まず、部署間の連携が疎遠になるリスクが高まります。
チームワークを強化するには、共通の目標を明確化し、役割分担や連携方法を定期的に見直すといった活動が求められます。
関連記事:仕事に欠かせないチームワークとは?強化するためのポイントや方法も解説
関連記事:チームワークを高めるにはどうすればいい?必要性や具体的手法を解説
関連記事:チームビルディングとは、効果的な目的と実践例で結束力を高める秘訣
従業員がストレスを抱えやすい
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の9つ目は、従業員がストレスを抱えやすいことです。
日常的に声を掛け合う機会が少ない環境では、従業員が不安や悩みを発散できずに溜め込んでしまうことが多いです。誰にも相談できないままメンタルヘルスを損ねるケースも珍しくありません。
チーム全体にとって望ましくない状況が続けば、業務パフォーマンスの低下にも直結します。周囲の助けや声かけが得られないため、一人で業務を抱え込んで燃え尽きてしまうリスクも高まります。
こうした事態を防ぐためには、ストレスが軽減されるように、従業員が気軽にコミュニケーションを図れる仕組みや文化づくりが欠かせません。
関連記事:キャパオーバーのサインに要注意!仕事の負担を軽減する方法
離職する従業員が多い
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の10個目は、離職する従業員が多いことです。
業務について悩みを打ち明ける相手が身近にいない場合、従業員は一人で問題に立ち向かわなければならず、不満や孤独を感じストレスが蓄積してしまいます。
業務上でのストレスが積み重なると、離職につながる恐れがあるでしょう。
従業員のモチベーションが低下する
社内コミュニケーション不足によって生じる課題の11個目は、従業員のモチベーションが低下することです。
従業員同士や上司と部下の間でコミュニケーションが不足すると、会社への帰属意識を失い、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
協力が必要な場面でも頼ることができず、業務の品質が低下し、顧客満足度の低下や生産性の低下が発生することもあるでしょう。
関連記事:職場の空気を変える!オープンコミュニケーションがもたらすメリットや方法を解説
社内コミュニケーションの課題が発生する原因

ここでは、社内コミュニケーションの課題が発生する原因について、以下の5点を解説します。
- リモートワークの普及で従業員同士が顔をあわせる機会が少ない
- お互いのことをよく知らないため会話が少ない
- 部署間の交流がほとんどない
- コミュニケーションを取りづらい雰囲気がある
- 従業員がコミュニケーションを取りたがらない
1つずつ見ていきましょう。
リモートワークの普及で従業員同士が顔をあわせる機会が少ない
社内コミュニケーションの課題が発生する原因の1つ目は、リモートワークの普及で従業員同士が顔をあわせる機会が少ないことです。
新型コロナウイルスの影響や働き方改革の推進により、リモートワークやフレックスタイム制の導入で出社時間が異なるなど働き方の多様化により、従業員同士が対面で交流する機会が限られている企業も少なくありません。
オフィスで共同作業を行う時間が少ないと、自然な会話や雑談も減少します。
チャットやオンライン会議を通じてのコミュニケーションも、オフィス環境で対面したことがないと、盛り上がらないこともあるでしょう。
関連記事:テレワーク時代のコミュニケーションとは?課題の克服とチーム活性化の工夫
お互いのことをよく知らないため会話が少ない
社内コミュニケーションの課題が発生する原因の2つ目は、お互いのことをよく知らないため会話が少ないことです。
互いの情報が少ないと、「共通の話題がない」「何を話せば良いのかわからない」という状況になりがちで、会話が弾まないことがあります。
また、チームメンバー間での情報共有が不十分となり、それぞれの強みや弱み、働き方の違いを理解する機会が減ることもあります。
結果的に、協力して問題を解決することができなかったり、チームワークが悪くなることも懸念されます。
関連記事:情報共有がチームワークを高める!具体的な手段やコツを解説
部署間の交流がほとんどない
社内コミュニケーションの課題が発生する原因の3つ目は、部署間の交流がほとんどないことです。
大企業では、事業所間や他の部署と交流する機会がないというケースも珍しくありません。
部署間のコミュニケーションが不足すると、経営層から発信される企業全体のビジョンや目標に対する共通の理解が欠け、組織の方向性について認識のズレが生じやすくなり、従業員エンゲージメントを向上できません。
コミュニケーションを取りづらい雰囲気がある
社内コミュニケーションの課題が発生する原因の4つ目は、コミュニケーションを取りづらい雰囲気があることです。
業務の効率化に焦点を当てすぎると、業務に関わりのない会話がしづらく、コミュニケーション不全になることがあります。
また、上司や先輩に相談しやすい環境でなければ、業務に関する悩みや不安、不満が蓄積してしまいます。
関連記事:コミュニケーション不全を防ぐには?発生原因とリスクを回避する方法を解説
従業員がコミュニケーションを取りたがらない
社内コミュニケーションの課題が発生する原因の5つ目は、従業員がコミュニケーションを取りたがらないことです。
社内コミュニケーションの促進に尽力しても、従業員がコミュニケーションに消極的な場合があります。
原因として、自分の意見が受け入れられないという不安がある可能性があります。解決するには、従業員が安心して本音を話せる環境を作っていく必要があるでしょう。
関連記事:アサーションとは?現代のコミュニケーションスキルの基礎知識
社内コミュニケーションの課題を解決する8つの方法

ここでは、社内コミュニケーションの課題を解決する方法について、以下の8点を解説します。
- 社内イベントを開催する
- 1on1ミーティングを実施する
- 社内報を発行する
- 社内コミュニケーションツールを導入する
- 休憩や雑談がしやすいスペースを設ける
- オフィスレイアウトを変更する
- 従業員のコミュニケーション能力の向上
- 従業員アンケートを実施する
1つずつ見ていきましょう。
社内イベントを開催する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の1つ目は、社内イベントを開催することです。
社内イベントは、従業員同士がリラックスし気軽に社内交流ができる機会として有効です。
年次パーティーやハロウィンなど季節テーマのイベントは、仕事から離れて楽しむ場となり、従業員同士のコミュニケーションを促進します。
また、スポーツ大会なども、チームメンバー間の信頼関係を築く手段の1つとして開催しましょう。
社内イベントを実施するときには、従業員が気軽に参加しやすい環境を整えることが大切です。従業員の意見を取り入れて、イベントの計画を立てることをおすすめします。
また、参加して価値を感じられるイベントを目指していくことも重要です。
1on1ミーティングを実施する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の2つ目は、1on1ミーティングを実施することです。
1on1ミーティングとは、社内のメンバーが1対1の対話を行うことです。通常、上司と部下が組み合わせとなり、目標設定や業務進捗の評価を行います。
1on1ミーティングの場では、上司が業務に関するフィードバックや指導を行い、部下の潜在能力を発揮させるための支援を提供していきます。
定期的に1on1ミーティングを設けることにより、部下が声をかけにくい状況でも、上司とのコミュニケーションの機会を確保できるでしょう。
社内報を発行する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の3つ目は、社内報を発行することです。社内報は、組織内の透明性を高め、従業員間の理解を深めるのに役立ちます。
企業の最新ニュース、従業員の成果や表彰、さらには社内イベントの報告など、多岐にわたる情報が掲載されるのが、社内報の特徴です。
特に大規模な会社では、従業員同士がお互いの進捗状況や業務活動を把握する機会が少ないことがあります。
社内報を通じて、他部署の人がどのような業務を行っているのかを知ることで、会話がしやすくなることもあるでしょう。
関連記事:読まれる社内報とは?目的・人気のテーマ・運用のポイントを徹底解説!
社内コミュニケーションツールを導入する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の4つ目は、社内コミュニケーションツールを導入することです。
オンラインコミュニケーションツールを導入することで、職場内で迅速に情報共有ができるようになります。
社内SNSやチャットツールを導入することで、従業員はチーム、部署、プロジェクトごとに手軽にメッセージをやり取りできるようになります。
多くのビジネスチャットツールでは、複数のチャットグループを作成して利用できるため、業務に関する情報伝達にも便利に使えるでしょう。
関連記事:ビジネスチャットにおけるコミュニケーションのポイントは?注目の背景や活用するメリット・デメリットも解説
休憩や雑談がしやすいスペースを設ける
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の5つ目は、休憩や雑談がしやすい休憩スペースを設けることです。
社員食堂や休憩室などでは、業務から一息ついて気軽に雑談する機会が増え、社員間の交流が深まります。
休憩場所が、さまざまな部署のメンバーが集まる場であれば、異なる部署の仲間との交流が生まれることもあるでしょう。
また、オフィス内に自由に利用できるミーティングスペースを設ける方法もあります。仕切りのない開放的な空間であれば、会話がしやすくコミュニケーションの機会が増える効果も期待できるでしょう。
オフィスレイアウトを変更する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の6つ目は、オフィスレイアウトを変更することです。
通常のオフィスでは、各部署が向き合うように席が配置されていますが、近くの席の従業員との交流だけに限られてしまうことがあります。
そのため、席をジグザグに配置したり、放射状に配置したりすると、従業員が席を離れて移動しやすくなり、自然な会話が生まれやすくなるでしょう。
さらに、フリーアドレス制を採用する方法もあります。フリーアドレスとは、固定席を作らず、従業員が日によって自由に席を選ぶ形式です。
フリーアドレスを導入すると、毎日異なる従業員と顔をあわせる機会が増えるため、他部署との交流がしやすくなるでしょう。
従業員のコミュニケーション能力の向上
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の7つ目は、従業員のコミュニケーション能力の向上です。
社員一人ひとりがコミュニケーションスキルを磨くことも欠かせません。コミュニケーション研修やワークショップを通じて、伝え方や聞き方のポイントを学ぶ機会を提供すれば、日常業務でのやりとりが円滑になります。
具体的には、ロールプレイやディスカッションなどの実践的な手法を使うことで、習慣化しやすいスキルアップが期待できます。
また、コミュニケーションの積極性を人事評価する制度を導入するなどして、積極的に情報共有や対話を促す仕組みづくりを行うのも有効です。
関連記事:コミュニケーション力は報連相で決まる!できない原因・重要性・定着法をわかりやすく紹介
従業員アンケートを実施する
社内コミュニケーションの課題を解決する方法の8つ目は、従業員アンケートを実施することです。
社内で抱える課題や不満点を従業員アンケートを通じて集約することで、当事者意識を高め早期に具体的な改善施策を打ち出すことができます。
匿名性を確保して、気軽に率直な意見を述べられるアンケート項目や調査方法を用意すると良いでしょう。
アンケート結果をもとに評価制度やコミュニケーションツールの使い勝手などを改善し、従業員の声を反映した取り組みを進めることで、従業員満足度や職場全体への信頼感を高められます。
継続的に実施することで、改善の成果や新たな課題の有無を確認しながら、社内コミュニケーションの質を高めるサイクルを確立できます。
関連記事:社内SNSでアンケートを取ろう!目的やプロセス・ポイントをまとめて解説
社内コミュニケーションの課題を解決するコツ

ここでは、社内コミュニケーションの課題を解決するコツについて、以下の4点を解説します。
- 現状を分析して自社の課題を把握する
- 具体的な社内コミュニケーションの目標を決める
- 従業員に繰り返し周知する
- 課題を解決した事例を参考にする
1つずつ見ていきましょう。
現状を分析して自社の課題を把握する
社内コミュニケーションの課題を解決するコツの1つ目は、現状を分析して自社の課題を把握することです。
まずは、自社が抱えているコミュニケーション上の問題を洗い出し、どこに原因があるのかを調査し明確にする必要があります。定量的なデータと定性的な声の両方を集めることで、より正確な分析が可能となります。
たとえば、「連絡の遅延が多いのはなぜか」「会議で意見が出ないのは何が障害になっているのか」など、実態を把握するにつれ解決策も見えてきます。
現状分析を怠ると、場当たり的な対策に終わり、なかなか根本改善が進まないケースが多いので注意が必要です。
関連記事:社内コミュニケーションの問題点と起こり得る課題、解決策を徹底解説
具体的な社内コミュニケーションの目標を決める
社内コミュニケーションの課題を解決するコツの2つ目は、具体的な社内コミュニケーションの目標を決めることです。
問題を特定したら、それを解消するための明確な目標を設定しましょう。たとえば、1ヶ月以内に「定例会議の発言数を増やす」や「ツールを使ったチャットの回数を2倍にする」といった具体的な数値目標です。
行動目標や数値化できる指標があると、取り組みの進捗を客観的に確認できます。達成が近づくにつれ、メンバーのモチベーション向上につながるでしょう。
目標は小さな成功体験につなげやすい内容に設定し、段階的にレベルアップしていくのが効果的です。
従業員に繰り返し周知する
社内コミュニケーションの課題を解決するコツの3つ目は、従業員に繰り返し周知することです。
新たな社内活動やツール導入は、初期段階で従業員全員に浸透させることが肝心です。周知不足だと、なかなか使われなかったり、形だけの取り組みに終わってしまう可能性があります。
定例ミーティングやメールマガジン、社内チャットなどあらゆる手段を通じて、取り組みの意義や使い方の説明を行いましょう。
継続的に周知を行うことで、時間の経過とともに新しい取り組みが職場文化として定着・醸成し、効果が持続するようになります。
関連記事:社内コミュニケーションを活性化させる3つのポイントと6つの施策とは?
課題を解決した事例を参考にする
社内コミュニケーションの課題を解決するコツの4つ目は、課題を解決した事例を参考にすることです。
他社の成功事例や社内の別部署の取り組みからヒントを得ることによって、より効果の高い方法を見つけられます。全くゼロから立ち上げるよりも、実際にうまくいった仕組みを参考にしたほうが導入成功率は高まります。
特に、似たようなコミュニケーション課題をクリアした企業の取り組み事例は自社でも応用しやすいことが多いです。必要に応じて担当者同士の情報交換やノウハウ共有を行うと良いでしょう。
事例を真似するだけでなく、自社の組織風土や働き方に合わせて最適化することがポイントです。
関連記事:社内コミュニケーションの目的と成功事例、効率化とイノベーションを実現する方法
まとめ

今回は、よくある社内コミュニケーションの課題、社内コミュニケーションが発生する原因、解決策8選を解説しました。
社内のコミュニケーション不足の状態に陥ると、ミスの頻発や業務の属人化、従業員の離職率が高まる可能性があるため、早めに適切な対策を行っていくことをおすすめします。
解決するには、社内イベントや1on1ミーティングの実施、社内コミュニケーションツールの導入などの方法があるため、自社にあった方法で取り入れてみてはいかがでしょうか。
本記事を参考に、社内コミュニケーションの改善に向けた一歩を踏み出しましょう。
また、社内コミュニケーション改善の成功事例を「社内コミュニケーションはどう改善すればよい?手段や成功事例も解説」の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
|
コミュニケーションツール活用のポイント
コミュニケーションツールを導入し利用しているものの、うまくコミュニケーションが取れないと感じていませんか?
|