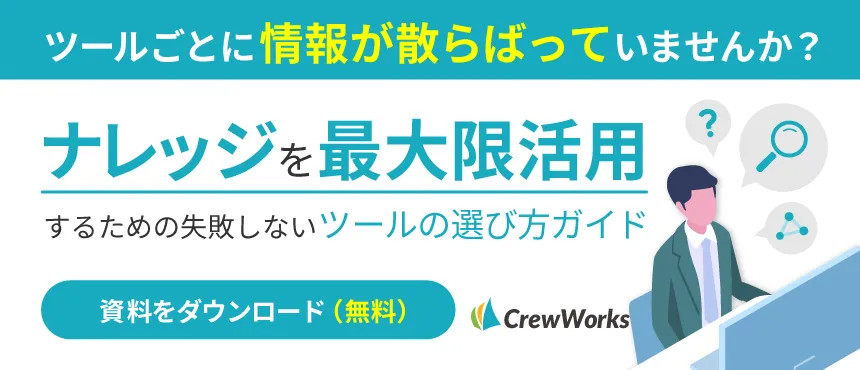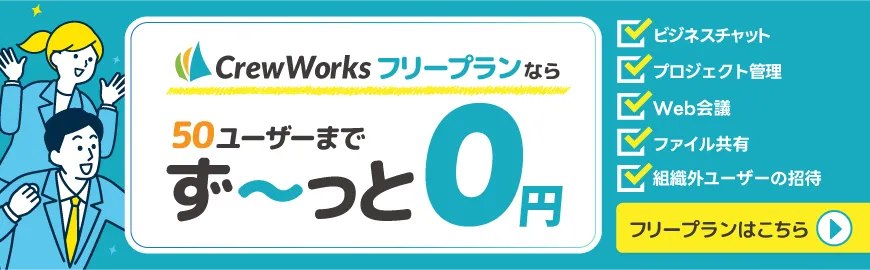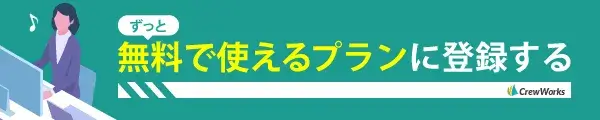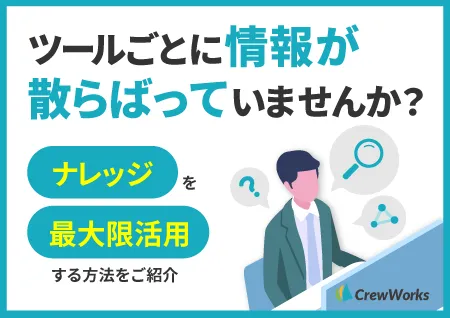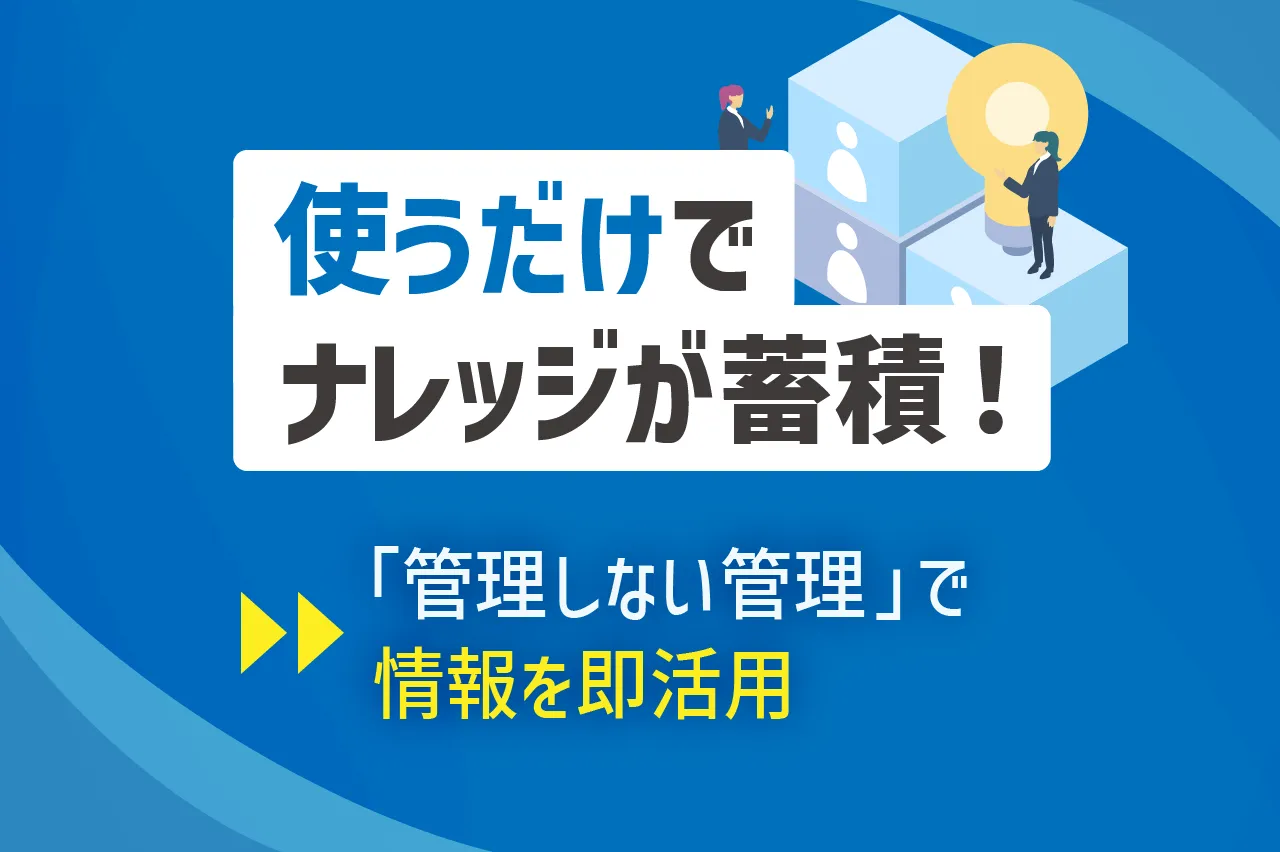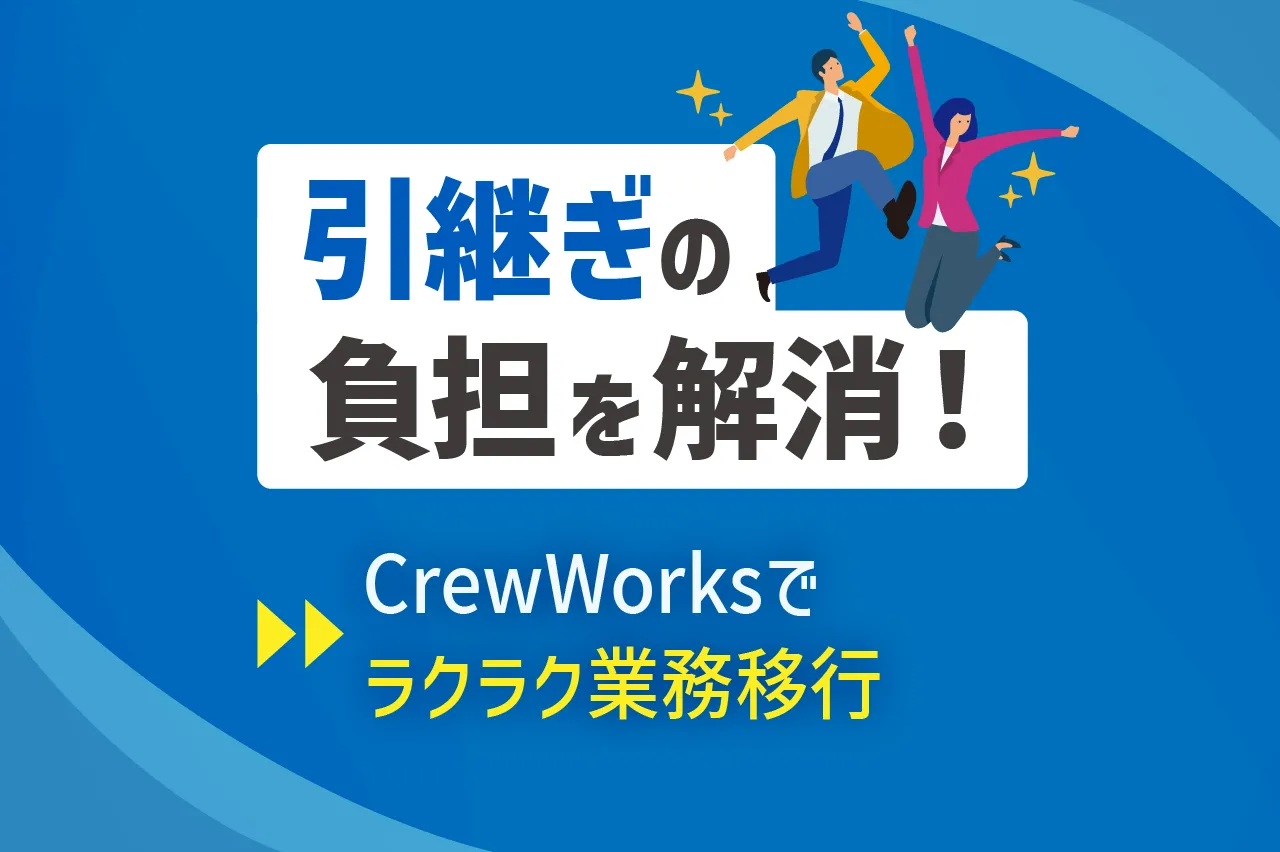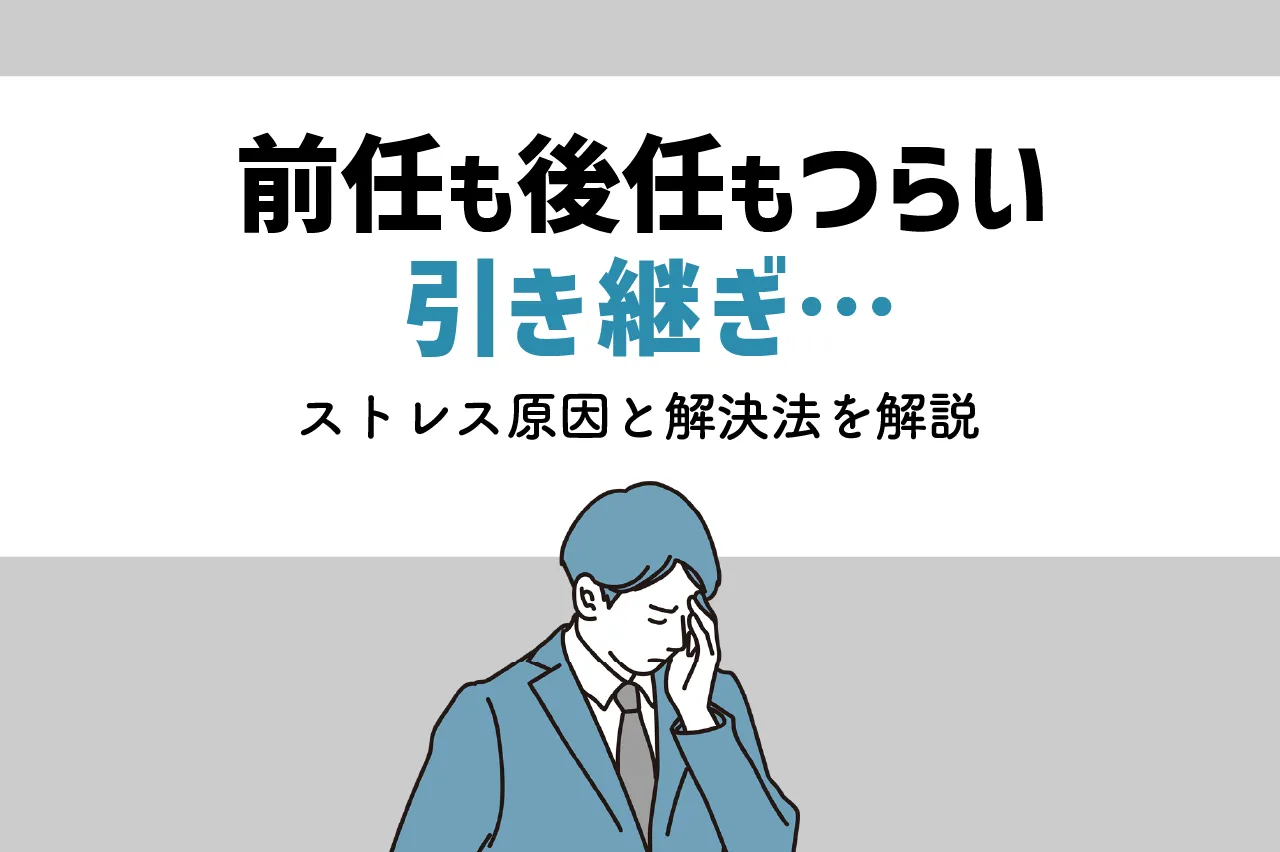ナレッジを蓄積する目的と方法とは?活用までの5ステップとコツ
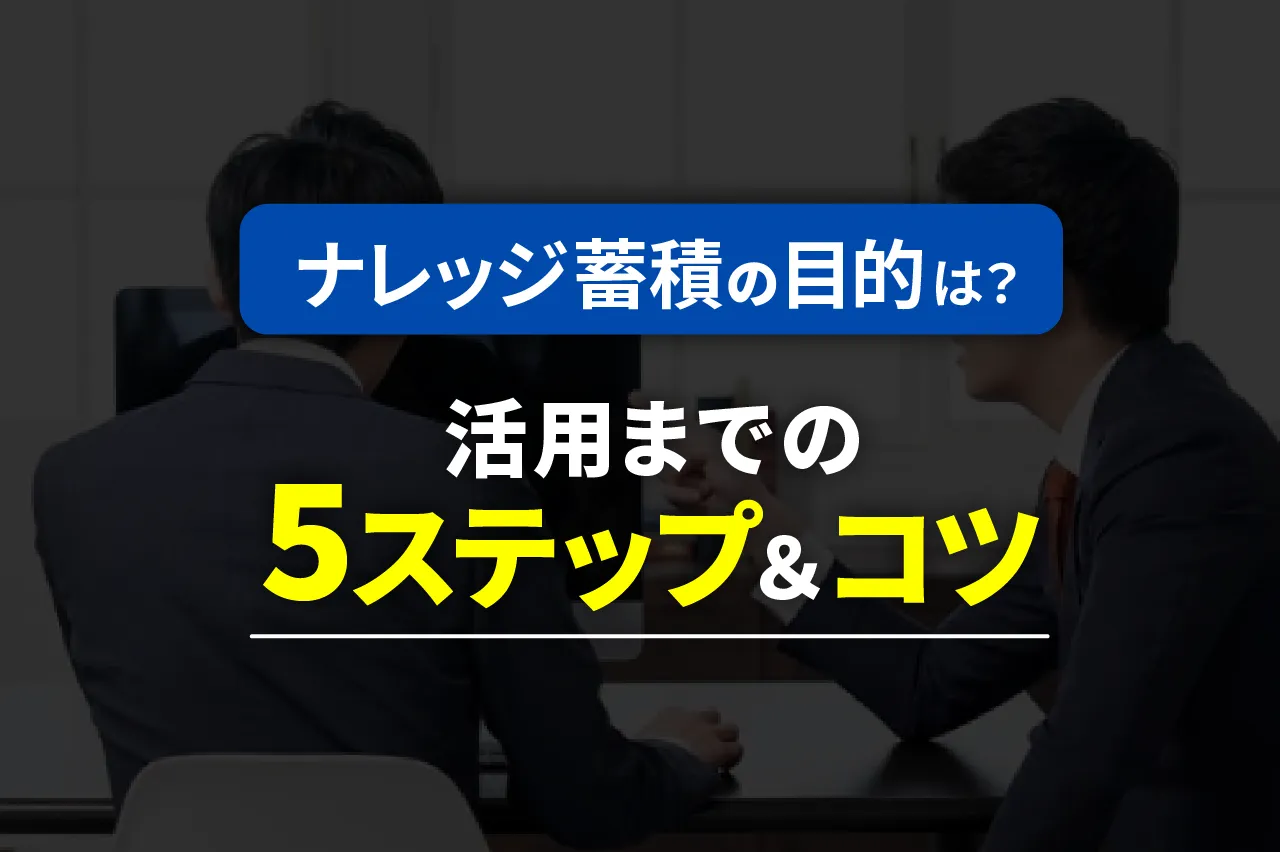
業務を円滑に進めるための知識が共有されていない状況では、チーム全体の成長や効率化が妨げられてしまいます。
従業員の負担軽減や企業の成長には、ナレッジを蓄積して共有していく仕組みは欠かせません。
そこで今回は、ナレッジ蓄積の目的、活用までの5つのステップ、有効なツールを解説します。
ナレッジを蓄積するときのコツも紹介しますので、社内の情報共有に課題を感じている方はぜひご覧ください。
【目次】
ナレッジ共有・活用の負担を軽減する方法は、以下の記事で紹介しています。
関連記事:ナレッジ共有・活用時の負担を解消!業務で使うだけでナレッジが蓄積されるツールとは?
ナレッジ蓄積の目的とメリット

ここでは、ナレッジ蓄積の目的とメリットについて、以下の4点を解説します。
- 生産性を高める
- 業務の属人化を防ぐ
- 社内教育を効率化できる
- 業務ミスを予防する
1つずつ見ていきましょう。
生産性を高める
ナレッジ蓄積の目的の1つ目は、生産性を高めることです。
従業員が資料を自己流で作成したり、同じ説明を何度も口頭で繰り返す手間を省いたりするためには、情報のデータベース化が有効です。
また、キャリアのある従業員や一部の従業員が持つ知見を共有することで、業務の進行がスムーズになり、チーム全体がより本質的な課題に集中できるようになります。
ナレッジの蓄積は、組織の強みを活かしながら、限られたリソースを最適に配分するための重要な取り組みの1つです。
関連記事:生産性向上が企業活動で求められている!取り組み方や成功のポイントも解説
業務の属人化を防ぐ
ナレッジ蓄積の目的の2つ目は、業務の属人化を防ぐことです。
働き方の多様化や人材の流動性が高まる中で、特定の業務が属人化すると、担当者の退職や異動のときに引継ぎが困難になり、業務が停滞する恐れがあります。
引継ぎがなければ、後任者には多大な労力やコストが発生しかねません。
そこで、社内ナレッジが蓄積・共有されていれば、誰でも業務内容を把握できるため、急な担当者変更にも柔軟に対応できます。
属人化を防ぐことで、組織全体の安定性と効率性が向上するでしょう。
関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説
関連記事:「あの人にしかできない仕事」は危険!属人化によるストレスと職場の崩壊リスク
社内教育を効率化できる
ナレッジ蓄積の目的の3つ目は、社内教育を効率化できることです。
口頭で伝えられる知識や技術は反復が難しく、習得に時間がかかることも少なくありません。しかし、ナレッジをデータベース化すれば、動画・画像・テキストといった多様な形式で情報の蓄積が可能です。
新入社員は必要なときに得たい知識を何度でも確認できるため、効率的に学習できます。
また、疑問点が生じたときにもデータベースで自己解決できるため、先輩社員が都度対応する負担を軽減できるのも大きなメリットです。
ナレッジの蓄積は、教育の質を高めるだけでなく、従業員全体の業務効率向上にも役立ちます。
関連記事:ナレッジの継承は企業活動で必要になる!うまくいかない要因や方法などを解説
業務ミスを予防する
ナレッジ蓄積の目的の4つ目は、業務ミスを予防することです。
過去の失敗や改善事例を共有することで、同じミスが繰り返されるリスクを低減できます。失敗したときに原因や状況、改善策を明確にし、従業員全員で共有する仕組みが作れるためです。
問題点を洗い出して対策を講じることで、業務の精度も向上するでしょう。
関連記事:ナレッジ活用で組織力を最大化!失敗しない進め方とツールの選び方を解説
ナレッジの蓄積と活用するまでの5ステップ

ここでは、ナレッジの蓄積と活用するまでのステップについて、以下の5点を解説します。
- 目的を周知する
- ナレッジを集約するためのシステムを決める
- 蓄積する情報を決める
- 運用体制を整える
- 蓄積したナレッジを共有する
1つずつ見ていきましょう。
目的を周知する
ナレッジの蓄積と活用するまでのステップの1つ目は、目的を周知することです。
なぜナレッジを蓄積することが必要なのかを明確に伝えておかなければ、従業員が積極的に協力する姿勢は生まれません。
知識やノウハウを言語化してデータベース化する作業は、日々忙しい従業員にとって時間のかかる業務だと捉えられるためです。
そのため、ナレッジ共有の目的や効果を丁寧に説明し、組織全体の業務効率化だけでなく、従業員一人一人にとって価値のある取り組みだと理解してもらう必要があります。
目的を共有することで、全員が取り組む意義を感じ、協力体制を築いていけるでしょう。
関連記事:ノウハウとは?ビジネスシーンにおける意味や使い方と活用メリットをわかりやすく解説
ナレッジを集約するためのシステムを決める
ナレッジの蓄積と活用するまでのステップの2つ目は、ナレッジを集約するためのシステムを決めることです。
グループウェアやタスク管理・プロジェクト管理ツールなど、ナレッジ共有を効率化するためのシステムを導入しましょう。
組織の規模や目的に合ったシステムを選ぶことで、ナレッジの蓄積と活用がスムーズに進みます。
関連記事:タスク管理とは?効率的な実施方法からおすすめのツール8選をまとめて比較・解説
関連記事:【2025年版】プロジェクト管理ツールおすすめ16選を徹底比較!5つの確認ポイントも紹介
蓄積する情報を決める
ナレッジの蓄積と活用するまでのステップの3つ目は、蓄積する情報を決めることです。
全ての情報を収集しようとすると、データが散漫になりかえって活用しにくくなってしまいます。そのため、自社や部署にとって有益なナレッジだけを厳選して蓄積していくことが重要です。
まず、どのようなナレッジが業務に役立つのかを考え、情報の種類や方向性を整理しましょう。このとき、情報収集の責任者を決めておくことも重要です。
担当者が曖昧になり、収集が進まない事態を防ぐためです。
また、蓄積したナレッジを活用するためには必要な情報がまとまり、すぐにアクセスできる状態にしておく必要があります。ナレッジを蓄積するだけでなく、活用する方法も検討しておく必要があります。
関連記事:ナレッジ化を始めよう!メリット・重要ポイント・おすすめツール8選
運用体制を整える
ナレッジの蓄積と活用するまでのステップの4つ目は、運用体制を整えることです。
ナレッジは、蓄積するだけでなく共有の仕組みを構築していくことも重要です。仕組みを整えるには、ナレッジ共有を業務プロセスに組み込みましょう。
例えば、共有のタイミングや内容をあらかじめ決めて記入しやすくしておくと、ナレッジ共有を業務の一環として定着させることが可能です。
共有がルーティン化されれば、従業員も負担を感じにくくなり、継続的な運用が実現するでしょう。
関連記事:成功した企業に学ぶ!ナレッジマネジメントの成功事例4選とコツを解説
蓄積したナレッジを共有する
ナレッジの蓄積と活用するまでのステップの5つ目は、蓄積したナレッジを共有することです。
ナレッジは単に集めるだけでなく、組織全体で共有し、活用できる状態にすることが重要です。そのためには、ナレッジの蓄積方法と並行して、共有方法についても十分に考慮する必要があります。
共有方法としては、Excelなどすでに業務で利用している無料ツールを活用する方法もありますが、検索性が優れたナレッジ蓄積に有効なツールの導入がオススメです。
共有されたナレッジは、教育コストの削減や業務の標準化、さらには顧客への均一なサービス提供にも貢献するでしょう。
重要なのは、ナレッジが個人の中に留まらず、組織全体の資産として循環する仕組みを整えることです。
関連記事:ナレッジ検索とは?検索方法・課題と対策・ツールの選び方を解説!
関連記事:ナレッジ共有・活用時の負担を解消!業務で使うだけでナレッジが蓄積されるツールとは?
ナレッジ蓄積に有効なツール

ここでは、ナレッジ蓄積に有効なツールについて、以下の6点を解説します。
- 文書管理システム
- 社内Wiki
- グループウェア
- 社内FAQ
- CRM
- ナレッジ共有ツール
1つずつ見ていきましょう。
文書管理システム
ナレッジ蓄積に有効なツールの1つ目は、文書管理システムです。 文書管理システムは、社内文書を保管・活用し一元化するためのツールです。
文書管理システムの活用は、必要なときすぐにアクセスできるよう管理ルールを明確にしておくことが重要です。
例えば、ファイルの保管場所やディレクトリ名、ファイル名の表記方法などを統一し、ルールを全従業員に周知しておきましょう。
情報の検索性を向上させることで、ナレッジの共有と活用がスムーズに行えます。
関連記事:文書管理システムのおすすめ13選を紹介!ツールを活用してスムーズに業務を進めよう
社内Wiki
ナレッジ蓄積に有効なツールの2つ目は、社内Wikiです。 社内Wikiは、社内のナレッジを一元管理し、個々の従業員が検索・参照できるツールです。
閲覧権限を設定すれば、議事録や社内向け資料の共有にも活用できます。従業員自身が簡単に情報を編集・更新できるため、最新のデータを維持しやすいツールです。
リモートワークや多拠点展開している企業でも、従業員間の知識共有が円滑に行えるでしょう。
関連記事:社内Wikiを徹底解説!おすすめツール8選と注目の背景・メリット・デメリットを紹介
グループウェア
ナレッジ蓄積に有効なツールの3つ目は、グループウェアです。グループウェアは、従業員間のコミュニケーションや業務連携を効率化するためのツールです。
ツールにもよりますが、多くの場合、メール・チャット・ファイル共有・スケジュール管理・社内申請など、多彩な機能を備えています。
場所や時間に縛られることなく、各プロジェクトの進捗状況を把握したり、必要な情報を持つスタッフを迅速に見つけたりすることが可能です。
例えば、重要な情報をチャットでやりとりしたり、ファイルを共有フォルダにアップロードしておくことで、ナレッジ共有の環境を整えられます。
関連記事:【2025年版】社内イントラのおすすめツール6選!メリット・導入ポイントも紹介
社内FAQ
ナレッジ蓄積に有効なツールの4つ目は、社内FAQです。 社内FAQシステムは、よくある質問とその回答をまとめて共有できるツールです。
業務で疑問が生じたときに、FAQを検索・参照することで自己解決が可能になります。
また、FAQは一定のフォーマットで記録されるため、操作がシンプルで扱いやすいという利点があります。
情報を容易に追加・更新できるため、組織や業務内容の変化にも対応できるでしょう。
関連記事:おすすめのFAQシステム5選を紹介!導入効果・効果を高める選び方も解説
CRM
ナレッジ蓄積に有効なツールの5つ目は、CRMです。 CRMは、顧客情報やコミュニケーション記録を一元管理し、営業活動を効率化するツールです。
顧客や取引先との過去のやり取りや詳細な情報を記録しておけば、他の営業担当者がフォローしやすくなり、スムーズな対応が可能になります。
また、請求書などのデータと連携し、売上管理を簡易化することが可能です。
さらに、個人の成功事例や失敗事例を共有することが、ノウハウの共有にもつながり、属人化の解消にも効果的です。
蓄積したナレッジはマーケティング活動にも活用できるため、企業全体の効率化が見込めます。
関連記事:顧客管理(CRM)ツールとはなにか?おすすめのツール10選を徹底解説!メリットと選定のポイントも紹介
ナレッジ共有ツール
ナレッジ蓄積に有効なツールの6つ目は、ナレッジ共有ツールです。 ナレッジ共有ツールは、社内の知識や経験を組織全体で共有し、有効活用することを目的としたツールです。
これまでは、マニュアルや議事録といった情報を紙媒体で管理したり、メールやチャットでやり取りしたりすることが一般的でした。
しかし、これらの方法では過去の情報が埋もれてしまいやすく、必要な情報を見つけ出すのに手間がかかるという課題がありました。
ナレッジ共有ツールを導入することで、これらの課題を解決できます。情報を一元的に管理し、キーワード検索などで必要な情報にすぐにアクセスできるようになるため、ナレッジの検索性が大幅に向上します。
さらに、ナレッジを共有した従業員に対して感謝の気持ちを伝えられる機能を持つツールもあり、従業員のナレッジ共有に対するモチベーションを高める効果も期待できます。
関連記事:【無料版あり】ナレッジ共有ツールのおすすめ8選!使い方や注意点も解説
ナレッジを蓄積するときのコツ

ここでは、ナレッジを蓄積するときのコツについて、以下の2点を解説します。
- 運用マニュアルを作成する
- 情報の格納時に階層を決めておく
1つずつ見ていきましょう。
運用マニュアルを作成する
ナレッジを蓄積するときのコツの1つ目は、運用マニュアルを作成することです。
社内で有益な情報やスキルを持っていても、ナレッジ共有の方法が複雑だと、従業員が共有を諦めてしまうことがあります。
その結果、貴重な知識が活用されず、組織全体の成長が妨げられてしまいます。
そのため、誰でも簡単にナレッジを更新・共有できるよう、運用マニュアルを整備することが大切です。
運用マニュアルは、個人のスキルや知識のレベルにかかわらず、全員が理解できる内容にまとめましょう。
分かりやすく標準化された運用マニュアルを用意することで、情報更新のハードルが下がり、ナレッジ蓄積がスムーズに進みます。
関連記事:社内マニュアルの作成方法!メリット・デメリットと作成時のコツも解説
情報の格納時に階層を決めておく
ナレッジを蓄積するときのコツの2つ目は、情報の格納時に階層を決めておくことです。
格納場所や構造が整備されていないと、ナレッジが集まりにくく、蓄積されても活用が進みません。
そのため、情報を「どこに・どのように」保存するかを、初期段階である程度計画しておくことが大切です。
最初から完璧な構造を考えるのは簡単ではありませんが、蓄積したナレッジを従業員がどのように活用するかをイメージしながら、カテゴリー分けや階層構造を設定するとスムーズです。
例えば、「部署別」「プロジェクト別」「業務プロセス別」といった分類を設けることで、検索性が向上するでしょう。
関連記事:パソコンのフォルダ整理術の決定版!仕事効率を格段にアップさせる方法
ナレッジの蓄積と活用におすすめのツール「CrewWorks」
CrewWorks(クルーワークス)は、ビジネスに必要な機能が揃ったオールインワンツールです。 ビジネスチャット・タスク管理・プロジェクト管理・Web会議機能が搭載されており、企業が抱えるコミュニケーションや情報共有の課題をスムーズに解決します。ナレッジを蓄積するためにマニュアルを随時更新し、常に誰でも閲覧できる状態を維持するのは難しいものです。しかしCrewWorksなら、コミュニケーション履歴をすべて保存し、全機能で検索が可能です。そのため、わざわざマニュアルを作成しなくても自然とナレッジが蓄積され、必要な情報を簡単に検索できます。
CrewWorksの特長
- 情報が自然と構造化され、必要な情報を一目で確認できる
- 使うだけでナレッジが自動構造化
- 最大50ユーザーまでずっと無料で利用できるフリープランあり
詳細はこちら: https://crewworks.net/
まとめ

今回は、ナレッジ蓄積の目的、活用までの5つのステップ、有効なツールを解説しました。
ナレッジを蓄積する目的は、業務効率化や属人化の防止などがあります。ナレッジは、単に情報を集めるだけでなく、効果的に活用するための仕組みづくりが不可欠です。
また、運用マニュアルの作成や情報の格納時に階層を設定することも大切です。
従業員全員がナレッジを効率よく共有・活用できる環境を構築するために、ナレッジ蓄積に役立つツールの導入を検討してみてください。
ナレッジ共有・活用の負担を軽減する方法は、以下の記事で紹介しています。
関連記事:ナレッジ共有・活用時の負担を解消!業務で使うだけでナレッジが蓄積されるツールとは?
|
ナレッジを最大限活用するための失敗しないツールの選び方ガイド
コミュニケーション・ナレッジマネジメントツールを個別に導入し、情報が散在し必要な情報が見つけられなくて困った経験はありませんか?
|